
草の葉ライブラリー
たった一冊の本が世界を変革していくことがある
本は売れなければならない。売れる本だけが価値をもたらす。売れる本によって本を作り出す人々の存在が確立されていくからである。これがこの世界を絶対的に支配している思想でありシステムであり、したがって数十部しか売れない本は価値のない本であり、数部しか売れない本はもう紙屑同然のものということになる。しかし本というものは食料品でも商品でも製品でもなく、まったく別の価値をもって存在するものであり、たった数部しか売れなかった本が、数十万部を売った本よりもはるかに高い価値をもっていることなど枚挙にいとまがない。ベストセラーなるものの大半が一読されたらたちまちごみとなって捨てられるが、たった五部しか売れなかった本が、永遠の生命をたたえて世界を変革していくことだってある。
この視点にたって創刊される「草の葉ライブラリー」は、たった数部しか売れない本に果敢に取り組み、独自の方式で読書社会に放っていく。荒廃して衰退していくばかりの読書社会に新たな生命の樹を打ち立てる本である。閉塞の世界を転覆させんとする力動をもった本である。地下水脈となって永遠に読み継がれていく本である。

一冊一冊手作りの出版のシステムを確立していく
これら数部しか売れない本を読書社会に送り出していくために、その制作のシステムを旧時代に引き戻すことにした。旧時代の本とは手書きだった。手書きで書かれた紙片が綴じられて一冊の書物が仕上がる。その書物を人がまた書き写し、その紙片を束ね、表紙をつけて綴じるともう一冊の書物になった。こうして一冊一冊がその書物を所望する人に配布されていった。
この手法を現代に確立させるための最上の道具がそろっている。その作品をコンピューターに打ち込み、スクリーンに現れる電子文字を編集レイアウトして、プリンターで印字し、簡易製本機で一冊の本に仕立てる。簡易製本機、これは驚くべき発明である。この機器が登場することによってだれも本が作れるようになった。その工程はすべて手作りである。その一冊一冊が工芸品のように制作される。
大量印刷技術によって、複雑なる販売流通によって、売れる本しか刊行しない、売れる本しか刊行できない現代の出版のシステムに反逆するシステムである。この旧時代的手づくり工法によって、真の価値をもった作品が新たな生命力を吹きこまれて一冊の本となって読書社会に送り出される。新しい時代を切り開く出版のシステムの誕生である。

読書社会に新しい地平を切り開くクラウドファンディング
長い苦闘の果てに書き上げた作品が、本となって読書社会に投じられるまで何段階ものハードルがあり、そして実に複雑なルートを通さねばならない。晴れてその本が書店に並べられたとしても、その本を手に取る人はゼロで、したがってその本は二三週間で返本される。ごみ同然となったその本は裁断され焼却される。これが今日の出版の現実である。この現実を切り開かんと、いま全く新しい出版のシステムが登場した。クラウドファンディングである。大望を抱く者が、しかしその大望に取り組む資金のない者が、社会に人々に助力を求めるシステムである。
草の葉ライブラリーはこのシステムによって、一冊一冊が読書社会に投じられていく。複雑な流通システム一切なしである。リターンにクリックされた購入者のもとに草の葉ライブラリーから発送される。出版システムの革命である。

生命の木立となって時代とともに成長していく草の葉ライブラリー
現在の出版のシステムは、その本を読書社会に投じたらそれで完了である。一度出した本を再編集して投じるなどということはめったに行われない。出版社は絶版の山を築いていくばかりである。大地を豊かにする名作がこうして捨てられていく。ゴッホの絵がなぜいまなお脈々と生命をたたえているのか。それは繰り返し彼の絵が展示されるからである。なぜモーツアルトの音楽がいまなお人々に愛されるのか、それは繰り返し演奏されるからである。生命力をたたえた本は、繰り返し新しい世代に向けて発行していくべきなのだ。「草の葉ライブラリー」は新しい編集、新しい体裁によって繰り返し刊行されていく。その時代の生命をその本に注ぎ込むことによって、その本は時代ともに成長していく。これらの活動はwebサイトの「noteウオールデン」に百本近いコラムやエッセイとなって植樹されている。「noteウオールデン」を訪れて下さい。

誰でも本が作れる、誰でも本が出版できる、誰でも出版社が作れる、このコンセプトによって「草の葉ライブリー」は、高尾五郎著「ゲルニカの旗 南の海の島」を読書社会に送り出します。地平を切り拓いていく本です。一冊の本が世界を変革していきます。

高尾五郎著 ゲルニカの旗 南の海の島
目次
ゲルニカの旗
最後の授業
吉崎美里と絶交する手紙
南の海の島
ゲルニカの旗(250枚)、最後の授業(120枚)、吉崎美里と絶交する手紙(65枚)、南の海の島(260枚)の四つの中編小説が編まれています。この四つの物語がどのように展開されていくのかその核心の部分を転載します。日本の歌が聞こえる。さまざまな賛歌が聞こえる。

ゲルニカの旗
ゲルニカの事件は実際にあった事件だった。卒業式、その日のために子どもたちが制作したゲルニカの大壁画が外された。そのことに一人の少女が憤然と抗議した。教育委員会はその少女の担任教師を処罰した。長い長い裁判闘争が起こった。大人たちの闘争に巻き込まれた少女。「ゲルニカの旗」は子どもが担うべきことではない悲劇を、胸に貼りつけて歩いていかねばならなかった少女のその後を、しびれるばかりに深くきびしく描き込んでいる。子どもたちの悲劇、そして明日をめざす教育を描いた屈指の作品である。

やがてこの挑戦は卒業制作として、六年生全員で取り組むことになった。一クラス六人の代表からなるゲルニカ制作実行委員会がつくられ、私もその一人になった。スケッチブックや画用紙や模造紙に何度も下書きをして、ゲルニカの荒々しい構図を再現しようとした。そしてそこに色彩をつけていく。色彩といってもグレー一色だが、しかしそのグレーが微妙に変化していく。その微妙な色調の変化を再現することがとてもむずかしかった。そんな段階をへて、百六十人の子供たちが見守るなか、体育館の床に縦三メートル七十センチ、横八メートル四十センチの布きれを敷いた。それは巨大な布だったが、しかし百六十人もの子供たちに取り囲まれてみると、とても小さく感じられた。
模写とはいえ大画面に再現するのはとても大変だった。正確に再現しようとするとどんどん構図が歪み、何度も何度も描き直していった。ようやく構図がきまると、百六十人の子供たちがペンキで彩色していくのだが、ばらばらに塗りこめられていたり、乱暴に塗られたり、線からはみだしたりしていて、制作委員が毎日遅くまでかかって修正していった。
その日の放課後、制作委員が体育館に残って、ゲルニカを描いているときだった。新田さんという一組の子がバタバタと足音をたてて体育館に入ってくると、
「ねえねえ、みんな聞いて。ゲルニカは卒業式には飾らないって」
ゲルニカは私たちの卒業式の日に正面ステージに飾られる。そのゲルニカを前にして、私たちは卒業する決意表明をして巣立っていく。それが私たちのゴールだった。思いもよらぬ新田さんの言葉にみんなの手が止まった。
「どうしてそんなことになるの。だってみんな卒業式めざして描いているんじゃないの」
「そうよ。それじゃあ、なんのためにかいているかわからないよね」
「それって裏切りだぜ。そんな裏切って許せねえよ」
「そうよ、そんなことぜったいに許せないよ」
そこに制作の進行を見に二組の野島先生がやってきた。その日の製作担当の先生が野島先生だったのだ。私たちは猛然と野島先生にかみついた。野島先生は困惑の色を浮かべながら、
「その問題はね、明日の制作委員会で吉永先生から話しがあるわよ。そこで吉永先生が説明してくれるはずだけど。そうね、ゲルニカは難しいのよ。ゲルニカに対する批判がでてきたり、学校の事情も変わってきたりして、いろいろと難しい問題がいっぱいでてきているの」
「その難しい問題ってなんですか」
「詳しくは明日、吉永先生から説明があるけど、今年の卒業式はちょっと特別なのよ」
「特別って、なにが特別なんですか」
「今年の卒業式の中心になるのは日の丸なの。日の丸を中心に飾って、君が代を歌う。校長先生たちはそういう卒業式にしたいっていうわけ。それでそういう卒業式にするためには、ゲルニカはちょっと邪魔になるんじゃないのかな。とにかくゲルニカは大きな絵でしょう。こんな大きな絵をもってくると日の丸が隠れてしまう。そのことを校長先生や教頭先生はすごく問題にしているのよ」
翌日の放課後に、美術室で制作委員会が開かれた。四クラスの制作委員二十四人の痛いばかりの視線をうけて、吉永先生はなんだか申し訳がないといった様子をただよわせて説明に立った。
「昨日もまた校長先生や教頭先生たちと遅くまで、ゲルニカをどのように展示するかという話し合いをしました。そこで幾つかの案がでたけど、その一つはもちろん卒業式に飾るということだね。最初の計画ではそういうことだった。しかしちょっといろんな事情ができて、それができなくなるかもしれないんだね」
そこで私たちの鋭い声が飛んだ。
「いろんな事情ってなんですか」
「君が代と日の丸のためですか」
「君が代、日の丸ってなんなんですか。私たちによくわかりません」
「そのことでゲルニカは犠牲になるんですか」
「まあ、ちょっとみんな興奮しないでくれよ。うん、そうだな、日の丸、君が代の問題にふれるとね、話がすごく複雑になるし長い話になるので、いまそのことにはふれません。問題はゲルニカをどうするかということだからね。それで第一の案として、あくまでもゲルニカは卒業式のステージに飾ることだね。しかしいろんな事情でそれができなくなったとき、第二案というものも考えなくてはいけない。そこで第二案として、君たちに提案するのだけど」
「第二案ってなんですか」
「うん、第二の案というのは、この絵をこの学校に永遠に飾っておくためにパネル板をつくる。ゲルニカが完成したらそのパネル板に貼る。そして全校集会を開いて、ゲルニカを在校生に贈る伝達式を行うという案なんだ。そういう案はどうだろうね」
「それって、ゲルニカを卒業式には飾らないってことですか」
「うん、そうなんだ。しかしそのパネル板は美術室の前に置いておく。この学校が続くかぎり、君たちの残した記念碑として、いつまでそこに飾っておくんだ」
「どうして美術室なんですか。どうしてゲルニカは卒業式に飾ってはいけないですか」
「ゲルニカって、卒業式には迷惑なものなんですか。私たちは迷惑なものをかいているんですか」
「私たちは卒業式という目標をたててやってきました。その目標に向かってみんな頑張ってきたんです。その目標がなくなるということです」
「これは約束違反です。先生たちってそんな簡単に約束を破るんですか」
「これは裏切りです。こんな裏切りを私たちはぜったいに認めません」
吉永先生は子供たちから発せられる抗議に顔を苦しそうにゆがめていく。いま先生はとても苦しい所に立っている。しかし私たちは譲れない。私たちは断固として卒業式にゲルニカを飾ってもらいたいといった。やがて吉永先生は、そんな私たちに全面的に降伏するよういった。
「わかった。君たちの意見はよくわかった。君たちが強く主張するように、ゲルニカはやっぱり、卒業式に飾らなければいけないね。ぼくもそう思う。君たちの意見を校長先生や教頭先生に伝えるよ。ぼくもそうなるように頑張っていくから、君たちも最後のスパートをかけてゲルニカを完成させて下さい」
そのゲルニカは刻々と完成に近づいていく。しかし先生たちからの返事がなかった。それは先生たちの間に激しい対立があるからだった。六年生の先生たちのなかにさえ、吉永先生を批判している先生たちがいた。校長先生や教頭先生はゲルニカを卒業式から排除すべきだと主張している。君が代斉唱と日の丸掲揚を中心にするか、それともゲルニカを中心にするのか、その二つの主張が激突しているのだ。
制作委員会では、ゲルニカ制作ニユースという新聞を毎週発行していた。制作の進行を報告したり、どんなことを応援してほしいか、これから活動はどう展開するかといったことを記事にしていた。その新聞を発行するたびに校長室にも届けていたが、その週は私が校長室に届けることになった。私は校長先生にいっぱい話したいことがあったからだ。
校長室に入り、大きな机の向こう側にすわっている校長先生に、その日刷り上った新聞を手渡すと、
「私たちの制作ニュースを読んでくれていますか」
と私はたずねた。
「毎号毎号しっかりと読んでいるよ」
「ゲルニカを卒業式に飾って下さいというのが私たち全員の意見です。この意見を聞いてくれますか」
「そうだね、それが君たちの意見だ。先生たちもその意見をできるかぎり実現させなければならないと思っているけどね」
「もうゲルニカは、卒業式に飾らないってみんないっていますが、なんだかそれがだんだん本当になっていくように思えますが、本当はどうなんですか」
「まだそう決まったわけではないよ。これから決めていくことなんだ。これからも先生たちと話し合って、一番よい方法で展示したいと思っている。先生たちもいまそのことを一生懸命考えているところなんだ」
「私たちがゲルニカに取り組んだとき、これを卒業式に展示すると決めました。その目標に向かって私たちは描いてきました。いまその目標がなくなると、いったい私たちは何をしてきたかがわからなくなります」
「そうだね。そのことは先生たちにもよくわかっている。君たちの意見がまた今日届けられた。しっかりと先生たちの心のなかに届いているから、今日はこれで帰りなさい」
私たちはその問題を真剣に話し合いたいのに、またそういって追い返されてしまった。いつもこうしてはぐらかされてしまう。こういう校長先生の態度に、私たちはいよいよ敵意を深めていくのだった。
ゲルニカが完成した。そして最後の制作委員会が開かれた。その会議には六年担任の四人の先生と教頭先生も同席した。ゲルニカをどうするのか、どのように展示するのか、吉永先生がその問題について説明した。
「ゲルニカをどのように展示するか、先生たちは真剣に話し合ってきました。そして最後の結論が出たから、そのことを報告します。ゲルニカは卒業式に飾ります」
ときっぱりと先生がいった。そのとき子供たちから、やったといった歓喜の声が上がり、パチパチと拍手が起こった。それほどうれしかったのだ。しかしその笑顔もだんだん曇っていった。その話はこう続けられていったからだ。
「卒業式に飾ることは決まりました。しかし正面にではなく、会場の後ろにゲルニカを貼ったパネル板が置かれます。正面のステージではありませんが、しかしゲルニカは後ろから君たちの姿をしっかりと見守ります。君たちはゲルニカに見守られて卒業していきます。そういうことになりました。そういう方法でゲルニカを展示します」
卒業式がやってきた。その朝、卒業式の会場となる体育館に入っていくと、ステージの上に日の丸が飾ってあった。ずらりと椅子がステージに向かって並んでいる。生徒の席があり、その背後がPTAの席だった。その華やかな式典の片隅にゲルニカが置かれてあった。まるでみんなの目から隠すように体育館の片隅におしやられていた。そのゲルニカをみたとき、私の目に涙がにじんでくるのだった。あんなに情熱をこめて、あんなに膨大な時間をかけて、あんなに希望に燃えて描いていったゲルニカが、こんな片隅に、こんな卑屈に、こんなにしょんぼりと置かれている。なにが私たちの卒業式を見守っているだ。
卒業式がはじまった。司会をする教頭先生がいった。君が代斉唱、全員ご起立をお願いしますと。みんながどどっと立ち上がった。私も立ち上がった。しかしそのとき私は叫んでいたのだ。
「私は歌えません。私は君が代は歌えません!」
そしてすとんと席にすわると、三組の子供たちもどどっと座っていった。式場にざわめきが起こった。吉永先生がびっくりして私たちの席まで飛んできた。しかしどうすることもできない。もっと驚愕していたのは教頭先生だった。なにかその様子はパニックに陥ったといった風だった。そのピンチを音楽の先生が救った。ピアノが奏でられると、体育館にはなんだか気の抜けたような君が代が斉唱された。
私たちの卒業式は卒業生の一人一人の名前が呼ばれると、校長先生の前に進み出て卒業証書を受け取る。そしてマイクの前に立って、感謝と決意の言葉を述べることになっていた。
「倉田佐織さん」
とうとう私の名前が呼ばれた。私は立ち上がり、校長先生の前に進みでて、両手で卒業証書をもらった。マイクの前に立つと、私は校長先生をひたとみつめていった。
「校長先生、どうしてゲルニカをステージの正面に飾ってくれなかったのですか。私たちは何度も何度も校長先生にお願いしました。しかしとうとうゲルニカを飾ってくれませんでした。ゲルニカは私たち六年生全員が、この小学校でのたくさんの思い出をこめて描いていったのです。この六年間は楽しい思い出ばかりではありませんでした。苦しくて心が夜のように暗いときがありました。朝がもうこないのではないかと思うほどのどん底がありました。だからゲルニカは遠い国でおこった悲惨な事件の絵だと思えませんでした。私たちの心がちぎれていました。私たちの心が叫んでいました。私たちの心が救いを求めていました。だからゲルニカは私たちの心の歌だったのです。私たちの希望の旗だったのです。その私たちに心の歌を歌わせないで、どうして君が代だけを歌えというのですか……」
「わかった、わかった。もうやめろ!」
と鋭い怒号が私を突き刺すように飛んできた。そしてそれを契機にPTAの席から一斉に野次と怒号が上がった。
「お前はもう引っ込め、君が代が歌えないのは日本人じゃない!」
「神聖な卒業式を汚すな!」
「引っこめろ、その子供を引っこめろ!」
大人たちがこのような激しい憎悪の野次を浴びせたのは、君が代斉唱のとき私が君が代を歌えませんと叫んで着席してしまったからだ。大人たちを私に注目していたのだ。野次と怒号はどんどん激しくなって、体育館はなにか騒然となっていく。そのとき吉永先生が立ち上がり、PTAの席にむかって、野次を制止するように両手をふりおろしながら叫んだ。
「みなさん、静かに聞いて下さい。子供の声を静かに聞いて下さい。お願いします。子供の声をまず静かに聞いて下さい」
しかしさかんに制止する先生の声を打ち消すように、さらに野次と怒号は激しくなる。その野次は吉永先生にも向けられていった。
「お前のような教師が、子供を駄目にするんだ!」
「責任をとれ。こんな子供をつくりだした責任をとれ!」
「教育長、この先生を懲罰にかけなさい!」
いよいよ激しくなる野次と怒号のなかでおびえながらも、しかし私は最後までいいきった。
「ゲルニカは、ゲルニカは、ゲルニカは私たちの心の歌だったのです。私たちの希望の旗だったのです。その私たちの心の歌を歌わせないで、どうして君が代だけを歌えというのですか。私たちの希望の旗を後ろにかくして、どうして君が代だけを飾るのですか。私はこのような卒業式をぜったいに認めたくありません。子供の声や叫びを拒否する校長先生のような人に、私はぜったいになりたくありません。私はいま強い怒りと悲しみをもって卒業していきます」
![]()
ゲルニカ事件――どちらがほんとうの教育か
さまざまなメディアが誕生し、あふれるばかりの情報の洪水ですが、しかしその核心たる日本人の精神は、いよいよ衰弱しているのは原田さんのご指摘の通りだと思います。情報の洪水とはすなわち言葉の洪水であり、言葉は一見あふれるばかりの豊穣さに満たされているように見えますが、しかし現代の言葉とはすぐに売れる言葉、すぐに伝播していく安っぽい言葉、なにか下半身だけをのぞこうとする刺激的で低俗な言葉があふれているのであって、それは言葉が成熟していくこととはまったく無縁なことです。ということは情報の洪水とは、荒廃の海をつくりだしていくということなのでしょう。
さて、原田さんにこのような長文のお手紙を差し上げる情熱にとらわれた主題ですが、しかしこの重く深い主題はこれから原田さんと二信三信のお手紙の交流のなかで、長い時間をかけて熟成していかねばならぬものだと考えますので、まずはその導入だけにとどめておきます。私は小さな塾を主宰して子供たちと生きております。そのこともあって「ひとりから」誌の第四号の特集にさまざまな啓示を受けるのでした。岡田さんや田淵さんが遭遇した出来事、小野さんの弁護活動や福田さんの子供の権利に対するまったく斬新な切り口。それぞれの報告に新鮮な驚きをうけましたが、しかしなんといっても私が深く思いをはせるのはゲルニカ事件でした(私ははじめてこのような事件があったことを知りました)。
小学六年生の卒業式でのあの一瞬、まさにゲルニカの絵そのもののような叫びは、はげしいいじめにあっていた彼女の魂の苦悩からきたものでした。そしてその一瞬は一瞬だけでは終りませんでした。彼女の町に右翼の街宣車がやってきて罵声をとばし、一家は村八分状態にされ、中学に進級するとそこでも陰湿ないじめにあう。その事件からすでに長い月日がたっているのに、彼女はいまだにその影を濃厚にひきずっているのです。彼女はあの瞬間、その胸に緋文字Aを縫いつけてしまったのです。
彼女の胸に縫いつけられた緋文字、それは苦悩と罪の徽。愚かな大人たちが刻印した大人たちの罪の象徴であり、日本の教育が強い覚悟で背負っていかねばならぬ日本の苦悩の象徴でもあります。なぜ一人の若者だけがこのような重い苦悩と罪を背負って生きなければならないのでしょうか。この若者の苦悩に出会った私たちは何をすべきなのでしょうか。原田さんが社会に送り出した労作「ゲルニカ事件――どちらがほんとうの教育か」はなぜ休刊なのでしょうか。なぜ日本の先生たちは教育の原点ともなるこの書を永遠のテキストとしないのでしょうか。ゲルニカ事件には日本の教育が必ずつきあたる根源的な問題がたっぷりと縫い込められているというのに。いまこそ私たちはゲルニカ事件を読まなければならないのです。
例えば、高校中退者の数は毎年十万人をこえ、それは一度に百の学校が地上から消え去ることに等しいのです。学校にいかない子供たちもまるでブームのように増えつづけています。そして学級崩壊です。これらの間題を根源的にさかのぼっていくと、ゲルニカ事件が鋭く提示した間題につきあたるのです。しかし教育の中枢にいる人々は決してこの問題に取り組まないでしょう。大多数の教師たちもまたこの問題を避けてしまうでしょう。それは日本の教育が体質的にこの間題を欠落させているからです。日本の教育とは集団を向上させることをその本質にしています。言い換えれば、日本の教育とはひたすら集団に個を埋没させることにあるのです。この体質を濃厚にもつ土壌のなかで、ゲルニカ事件があらゆる領域で敗退していくのはある意味では当然のことなのでしょう。そうであるならば、それだからこそ、私たちはゲルニカ事件の問題をくり返しくり返し社会のなかに投げこんでいかねばならぬと思うのです。
教育の本質とは集団を形成していくことではなく、個を創造し確立していくことにあるのだと。金住さんのいわれる自己決定権をつくりだすことのできる精神や魂をつくりだしていくことにこそ教育の本質があるのだと。そのことにしかと気づいた一人一人がそれぞれの領域でそれぞれのやり方で、地下水脈となって地中に深くしみこむまで、あきらめることなくその活動をつづけていくべきなのです。やがてその地下水脈は怒涛のように地上に吹き出してくる日は必ずやってくるはずです。
さて、私たちはどうすべきなのか。何をしたらいいのか。ここから新しい展開に入っていきますが、それには沢山の言葉が必要になりますので、最初のお便りはこのあたりでとどめます。原田さんとこのような深い交流ができることを大変幸福に思います。なにか深く大きなそして刺激的な果実がたわわに実っていくような予感がするのです。

最後の授業
これは北アルプスの麓に広がる安曇平という地のある町でおこった出来事です。すでにみなさんはその町の名前を知っていますね。あれだけ騒がれた事件ですから。その町の人々にはとてもつらいことですから、その町の名をA町としておくことにします。その町の名をつけた中学校もまたやはりA中学校としておきますが、この中学校は信州教育と尊敬をこめてよばれる数々の実践活動を生みだしていった輝かしい歴史をもった学校でした。この中学校に通う瀧沢隆君という中学生が、自宅の納屋で首を吊って自殺するという痛ましい事牛がおこったのでしたね。
残念なことに、まるで流行のように、子供たちがあちこちで自殺しています。子供たちの自殺があまりにも頻繁に起こるので、いまでは新聞記事にもなりません。しかしこの隆君の自殺事件はちがっていました。連日にわたって新聞もテレビも週刊誌も、なにかヒステリ一をおこしたと思われるばかりの騒ぎ方でした。どうしてこんな騒動に発展していったかといいますと、その事件を取材するためにつめかけた地元記者たちが、その学校の校長先生を取り囲んで、
「隆君は遺書を残していますが、この遺書を先生はどう思われますか?」
とたずねたのです。その学校の校長先生は篠田政雄さんですが、そのとき篠田校長はなにか吐き捨てるように、
「こんな貧しい遺書で死ぬなんてあわれです」
と言ったのです。驚いた記者たちは、
「貧しいですか?」
「貧しくて幼稚な遺書です」
「幼稚なんですか?」
「これが幼椎でなくてなんなのでしょうか。こんな幼稚な遺書で死んでいく子供はあわれにつきます」
校長先生はさらに取材を続けようとつめよる記者たちをかきわけて、逃げ込むように校門に消えていったのですが、そのときその一部始終をテレビ局のクルーが音声とともに録画していたのです。その映像とその会話が、各テレビ局に配信され、日本中にそのシーンが、それはもう繰り返し放映されていったのでした。
翌日の新聞も一斉にこの事を報じました。社会面のほぼ全面を、さらに社説までにとりあげて、校長先生の言動をはげしく非難するのでした。凄まじいのはテレビでした。昼のワイドショーで、夕刻のニュースショーで、さらには深夜のニュース番組で、いずれもトップニュースとしてこの事件を報じるのでした。
いったいこの事件をマスコミはどのように報じていったのでしょうか。そのあたりをある日の昼のワイドショーを子細に再現してみましょう。いかに日本中がすさまじい騒動の嵐につつまれたかがわかろうというものです。
まずその画面に重々しい悲しみの音楽がながれて、隆君の遺書が写し出されます。その遺書を声優が悲しみをこめて読んでいきます。
「お父さん、お母さん、由香、それとぼくの大好きなおじいちゃんおばあちゃん。ぼくが死ぬことをゆるしてください。ぼくはもう生きていくことはできなくなりました。もうつかれました。とても生きていく力はありません。HYSFNにもうぼくはつきあえません。ぼくはもう二度ほど死ぬ目にあっています。二年のときは日本海で死ねといわれたし、またこのあいだの台風のあと犀川横断のときも死にそこないました。だんだんバツゲームもひどくなって、今度はT先生の部屋をおそうなんてぼくにはできません。ぼくはHYSFNたちにつきあうのはもうつかれました。いままで五十万円たまっています。いつかぜったいに返そうと思っていましたが、返せなくなってごめんなさい。お父さんとお母さんにはいろいろと感謝しています。由香はぼくのぶんまでお父さんとお母さんを大事にして下さい。おじいちゃん、おばあちゃん、いつまでも元気でいてください。ぼくはみんなが大好きでした。ぼくが死ぬことをどうかどうかゆるしてください」
日本中を悲しませたその遺書の全文が読まれると、画面は中学校の校門の前に立つレポ一タ一を写し出します。そのレポーターは、演技なのでしょうが、なにか悲しみと怒りをないまじえたような表情をつくって報告をはじめます。
「この中学はA町の中心にそびえ立っています。ご覧のようにいかにも古い歴史と伝統を感じさせる学校です。隆君が在席していた三年二組の教室は、校舎の二階、ちょうどあのあたりにありますが、その教室には隆君の遺書の中にでてくるHYSFNという少年たちの机もあるはずです。隆君は十月二十日の深夜に遺書をかき、そして翌日自宅の納屋で首を吊って自殺したのですが、いったいなにが隆君をそのように追いつめていったのか。いまでは隆君の書き残した遺書でしか心のうちを推測できないのですが、しかしこの遺書には私たちに伝えたいメッセージといったものがたくさん書き残されているのです。そしてこのメッセージに書かれたものをたどっていくとき、隆君がどんないじめにあい、どんなふうに追いつめられていったかがわかるはずなのです。いま私たち取材班はこの隆君の死にいたる道をたどっていくことします。
なんでもこの遺書に書かれているHYSFNという子供たちは、先生たちにいわせるとごく普通の生徒たちだといいますが、しかしクラスの子供たちからみると、先生たちもちょっと手がだせないような不良グループだったようです。隆君もまたそのグループの一人だったようですが、しかし実状は、無理矢理そのグループに引き込まれた隆君は、何度もそのグループから抜け出そうとしたけど、そのたびに激しい暴力にあって抜け出せなかったということが真相だったようです。隆君の遺書がなによりもそのことを痛切に叫んでいます。この悲しみの遺書を、貧しくて幼椎だといった篠田校長、そしてこんなに追いつめられていたのに、少しも察知できなかった脳天気な教師たち。こういう悲劇を生み出していく日本の学校の実態にせまっていきたいと思います」
![]()
篠田校長にたいする取材はすさまじいばかりでした。学校はもちろん自宅まで大勢のマスコミの取材者たちが、二十四時間張り込んでその姿を捕らえようとするのでした。
隆君の葬儀が三日後に行われましたが、そのときも大変な騒動でした。篠田校長が車から降りてくると、何十人もの取材者がどっと襲いかかるように校長先生を取り囲み、マイクをつきたて、それぞれが質問をぶつけるのでした。なにかそれは獲物に襲いかかるハイエナといった光景でした。ようやくその取材者たちの群れから抜け出して祭場に入っていくと、一斉に険しい視線が校長先生に向けられるのでした。
校長先生が焼香する番がきました。そのとき親族のなかから突然猛々しい声が飛んでくるのです。隆君の叔父さんでした。
「お前なんか、焼香する資格なんてない!」
そして激昂したその叔父さんは、校長先生のところに飛んできて、校長先生の胸倉をぐいとつかむと、
「お前なんか帰れ、ここにくる資格はない!」
この興奮した叔父さんを、隆君のお父さんやお母さんが、必死におしとどめて席に引き戻しました。
校長先生は焼香台の前に立つと、隆君の遺影を見つめました。美しい笑顔です。少年の輝きがこぼれるばかりの笑顔です。校長先生は両手をあわせて、ずいぶん長く黙祷していました。そして焼香をおえると、遺族の列にむかって頭をさげ、退場しようと歩み出したとき、今度は隆君のお母さんが立ち上がって校長先生を呼びとめ、校長先生の前につつと歩みよるとこういいました。
「校長先生。先生はいま隆にどんな言葉をかけて下さったのですか」
「………………………………」
「まさか、幼椎な貧しい遺書を書いて死んで、あわれだとおっしゃったのではありませんね」
「………………………………」
「隆は校長先生をとても尊敬していました。校長先生はちょっとちがう、校長先生はちょっとすごいって。なにがちがうのか、なにがすごいのかわからないいい方ですが、でも隆にとってそのいい方は、最高のことを表現するいい方だったのです。隆はそんなにも校長先生を尊敬していたのです。その尊敬していた校長先生に、貧しい幼稚な遺書を書いたものだ、あわれな死に方をしたものだといわれて、どんなに悲しい思いをしているでしょうか。若くして無念のなかで死ぬと、その魂はいつまでも成仏できずあたりをさまよっていると聞きます。隆の魂はいまこのあたりにいるのです。隆の魂はまだ生きています。立派な遺書だった、美しい遺書だったなんていってもらうつもりありません。でもあの子はあの子なりに力いっぱい書いたのです。ですから校長先生、力いっぱい書いた遺書なんだね、力いっぱい生きたんだねって、隆の前でいって下さいませんか」
しかし校長先生はただ軽くお母さんの前に頭をたれると立ち去りました。この様子を固唾をのんで見守っていた参列者から、この非情な校長先生に怒りの声が投げつけられました。
「学校が子供を殺したんだ!」
さらにはこんな怒号も飛びました。
「お前たちは殺人者なんだ!」
そして参列者の怒りが頂点に達したかのように、参列者の一人が折り畳みの椅子を校長先生に向かって投げつけるのでした。
そのシーンを沢山のテレビ局のカメラが、さまざまな角度から一部始終とらえていました。そしてまた一斉にそのシーンがありとあらゆるチャンネルで流されるのでした。篠田校長にたいする非難はすさまじいばかりでした。なにか日本列島が一大ヒステリーをおこしたかのような騒動になりました。マスコミの攻撃は教育委員会や文部科学省に校長を処分せよと迫り、さらにはこの事件はいじめによる殺人事件だから、警察はただちに捜査を開始せよという論調になっていくのでした。

吉崎美里と絶交する手紙
小学六年生の工藤舞は、同じクラスの吉崎美里に手紙を書く。小学六年生が援助交際をしているのだ。こんなことが現実に起こっているのか。日本の子どもたちは実に六人に一人が貧困のなかで生きているのだ。そして吉崎美里からの手紙が工藤舞へ。そこには驚くべきことが書かれていた。
![]()
これまで私にとって君は美里だったけど、君と絶交するために吉崎と呼ぶことにする。もう私たちの関係って遠くはなれてしまって、いまさらこんな絶交の手紙を書いたってなんの意味ないことだと思ったりするけど。あと半年もすれば卒業で、吉崎とも永遠の別れだし、それまで私は黙ってたえていればいいことだとも思う。けれども、いま吉崎にこの手紙を書かなければ、私はこの先一歩もすすめない。受験はどんどん迫ってくる。塾にいってもまったく勉強できず、このままではなにか自滅していくばかりで、この手紙を書いて心の整理をつけるというか、自分の気持ちにけりをつけたいと思うのだ。
その日は、塾にいく日だったが、塾どころではない。とにかく君の命令は圧倒的で、私はその時間にびくびくしながら児童館にいった。驚いたことに、そのスタジオに信長がいて、信長をいじめていた男子グループ、松永と久保田と近藤もそこにいた。これってどういうことなのと私がたずねる前に、君はいきなり言った。
「あたしたち、これからバンドつくるから、あんた、キーボードやってよ」
私はすでに私立中学めざして、受験体制モードに入っていた。しかしそんないい訳など許さないとでもいうように、また君はきびしく言った。
「工藤のピアノは上級クラスだってきいたけど、その力をクラスに提供すべきだよ。工藤がお勉強で忙しいことはわかっているけど、みんなから選ばれたクラス委員なんだから、あんたがいますべきことはクラスのことなんだ」
そして一枚の紙片を私の手に差し出した。そこにはこう書かれていた。
二組バンド結成とスプリング・コンサートに向けて
日時 三月十五日
場所 五年二組の教室
対象 全校生徒(希望者の入場券をつくる)
歌 マライア・キャリーの「ヒーロー」その他。
スタッフ
マネージャー 木村信長
キーボード 工藤舞
ドラム 久保田康孝
ギター 近藤学
ベース 松永洋次
ボーカル 吉崎美里
私はしばらくそのコピーに目を這わせていたが、「バンドつくるっていったって、久保田はドラムをたたいたことあるの、ただ太鼓たたけばいいってもんじゃないと思うけど。近藤だって、松永だって、ギターとかベースなんて弾いたことないわけでしょう。これって全然むりな話じゃない」とあいた口がふさがらない、あきれてものがいえないといった感想をもらしたら、「そんなの、やってみなきゃわかんねえよ」と松永が、「工藤が入れば、バンドなんてちゃんとできるよ」と久保田が、そして「助けてくれよ、工藤、あんたの力が必要なんだ」と近藤が言った。
そしてそこにマネージャー役になるという信長が割りこんで、「だからね、つまりさ、このバンドづくりのコンセプトは、いまうちのクラスは荒廃しているっていうか、砂漠化しているわけだから、そこに父母たちが進出してきてクラスを監視するようになって、これってさ、もっとクラスを砂漠化しているわけだから、それでさ、クラスを根本的に立て直すのはバンドが必要だというか、バンドの力で砂漠に花を咲かせるというか、そういうことからクラスの荒廃を開拓していくというか、砂漠化したクラスに友愛の花を咲かせるということでさ」
信長がクラスで発言すると、みんな、クセーよ、クセーよといった声が教室内に広がり、また演説をはじめたよ、そんなクセー演説は区議会議員の親父と一緒に駅前でやってくれといった声が飛び交うのだが、しかしそのときは松永も近藤も久保田も、なんだか信長のそんな演説にうなずき、コンセプトだとか、荒廃を開拓していくとか、砂漠に友愛の花を咲かせるといったセリフにうっとりとなっている気配なのだ。
けれども私は逆に、信長のクセー演説に自分を取り戻して、「いきなりそんなこと言われても困るから、すこし考えさせて」と言って児童館を後にした。それがそのときの私の意志だった。つまりノーである。絶対にノーだった。私はすでに私立中学受験のシフトをとっていた。受験塾に高額の授業料をおさめ、週三回の塾通いをはじめたばかりだった。母親はとにかく自分の出身校に入れたいと焦っている。そんな体制をとっている私が、バンドづくりなんてことをはじめたら、彼女はたぶん発狂するだろう。
けれども家に戻り、あらためて渡されたコピーを見ていると、しみじみと吉崎という人間の大きさというか、深さというか、どんなに吉崎がクラスの危機を自分の存在の危機として立ち向かっているかということがわかった。私を驚かせたのは、その立ち向かい方だ。信長を猛烈にいじめていたのは松永や久保田や近藤だった。そのいじめる側といじめられる人間を同じステージにあげて、そしてバンドづくりに取り組むなんて。吉崎がその存在をかけて私のなかに打ち込んできたそのプランは、私の存在をぐらりと揺るがした。私はその夜、自分の意見を変えた。つまりイエスの側に立ったのだ。
そのバンドづくりに参加して、すぐにわかったことはスプリング・コンサートなんて絵に描いた餅だった。とにかく全員ど素人なのだ。それなのに吉崎の目標は限りなく高い。マライア・キャリーの「ヒーロー」に取り組むのだ。私はみんなに言った。
「こんなクソみたいな練習、はっきり言って無駄だよ、コンサートやりたいんなら、毎日集まって徹底的にやらなきゃだめだよ、土曜日や日曜日は、朝から集まるの、朝から夜まで徹底的にやるの!」
そんな私の挑戦にママはもう猛烈に怒りだし、パパが私の側に立ったのがさらに事態を悪化させて、私の家はちょっと崩壊っぽくなった。けれども、結局は私の人生は私のものだからと、私もまた春のコンサートにむけて、それこそ学校以外の全時間、全情熱のありたっけを注ぎ込んだ。なにか熱病にとらわれたかのように、バンドづくりに熱中できたのはロックなのだ。ロックは私たちの魂の底までとらえてしまう。ロックは私たちの魂の叫びなのだということがよくわかった。
コンサートが終わったとき、久保田も松永も近藤も私も泣いてしまった。一番大泣きしたのが信長だった。一人一人に抱きついて、声をあげてわあわあ泣いていた。けれども、吉崎だけは泣かなかった。それどころかぷりぷりと怒っていた。「ヒーロー」の歌詞をまちがえたって。あんなものはまちがいではなく、吉崎の歌ったヒーローこそ、私たちのヒーローだった。教室がいっぱいになり、廊下にまであふれた人たちの熱狂的な拍手は、そのヒーローにささげられたものだった。
六年生になって最初の日に、クラス委員の選挙があった。私は吉崎こそクラス委員になるべきだと思っていた。吉崎こそ崩壊寸前のクラスを救い出した子供なのだ。しかし選ばれたのは私だった。私は立ち上がって、その選挙に異議をとなえたというか、クラス委員になることを辞退したいと発言した。私は五年生の時にクラス委員に選ばれたけれど、その任務が果たせなかった。クラスは荒れ、父母たちが教室に見回りにくるほど混乱していった。そんなクラスにしてしまったのは、クラス委員の力がなかったからで、そんな私がまた選ばれるのは間違っていると言った。そして、いまクラスは一つにまとまった。素晴らしいクラスになった。そんなクラスにした人こそクラス委員に選ぶべきで、その人はみんなわかっているはずで、その人こそクラス委員になってもらうべきなのだと言ったとき、吉崎が叫んだ。
「工藤がしたくないからって、勝手に他人になすりつけんなよ!」
そのクラス会の後で、私は吉崎にどうしてあんな発言になってしまったのかを説明したけど、吉崎は工藤がクラス委員を辞退したいと発言するのは勝手だけど、それを私に押し付けるのは間違いだと言った。そこで口論になった。バンドづくりのとき、それこそ怒鳴りあいの喧嘩を何度もしたけど、それに比べたらそれは小さな争いだった。けれども、そのときから私たちの距離がどんどん離れていった。吉崎は私を無視しはじめ、私もまた自分の中に閉じこもっていった。とにかく受験塾のテストが毎月あり、その点数をあげるには、周囲のことを断絶して勉強に打ち込まなければならないのだ。けれども、私はいつも吉崎を見ていた。吉崎のことが気になり、どんどん離れていく吉崎との熱い交流を取り戻したいと思っていた。しかし吉崎はどんどん私との距離を引き離していった。
その日の昼休み、私は一人教室に残り、塾の宿題をしていた。私はそんな嫌なことをする子供になっていた。すると、がらんとした教室に吉崎たちが入ってきて、何やら内緒の話をしだした。私に聞こえないようにひそひそと話しているけど、しかし何が話されているのかほとんど聞こえた。こんなに大きくなるの、これがあたしたちのなかに入ってくるの、そんなこと耐えられない、あたしはぜったいにこんなことしない、馬鹿ね、女ならだれだってするのよ、行く行くってうめくらしいよ、来て来てじゃないの、入って入ってもっと深く入ってよ。耳をふさぎたくなる会話が飛び交っていた。私はたまらずに席を立って教室を出ようとしたら、野村が声をかけてきた。
「工藤さん、これがコンドームってもんなんだって、見たことないでしょう、こういうお勉強も必要だと思うけど」
そして、昼休みにも受験勉強している私を嘲笑するような、下品な笑いがどっと起こった。私は背中にいっぱいに怒りを見せて教室から出ていった。
七月に入ると、吉崎はしばしば学校を休むようになった。そして吉崎の悪い噂がいっぱい私の耳にも入ってきた。私はそんな噂をまったく信じなかった。グレース姫とか、エンコーとか、リトルプリンセスとか、テイチャーズペットとか。なによ、それっていう感じだった。それがみんな小学生の援助交際という怪しげな世界の隠語だということをはじめて知ったけど、だいたい私はエンコーという言葉さえ別の次元、別の宇宙の言葉だと思っていたのだ。ヒーローを歌った誇り高い吉崎がそんなことをするわけがない、宇宙の彼方にある別次元のような汚れた世界にまぎれこんでいくわけがない、と。
けれども、旗の台の駅のプラットホームで、吉崎の姿をみたとき私の信念がぐらついた。向こう側のプラットホームに立っていた吉崎は、まるで少女雑誌のグラビアから抜け出してきたようだった。ブルーのリボンを髪に巻きつけ、派手な化粧をしていて、空色のスカートはすかすかで、小鹿のような姿態をさらしている。私に気づいた吉崎は、笑いかけ、手をちょこちょこと振ったが、私は凍りついてしまった。あの噂の数々はみんな本当かもしれない。でも一人になるとまた思った。渋谷とか原宿にでれば、あんな風にどぎつく化粧した小学生なんていっぱいいる。そんな姿を見て吉崎がエンコーしているなんて思うのはやっぱり間違いだって。
ちょうどその頃、吉崎に関する噂の出所であるらしいホームページのアドレスを知った。その怪しいサイトを開き、「ミサトのちょっとあぶない日記」というページにクリックしてみると、裸の少女の写真が載っていて、日記風の短文が打ち込まれていた。「あたし、せんせえーの苦しみ、よーくわかる、うるせえガキどものお世話、ほんとうに疲れるよね、ごくろうさま、だからあたし、せんせーえのかわいいペットになってあげるんだよ」とか「あたし、せんせーえ、大好き、だからなんでもしちうゃんだよ、せんせーえの疲れたものをちゃんと立たせてあげるし、なめなめだってしちゃんだからね」とか。私はそんな吐き気がする落書きを読んですぐに思った。あの誇り高い吉崎がこんな汚れた落書きを書くわけがない。そこに張り付けられている写真だって吉崎ではない。顔を隠して撮られているが、私にはそれが吉崎でないことぐらいすぐにわかった。
夏休みになり八月に入った日だった。それまで何度も信長からメールが入っていて、そのメールの大半は、吉崎に関する情報だったが、その日のメールは情報ではなく命令だった。二組バンドの緊急会議を開くから児童館にきてくれ、と。二組バンドなんてもうとっくの昔に解散している。いったい緊急会議ってなんなのとメールを打ち返したら、とにかく児童館にきて、危機が迫っている、美里が危ないんだ、というメールが打ちこまれてきた。それでその時間に児童館にいくと、松永も、久保田も、近藤もきていて、信長は私たち四人にちょっと呆然とさせるようなことを話しだしたのだ。
最近、小学生の援助交際のサイトを運営していた人が逮捕され、なんでもそのサイトに品川の小学生数人が関係しているらしく、警察は関係した小学生たちを調べているらしいと切り出してきたのだ。信長のお父さんは、教育委員会や警察関係にもパイプを持っている区議会議員なのだ。そこから得た情報だった。信長はその情報をなんだか飛躍させたというか、妄想を拡大させたというか、このままでは確実に捜査の手は吉崎にも及んで、やがて吉崎が逮捕されるかもしれないと言った。そして例の演説口調で、
「だからね、美里が警察につかまったらさ、輝かしい栄光に包まれた二組バンドが汚されるっていうか、泥まみれになるっていうかさ、そんなこと絶対に許せないだろう、工藤さん、いまぼくたちがやることは受験勉強じゃないんだ、そう思わない、いまぼくたちが取り組むことはコンサートなんだ、二組バンドの第二回目のコンサートをやる、今度は体育館で、そこに全校生を集めてやるんだ、ぼくたちはまたコンサートに向かって燃え上がっていく、そうしたらさ、美里はまたヒーローになる、美里はヒーローなんだ、ヒーローがさ、なんでエンコーなんてやってんだよ」
信長はとうとう泣きだしてしまった。そんな信長をみて私の中にじいんと感動が走ってきた。バンドづくりのとき、吉崎はいつも信長に厳しく、「あんたがいじめられるのは、自分のことしか考えない人間だからよ、もっと全体のことを考えなさいよ」とか「あんたはすぐに泣く、その涙はいつだって自分のために流している安っぽい涙なのよ」とか、「いじめられたくなかったら、他人のために涙を流せる人間にならなくちゃいけないのよ、人のために涙を流す人間になってよね」って。そんな吉崎のしごきに信長がたえられたのは、信長は吉崎のことが好きだったからなのだが、信長はとうとう他人のために泣くことのできる子供になっていたのだ。
泣きながら訴える二組バンドの元マネージャーに、私たちはちょっとたじろいでしまった。けれども、君がその話をあっさりと拒絶したように、二組バンドを再結成して、クリスマス・コンサートを開くなんて不可能なことだった。それは信長の妄想がつくりだした夢のまた夢の話だった。そんなことできるわけがない。受験がもうすぐそこに迫っている。いま私たちが取り組まなければならないのは受験だった。
信長が泣いて訴えてきたその話を、そんな風に退けてみた。けれども、吉崎のことが何度も何度も私のなかによぎっていく。中学受験はもうに目の前に迫っている。いまは勉強に集中すべきだと思うけど、やっぱり吉崎のことが頭から離れない。そこで、そんな自分に鞭を入れ、私の道を歩くために、君に絶交を告げる手紙を書くことにしたのだ。吉崎と私をつないだ絆はマライアの「ヒーロー」だった。私にいま必要なのは、英語ではなく日本語だから、この歌詞を一行一行自分で訳してみた。間違っていたらごめんなさいということだけど、でもこれが吉崎に伝えなければならない私の絶交の言葉なのだ。
「そこにヒーローがいるじゃない、自分をしっかりとみてよ、自分はいったいなんなの、自分はいったい何をしているの、怖がることはない、自分をしっかりみつめてよ、そこに答えはあるんだから、絶望でふさがった苦しみの底から、ヒーローがやってくる、胸がつぶれるばかりの悲しみの底から、ヒーローがやってくる、苦しみに打ち勝つ力を手にして、勇気と希望を手にして、ヒーローがやってくる。ヒーローは自分の中にいるんだよ、世界にたった一人で立ち向かう旅、それは果てしなく続く長い道、だれも助けてくれない旅、頼れるものは自分だけ、でもどんなに苦しくとも、どんなに暗い茨の道でも、希望をしっかりとたずさえて歩き続けていけば、やがてそのとき、きっと私たちの未来につながる道がみつかるのよ」

南の海の島
その遠く隔てた距離のために、彼とは卒業してからたしか二年目か三年目に一度東京で会ったきりだった。しかし年賀状とか、あるいはちょっとした近況のやりとりは続けていたのだ。ところが三年前、ひどく謎めいた、なにかただならぬ手紙をよこしたあと、ぷつりと音信を断ってしまった。それは私とだけではなく、彼と親しくしていた共通の友人にたずねても同様な返事がかえってきたから、私たちの前から姿を消さなければならない、なにかただならぬ事件といったものが、彼の身の上に起こったのかもしれないと思ったりした。
実際、その手紙は謎めいていた。分校をつぶしたとか、子供を殺してしまったとか、一家を虐殺したとか、村をつぶしたとか、ぼくは裏切り者だとか、この罪を永遠に許さないといった言葉が書かれていたのだ。しかしそれ以上のことはなにも書かれていない。いったい村をつぶしたとはどういうことなのか、子供を殺したということはどういうことなのか、一家を虐殺したとはどういうことなのか、私は二度ならず三度まで手紙をしたためたのだが彼からの返事はなかった。
そんな彼のことがずいぶん気になっていて、幾度か彼の住む島を訪ねようとしたが、飛行機をつかっても最低一週間、もし海が荒れて船が欠航でもしようものなら二週間近くの休暇を覚悟しておかねばならない。そんな長い休暇をとるには一大決心を要することで、なかなかふんぎりがつかずにずるずると時を重ねていたのだ。
ところが今年の賀状の束のなかに、彼の賀状もまじっていた。それを手にしたとき、どんな事態に見舞われたのかわからぬが、彼は再び立ち上がったと思った。彼は挫折することや絶望することを禁じられた男だった。挫折や絶望のなかにではなく、理想のなかに倒れるためにこの世に放たれた男だったのだ。
彼の賀状ほどうれしいものはなかった。というのはその年が終わろうとする十二月の半ばに、四年という長かったのか短かったのかわからぬ結婚生活にピリオドを打って、私は離婚したのだ。私と彼女を引裂いた亀裂はもうずいぶん前から走っていて、そのピリオドはいわば私たちの解放であったのだが、離婚という現実にいざ直面してみると、やはり十分すぎるほど打ちのめされた。そんなときはるか遠方より思いがけない、しかし私が一番会いたかった男からの便りは、光のない洞を徘徊しているような私には、なにか一つの救いのような意味をもっていたのだ。
幸い私たちには子供がいなかった。仕事をもっている彼女が子供をつくることを始終拒否したのだが、今にして思うとはじめから彼女はこの日がくることを予感していたのではないかとも思えるのだった。そんな冷静な読み方をしていた彼女に新しい憎しみが湧くのだが、離婚とはこのどろどろとした感情の泥流があとからあとから押し寄せ、暗い淵へ暗い淵へと押し流していくことだった。どこまでも沈みこんでいく気持ちのバランスを取り戻そうと、男と女が一緒になることも別れることも、同じ次元の行為なのだと思おうとした。しかし離婚と結婚とはまるで別の次元のことだった。離婚とは切り崩していくことだった。なにもかも、ことごとく、ずたずたに切り崩していくことだった。
その日はぐずぐずと雨が降っていた。いつものように残業を終えてアパートに戻ってみると、部屋がすっからかんになっていた。彼女の持ち物がすべて運び出されていたのだ。私の生活が困らぬ程度のものは残していってくれたのだが、小さな部屋を占領していたタンスやら鏡台やら彼女の机やらを運び出されたあとは、ほとんど空っぽに等しかった。それは前から二人のあいだで了解ずみのことだったが、いざその光景を目の当りにしたとき、なにか私の内部がざっくりとえぐりとられたように思えた。その場にいたたまれなくなった私は外に飛び出し、雨のなかをあてどもなく歩きつづけたが、私は人を愛することができない失格者であり、人生の脱落者なのだという声がどこまでも追いかけてきた。
私の会社は事務機器メーカーとしては日本で一、二を争う会社だった。給料だってボーナスだって悪くはなかったし、ずっと本社勤めでいわば陽の当たるポストを歩いていた。次第に大きな仕事を受持つようになり、そのことに情熱を燃やしていた。私はそんな生き方になんの疑問ももたなかった。ところが離婚したあたりから、なにかさっぱり仕事が面白くなくなっていった。ひどく醒めた目で、いったいこんなことをしてどうなるのだ、結局商品をばらまいて、金をせしめていくだけのことではないか、といった調子で自分の仕事を眺めるようになったのだ。いったんそんな眺め方をしてみると、次々に疑問が湧きおこっていくのだった。これでいいのだろうか。こんな人生でいいのだろうか、と。築き上げてきたものがどっと崩れていくなか、最後の砦までも疑いだしていたのだ。
ちょうどその頃、友人の紹介で一人の男が私をたずねてきた。私の会社のオフイスは最新の事務機器がならび、モデルルームになるほど垢抜けていた。そんななかにあらわれたその男は、あまりの場違いさにちょっとおろおろしていた。浅黒い肌をしたその男は、どことなくみすぼらしかった。履いているズックの靴の小指のあたりが、すりきれていて中身が見えていた。男は小井丸だと名乗った。彼はインド中部のアーマドガナルという所から出てきたのだった。
私は彼にすぐに好意をもった。どこかでこういうタイプの人間と会ったことがあり、なにかひどくなつかしい思いにとらわれた。与え続ける人間のにおいなのだ。常に自分を与え続けるタイプの人間だということをその全身ににじませていた。だれなのだろうか、いったいどこで会ったのだろうかと、しばし思案をめぐらせたが、小井丸と別れたあと、それがだれなのかわかった。樫山だった。風貌はまるで違っていたが、そこから漂ってくる雰囲気がそっくりなのだ。小井丸はインドの奥地で学校づくりをしているのだった。
学校といっても寺小屋に毛の生えたようなものだった。しかしそのあたりのいくつもの部落から二百人近い子供たちが通ってくるというのだ。何枚もの写真をみせながらその学校について説明したあと、ちょっと言いにくそうに鉛筆を寄附してくれないだろうかと切り出した。私はどのぐらい必要なんですかとたずねたが、その数があまりにもひかえめだったので思わず苦笑してしまった。鉛筆が手に入ったとしても、ノートといったものはあるんですか、消しゴムだって、筆箱だって、色鉛筆だって、クレヨンだって、と私は日本の学校で使う文房具をあげていった。そのとき私はこの男のためにひと肌ぬいでやろうと決意していたのだ。私はなにかに憑かれたようにそのことに熱中した。部長や専務にまで働きかけ、私の管轄する支店や小売店などにも何度も足を運んで、二百キロ、ダンボール箱にして十個になるまでの学用品を集めて送りだしたのだ。
小井丸から驚きと感動をにじませた礼状が届き、それに追いかけるように、私が送った鉛筆やクレヨンでかいた子供たちの手紙や絵をつめこんだ小包が届いた。その子供たちの絵は、私に学生時代のある熱い体験をいやが上にも思いださせた。そしてそのなかに百人近い子供たちが、貧弱な木造の校舎を背にしておさまっている写真も同封されていたが、その写真をくり返し眺めているうちに、なにかそのなかに私の魂といったものが吸いこまれていくような気がした。彼に小包が無事に着いたことを感謝する手紙を書いたとき、そのことにふれ、自分もまたその地であなたと同じような情熱を燃やせたら幸福だろうなと書いたのだ。
しばらくしてまた彼から長文の手紙が届いた。レター・ぺーパーに小さな文字でぎっしりと書きこまれていたその手紙は、《日本人特有の婉曲な表現なのでしょうが、あなたの手紙をぼくは馬鹿だからまともに受けました。そしてあなたにこの地にお誘いする手紙を書くことにしました》という書き出しではじまっていた。そしてその地で格闘してきた彼の歴史といったことがめんめんと綴られ、いまなお困難な状況にあり個人の力ではどうすることもできない障害の山がいくつもあり、ぼくの小さな行為など乾いた砂漠に流しこむコップ一杯の水ほどの意味しかないという思いにとらわれ、幾度も絶望と無力感に襲われると書かれていた。
もしその手紙がただ甘い誘いの手紙、未来は薔薇色に包まれているとか、大きな可能性が一つ一つ実現されていくとかいった明るい言葉が書かれていたら、私の心はかくも大きく動きはしなかっただろう。小井丸の赤裸々な吐露が続き、ぼくの小さな行為など、砂漠のなかに流しこむコップ一杯の水にすぎないのではないかという無力感に襲われるというくだりを読んだとき、私はいま自身が落ちこんでいる無力感とか虚脱感は、なんと小さくけちくさいのだろうと思わずにいられなかった。そして自分もまた小井丸のような生そのものが燃焼できるような人生を歩んでみたいという思いに、はげしくとらわれるのだった。
私にはたった一週間にすぎなかったがある熱い体験があった。夏休みに入ると、宗教部の部員たちは、そのころ日本のチベットなどといわれた岩手県の葛尾村を目指す。その村でなにをするかというと、村の子供たちと劇づくり、それもミュージカルを作り上げるのだ。そんな活動がもう何年も前から行われていた。私もまたその夏、葛尾村を目指したのだ。東北本線の沼宮内という駅で降り、そこから一時間半もバスにゆられ、いくつもの峠をこえていく旅に、なるほどそこは日本のチベットだと思った。村に入ると私たち一行は大歓迎された。村の学校の校庭で歓迎式といったものが村の人々が見守るなかで行われた。彼らの活動がすでに深くその地に根をはっていることに、私はひどく感動したものだ。
その日から村の子供たちとの活動がはじまった。村の子供たち、村の大人たち、そして東京からきた大学生たちでミュージカルの舞台を作り上げるのだ。一週間の滞在だった。舞台装置がつくられ、コーラス隊やちょっとした合奏団がつくられ、ステージで演じる子供たちはセリフをおぼえ、さらに歌いながら踊り、踊りながら歌わねばならない。なかなか高度なステージを樫山たちはつくり上げようとしていた。発表会の日がやってきた。小学校の体育館にはそれこそ村中の人々が集まってきた。その劇は素晴らしい出来だった。私たちの熱意に子供たちはしっかりとこたえてくれたのだ。
別れの日がやってきた。子供たちは停留所まで見送りにきた。バスに私たちが乗り込むと、もう子供たちは泣きだしていた。そしてバスのあとをどこまでも追いかけてくる。私のなかに熱いものがつきあげて胸がふるえた。東京に戻ってきてもその感動の余韻がいつまでも残っていて、経済学部に籍をおきただ漠然と会社員になろうとしてきた私は、むしろ教師に向いているのかもしれないと思ったが、もう針路を変更するには遅すぎた。
小井丸に会ってからその熱い体験が幾度も蘇ってくるのだった。そしてあれこそ私の中心なのではないのか。あの体験こそ私がずっと求めていたものではないのか。樫山という男に強く心ひかれてきたのも、僻地に赴任した彼のことがいつも気になっていたのも、そしてインドの奥地で苦闘する小井丸にはげしく心ゆさぶられるのも、あの体験があったからなのだ。あれこそ私がこの地上に立つための体験だったのではないかと思うようになった。もう私の心の動きを止めることはできなかった。小井丸に私の決意を伝えると、あなたがくるなと言っても私はいくつもりです、私はあなたのもとでもう一度人生を最初からやり直してみたいのですという手紙をしたためると、次の日はもう会社に辞表を出していた。
そして旅立ちの日を六月の半ばときめると身辺の整理をはじめた。離婚によって私は丸裸同然だったから、もう整理するものなどないに等しかったのだが、それでもすべきことは沢山あった。もう二度と日本に戻ってこないなどとは思わなかったが、それでも数年間はどんな事態に見舞われても戻るまいと決意していたから、実家はむろん親戚とかさらには私を愛してくれた先輩や友人たちには、きちんと挨拶をしておこうと思った。そんななかどうしても会っておかねばならなかったのは樫山だったのだ。
全身白く塗装した南海丸は二百五十トン、定員五十人という連絡船だった。この船が飛び石状に点在する七つの島を、五日間もかけて周航するのである。深夜の船出は、乗客がわずか十二、三人だということもあって、何やら密航船か落人たちを乗せた逃亡船かといったものさびしい風情に包まれ、腹の底に響く機動の音もどことなくたよりがなかった。
月光があたりをこうこうと浮かび出す夜で、桜島が雄大な裾を夜の底にひろげていた。私はこの山を見るのがはじめてだった。デッキに出て、海の風をうけながらその山を眺めていると、学生時代に読んだホーソンの「ザ・グレイト・ストン・フェイス」という物語を思い出していた。巨大な岩壁に自然が人面の像を刻んである。何か永遠のあこがれのような気高さをたたえたその像を毎日見上げながら育った子供が、年老いてみると実はその像そっくりだったという物語である。それと同じようにこの地に住む人々には、桜島はただの一風物ではなく、精神の領域にそびえ立っているように思えた。
あの風変わりな樫山英雄もまたこの山を見ながら育ったのである。いったい何度この山を友か恋人でも語るような熱い調子で語ったことだろう。なるほどいつまでも見飽きることがない。写真などで見る陳腐さはどこにもなく、ある精神を投映させる風格があった。樫山という男のあの不思議な深み、あのとらえがたい高みは決してこの山とは無関係ではないように思えるのだった。
湾を抜け、大海原に出ると小さな船は大きく揺れはじめた。次第に気分が悪くなっていった私は、畳の上にごろりと横になっていると、酔い止めの薬がきいてきたのかいつの間にか眠りに落ちていた。幾度もなる汽笛の音で目を覚ましたときは、すでに夜があけていた。デッキに出てみると最初の寄港地である前之島が海上に寝そべるように横たわっていた。早朝の大気は南の海とはいえさすがに冷たかった。たったいま地平線を昇ってきたのであろう太陽の火の矢を斜めにうけた南海丸は、またボウーと汽笛を鳴らし、突堤をゆっくりと回って小さな港内に入っていった。
人を下ろし荷を下ろした南海丸が前之島を後にしたころには、もう太陽は頭上に昇り、南国らしい熱い陽をちかちかと降り注いでいた。海は紺碧、空は抜けるような青で、雲一つなかった。次なる寄港地である平島の島影が、ぼんやりと地平線にその姿を見せている。ここは海の道だという。一つの島が消えると、次の島が現れる。羅針盤を持たぬ時代に生きた人間たちはこの海の道を通って、大陸にあるいは日本列島に渡ったのだ。
海の道は美しかったが、うねる波、揺れる船にまたおかしくなってきた。船室に戻り、今朝飲んだばかりの薬を飲みこんでごろりと横になっていたが、吐き気と頭痛は興じる一方で、とうとう胃袋の中身をすべてぶちまけるように吐いてしまった。それからはもう地獄の苦しみだった。吐き出すものがないのに吐きつづけなければならない。ギシギシと揺れる船は全身をねじっていくようだった。樫山にはこの苦しみを乗り越えなければ会えないというわけだ。いまさらのように彼との距離の遠さを感じるのだった。
平島から瀬戸島、千石島、笠戸島と回った南海丸が、樫山の住む姫島を間近にとらえたのは、鹿児島を出港してから二日目の朝十時ごろだった。五月の陽光をうけて白い砂浜がきらきらと輝いていた。緑につつまれた丘陵がゆるい起伏を描いている。おだやかで柔和なたたずまいをした島だった。とうとうきた、これでようやく地獄の苦しみから解放されると思った。しかしそれにしてもなんという遠さなのだろう。まるで地の果てにきたように思えるほどだった。

高尾五郎の代表作「ゼームス坂物語」四部作は、清流出版より刊行されています。
第一巻 木立は緑なり

金字塔のまぶしさ──竹内敏
さわやかである。しかもそれは口当たりのいい炭酸飲料ではなく、ビールのようにこくがあるのだ。「木立ちは緑なり」という表題からして颯爽としているではないか。それはまた白樺派のような理想主義があふれてはいても、民衆の切実な現実に根ざしているという点では、白樺派をこえている。九編からなるオムニバス風の物語にそれぞれ個性的な子供やその親が登場する。そして作者の分身を思わす塾教師の長太、児童館職員の弘、さらには智子の自立のドラマを伴走させることによって重厚な流れを形成している。あとに続く自分にとって、この金字塔はあまりにまぶしい。しかも、この金字塔は、向こうにあるのではなく、向こうから自分に迫ってくるのである。木立は緑なり、君はどうするの? と。(品川児童館)
第二巻 あの朝の光はどう

ここに教育の本質が──盛岡哲也
教育の育の字は、逆さの子に肉のなかで一番おいしい羊の肉(月)を食べさせるという意味である。つまり教育というのは本来、恵まれない不遇な子供たちにこそ最もおいしい羊の肉を与え、生きる力を培っていくということだ。「ゼームス坂物語」二巻を読み終わって頭に浮かぶのは、その教育の本質を描いた本であるというこだ。ストーリーの展開がまたすばらしい。読んでいくうちにどうなっていくのだろう、どんな結末になっていくのだろうかと、途中で止められず、時間も忘れてページをくる。そしてストーリーの山場には何度も、熱い感動の涙が胸のそこから止めどなく流れてきた。この物語が多くの人々に愛読され、共感の輪が広がることが、この本の出現の真の意義であると考えるのは私一人であろうか。(教育評論家)
第三巻 山に登りて告げよ

透明な風が吹き渡る──服部みずほ
「ゼームス坂物語」の一部と二部から私はたくさんのフレーズをノートに写しました。子供たちの姿を見失ったとき、教師としての自信を失った時などによくそのノートを開き、そのフレーズを指でなぞるように味わいます。教師の姿勢や、教育のあり方を根源的ところで問いかけてくるからです。
第三部もまた魅力的な子供がたちがたくさん登場してきますが、なかでも茜さんってなんて素敵な少女なのでしょうか。本当に透明な風が吹き渡っていきました。望月先生に次々に襲いかかる悲劇。弘さんはこの悲劇の底からどのようにして立ち直っていくのでしようか。現代という時代に翻弄される三人。しかし押し寄せる荒波に真っ直ぐ立ち向かい、新しい道を切り開いていこうと英雄的な戦いをする三人。これはまさしく現代に叙事詩です。第四部が待ち遠しく仕方がありません。(小学校教師)
第四巻 大いなる旅立ち

希望と祈りの物語──安藤達雄
私もまた智子と同じように教師生活にピリオドを打ち下町で小さな塾を開設したとき、はじめて教育の深さや大きさや怖さがわかっていった。子供たちの目をしっかりと見つめ、子供たちの苦しみや歓びを自分のものとしなければならなかった。それはこの小説に書かれている通りだ。この小説はまるで自分のことが書かれているのではないかと思った。そして驚いたことに子供たちがこの物語に熱中しだしたのだ。この小説は決してやさしくはない。難しい漢字もたくさん出てくる。それでも子供たちは懸命にしがみつき読んでいくのだ。そして全巻を読みきったある子がこういった。「先生、ぼくはこの本を読んで、はじめて生きるということの意味がわかった」と。子供たちからこのような深い言葉を引き出してくる「ゼームス坂物語」。これは高尾五郎の輝かしい勝利以外なにものでもない。(塾教師)

リターン
2600円コース
高尾五郎著
ゲルニカの旗 南の海の島

A4版 360ページ
一冊一冊が手作りです。生命の木立となって、時代とともに成長していく本です。カラーの挿絵が六点挿入されていて、一冊一冊が工芸品のように作られていきます。誰でも本が作れる、誰でも本が出版できる、誰でも出版社が作れる、このコンセプトによって「草の葉ライブリー」は、高尾五郎著「ゲルニカの旗 南の海の島」を読書社会に送り出します。地平を切り拓いていく本です。

資金の使い道について
制作費
人件費
広報費
リターンの送料
CAMPFIRE掲載手数料、決済手数料
に充当させます。









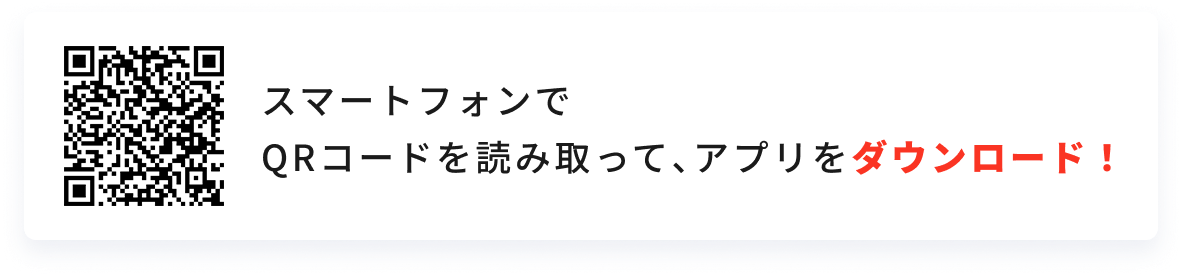


コメント
もっと見る