
それは二〇一〇年のことだった。信州を襲った台風が、明科神宮に立っていた樹齢三百年の銀杏の大木を倒すのだが、その大木は鎌倉時代に建立された蔵の上にどっと横転した。無残に押しつぶされた蔵はもはや解体する以外になく、その作業をすすめていると、その蔵の下に強固に防護された地下倉があった。その地下倉に鎌倉時代の財宝や刀剣や仏像などが所蔵されていたのだが、そのなかに日本の文学の歴史を塗り替える「三浦家所蔵新編竹取物語」という文書もまた発見された。

信州の民話伝承館「おはなしのおうち」にて
まあまあ、いらっしゃい、大きくなって、もう夏海ちゃんではなく夏海さんですね、ああ、なんてことなの、一瞬、お母さんが現れたのかと思ったぐらい、ほんとうにお母さんに似てきた、大学の国文科に合格しましたっていう手紙をもらったとき、ぱあっと思い浮かんだのは、お母さんに連れられて、ここにやってきたときの夏海ちゃん、あなたはいつも「おはなしのおうち」にくると「おばさん、おばさん、あのお話して」って、あのお話っておぼえているかしら、夏海さんがその頃一番好きだったお話、
昔昔のことでごせえますよ、ある村に、お爺さんとお婆さんが住んでおったんでごぜえます、お婆さんは、川へ洗濯に、お爺さんは、山へ芝刈りにいったんでごぜえますが、お爺さんは峠をこえると、よっこらしょと背負子をおろし、鎌さとって、芝を刈ろうとしたそんとき、ぷっとおならをしたんでごせえます、お爺さんは、芝を刈らずにくさ(草)かったんでごせえますねえ。
あなたはこの話しをはじめると、両手を口にあてて、もう笑うまい笑うまいと必死にこらえるけど、お爺さんがぷっとおならをしましたっていうところにくると、もうこらえきれなくなって、かわいいお口をいっぱいあけて、ははははって笑って、なんてかわいかったんでしょう、あなたのその笑い声だけで、おばさんは元気もりもりになったものよ。

お母さんが亡くなってもう三年になるんですね、おばさんはいつもお母さんが亡くなった日には、お母さんが出した本や論文をいっぱいここに積んで、お母さんの好きだったワインをあけて、おばさんはお酒は飲めないけど、でもその日はちびりちびり飲みながら天国のお母さんとお話ししているのよ。
夏海さんもお母さんが亡くなって、つらい日が続いたんでしょうけど、とうとう大学生になったのね、国文科に入って民話の研究をしたいなんて、やっぱりお母さんの魂があなたのなかにしっかりと流れているってことなのかな、あなたもこれからだんだんわかっていくことですけど、お母さんは立派な仕事をした国文学者でした。
お母さんの名前を一躍有名にしたのが、ここにある「竹取物語論」という本、この本にはおばさんもいっぱい思い出があるの、お母さんは民話を採集するために日本各地を回ってたけど、その取材の旅の帰りにはいつもここに寄って、新しく採集してきた民話を、それはもう目をきらきらさせて話してくれたのよ、そのお母さんが、あるときこう、おばさんに訊いたことがあるの。
三好さんは、なぜ竹取物語を語らないんですかって、おばさんは、すぐにいったんだわ、「ああ、あれは、ぜんぜん好きになれんわ」ってね、そしたらお母さんも、まったく同じだというじゃないのよ、それからもう二人で「竹取物語」をぼろくそにけなしあったんだわ、なあに、あのかぐや姫っていうのは、上げ膳下げ膳のお嬢様暮らしで、さんざん男をもて遊んでおいて、お迎えがきたからって、はい、さようならって月に帰っていく調子のいい女じゃないのってね。

いったいあの姫は、何をしに地球にやってきたわけなんだろうね、あの女がやったことといったら、お爺さんに成金御殿をたてさせたことぐらいじゃないの、いってみれば、成金思想とか拝金思想とが物語の根底にあるんだわ、それに天皇さまにだけには、ひらひらと媚びを売るいやらしさ、日本人のもっている、もっともいやらしい精神をたっぷりと縫いこんだ物語ということになるわけさ、出てくるのは、つまらない男ばかりだけど、唯一まともなのは、大伴御行(おおとものみゆき)という男ぐらいで、彼だけはちゃんとかぐや姫の正体を見抜くんだわ、あの女は大悪党だって。
二人でそんなふうにさんざんけなしたら、なんとその一年後に、お母さんは「竹取物語論」を発表するんだわ。「竹取物語」は欠陥だらけの底の浅い、精神の貧困さを露呈した文学であり、このような貧弱な物語を、まるで物語の源流のようにたてまつってきたために、日本の文学は五百年遅れたってね、もうそれは言葉するどく論じているんよ。
この本が世にでると、大変な反響を呼んで、国文学の世界だけでなく、新聞や雑誌までにその騒動はひろがっていって、あちこちで竹取物語論争が起こったもんだわ、学者の世界というところもまた封建的だから、お母さんもそれはひどい攻撃をうけたけんど、しかし攻撃されれば攻撃されるほど、いよいよこの本の価値は高くなっていって、その騷動がおわってみると、それまで古典文学の神様的存在だった竹取物語は、無残なばかりに地に引きずり下ろされてしまったんだわ。

しかしお母さんがこの本を書いた目的は、この物語の価値を暴落させることでも、地に引きずり下ろすことでもなかったんよ。お母さんは、この本の最後の章で書いていることだけんど、竹取物語には、たった一行だけど不思議な言葉が書かれているのよ、それは月からの使者がきて、かぐや姫を迎えるときその使者がいうんよ、その姫は月の世界である罪を犯した、その罪のために地球に追放されたが、しかしその罪もいま許されて月に帰ることになったってね。
いったいかぐや姫は、月でどのような罪を犯したのか、そして地球でどのようにしてその罪をつぐなったから、月に帰還することができたのか、その謎をひめた一行があることによって、竹取物語の価値はかろうじて救われている、この一行があるために竹取物語は、現代によみがえる道が残されているって書いているんだわ。
そしてもし、現代の物語作家が、この謎の一行に光をあてて、新しい竹取物語を書いたら、原典である古い竹取物語そのものもまた、新しい生命がそそぎこまれて現代に蘇っていくだろうってね、つまりお母さんがあらわしたこの本は、現代の物語作家たちに対する挑戦でもあったんだわね、一千年も生きてきた日本の物語の原形をなす作品だから、いまの子供たちや若者たちの心にすうっと入っていける物語に再創造して蘇らせてほしいってね。

しかしそんな物語はうまれなかったわ、鋭い問いを投げかけたお母さんも去ってしまった、竹取物語は結局はそれだけのもんだって思っていたんよ、ところがとうとう、おばさんはお母さんが待望していたその作品に出会ったんだわ、ここから車で三十分も走れば明科という町にでるけんど、そこに立っている明科神宮の土蔵のなかから『三浦家所蔵新編竹取物語』という古文書が発見されるのよ。
歴史をひもとけばわかることだけど、三浦家というのは鎌倉時代に三浦半島に興隆した一族なんだわ、頼朝が鎌倉に幕府を開いて以来、幕府をささえてきた豪族であったけんど、宝治元年に、いわゆる宝冶の乱で、三浦一族は法華堂にたてこもって、一族五百余名がことごとく自害していく、そのときその乱が起こる直前に、三浦家再興の時のために三浦家所蔵の文書などを、はるか信州の地にまで運んできたという言い伝えがあったんよ、明科神宮寺もまたその一族が建立したものであるといわれてきたんだけど、そのことがその文書の発見によっても裏付けられたということになるんだわね。
その古文書は、信州大学の小山先生たちのグループによって解読され、いまもその作業は続行中だけど、おばさんは小山先生とは昔からのお友達で、その解読作業に加えてもらったんよ、毎週のように小山先生はこの「お話のお家」にやってきて、一行一行の解読の成果を説明してくれるんだけんど、それはもうぞくぞくするばかりの興奮の日々だったわね、それは大変な物語なんだわ、なによりも驚いたことは、なんとその物語には、お母さんが指摘した、かぐや姫が月の世界で犯した罪がなんであったかという謎が、それは見事に解き明かされているんだわ、なにかこの物語は、あの謎の一行に光をあてるために、書かれたのではないかと思われるばかりなのよ、ということは、なんと七百五十年も前の鎌倉時代に、お母さんや私たちと、同じことを考えていた作家がいたということになるわね。

竹取物語を面白くしているのは、かぐや姫に求婚した五人の皇子の冒険譚といったものだけど、その冒険というものがどれもこれもけち臭いというか、こすっからいというか、嘘をついたり、偽装したり、山中に身を隠したりと、その頃の貴族の実態を暴いているといえばそれなりの意味があるのだろうけど、まあけちくさい人物ばかり、ところが、明科神宮で発見された竹取物語には、五人の皇子たちが人間の苦悩もった人物として描かれているの、彼らが背負ってしまった悲劇には、なにやらシェクスピアの劇のような深さがある、そうして皇子たちを実際に、海ヘ、陸ヘ、砂漢ヘと旅だたせている。そのことがこの物語を宇宙的規模にしている。
五人の皇子の物語のなかで、最後に登場するのが、石作皇子という皇子だけど、この皇子が長い放浪の旅を終え、瓦礫の山にぬかずいて、慟哭しながらいう台詞があるの、その場面でおばさんも思わず慟哭してしまったのは、この物語がまさに人間の苦悩というものを彫り込んでいるからなのね、おばさんだけじゃないわよ、きっとこの物語を語る語り手たちのだれにも、この皇子の苦悩の魂がのりうつって、慟哭しながらその台詞をいわなきゃあならんだろうさ。
そしてこの竹取物語をさらに魅力的にしているのが、原典にはない永吉という若者を登場させたことにある、竹取物語はもともと貴族たちを登場させた貴族の物語だった、しかしこの鎌倉時代の作者は、貧しい竹採り村の若者を登場させることによって、私たち庶民の物語にしてしまったのね、永吉を登場させることによって、かぐや姫は人々に愛される姫になったともいえる、永吉に愛されるかぐや姫はなんて愛らしいんだろう、だからこそ姫が月に帰っていくシーンが、一層ドラマチックになっているのね、どうしてこんな作品が七百五十年も眠っていたんだろう、もしこの物語が鎌倉時代に、いいえ、室町時代でも、江戸時代でもいい、世にでて広く読まれていたら日本の文学は、もっとちがったものになっていたでしようね。
夏海さんから大学の国文科に合格しましたって、はずむようなうれしい手紙をもらったとき、入学のお祝いになにか贈り物をしたいといろいろ考えた、でもおばさんは貧乏だから高いものは買えない、それでね、あなたへの贈り物はこれしかないって思ったのよ、だからここにきてもらった、この文書の解読作業も間もなく終了して、その全文が近々に公表されるでしょう、でもいまはまだれにも話されていない、だからいまここでお話しするのは、世界最初の初演ということになるわね、これから日本の民話を研究しようとする夏海さんに、そして夏海さんのなかで生きている私の大切なお友達に、鎌倉時代の円空さんが草した「かぐや姫」を。

一の章 貧しい村
「見ろ、この村を! わずかな畑しかないのに、草ぼうぼうだ。村にとって一番大切な畑を耕すことをわすれて、どいつもこいつも竹薮のなかにはいって、黄金探しをしている、そしてよるとさわると、一本松の五郎吉は、西の竹薮で黄金の小判一枚みつけたとか、甚衛兵さんとこの嫁が、鹿の谷の沢で二枚みつけたとか、佐助どんが、カラスがくわえていた小判を石でたたき落としたとか、もうそんな話ばっかりだ、そうして、その黄金がでたというところに、わんさかとでかけていく。こうして、いよいよこの村の人間は、怠け者になるどころか、狂っていくんだ。黄金の小判を、あっちに一枚、こっちに一枚と隠している人間が、だれだか君は知っているのか」

二の章 五人の皇子たちの求婚
辺鄙な村里に忽然と巨大な御殿がつくられたという噂は、またたくまに日本中にひろがっていって、近在の村や町から毎日のように御殿見物する人がやってきた。反り返った屋根に瓦が黒くひかる華麗な御殿、そのなかにかぐやなる姫が住んでいる。その姫はたとえようもなく美しく、ひとたび姫の笑顔にふれると、たちまち病も癒えていくなどというおひれまでついていたものだから、御殿をたずねる人がひっきりなしだった。 その噂はやがて都まで広がっていくと、貴族や武者たちが競うようにこの村にやってくる。彼らがそんな情熱にとらわれたのは、もうこれはただひとつ、姫に求婚するためだった。白く輝く高き峰をだれもが征服してみたいと思うのが人の常。はるか山奥の村に、たとえようもなく気高く美しき人がいるときいては、男たちの心が燃えないわけはないのだ。
三の章 石上皇子
こうして五人の皇子の物語がはじまっていくが、まず最初に挫折したのが、あの平安時代のバードウォッチャー、石上皇子(いしのうえのおうじ)だった。
姫のいう子安貝なるものを取るために、まず唐の国に渡らねばならなかったが、この皇子の父親は、時の政治を左右するばかりの高い位置をしめていたから、もし皇子が唐の国に渡るといえば、きっと息子のためにその遠征隊なるものを組織してくれたはずだった。しかしこの皇子には、とても外国に渡る勇気などなかった。当時は外国に渡るということは、命を捨てる覚悟をもたねばならなかったのである。しかし姫を忘れることはできない。姫がいとおしくてたまらない。姫の姿をみたいと相変わらずこの皇子は、姫の御殿をうろつくストーカー行為から足を洗えなかった。

四の章 車持皇子
この時代、大きな戦乱もなければ、変革の波というものをおこっていない。いわば古代国家の爛熟期といったもので、この時代の貴族たちは、なにかぬるっとした平和という澱みのなかで生きていたのである。五人の皇子たちが、競ってかぐや姫に求婚したその情熱も、この平穏なぬるま湯のような時代だったからで、ちょっと熱をもった貴族たちにとって、がっちりとした体系をもった社会が息苦しかったのだろう。だから未知なるものに挑戦することは、彼らの野生の血をぞくぞくさせたのである。
はるか南方洋上にあるという蓬莱という島にいって、その島にだけ生育するという宝玉の枝を、持ち帰ってきた皇子に姫をあたえるという竹採りの爺さんの出した挑戦に、取り組んだ車持皇子(くるまもちのおうじ)の情熱というものは、ちょっと恐ろしいばかりだった。
五の章 大伴御行
「よっしゃ、わかった」と手を叩き、うっししし、うっひひひと奇妙な笑いをつくって、姫の屋敷をあとにした、大伴御行(おおとものみゆき)という大納言の物語をはじめよう。この人物の生涯もまた波乱に満ちたものだった。あの日、熱き思いが姫に通じて、とうとう姫と婚約できたと勝手に思いこんだ大納言は、屋敷に戻ると、さっそく家臣たちを居室に集めて命ずるのだ。
「おれは、これから唐の国に旅立つことにする。すぐにその準備をはじめよ」
びっくりした家臣たちは、「いったいまたどうして唐の国でございますか」
すると大納言は、
「唐の国には、龍なる獣がいることは知っておったが、最近の情報ではそのなかに、首に五色の光る珠をつけたものがいるらしいのだ。この珠はとてつもない価値をもち、なんでも一国を買い取ることができるらしい。そこでおれはこの珠をとりに、唐の国に遠征することにしたのだ」

六の章 阿倍皇子
唐の国との貿易で巨万の富をたくわえている右大臣阿部皇子は、姫との求婚が成ったと思い、都にもどってくると早速、取引先の大貿易商・王慶に、火鼠という獣のことや、その獣の皮でつくった着物のことをたずねる文を送った。二ヵ月後、唐の国からまた貿易船がやってきて、王慶からの返事が届いた。その文にはこう書かれていた。
《おたずねの火鼠とやらも、その獣の皮でつくった着物なるものも、この国にはございませんぬが、それはひょっとすると、はるか北方か、あるいは南方かに生息する虎なる獣のことではございませぬか。それなる獣は、燃えるがごとき黄金の毛でつつまれており、そのふさふさした毛が見る者には火が燃えていると映るのです。おたずねの火鼠なるものが虎ならばたしかに存在しており、またその獣の皮でつくられた衣服というものもございます……》
七の章 石作皇子
かぐや姫に求婚した五人の皇子も、とうとう残るは一人になってしまった。五人のなかで一番地位の低い皇子であったが、しかし頭のきれるロマンにあふれた石作皇子(いしづくりのおうじ)が。いったいこの最後の皇子はどうなったのだろうか。
この皇子も姫の館からもどると、身辺の整理をし、自分が不在の間にもその役目がしっかりと勤まるよう重々に備え、四人の従臣たちをひきつれて海路太宰府にむかった。その当時、外国との貿易の最大の拠点が太宰府だったからだが、幸運なことに皇子の一行が太宰府に着いたとき、たまたま唐にむかうという貿易船が停泊していた。
ひどく高い運賃を要求されたが、しかし渡りに船とばかりにその船にのったが、さすが何回となく海を渡っている貿易船は、これといった難事にもあわずに一か月ほどで《差異群》という港町に到着した。その港は当時アジア一栄えていて、突堤がいくも海に突き出し、そこに何百という大小の船が停泊していた。港のにぎわい。町の喧騒。なにもかも桁違いの大きさに皇子は度肝を抜かれた。この国にくらべたら日本などという国は、なにやら箱庭ごときものだなと思わせるばかりだった。

八の章 帝
こうして五人の皇子の物語を語り終えたが、もう一人姫に求婚をした人物がいたのだが、その人の物語も語っておかねばならない。五人の皇子はいずれも無残な死をむかえたり、行方が知れなくなったりした。そんな噂が広まるにつれて、都ではいよいよ姫の評判は高まり、以前にもまして姫に求婚せんとする皇子や武者たちが、熱き心を抱いて竹採り村をめざしてくる。そんななかでも大変な人物が姫に心を寄せはじめていた。この地上でその上になにもないという地位にいる帝である。
かぐや姫の噂はこの帝の耳にもはいってきて、その噂を聞くたびにかぐやなる姫に会いたいという思いを募らせていくのだった。この帝はとても不幸な歴史をもっていた。天皇の長子として生まれたが、生まれた時から不運がつきまとい、まるで蹴毬の毬のように、あっちにやられこっちにやられと、すさまじい権力闘争の餌食にされてきた。この時代もまた政権は裏切りと謀略のなかで勝ちとられていく。そんな環境のなかで育ってきたものだから、この帝は人間というものがいっさい信じられなくなっていたのだ。
九の章 籠売り娘
さて、かぐや姫とあの永吉はいったいどうなったのだろうか。その話をするにはもう一度、時をもとに戻さねばならない。永吉がかぐや姫の手をとって村の裏山につれていったときのことから。永吉はかぐや姫御殿の前を通るたびに怒りにかられて石を投げ込んでいた。その石が投げられると屋根瓦にあたって、かちん、からからからから……、かちん、からからからから……という音をたてる。
ところがあの日以来ばたりとその音がしなくなったのだ。今日こそ石が投げられるだろう、今日こそ瓦をからからと小気味よい音をたてて石が転がり落ちていくだろうと毎日その音を待っていたが、その音はあの日から途絶えたまま。それはなんだか姫の心にぽっかりと穴があいたようだった。というのも永吉という若者はもう姫の心を占領してしまっていたのだ。永吉に会いたい、永吉に会いたいという思いが日毎に大きくふくらんでいく。
十の章 紙づくり工房
若い二人の行動はすばやい。もう次の日からその壮大な計画に踏み出していた。竹採りの山から流れていく潮沢川が犀川に流れ込んでいく。その合流する川のほとりの土地を永吉は手にいれていたのだ。生い茂っている草をまず刈っていった。その地に点在する木立も切り倒した。切り株もまた土から引き抜く。傾斜のある土地だったので、山から何度も土を運んでは、その土地を平らにしなければならなかった。姫も泥だらけになって働いた。
お昼になると、石を積んだ炉に薪をくべて火をつくる。その上に鍋をのせ飯をたく。川でとった魚を竹串にさして焼き、野で摘んだ若菜をきざんで味噌汁もつくる。支度ができると、姫は「永吉さん、ご飯ですよ」。すると土と格闘していた永吉は、川で顔や手を洗い、たきあがった飯に食らいつくのだ。うまいうまいといって食べる永吉。それをみる姫のみちたりた笑顔。幸福というものはこういうところにあるのだなあ、と姫はしみじみと思うのだった。

十一の章 月に帰るかぐや姫
とうとうその七月十五日がやってきてしまった。
噂というものはいつの時代でもまたたく間に広がっていくものだ。七月の十五日に、かぐや姫を奪い返すために月から大部隊が攻め寄せてくるという噂はもう国中に広がって、あちこちの村や町から、はたまた都から何千何万という人が竹取りの村におしかけてきた。そして姫の御殿がみえる山の上や、畑や、楠や、柿の木や、橋の上や、家々の屋根や、鎮守の森や、神社の鳥居といったさまざまな場所に陣取って、いまかいまかとまちわびているのだった。月から攻め寄せる大軍を、朝廷からくりだされた三千の武者たちが迎え撃つ。その壮大な戦闘をみないわけにはいかないのだ。
日が落ちていくと、あたりの闇が次第に深くなっていく。そして空にぽっかりと月が浮かびあがった。その月ははちきれんばかりの満月だった。あわただしく騎馬が走ってきてはまた走りさっていく。あちこちで部隊を動かす指揮官の声が鋭く飛び交う。

草の葉ライブラリー
たった一冊の本が世界を変革していくことがある
本は売れなければならない。売れる本だけが価値をもたらす。売れる本によって本を作り出す人々の存在が確立されていくからである。これがこの世界を絶対的に支配している思想でありシステムであり、したがって数十部しか売れない本は価値のない本であり、数部しか売れない本はもう紙屑同然のものということになる。しかし本というものは食料品でも商品でも製品でもなく、まったく別の価値をもって存在するものであり、たった数部しか売れなかった本が、数十万部を売った本よりもはるかに高い価値をもっていることなど枚挙にいとまがない。ベストセラーなるものの大半が一読されたらたちまちごみとなって捨てられるが、たった五部しか売れなかった本が、永遠の生命をたたえて世界を変革していくことだってある。
この視点にたって創刊される「草の葉ライブラリー」は、たった数部しか売れない本に果敢に取り組み、独自の方式で読書社会に放っていく。荒廃して衰退していくばかりの読書社会に新たな生命の樹を打ち立てる本である。閉塞の世界を転覆させんとする力動をもった本である。地下水脈となって永遠に読み継がれていく本である。

一冊一冊手作りの出版のシステムを確立していく
これら数部しか売れない本を読書社会に送り出していくために、その制作のシステムを旧時代に引き戻すことにした。旧時代の本とは手書きだった。手書きで書かれた紙片が綴じられて一冊の書物が仕上がる。その書物を人がまた書き写し、その紙片を束ね、表紙をつけて綴じるともう一冊の書物になった。こうして一冊一冊がその書物を所望する人に配布されていった。
この手法を現代に確立させるための最上の道具がそろっている。その作品をコンピューターに打ち込み、スクリーンに現れる電子文字を編集レイアウトして、プリンターで印字し、簡易製本機で一冊の本に仕立てる。簡易製本機、これは驚くべき発明である。この機器が登場することによってだれも本が作れるようになった。その工程はすべて手作りである。その一冊一冊が工芸品のように制作される。
大量印刷技術によって、複雑なる販売流通によって、売れる本しか刊行しない、売れる本しか刊行できない現代の出版のシステムに反逆するシステムである。この旧時代的手づくり工法によって、真の価値をもった作品が新たな生命力を吹きこまれて一冊の本となって読書社会に送り出される。新しい時代を切り開く出版のシステムの誕生である。

読書社会に新しい地平を切り開くクラウドファンディング
長い苦闘の果てに書き上げた作品が、本となって読書社会に投じられるまで何段階ものハードルがあり、そして実に複雑なルートを通さねばならない。晴れてその本が書店に並べられたとしても、その本を手に取る人はゼロで、したがってその本は二三週間で返本される。ごみ同然となったその本は裁断され焼却される。これが今日の出版の現実である。この現実を切り開かんと、いま全く新しい出版のシステムが登場した。クラウドファンディングである。大望を抱く者が、しかしその大望に取り組む資金のない者が、社会に人々に助力を求めるシステムである。
草の葉ライブラリーはこのシステムによって、一冊一冊が読書社会に投じられていく。複雑な流通システム一切なしである。リターンにクリックされた購入者のもとに草の葉ライブラリーから発送される。出版システムの革命である。

生命の木立となって時代とともに成長していく草の葉ライブラリー
現在の出版のシステムは、その本を読書社会に投じたらそれで完了である。一度出した本を再編集して投じるなどということはめったに行われない。出版社は絶版の山を築いていくばかりである。大地を豊かにする名作がこうして捨てられていく。ゴッホの絵がなぜいまなお脈々と生命をたたえているのか。それは繰り返し彼の絵が展示されるからである。なぜモーツアルトの音楽がいまなお人々に愛されるのか、それは繰り返し演奏されるからである。生命力をたたえた本は、繰り返し新しい世代に向けて発行していくべきなのだ。「草の葉ライブラリー」は新しい編集、新しい体裁によって繰り返し刊行されていく。その時代の生命をその本に注ぎ込むことによって、その本は時代ともに成長していく。これらの活動はwebサイトの「noteウオールデン」に百編近いコラムやエッセイとなって植樹されている。「noteウオールデン」を訪れて下さい。


リターン
1500円コース

「明科神宮に七百五十年眠っていた かぐや姫」 A4版 160ページ
一冊一一冊が手づくり造本です。素朴な体裁ですが、あなたの手に渡るとき、七百五十年眠っていた物語に生命が吹き込まれます。礼状と九十七歳の画家、周藤佐夫郎さんのポストカードを挟み込んでお送りします。

2600円コース

「ゲルニカの旗 南の海の島」 A4版 370ページ
四編の中編小説が編まれている。「草の葉ライブラリー」がはじめてCAMPFIREに投じた記念碑的な一冊。手づくりの素朴な体裁の本ですが、五十年後には一冊数十万円の値がつくでしょう。礼状と九十七歳の画家、周藤佐夫郎さんのポストカードを挟み込んでお送りします。

4000円コース

「目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ」 B6判 オフセット印刷 560ページ
一千枚になんなんとする長編小説。一人の青年が自己を確立していく物語。そして新しい地平を切り拓いていこうと苦闘する青年たちの物語。 礼状と九十七歳の画家、周藤佐夫郎さんのポストカードを挟み込んでお送りします。

資金の使い道について
制作費
人件費
広報費
リターンの送料
CAMPFIRE掲載手数料、決済手数料
に充当させます。









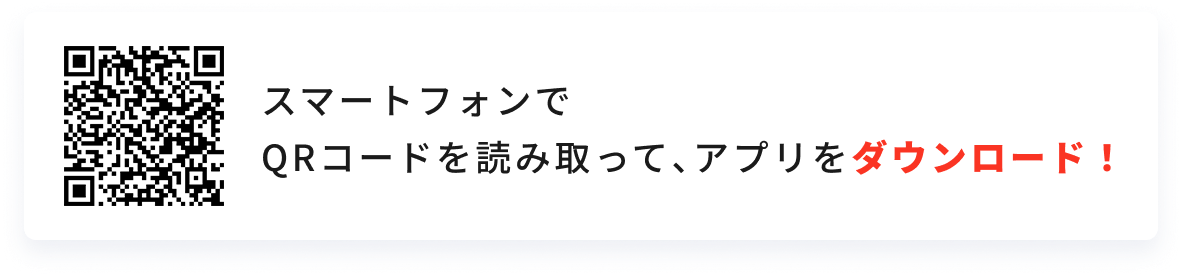


コメント
もっと見る