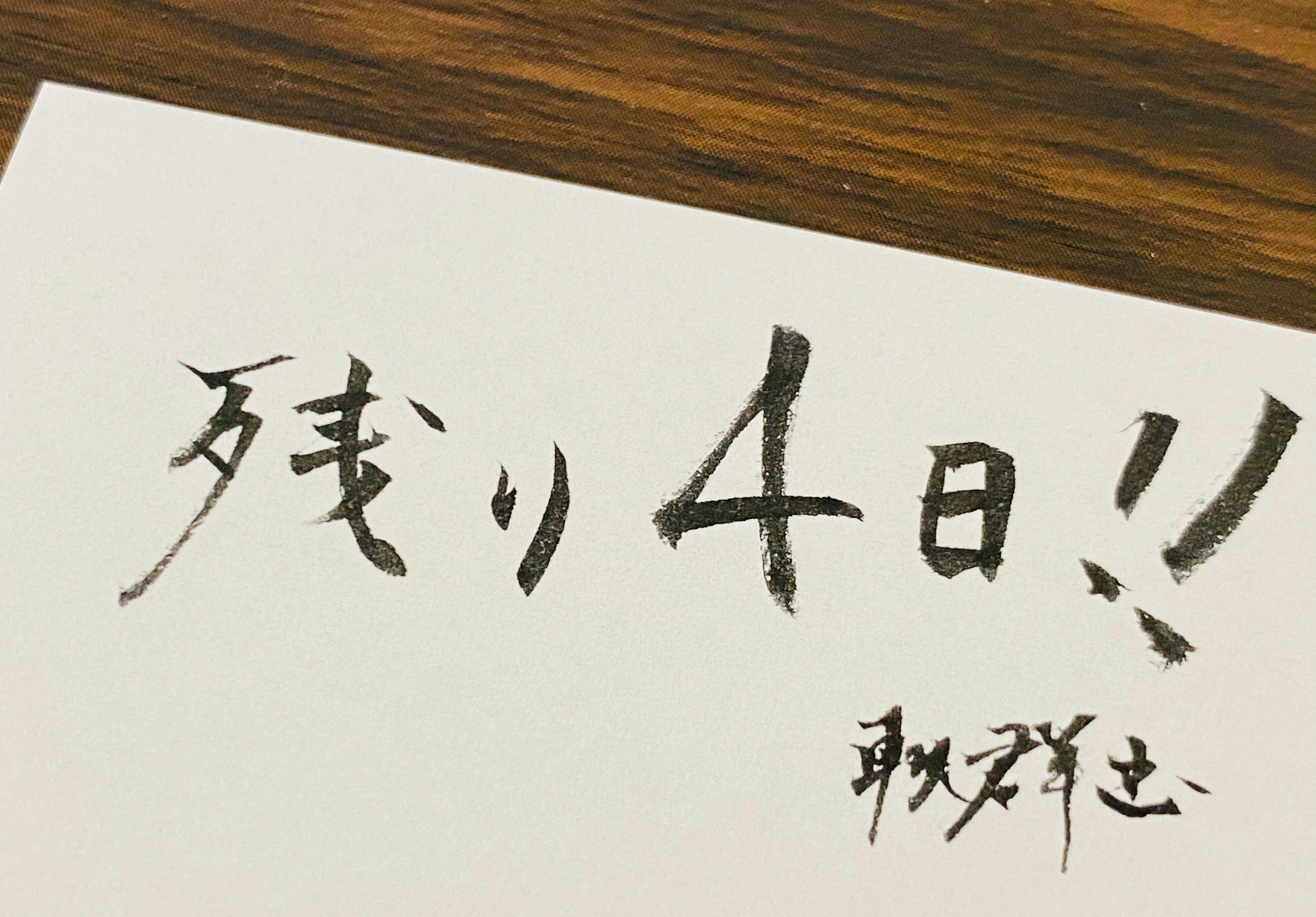
こんにちは、Living in PeaceのS.Sです。
ちょうど10年前の8月頭、NGOでのインターンシップのため、私はケニア共和国のダダーブ難民キャンプに降り立ちました。今回バトンを渡されて私が書こうと思えたのは、この時に出会った一人の難民の友人Aのことです。私が彼と過ごした期間はたった2か月に過ぎず、彼の人生の一端を垣間見たに過ぎませんが、私がキャンプを離れた後も、私は彼に少なからず精神的に支えられてきました。
私は、Aのことをケニアに行く前から知っていました。Aは、私が日本で関わっていたプロジェクトの支援対象候補のうちの1名だったからです。アントレプレナーの発掘のように、難民の中からアーティストを発掘するというプロジェクトで、彼は最終選考に残った3組のうちの1組のボーカルでした。プロジェクトスタッフの中でも女性人気が高かったと記憶しています。
彼と最初に対面したのは、パーティーの場でした。キャンプに行ったばかりの頃、当時UNHCRの代表であり現国連事務総長のアントニオ・グテーレス氏がダダーブに来る機会があり、援助機関がそのためのウェルカムパーティーを開きました。パーティーといっても、援助機関職員のレクリエーション目的で設置されているボコボコのテニスコート一面にプラスチックの椅子を並べ、前方に台を用意した程度のもので、当然、屋根はありません。Aは、このパーティーで、アーティスト候補だったの他の2組と一緒に、聴衆である援助機関職員の面前で歌を披露しました。

式次第が一通り終わった後、アーティスト発掘プロジェクトを主導していた知り合いのK氏が、私とAを引き合わせてくれました。しかし、Aが自己紹介をしてくれているのに、私は一言もしゃべれませんでした。受験科目としての英語は得意でしたが、英語環境は初めてだったので、緊張して何も話せなかったのです。二人とも私が何かしゃべるのを待っていましたが、私が一言も発しなかったので、その場は適当に切り上げて挨拶程度に終わったと思います。その後、彼と親しくなり英語にも慣れた後、Aに、「最初、英語が話せなくてこいつ大丈夫か?って思った」って笑いながら言われたのをよく覚えています。
援助機関は、コンパウンドと呼ばれる地区に集住し、その中でコックや清掃員を雇って生活しています。難民や地元のケニア人をインセンティブ・ワーカーとして雇っているため、所得創出の機会にもなっており、Aは、インセンティブ・ワーカーの一人として、ショップの店員をしていました。3畳程度のショップにはパサパサのビスケットや暑さで溶けたチョコといったお菓子やハンガー等の生活用品がおいてある程度でしたが(屋根はあります。)、援助機関職員であるお客さんから話しかけられることもよくあるので、コックや清掃員と異なり英語が求められていたと思います。Aは、英語を含め4カ国語を自由に操るので、ショップ店員として十分すぎる程の能力を持っていました。
私が生活していたコンパウンドから彼のショップまでは、援助機関が集住する長方形のコンパウンドの西側を縦に走る一本道を15分ほど歩いていきます。一本道にライトはポツポツとしかなく、午後6時半頃になると真っ暗になります。帰りが遅くなったときは、真っ暗闇の中を携帯の液晶で足元の砂を照らしながら、車にひかれないように道の端っこを歩いて帰っていました。コンパウンドと外界を仕切る金網フェンスに巻き付いているトゲトゲの固い草が足元の柔らかい砂の中から顔をのぞかせていることがあり、それをサンダルで踏み抜いて怪我しかけたこともありました。

最初は1週間に1回程度で、店に立ち寄っても少し話す程度でしたが、そのうちほぼ毎日通うようになっていました。インセンティブ・ワーカーはコンパウンド内に住み込んで働いていましたが、難民は、家があるキャンプまで時折、帰っていました。ショップの壁は、日本でよく見かける網目のフェンスで囲まれているため、中に誰がいるか遠くからでもわかるのですが、ドアが閉まっている場合には店が閉まっておりAがいないことを意味します。ショップに向かう道からドアが閉まっているのが見えた時は、別のショップで買った20円の瓶コーラを片手に、自分のコンパウンドまでトボトボ歩いて帰っていたものでした。
3畳程度の狭いショップでしたが、Aがいつも小さな椅子を出してくれたので、私はそれに腰かけて、小さなカウンター越しに彼と話していました。
日本の小学校低学年の頃に内戦で祖国を追われた彼は、東アフリカの難民キャンプを家族とともに十数年転々として、ダダーブに来たと話していました。両親と兄弟で確か8人ほどの家族の中で、唯一の稼ぎ手は彼のみで、弟・妹達は学校に通うくらいの年齢だったはずですが、そうした重圧にもかかわらず、彼はいつも優しく寛大で、愛想がない私に対していつも笑顔で話しかけてくれました。長年にわたる避難生活に比べたら、雨がほとんど降らず強い日差しが照り付ける酷暑の砂漠であっても、居住する場所と収入があるだけ安定している方だったのかもしれません。
援助機関側の人間である私に何かを乞うようなことも全くなく、私とほとんど年が変わらないのに(一つ上)非常にしっかりした人でした。援助する側と援助される側という所与の関係があるためお互いにどうしてもバイアスがかかってしまいますが、足繁く通っていた私と一人の友人として付き合おうとしてくれていたように思います。長年援助を受ける側として生活してきたにもかかわらず、援助慣れせずに語学も勉強しており、人間として本当に強く、心から尊敬していました。
彼との話の大半は他愛もないもので、スワヒリ語を教えてもらったりしていました。彼のショップで買い物をすることはほとんどありませんでしたが、アイスがあったのでそれを買って一緒に食べたりもしました。日中40度近くにまでなる砂漠の中でたまに食べるアイスは格別で、甘いものを日常的に摂取する食文化で生きてきたAにとってもきっと同じだったのではないかなという気がします。冷凍庫の温度が高くて溶けているものもありましたが、それはそれで良い思い出です。

丸々2ヶ月滞在した最後の日、平日でしたが、午前の業務時間中に彼のショップに行きました。彼に会った最初の頃から、私がいつまで滞在予定かは話しており、短い短いと散々言われ続けていたくらいなので、この日が最後になることも彼には当然話していました。もう会うことができないとわかっていたのでお互い非常に名残惜しかったですが、彼は最後に、いつも身につけていたビーズのブレスレットを記念ということで私にくれました。黄色と黄緑色のビーズが交互に斜線に並べられたきれいなもので、そのブレスレットは今でも身につけています。
普段ショップを開けている間はお店を離れることはできないのですが、別れ際、彼は少しの間だけ私を見送りに来てくれました。それでもお店から10メートルもない程度ですが、その彼の気持ちが嬉しかったのを覚えています。最後に彼と抱擁して、別れました。私が覚えている彼の最後の姿は、彼がショップの方に振り返りながら私に手を振っくれた時のものです。カメラを持ち歩いていなかったので、彼との写真がそもそもあまり残っていないのですが、最後の姿は10年が経とうとしている今でも頭の中に残っています。
こうしてインターンを終えて日本に帰ってきましたが、SNSで彼と繋がっていたので帰国後もそれなりにやり取りしていました。
確か2013年頃だったと思いますが、彼が第三国定住することになったとの連絡がありました。特にダダーブからの第三国定住の門は狭く、その中でも彼の家族が選ばれたのは彼の語学力や能力もあると思いますが、本当に幸運だったと思います。
この時、私は彼から初めて送金をお願いされました。彼からお願いされたのは、後にも先にもこの時だけだったと思います。私はかなり迷いましたが、これを断りました。お金を裨益者個人に直接送るという極めて生々しい行為に強い抵抗があったためでした。今まで、少なくとも私にとっては対等な友人として付き合うことができていたのに、この時に送金したために、彼と私を繋ぐ紐帯がお金になってしまうのも嫌でした。私と同じように難民キャンプでインターンをした先輩に相談したところ、その先輩が知り合った難民に送金したら、その後連絡が途絶えたという話も聞いていたのも響きました。
ただ、彼はダダーブにいた頃から苦しい生活だったのは恐らく間違いないなく、私がキャンプに滞在していた頃から一度もお金を無心されたことはないので、この時は本当に切羽詰まっていたからお願いしてきたのかもしれないと今でも思います。結局、彼と家族は無事に第三国定住できたようですが、これを端緒に、彼から連絡があってもその内容が淡泊になったように感じています。彼とは今でも繋がっていますが、この選択が正しかったのか、わかりません。
今となっては、AとSNSで若干やり取りしたり彼の投稿を見たりする中で、彼もやはり普通の人間のような側面があるのだなと感じることはあります。私が直接援助していたわけではないものの、援助する側と援助される側という関係性から、非常にデリケートで壊れやすく、難しい関係だと思います。しかし、10年前に難民キャンプで出会い、非常に優れた語学力だけでなく努力家でもあり人格者でもあったAの人間像や滞在中に築いた彼との友情は、私という人間が感じた紛れもない事実です。そんな彼の姿を、私が本当に辛い時に思い出して励まされることもあります。事後的に美化されている部分はあると思いますが、彼にはそうやって今でも精神的に支えてもらっています。

今回のプロジェクトを支援することで、彼ら/彼女らを応援しながらも、その姿を見て逆に励まされるということはあるのではないでしょうか。今回のプロジェクトが、難民の就労支援に繋がることはもちろんですが、難民というバイアスを取り除き、一人の人間として支援対象者の方と向き合う一つの機会になり、難民に対する認識が変わるきっかけになれば嬉しいです。
シエラレオネから活動に参加している、有澤孝治にバトンをつなぎます。
※本記事は、特定を避けるため、国名や氏名等を省略しています。




