
みらい子育て全国ネットワーク(miraco)の代表、天野妙です。
私たちのプロジェクトのページをご覧いただき、ありがとうございます。
私の第1子が保育園に入れなかったのは10年前。不承諾通知を手にし、絶望と閉塞感に襲われ、どうしていいのかわかりませんでしたが、心のどこかで「こういう日本に生まれたのだから仕方がない。」と諦め、「きっと誰かが解決してくれるだろう」と思っていました。
あれから10年・・・
問題を解決してくれるヒーローは現れていません。
いまでも、保育園の結果通知をドキドキしながら待っている人がいます。保活で何十園も見学する人がいます。落選して仕事を手放す寸前の人がいます。女性だけではなく、男性にも同じような境遇の方がいます。
それって、おかしくないですか?
保活の壁、待機児童の壁、3歳の壁、小1の壁、小4の壁・・・日本の子育ては「壁」の連続。そんな「壁」にモヤモヤする人、人生の選択を迫られる人、壁にあたった事すら無かったことにされている人・・・
子育ての壁にぶちあたる人を1人でも減らしたい!
日本を「子育てしやすい国」にしたい!
そんな思いではじめたプロジェクトです。

私たちの活動のきっかけは、東京都武蔵野市吉祥寺での保育園不足でした。世間ではちょうど「保育園落ちた日本死ね!!!」のブログを契機に大きな社会問題となっている時期でした。
少子化なのになぜ保育園に入れないの?と、親たちが立ち上がり、「吉祥寺に認可保育園を増やしてほしい!」という署名を始め、集まった4276筆の声を持って武蔵野市に届けました。

…しかしながら、思うように保育園の整備が進まない状況が続きました。
これは武蔵野市だけの問題ではなく国の問題なのでは?40年解決してこなかった待機児童問題、何とかしなきゃ!
そんな思いで「希望するみんなが保育園に入れる社会をめざす会」を立ち上げたのが2017年1月。
「♯保育園に入りたい」というハッシュタグで発信を呼びかけたところ、2017年2月の1か月間だけで、3,600ツイート、21,400リツイート、16,000,000インプレッション…全国各地からの悲痛な声がTwitter上に流れました。
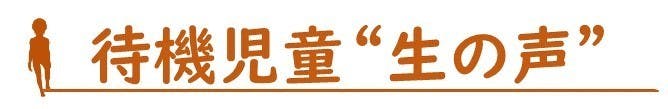
♯保育園に入りたい、♯保育園落ちた、の声は2018年も、そして今年も、2月になるとネット上に溢れかえっています。
退職や次の出産など様々な不安が頭をよぎる…そんな声が東京以外の地域からも発信されています。

メンバーがみなそれぞれ仕事や子育てに奮闘しながらも時間を捻出し、2年間、活動を続けてきました。
子育て当事者と集い、話し、発信し、政策決定者である国会議員や行政との直接対話を重ねてきました。

発足から約2年たった今、活動を通じて見えてきたものがあります。
それは、保育園問題は子育てにおける数ある「壁」の一つに過ぎないということ。
その「壁」がいつまでもなくならない原因は、「子育てしやすい世の中にしよう」という文化や風土に欠けていることにあるのではないか、ということです。
- 子育てしやすい社会・文化をつくりたい。
- 私たち一人一人が生き方を自由に選択し、尊重される社会をめざしたい。
このような考えに至り、私たちは「みらい子育て全国ネットワーク(miraco)」へ生まれ変わることにしました。
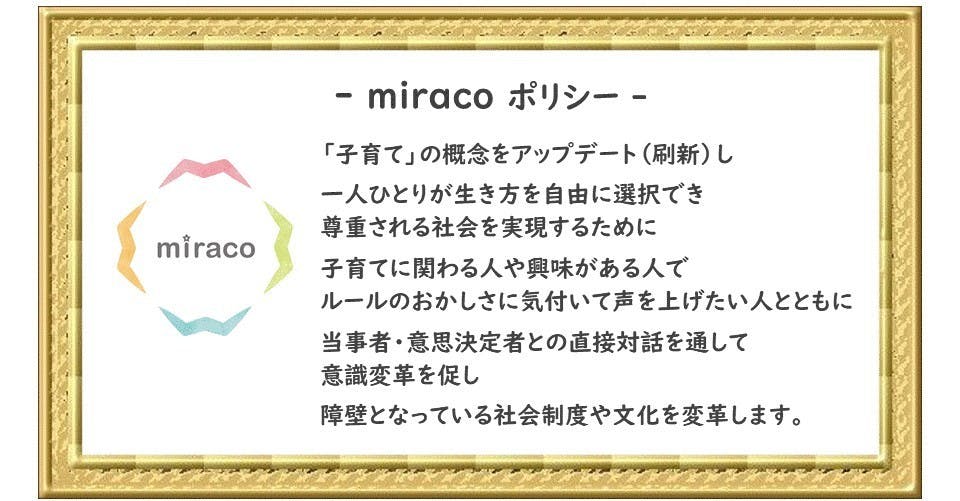
miracoのポリシーや活動に賛同する人たちが集まり、いま私たちのメンバーは40人を超えました。働きながら子育てをするパパ・ママのみならず、主婦も、そして子育てはこれからという人までが、同じ方向を向いてプロボノ(ボランティア)として活動しています。
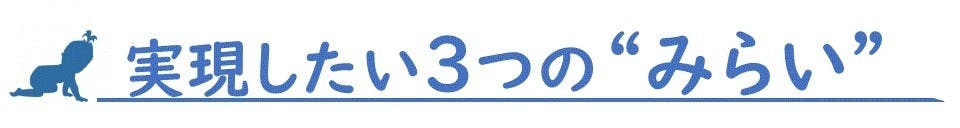
「子育てしやすい社会」の実現のためには、何が必要でしょうか?
私たちmiracoは、3つの“みらい”の実現に向けて活動します!

《課題》
現在、待機児童は約2万人、潜在数は数十万人いるといわれており、共働きフルタイム勤務の家庭でも入園が困難なエリアがあります。また、保育園の数不足だけでなく、保育士不足や、保育事故の問題なども起きており、「保育士の処遇」や「保育の質」も大きな問題となっています。
▼議員会館やイベントホールで、保育園の問題に関するイベントを開催し、参加者からの生の声を集め、発信します。
▼保護者に対して、保活でどのような苦労をしたのかを語ってもらう「保活ストーリー」や、保育園に入れたがその後に感じた不安や懸念などを語ってもらう「保育園ストーリー」についてのアンケートを行います。
▼保育者(保育園従事者など)に対して、働く環境や、働き続けやすい保育現場づくりのための課題や解決策についての声を集める「保育者アンケート」を行います。また、保育者の生の声を聞く場として、座談会などを開催します。
▼SNSを通じて『#保育園に入りたい』の声の発信や、アンケートの収集などを継続して行います。
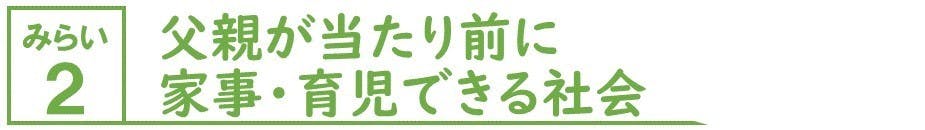
《課題》
日本には依然として「男は仕事、女は家庭」の意識が横たわっています。たとえば、男性の育休取得率は5.14%、しかもその大半が5日以下にとどまっています。「イクメン」という言葉が定着し、子育てに積極的に関わりたい男性が出てきた一方で、職場の上司や同僚の理解が得られず、子育てしたくてもできずに悩む父親も多くみられるようになりました。

▼議員会館やイベントホールで、男性の育休・産休などの男の家庭進出に関するイベントを開催し、参加者からの生の声を集め、発信します。
▼男性の育休・産休など、社員が子育てにもコミットしやすくなる取り組みを行っている企業のトップへの取材を行います。経営者の意識変革を促すとともに、メディアやSNSを通じて発信します。
▼現在5.14%にとどまっている男性の育児休業取得率を爆上げすべく、「男性育休100%宣言」企業を募集・公表し、男性の育児休業の常識化をめざします。
▼SNSを通じて『#男の産休』『#男の育休』の声の発信や、アンケートの収集などを継続して行います。
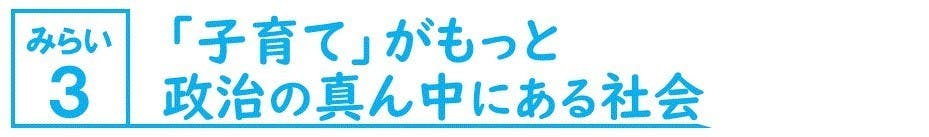
《課題》
“みらい”1と2の実現には、子育てに関心のある政治家を増やしていく必要があります。しかし、子育て・若者世代の投票率が低いことなどもあり、政治家の「子育て政策」のアピールが選挙での当選しやすさに直結していないのが現状です。

▼議員会館やイベントホールで、「子育て政策の優先順位を上げる」ためのイベントを開催し、参加者からの生の声を集め、発信します。
▼市長選挙、区長選挙および国会議員選挙の立候補者に対し、「#子育て政策聞いてみた」アンケートを実施します。
▼データ分析を行い、選挙におよぼす子育て・若者世代の投票率の影響について見える化を行います。
▼誰もが『#子育て政策聞いてみた』アンケートを実施できるように、アンケートのノウハウを公開します。
▼SNSを通じて『#子育て政策聞いてみた』による発信を継続して行います。
《3つのプロジェクト共通》
▼アンケートやイベント、取材などで得られた当事者のリアルな声や情報を、冊子や電子媒体にまとめ、議員、行政の政策担当者や保護者、事業者、学生、メディアなどの子育てのステークホルダーに届けます。
▼議員や行政の政策担当者へは、ロビー活動による直接対話を通じて声を届けます。

プロジェクトでの取り組みをイメージしていただきやすいよう、過去の活動をいくつかご紹介します。
 片山さつき議員(人生100年時代戦略本部副本部長(当時))にも手渡した署名『幼児教育・保育無償化は本当に必要な人から。圧倒的に足りていない保育の量と質の拡充を同時に!』は現在35,954筆。
片山さつき議員(人生100年時代戦略本部副本部長(当時))にも手渡した署名『幼児教育・保育無償化は本当に必要な人から。圧倒的に足りていない保育の量と質の拡充を同時に!』は現在35,954筆。
 全国各地からの声を集めた小冊子『私たちの「保活」ストーリー』2018年版は、国会議員600人以上に配付。保活に対する当事者の思いを直接伝えました。
全国各地からの声を集めた小冊子『私たちの「保活」ストーリー』2018年版は、国会議員600人以上に配付。保活に対する当事者の思いを直接伝えました。
 議員会館で開催したイベントでは、待機児童問題や男の産休・育休について、パパ、ママの声を国会議員に伝えました。イベント後、具体的な政策について与野党の議員との議論へとつながっています。
議員会館で開催したイベントでは、待機児童問題や男の産休・育休について、パパ、ママの声を国会議員に伝えました。イベント後、具体的な政策について与野党の議員との議論へとつながっています。
 2017年の衆議院選挙や2018年の首長(市長・区長)選挙(7自治体)で立候補者への「#子育て政策聞いてみた」アンケートを実施。待機児童や学童保育などのアンケート結果をSNSやホームページ上に比較して示し違いを見える化しました。(写真は新宿区長選の例)
2017年の衆議院選挙や2018年の首長(市長・区長)選挙(7自治体)で立候補者への「#子育て政策聞いてみた」アンケートを実施。待機児童や学童保育などのアンケート結果をSNSやホームページ上に比較して示し違いを見える化しました。(写真は新宿区長選の例)
合計160万円が必要です!
◆イベント開催(6回を予定) 60万円/年
(登壇者の謝礼/資料印刷代/広告費 等)
◆ホームページ制作費 30万円
(新ホームページの製作費 等)
◆ホームページ維持費/年 6万円/年
(サーバー代+ドメイン代 等)
◆保育園ストーリー冊子製作費 8万円
(冊子印刷費 800部)
◆保育者アンケート冊子製作費 8万円
(冊子印刷費 800部)
◆保活ストーリー冊子製作費 8万円
(冊子印刷費 800部)
◆運営費 20万円/年
◆クラウドファンディング手数料 20万円
(14%)
※本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、集まった金額に応じて計画を実行し、リターンをお届けします。

活動をはじめてから2年。
「私もおかしいと思ってました!」
「どうやって声をあげればいいですか?」
たくさんの方が、miracoに声をかけてくれました。
「自分にはまだ子どもがいないけど、何とかしたいです!」
「子育てを男性の視点で語ることも大事だと思うんです!」
独身の人も専業主婦も、そして男性も・・・
私たちの活動に加わってくれるようになりました。
その一方で
「〇〇党の(政治)団体でしょ?」
「保育園の数を増やせばいいって思ってる「量」だけの人でしょ?」
など、知らず知らずのうちに思いもよらない「レッテル」を貼られ、
嫌な思いをすることや、仕事に支障が生じることもあります。
それでも現代の「子育て」の困難や、この「壁」に対して
「私たちの代で終わりにさせよう」
「我が子に同じ思いをさせたくない」
という強い思いを持って活動を続けています。
子ども達に残す未来を変えていくためには、 皆さんのご支援が必要です。
ご協力をお願いいたします。
最新の活動報告
もっと見る
#異次元の子育て政策 王座決定戦開催中!
2023/02/09 12:56こんにちは。みらい子育て全国ネットワークです。miracoでは現在、『#異次元の子育て政策 王座決定戦』を開催しています!◆◇異次元って・・・なんだ??◇◆2023年1月4日。岸田総理は、年頭会見において「異次元の少子化対策」を今年の優先課題とするとして、(1)児童手当などの経済的支援の強化(2)学童保育や病児保育、産後ケアなどの支援拡充(3)働き方改革の推進を3本柱にすると語られました。これを聞いて、「異次元・・・なのか・・・???」って思いませんでしたか?miracoは、思いました。そこで、もっと異次元感出していこうよ!との思いから、新企画「#異次元の子育て政策 王座決定戦」を開催することにいたしました!1月に「#異次元の子育て政策」案を募り、半月足らずの募集期間で70を超える政策の応募が!そんなの当たり前にやってほしい!という政策から、「異次元級!!!」という政策まで幅広くご応募いただきました。◆◇現在グループリーグを開催中!◇◆A~Hの8ブロックでグループリーグを開催しています!A・Bブロックはあと18時間の投票ですので、ぜひすぐに、下記のURL中ほどの設問リンクから投票に参加してください!#異次元の子育て政策 王座決定戦グループ予選 開催中!※各政策の内容については、各設問先のリプ欄に記載されています。各グループリーグの勝者が決勝トーナメントに進みます!詳しくはぜひこちらのページをお読み下さい。#異次元の子育て政策 王座決定戦グループ予選 開催中!なお、今回は投票で王座を決めるという形式ですが、「子どもたちが夢中で読んでる『最強王』みたいにやったら面白いよね!」という遊び心も持ちつつ、開催しています。政策の優劣をつけるということではなく、全ての施策が子育て支援策となり得るという示唆ですので、「組み合わせがおかしい」や「この政策は変だ」などと感じた場合があっても、一つの意見として寛容に受け止めていただけると幸いです。 もっと見る
「子育ての実情アンケート」結果発表! そして #GoTo候補者 へ!
2022/06/29 06:30こんにちは。みらい子育て全国ネットワークです。「政治家に届けたい! 子育ての実情アンケート」へのご協力、ありがとうございました!おかげさまで、3371件もの回答が集まりました!いただいたアンケートの結果をホームページに掲載しましたのでぜひご覧ください。結果ページでは、回答者のお住まいの都道府県・親の年代・子どもの年代等によってフィルターがかけられるようになっています。あなたの都道府県の声だけを抽出することもできますよ!そして、このアンケートの結果を政治家に届けられる『子育ての「困りごと」』のプリントとしてまとめました。このプリントを使って、あなたの声がさらに政治家に届きやすくなるアクションをしてみませんか?ぜひ、お答えいただいたみなさん自身の手で、この声を直接候補者に届けましょう!それが#GoTo候補者 です!#GoTo候補者とは? あなたの一票をブーストするキャンペーンです!詳しくはぜひ、ホームページをご覧ください!私たちと一緒に、Let's #GoTo候補者! もっと見る
【締め切りまであと3日!】「政治家に届けたい!子育ての実情アンケート」回答お願いします!
2022/06/13 07:00皆さまこんにちは。みらい子育て全国ネットワークです。先日もお知らせしたとおり、現在みらこでは「政治家に届けたい!子育ての実情アンケート」を実施中です!みなさま、もうお答えいただけましたでしょうか?締切を6/15まで延長してますので、ぜひご回答ください!!子育てをしている中で「こんなおかしなルールが横行しているのは変!」「これは政治で変えられるのでは?」「子どものためによくないよ!」と、政治家にひとこと言いたい!伝えたい!ことを政治家の皆さんに届けるために、 妊娠中〜就学中のお子さんを子育てしている方々の声を、ぜひお聞かせください!!もう答えたよ! という方や、答えてほしい子育て中の人がいる方、拡散のご協力も、よろしくお願いいたします。▼▼アンケートはこちらのページから▼▼政治家に届けたい!子育ての実情アンケート▼現在の途中経過はこちらからご覧になれます!▼ 政治家に届けたい!子育ての実情アンケートの結果(仮)また、こちらのアンケートを使用した参議院選挙時のキャンペーン「#GoTo候補者2022」の展開を準備中!みらこのInstagramアカウントをフォローしてお待ちください!▼みらこInstagramはこちらから▼Instagram - みらい子育て全国ネットワーク(miraco) ▼LINEアカウントも始めました。ぜひご登録ください!▼LINE - みらい子育て全国ネットワーク(miraco)みらい子育て全国ネットワーク もっと見る









コメント
もっと見る