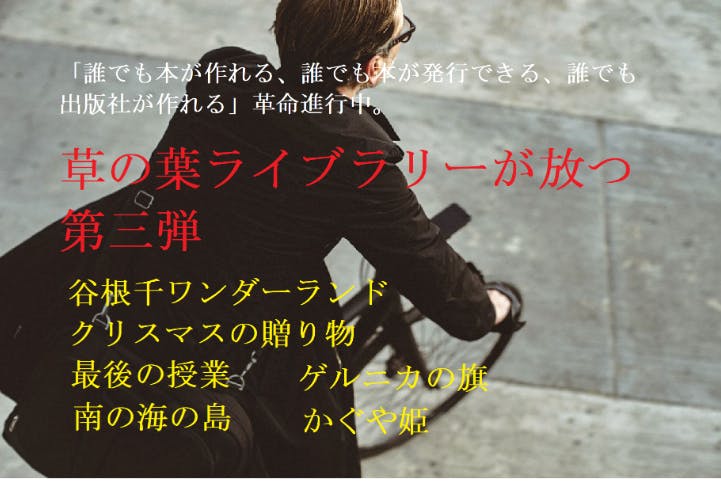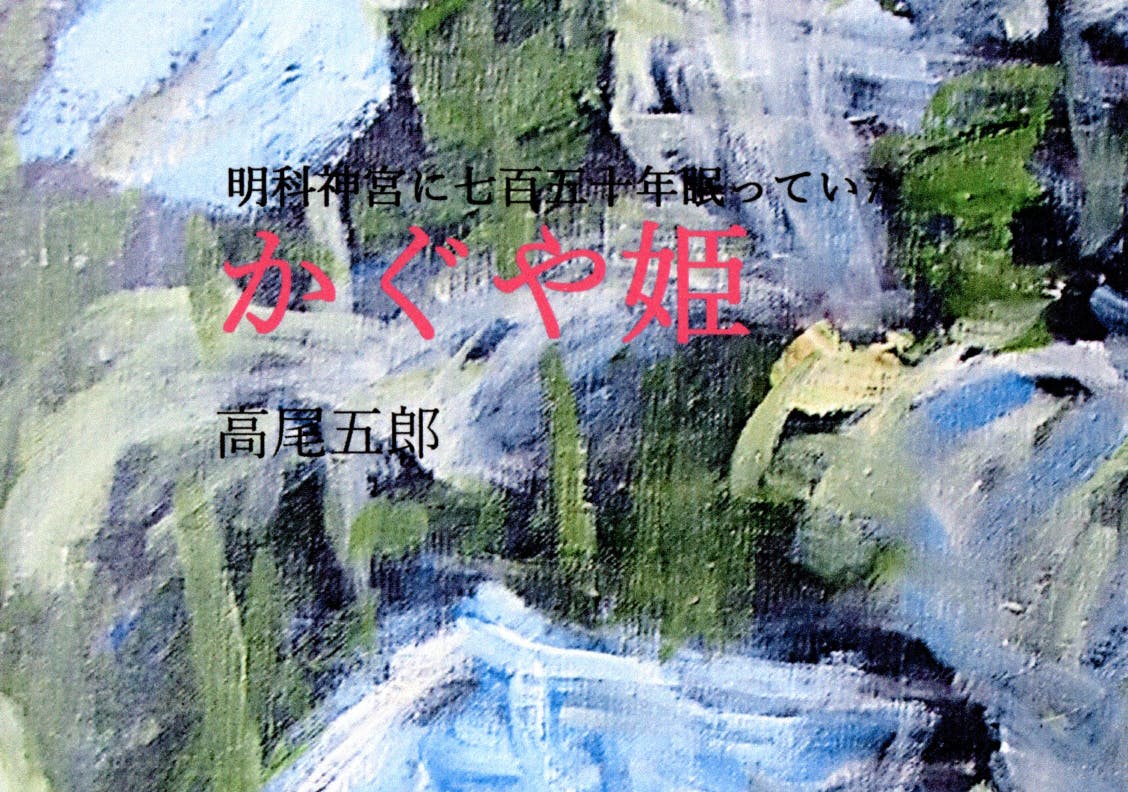アン・リンドバーグが見えてくる
須賀敦子がこの地上から去ってからすでに二十年近い月日が流れてしまったが、須賀さんと結ばれている精神の紐帯というものを私はいよいよ強く感じるのだ。私が須賀敦子という存在を知ったのは、ある雑誌に連載されていたアン・リンドバーグについて書かれたエッセイに目を投じたときだった。アンは夫のリチャード・リンドバーグと極東に向かって飛び立つ。しかしシリウスと名付けた単発機は千島列島で不時着するのだ。そのときの様子を描いたアンのエッセイに、須賀さんは心奪われ、いつか自分もこのような文章を書ける人になりたいと思うのだ。日本はアメリカと大戦争を勃発させた。須賀さん、中学生のときのことである。
それから数十年後に、再びアン・リンドバーグと対峙することになる。そのあたりをちょっと長めに、須賀さんのエッセイから転載してみる。これは山崎範子の本質に向かっていく行程でもある。
《さらに時間が経って、まったく関係のない調べものをしていたときに、アンの最初の著書の表題が、『北から東洋へ』"From North to Orient"だということを知った。これこそ、かつて私を夢中にさせたあの千島での不時着陸のときの文章がのっている本に違いないとは思ったけれど、それも手に入れる方法をもたないまま、また月日が流れて、私は大学を卒業し、フランス留学から帰って、放送局に勤務していた。ある日、友人がきっときみの気に入るよ、と貸してくれた本の著者の名が、ながいこと記憶にしみこんでいたアン・モロウ・リンドバーグだった。この人についてならいっぱい知っている。
『海からの贈物」というその本は、現在も文庫本で手軽に読むことができるから、私の記憶の中のほとんどまぼろしのようなエッセイの話よりは、ずっと現実味がある。手にとったとき、吉田健一訳と知って、私はちょっと意外な気がしたが、尊敬する書き手があとがきでアンの著作を賞讃していて、私はうれしかった。もしかしたら、戦争中に読んだあの文章も、おなじ訳者の手になったのではなかったかという思いがあったが、そのころの私はそういうことをきちんと調べる習慣をもっていなかった。
一九五五年に出版された『海からの贈物』は、著者が夏をすごした海辺で出会ったいろいろな貝がらをテーマに七つの章を立てて、人生、とくに女にとって人生はどういうものかについて綴ったもので、小さいけれどアンの行きとどいた奥行のある思索が各章にみち美しい本である。たとえば、つぎのような箇所を読むと、ずっと昔、幼い日に私を感動させたあの文章の重みが、もういちど、ずっしりと心にひびいてくる。
「今日、アメリカに住んでいる私たちには他のどこの国にいる人たちにも増して、簡易な生活と複雑な生活のいずれかを選ぶ贅沢が許されているのだということを幾分、皮肉な気持になって思い返す。そして私たちの中の大部分は、簡易な生活を選ぶことができるのにその反対の、複雑な生活を選ぶのである。戦争とか、収容所とか、戦後の耐乏生活とかいうものは、人間にいや応なしに簡易な生き方をすることを強いて、修道僧や尼さんは自分からそういう生き方を選ぶ。しかし、私のように、偶然に何日間か、そういう簡易な生活をすることになると、同時に、それが私たちをどんなに落着いた気分にさるものかということも発見する」
「我々が一人でいる時というのは、我々の一生のうちで極めて重要な役割を果たすものなのである。或る種の力は、我々が一人でいる時だけにしか湧いてこないものであって、芸術家は創造するために、文筆家は考えを練るために、音楽家は作曲するために、そして聖者は祈るために一人にならなければならない。しかし女にとっては、自分というものの本質を再び見いだすために一人になる必要があるので、その時に見いだした自分というものが、女のいろいろな複雑な人間的な関係の、なくてはならない中心になるのである。女はチャールズ・モーガンが言う、『同転している車の軸が不動であるのと同様に、精神と肉体の活動のうちに不動である魂の静寂』を得なければならない」(新潮文庫)
半世紀まえにひとりの女の子が夢中になったアン・モロウ・リンドバーグという作家の、ものごとの本質をきっちりと捉えて、それ以上にもそれ以下にも書かないという信念は、この引用を通して読者に伝わるであろう。何冊かの本をとおして、アンは、女が、感情の面だけによりかかるのではなく、女らしい知性の世界を開拓することができることを、しかも重かったり大きすぎたりする言葉を使わないで書けることを私に教えてくれた。徒党を組まない思考への意志が、どのページにもひたひたとみなぎっている。》
![]()
撃墜されたサンテグジュペリも見えてくる
そして、雑誌連載の次の号に、須賀敦子の存在が私のなかに決定的な痕跡を残すエッセイを載せるのだ。サンテグジュペリのことが書かれていたのだ。ここでもちょっと長めの転載をしてみるのは、これもまた山崎範子の精神の投映していくものだから。
《最初は、『星の王子さま』はなんだか子どもの本みたいなものを、と不満だったのが、読みすすむうちに、きらめく星と砂漠の時空にひろがる広大なサンテグジュペリの世界に私たちは迷いこみ、すこしずつ、深みにはまっていった。いや、迷っていたのは、クラスで私ひとりだったかもしれない。それまでに読んだどんな話よりも透明な空想にいろどられていながら、人間への深い思いによって地球にしっかりとつなぎとめられたサンテグジュペリの作品は、他にも読むべき古典がたくさんあるのをながいこと私に忘れさせるほど、夢と魅惑に満ちていた。
飛行家のアン・リンドバーグが書いたものに揺りうごかされ、いつか自分もこんなものを書けたらと思ったのは、十二、三歳のころだったけれど、それからまた六、七年たって、ふたたび私の心をつよく捉えたこの作家が、これまた飛行家というのは、それにしてもどういう偶然だったのか。
ジグザグのように歩いてきたながい人生の道で、あのとき信州にもっていったサンテグジュペリの本のうち、『戦う操縦士』だけが、どんなめぐりあわせだろう、傍線・付箋だらけになってはいるが、まだ私の手元にある。黄ばんだ紙切れがはさまった一二七ページには、あのときの友人たちに捧げたいようなサンテックスの文章に、青えんぴつの鈎カツコがついている。
「人間は絆の塊りだ。人間には絆ばかりが重要なのだ」
もうひとつ、やはりこの本で読んだ、私にとって忘れることのできない文章がある。人生のいくつかの場面で、途方に暮れて立ちつくしたとき、それは、私を支えつづけてくれた。いや、もうすこしごまかしてもいいようなときに、あの文章のために、他人には余計と見えた苦労をしたこともあったかもしれない。若いひとたちにはすこし古びてみえるかもしれないけれど、堀口大学の訳文をそのまま、引用してみる。
「建築成った伽藍内の堂守や貸椅子係の職に就こうと考えるような人間は、すでにその瞬間から敗北者であると。それに反して、何人にあれ、その胸中に建造すべき伽藍を抱いている者は、すでに勝利者なのである。勝利は愛情の結実だ。……知能は愛情に奉仕する場合にだけ役立つのである」》
そしてこのエッセイはこう結ばれていく。
《サンテグジュペリが、ドイツ軍に占領されたフランスの解放をねがって、北アフリカで軍事行動に参加中、一九四四年、偵察飛行に出たまま行方不明になったという話が私の意識を刺しつづけた。自分は中学生だったとはいえ、戦争中なにも考えることなく罩事政権のいうなりになっていたことが口惜しく、彼のような生き方への憧憬は年齢とともに私のなかでつよくなった。行動をともなわない文学は、というような口はばったい批判、理論ともいえないような理論を友人たちと論じてすごした時間を、いまはとりかえしたい気持だし、自分は、行動だけに振れたり、文学にとじこもろうとしたり、究極の均衡(そんなものがあるとすれば、だが)に到るのはいつも困難だった。自分にとっては人間とその運命にこだわりつづけることが、文学にも行動にも安全な中心をもたらすひとつの手段であるらしいと理解するまで、ずいぶん道が長かった。
『戦う操縦士』とともにもう一冊、おそらくはフランスに留学する直前に買った、ガリマール書店版の『城砦』が本棚にある。ページも、そのあいだに入れた手製の栞も、茶色に古びているけれど、あるページには濃いえんぴつで、下線がひいてあった。
「きみは人生に意義をもとめているが、人生の意義とは自分自身になることだ」
さらに、表紙の裏にはさんであった封筒には、だれかフランス人が書いたと思われる授業料のメモらしい数字と名前の下に、あのころの私の角ばった大きな字体で、サンテグジュペリからの言葉が記されていた。
「大切なのは、どこかを指して行くことなので、到着することではないのだ、というのも、死、以外に到着というものはあり得ないのだから」》
アン・リンドバーグを描いたエッセイ「葦の中からの声」と、このサンテグジュペリを描いたエッセイ「星と地球のあいだ」を読んだ私は、須賀敦子に挑戦の矢の矢を放つのだ。