自己紹介
本プロジェクトをご覧いただきありがとうございます!

滋賀県米原市で生木専門の木工所=スーパー生木ラボをを運営している鈴木孝平と申します。
100%国産の丸太から暮らしの道具をつくることをナリワイとしています。
なぜ100%国産の材料にこだわっているかというと、、、
豊富な樹木が暮らしに生かされていない?
実は日本の国土面積の約7割は山林です。

日本人はそこに生えている木々を豊富な資源として、昔から自分たちの暮らしに役立ててきました。
しかも、その種類は約1200種類にもおよぶと言われています。
これほどまでに豊かな樹種がある国は世界的に見ても珍しいです。
近くて遠い日本の山

これだけ豊富な山林資源があるというのに、都会に暮らしているとその実感がないのではないでしょうか?
都市部から自然豊かな地方へ移住したことがきっかけで、この違和感はムクムクと私の中に広がっていきました。
林業時代の疑問:山の木は使えない?

この文章を書いている私(鈴木)は、京都から滋賀に移住したことで、自然の中で働く仕事がしたいと思うようになりました。
その流れで小規模な林業を始めることに。
杉や檜など人工林の間伐をしたり、重機で軽トラが山に入れる道を作ったり、充実した日々を送っていたある日のこと。
ふと疑問が頭に浮かびました。
「目の前にあるこの木って使えないの?」
当たり前すぎて思いもしなかったことでした。
生の木は使えない?
DIYで頻繁に使われる材料は木です。
山に生えている樹木ももちろん木です。
違いは「乾燥しているか」と「製材してあるか」だけです。
結局のところ地域の山の木を暮らしに取り入れることのハードルは「乾燥」にあったんだと、当時の私は思いました。
乾燥させる設備がないから地域の山の材はあまり流通してないんだと。
そこでまた新たな疑問です。
「このまま加工しちゃダメなの?」

生木の木工=グリーンウッドワークとの出会い

きっと使えるはずだ。
むしろ使えないはずがない。
根拠のない自信を元にインターネットや本で調べること数日。
どうやら欧米諸国でGreenwoodworkというものがあるらしいことが判明。
「やっぱり生木、そのまま使えるやん!」
なんで誰も教えてくれなかったの!と思いつつも、生木の手仕事を始めることに。
独学と修行の日々

2018年頃、まだそんなに情報もなかったので英語のYouTubeや書籍を読み漁り、わかるようなわからないような感じで、ひたすら毎日フレッシュな生の木を削る日々。
林業で伐採した木を少し家に持ちかえっては斧やナイフで削る削る。
「生木の沼」にどハマりするのに時間はかからなかった。
気がつけば生木専門の木工所を設立

地域の山の木でものづくりを始めて2〜3年がたった2020年。
気がつけばお皿やサラダボウルなどをつくる木工ろくろの機械まで揃えてしまいました。
作品の注文をいただくことも少しづつ増えていったことで作品づくりがメインのナリワイとなり、林業の現場からは遠ざかりました。
だからこそより一層、国産の山の木を使ったものづくりをしていきたいと思うようになりました。
業界でもめっちゃマイナーな生木の木工=グリーンウッドワーク
アメリカやイギリスでこそ、老若男女が楽しむ趣味として密かな人気が感じられる生木の木工ですが、いざ日本の木工業界に目を向けてみるとどうでしょうか。
クラフトフェアなどのイベントに参加してみると、いわゆる同業の木工作家さんとお話しすることがあります。
99%聞かれる質問リストがこちら↓
「生木だと割れないの?」
「歪むでしょ?」
「生木ってどこで手に入るの?」
つまり、大半の木工作家さんは生木を削ったことがないということがわかります。
「そこにあるものを使う」というシンプルな原則
欲をいえば私だってアメリカンチェリー!とか、ブラックウォールナット!とかゼブラウッド!とかとか、耳障りがかっこいい海外の木材を使いたいと思うこともあります。
ただ、これだけ日本の山にはたくさんの使われていない木があるのだから、まずはそこにあるものを使うのがものづくりをする流れとしては自然じゃないでしょうか。
少なくとも私にはそう思えました。
前向きに、生木だからできるものづくりを

確かに生木は歪んだり、反ったりすることがあります。
場合によっては乾燥工程で割れる場合もあります。
つくるものによってはネガティブな要素として捉えられますが、
あえてそれらの反応を前向きに考えることができたら、生木でのものづくりはもっともっと面白いものになると思っています。
例えば、
歪みや反り→その木が一番気持ちのいい形で落ち着く
ひび割れ→特有の表情
などなど。
サラダボウルを生木から作ると、フチがふわりと歪みます。
これまでの経験上、歪みが生み出す有機的なフォルムを好んで購入していく方も少なくありません。
生木を活かすも殺すも人次第

私は現在生木を削った作品を販売したり、講座の講師として生計を立てて暮らしています。
生木を削り始めた頃は、まさかこれが仕事になるとは思いませんでしたし、
妻や周りの友人も同じ思いだったはずです。
家の前でしゃもじを削っていた時に、
前を通りかかった近所のおばあさんからは「遊んでばっかでええなアンタは〜」とまで言われたことがあります。泣
周りから見れば遊んでいるようでも、ちゃんとお客様が喜んでもらえるものづくりをすれば、生木を削ろうが仕事になります。
生木は使える。仕事になる。

結局のところ、私が生木専門の木工所を運営して世の中に伝えたいことは「生木は使えるし、ちゃんとやれば仕事にもなる」ということです。
まだまだこれからの部分もありますが、活動を通じて少しづつ生木が木工の材料として魅力のあるものだ!ということが広まってきた実感もあります。
仕事にしたい!という方が講座に参加したり、工房に学びにこられることも増えてきました。
生木で広がる国産100%のものづくり
だんだん広がる生木の輪が楽しくなってきたこともあり、
2023年には自主企画で地域の山で伐採した一本の桜の木を丸太に切って、「一本の木を使い切る」趣旨のもと、自主企画の展示販売会、「第1回 山の資源と暮らし展」を主催しました。


滋賀、京都、大阪、三重、岐阜、愛知、富山、神奈川から集まった賛同者は14名。
地元新聞社にも取り上げられ「生木のものづくり」をテーマに参加者や来場者との交流もたくさん見られました。

第2回 山の資源と暮らし展を開催します

そして、この企画展は全国47都道府県を巡回します。
記念すべき1回目は滋賀でした。
参加者の方とのご縁があり、今年は神奈川県の大磯で行います。
今年の参加者は北海道から大阪まで、合計33名が展示会の趣旨に賛同してくれました。
しかも材料となる生木は、大磯の森林整備団体「里山をきれいにする会すもあ」(薪屋大磯)さんの活動で出た丸太を使わせていただきます!
簡単ですが下記にご紹介させていただきます。
「里山をきれいにする会すもあ」(薪屋大磯)ってどんな団体?


里山をきれいにする会すもあ(薪屋大磯)
「神奈川県大磯町を中心に里山保全活動を行っているボランティア団体です。
今は身近な里山の木を使う人がいなくなり、山が荒れて倒木・獣害などのさまざまな問題が起こっています。ただ木を伐るだけでなく、「薪屋大磯」の屋号で伐った木の活用に取り組んでいます。
大磯の里山の木がうつわになり、そのうつわを暮らしの中で使っていただけることを楽しみにしております。」

今回は薪屋大磯さんが活動拠点にされている山に生えていたスダジイという木を伐採する場面の見学から始まり、山から下ろしてくる作業も体験させていただきました。

チェンソーで玉切りした丸太をログキャリアで運搬します。

斜面ではスリングベルトを使って2人がかりで引きずり下ろします。
 今回はこちらの丸太を購入させていただきました。
今回はこちらの丸太を購入させていただきました。
大磯うつわの日にもエントリーしました!

ということで前置きが長くなりましたが、
「大磯の山から生まれる木のうつわ尽くし」の展示会をやります!
 シオタニミカ
シオタニミカ

 ブレンケ
ブレンケ

 サンビー木工室
サンビー木工室
 UPI Spoon Club
UPI Spoon Club
さらに今年は大磯町で長く続いている手作りのうつわイベント「大磯うつわの日」にもエントリーさせていただいています。
大磯うつわの日とは?
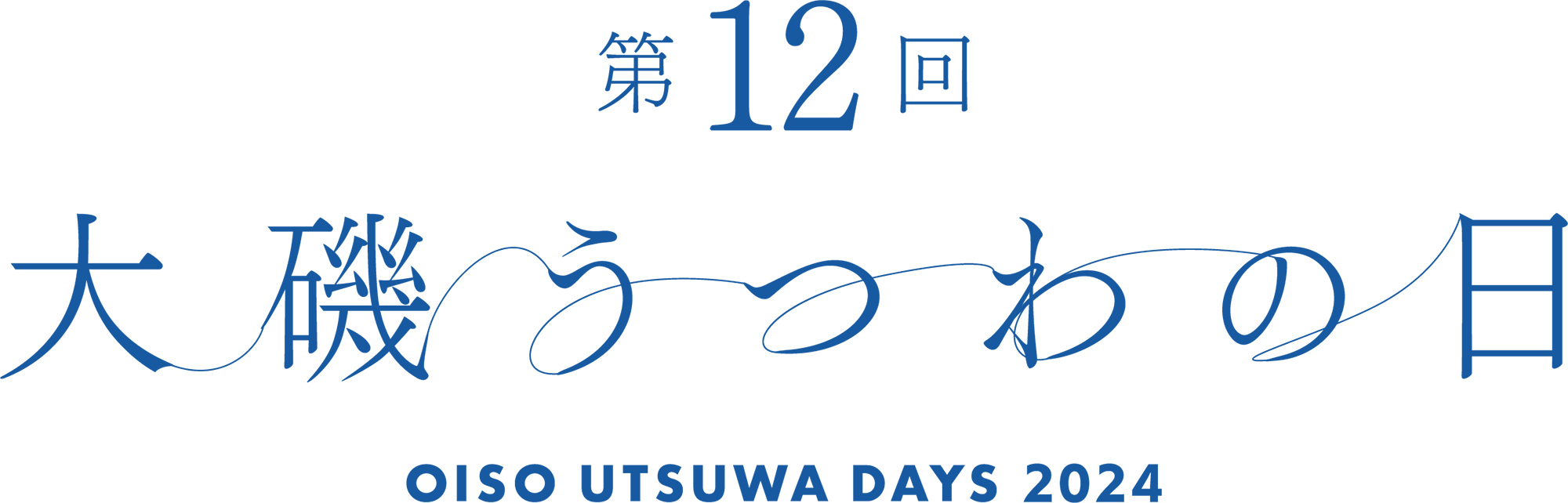
大磯町の60ヶ所で同時に開催される展示会を目指してマップ片手にお客様が練り歩くという、うつわ好きにはたまらないイベントとして関東でも人気のイベントです。
去年の様子は大磯うつわの日公式HPでご覧いただけます。
第11回「大磯うつわの日」の記録を見にいく
なぜクラウドファンディングか?

活動資金の調達にあたり、どうすれば毎年継続して続けられるだけの費用を準備できるか考えました。
「山の資源と暮らし展」のコンセプトは「国産の草木花を無理なく現代の暮らしに取り入れるきっかけを提案する手づくりの展示販売会」です。
生木ラボは発起人として毎年の巡回展示のため旗振り役をさせていただいています。
ただし一度やって終わるのは寂しいので、できれば各地で旗振り役が現れて、毎年の継続イベントとして草の根的に広がっていけばいいなと実は考えていました。
続けて各地に根付く企画にするために
何をするにも些細な出費が経費として発生します。
個人の持ち出しではなく、せめて赤字にはならないように、ちゃんとお客様が楽しみにしてくれるイベントで、なおかつ作品も購入いただけて、作る側も張り合いのある「イケてる」雰囲気になれば勝手に続くのでは?ということで、クラウドファンディングに挑戦する運びとなりました。
各地の特色ある木を使ったり、地元に残る民芸品や郷土品などと生木の木工が結びつくこともありうるでしょう。
そうなれば「その土地に根ざす作り手やものづくり」だからこそ応援したいという方が現れることもあるでしょう。
「実行したい人を応援したい人が支援できる仕組み」がクラウドファンディングだと思うので、
各地の「山の資源と暮らし展」を毎年の楽しみとして、ご支援いただけるような流れが生まれたらこの上ない幸せです!
参加作家によるリターンのご紹介
 シオタニミカ作 「熊山ボウル」リターン価格 39,600円
シオタニミカ作 「熊山ボウル」リターン価格 39,600円
 サンビー木工室 作 「クリの拭き漆匙 」リターン価格 11,000円
サンビー木工室 作 「クリの拭き漆匙 」リターン価格 11,000円
 Kifu 作 「布着せ皿」リターン価格 16,000円
Kifu 作 「布着せ皿」リターン価格 16,000円

ご支援をいただい方へのリターンについてご説明します。
参加者それぞれが普段の制作スタイルでつくった作品を提供いたします。
作品名、作者、作品写真、価格(税込)、技法、サイズ、仕上げ方法などをリターン一覧からご覧いただけるようになっているので、ぜひチェックしてみてください。
通常の価格にプロジェクト支援金を上乗せした金額設定になっておりますので、作家のみなさまへ公正に利益をお渡しいたします。
「プロジェクト支援+作品購入」という意味合いでのリターン購入になります。
作品以外にもワークショップ、木工体験なども期間中に追加される予定なので、ぜひ「山の資源と暮らし展」公式インスタグラムアカウントのフォローもお願いいたします。
アカウントをフォローする
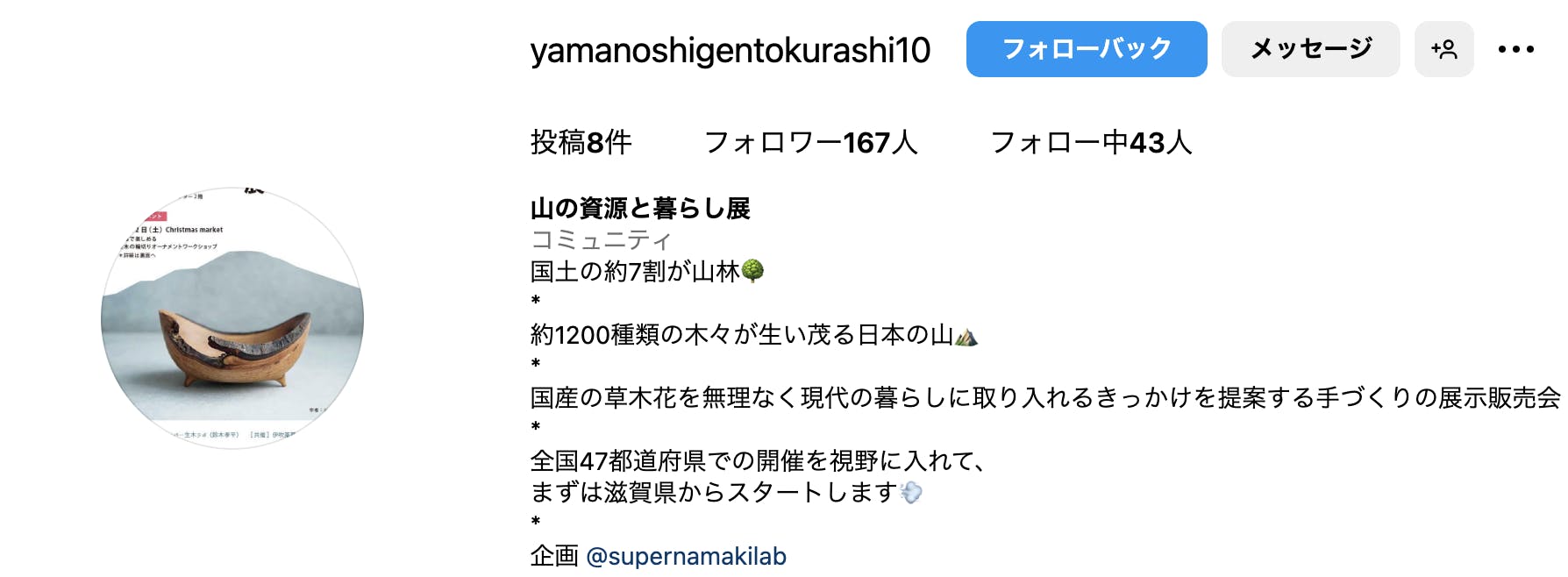
資金の使い道について
総額80万円を目標に設定しています。(70万円+クラウドファンディング手数料17%など)
みなさまからいただいたご支援は下記の内容の通り大切に使わせていただきます。
・展示会の開催に必要な人件費(会場の設営、撤収、会期中のスタッフ日当など)
・広告宣伝費(チラシ、dm、SNS広告など)
・送料運賃(全国の賛同者への丸太を発送)
・材料購入(大磯町の里山の木)
・展示用什器材料費
・車両費(逗子〜大磯のガソリン代)
・備品費 (コピー用紙、インク代、茶菓子等)
今後のスケジュール
9月上旬 クラウドファンディング開始
10月18日(金)〜10月20日(日) 第2回山の資源と暮らし展 in 大磯 開催
11月〜12月 リターン発送
最後に
ご紹介が遅れましたが、実は今回の「山の資源と暮らし展」。
遠方ということもあり、丸太の運搬、発送の段取りから何まで実務的なところは逗子のWOODWORK CENTERさんに全面的なご協力をいただいています。

WOODWORK CENTERさんは会員制のシェア工房として、会員さんの「作りたい!」をありとあらゆる手段で応援している工房です。

店長の靏田さんには1回目の山の資源と暮らし展にも参加いただいたり、ウッドターニングのワークショップ講師としてスーパー生木ラボを招いていただいたりと大変お世話になっています。
そのほかにもメインビジュアルを華麗に作ってくれた鎌倉の木工作家、シオタニミカさん。
それから夏の暑い山で森林整備の活動を快く見せてくださった上に、大磯の里山の木を材料として提供してくださった薪屋大磯のみなさま。
こうしてキーボードを叩いていると、一年ごとに広がっていく「生木の輪」が現実の出来事だということに少しビビってしまうというか、笑ってしまうというか、なんとも不思議な気持ちになります。
とにかくここに書ききれないくらいほかにもたくさんの生木で繋がった友人、知人がいます。
おそらくこの輪が年々広がっていくことになります。
1年、2年、経つにつれて「生木は使えない」「割れるから、反るからダメだよね」
といったネガティブな反応が少しづつ減っていくことでしょう。
そしてこれからは「生木だから面白い」「生木だからイケてる」表現も次々と生み出されるはずです。
近くて遠い存在になった日本の里山が、生木の力でちょっとづつ近づいてくる日も遠くないと願っています。
2024年9月4日
山の資源と暮らし展 発起人
スーパー生木ラボ 代表 鈴木 孝平
応援コメント(順不同、敬称略)

本プロジェクトへいただきました応援メッセージを紹介させていただきます。
---
私も同じように疑問に思っていました。
身近な山の木で作品を創る。
まさにいのちの循環。
この活動があたりまえになる事を願います。
---
鈴木さんは、木の種類や木目の癖を生かして、モノに仕上げるセンスがいい。木が好き、作ることが好きなんだなぁと伝わって来る作品はどれもフッとなついてくるような表情を見せてくれる。うちの工房の仕事は、鈴木さんの仕事とは一見、違うように見えるけれど、木の適材適所を見極めて製作するところは同じ。同じように木工を生業としている者として、鈴木さんのこの活動、応援しています。
---
山の資源が使える仕組みを暮らし展という形で提示した鈴木さん。
この取り組みが全国に広がっていくのを楽しみにしています。
---
ものづくりの現場を訪ね、記録することを生業にしていますが、数年前、それまで気にも留めなかった「生木」の存在に気づかせてくれたのが鈴木さんでした。生木のまま加工ができれば、地域の人が身近な資源を活用でき、結果的に山に人の手が入るようになる。放置資源や荒廃山林の問題が各地で深刻化する今、グリーンウッドワークは現代におけるその糸口であり希望であり、また全ての人にひらかれたツールでもあります。このプロジェクトは、そんな生木の力を信じて、かつては当たり前のように結ばれていた人と自然を繋ぎなおす大きな試み。応援しています。
---
素材がもつ力を引き出すには、その背景にある歴史や土地の文脈を理解することが不可欠です。今回の取り組みは、木材という素材を通して、地域の価値を再発見し、ただの実用品ではなく、文化的な存在意義を見直す挑戦だと感じています。手仕事を通じて素材と人との新たな関係が築かれ、その関係が永続的な価値を生み出すことを期待しています。
---
ごろごろ丸太が。
工房に伺えばこの木が、器になるのかと魔法の様なお仕事ぶり。切られても生きている木の特徴に合わせて仕立てられた器は不思議と手に馴染みます。
家でネットを使えば必要なものが手に入る便利な昨今ですが、昔から人間は自然から多くのものを分け与えられている事を鈴木さんの作品を通して教わりました!
山で生の木に触れ、それが生活に身近な道具となる。自然を敬う素敵な活動に共感し、応援させて頂きます。
---
生木の輪が全国に広まることを願っています!
---
生木で魅力的な作品を生み出し続けるスーパー生木ラボの鈴木孝平さんが、ワクワクするような活動を始めるとお聞きしました。
この企画を通して日本の山や森の木がもっと身近なもの・もっと魅力的なものとして多くの方々に手に取っていただけるようになるでしょう。
鈴木さんが生み出す『生木からつくる作品たちの魅力』で「山の資源と暮らし展」が毎年日本全国を巡り続け、国産木材への関心がより広がっていくことを期待しております。
国産材を製材することを生業としている私にとっても、それが鈴木さんと同じく木を扱うものとしての願いです。
---
鈴木さんが発信して、実際にその手で生み出す生木作品の魅力を、是非たくさんの方に知って欲しいです!
おきばりやす〜!
---
自然に向き合ったモノづくり何度か主催である鈴木さんの個展や工房に行かせていただきその自然の成り行きを活かす、温かみのあるモノづくりが好きで製作を依頼させていただきました。完成が楽しみです。プロジェクトの実施により沢山の方々にも、自然の温もりが届くことを願っております。微力ながら応援させていただきます。
---
生木の器やカトラリーは''生きている''。きっと無理がなく、あるがままになるがままに作られているからであり、割れや反りは木のストーリーを想見させ、唯一無二の個性として大切にされているからだと思う。それを作り出す木と、鈴木さんのおおらかさに私は惹かれて、より自然を好きになった。
---
この度のクラウドファンディングプロジェクトを心より応援したいと思います。
鈴木さんが創り出す器は私達のレストランでも使わせていただいており、木そのものの姿を感じる佇まいや暖かさに惹かれています。
各地での展示会を私たちも楽しみにしています。作家の皆様の作風をこの目と手でしっかり感じ取り、その想いを直接お聞きすることができることを楽しみにしています。
このプロジェクトが実現することで、より多くの人々にこの素晴らしい体験を届けられることを心より期待しています。微力ながら、応援させていただきます。成功をお祈り申し上げます。
---
木の作品に触れていると心が温かくなる、自分の暮らす地域の自然が愛おしくなる、そう感じます。人の暮らしと密接に関わり循環してきた里山の自然。山に自生する樹木や山野草を豊かに暮らしの中に繋げていくことは、文化を継承していくことでもあり人間を含むすべての生き物の生命を豊かに繋げていくこと。未来に何を伝えていきたいかが、鈴木さんの活動にぎゅっと詰まっていると感じます。
---
スーパー生木ラボさんの活動は、ご家族で移住されてきてから注目してきました。最近は制作物や活動の幅も拡がり、身近な資源の活用について、気付かされる事も多いです。今回の「山と資源と暮らし展」は「山」も「資源」も「暮らし」に繋がっているというコンセプトは、「暮らし」という豊かさについてドキドキする機会があるのかと、ワクワクします。微力ながら応援させていただきます。この活動がもっと色々な人との関わりになることを応援しています。
---
やまくら第二回目の開催おめでとうございます!参加者さまもたくさんですばらしうれしいですわね。奥深く楽しく時においしい可能性無限大のハッピー生木ワールドが広がり繋がっていきますように。人外枠からも全力応援いたします。フレッフレッ生木フレッシュフレッシュ生木ワーーー
---
生木ラボさんの取り組みは常に、地域に根差し地に足のついた堅実さと、今回の企画のような野心的さがあって、いつもワクワクするような未来を想像させられますね。微力ながら応援しています!
---
山や森を守るのは簡単なことではないと思いますが、声をあげてくださりありがとうございます。たくさんの方が、身近なものから木を好きになって、森への関心も深まるといいなと思います!
---
鈴木さんの展示会の際、生木の温もりや香りを感じ、生木ならではの魅力を知りました。木のヒビ割れや穴、これは作品の個性としてあえて残して仕上げるというのも面白いアイデアだなと思いました。自然のままに出来上がる作品の良さをもっとたくさんの人に伝わることを願っています。活動を続けていくことがより多くの人に知ってもらえる1番の近道なのでは…と思います。展示会の成功、そしてこれからの出会いや、この輪がより広がっていくよう応援させていただきます。
---
私自身、林業が盛んな山で育ち自然はいつも近くにありました山や自然には、便利になりすぎた世の中が失いつつある"豊かさ"が確かに在ります鈴木さんの作品からは木がきちんと生きていた痕跡が色濃く残り、それらからは、木々が揺れる音や水の流れる音までも聞こえるような、迫力を感じます。自然の循環、この素晴らしい活動を微力ながら応援させていただきます。
---
自分たちの身近な山や森の使われていない木を気軽に使って自分で自由にものが作れたら最高に楽しいと思う
生木ラボの鈴木さんはそれを形にしているカッコいい人
そんな鈴木さんが仲間たちと日本の山や森を身近に感じてもらうための展示会「山の資源と暮らし展」を全国で開催していくためのクラファンを立ち上げます。
今は身近な里山の木を使う人がいなくなり、山が荒れて倒木・獣害などのさまざまな問題が起こっています。人の暮らしが里山から離れその大切さも忘れてしまいました。
鈴木さんたちが行う生木を使ったモノづくりはそれを繋ぎ直してくれる古くて新しい技術。まるで漆みたいだと感じています。
何より生木のモノづくり、カッコいいのでぜひ見て欲しい。
鈴木さんがやってるモノづくりは楽しそうなのでぜひ感じて欲しいです。
僕もウルシの木を山に植えるようになって山のことを少しづつ知るようになりました。山や素材に近づくことはとても楽しいし世界が変わって見えるようになると感じています。
漆と人の暮らしが離れて漆の量が減って行きました。
人が山に入らなくなり山が荒れていきました。山や森を次世代に楽しく繋ぐために僕たちにもできることがある。
この「山の資源と暮らし展」がこれから全国で開催されて地元の山や森と人を繋ぐ架け橋になってくれることを願っています。
---
自然に寄り添うものづくりをされる鈴木さんにより、国内の木の多様さ面白さを改めて感じ、私も手に取り愛でています。日本の豊かな資源に目を向ける、このご活動に賛同します。












コメント
もっと見る