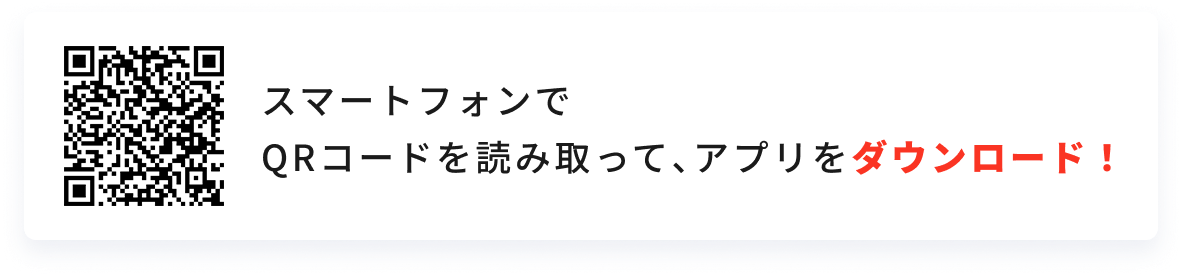50年代の牧志公設市場の様子
【TITLE】PLAY BACK 沖縄【Director】島田雄史【Length】About 20min
50年代の牧志公設市場の様子
【TITLE】PLAY BACK 沖縄【Director】島田雄史【Length】About 20min
INTRODUCTION
FAAVOをご覧のみなさん、はじめまして!島田雄史といいます。 神奈川生まれ神奈川育ちの私ですが、幼い頃、祖母から琉球王国の尚家の血が流れていると聞かされていました。祖母自身、戦時中、学年が対象外で前線には行く事がありませんでしたが、ひめゆり女学校の一生徒でした。私は沖縄には人生で2度しか行った事がありませんし、しかも一度は高校の修学旅行です。 現在私は東京で映画製作の世界にいますが、私のように遠く離れた街の人間にも沖縄の血が少なからず流れています。その事実を受け止めつつ、今、私は生活しています。 今回の「地元ショートフィルム・ファンディングプロジェクト」では、 旅に出る事でその人にとって人生の契機になるような経験を描く事。また、観光地としてあまり知られていない 秘めた沖縄の食文化、人の温かさを描き出したいと考えています。 私の個人的な経験を元に、ドキュメンタリー/フィクション要素を取り入れ制作致します。STORY
MAIN CHARACTER ◉リュウ(25)… 番組制作会社で働いていたが、現在は失業中。 ◉ケイ (23)… リュウの彼女。ブティックで働いている。 ◉肉屋のおばちゃん(54)… 沖縄の中央市場で肉屋を経営 ◉そば屋のおっちゃん(58)…沖縄の中央市場でそば屋を経営 TV番組制作会社で働いていたリュウ(25)は、変わらない日常を抜け出したくなって仕事を辞めた。 同棲している彼女のケイ(23)は、そんなリュウを心配しつつ彼に旅に出るように促す。東京育ちのリュウは先祖のルーツが沖縄にある事を小さい頃から聞かされていて、その街に旅立つ決意をした。 向った先は 那覇市の中央市場。そこの肉屋のおばちゃんや、ソーキそば屋のおっちゃん達との出会いによって、リュウの心の中に変化が現れる。PVあらすじ〜タイトル「(仮)PLAY BACK 沖縄」
起
 東京のTV番組制作会社で働いていたリュウ(25)は、変わらない日常を抜け出したくなって仕事を辞めた。
けれども、何をすれば自分に充実感が得られるのか分からず、途方に暮れる毎日を過ごしてしまう。再度、番組制作会社に就職しようと考えるが、度重なるルーティーン作業を思い出しやめてしまう。
同棲している彼女のケイ(23)は、そんなリュウを心配して旅に出るよう促す。
行き先は「都会と違う時間が流れるっていうから」という理由で沖縄を薦られる。
「一緒に行こうよ」とリュウはケイを誘うが、首を縦に振らない。
「今のリュウには一人で考える時間が必要なんだよ」
しぶしぶケイの薦めを受け入れて、リュウはカメラバックに一眼レフを詰め込み、沖縄へと向った。
東京のTV番組制作会社で働いていたリュウ(25)は、変わらない日常を抜け出したくなって仕事を辞めた。
けれども、何をすれば自分に充実感が得られるのか分からず、途方に暮れる毎日を過ごしてしまう。再度、番組制作会社に就職しようと考えるが、度重なるルーティーン作業を思い出しやめてしまう。
同棲している彼女のケイ(23)は、そんなリュウを心配して旅に出るよう促す。
行き先は「都会と違う時間が流れるっていうから」という理由で沖縄を薦られる。
「一緒に行こうよ」とリュウはケイを誘うが、首を縦に振らない。
「今のリュウには一人で考える時間が必要なんだよ」
しぶしぶケイの薦めを受け入れて、リュウはカメラバックに一眼レフを詰め込み、沖縄へと向った。
承
 ▲市場の近くには1杯300円でソーキそばが食べられる。
リュウにとって沖縄はそう遠い存在ではなかった。
大学時代、自転車で東京から沖縄に向かって旅をした事があったからだ。
今思うと、何がその衝動へかき立てたのか分からない。当時、出会った市場のおばちゃんとの思い出が蘇る。
長旅でお金もなく、空腹だった時、おばちゃんに案内され、ソーキそば屋でおごって貰った。
一杯300円で、もの凄く美味しかった記憶がある。
「那覇に着いたら、直ぐにあの店に行ってみよう」リュウは密かな決意をした。
▲市場の近くには1杯300円でソーキそばが食べられる。
リュウにとって沖縄はそう遠い存在ではなかった。
大学時代、自転車で東京から沖縄に向かって旅をした事があったからだ。
今思うと、何がその衝動へかき立てたのか分からない。当時、出会った市場のおばちゃんとの思い出が蘇る。
長旅でお金もなく、空腹だった時、おばちゃんに案内され、ソーキそば屋でおごって貰った。
一杯300円で、もの凄く美味しかった記憶がある。
「那覇に着いたら、直ぐにあの店に行ってみよう」リュウは密かな決意をした。
転
 ▲那覇市の国際通り横にある牧志公設市場。
那覇市に着いたリュウは早速、牧志公設市場へ向う。
そこで、偶然にも以前、お世話になった肉屋のおばちゃんと再会する。そのおばちゃんはリュウの事を覚えてくれていた。
▲那覇市の国際通り横にある牧志公設市場。
那覇市に着いたリュウは早速、牧志公設市場へ向う。
そこで、偶然にも以前、お世話になった肉屋のおばちゃんと再会する。そのおばちゃんはリュウの事を覚えてくれていた。
 ▲市場で働くおばぁ。市場の人達は人情味がある。
東京の人々の淡白な空気とは異なり、人情というものがこの街に残っている事を再確認するリュウ。
「あのソーキそば屋ってどこでしたっけ?」と多少興奮気味に尋ねるリュウ。
「…実はね、あそこの店、たたんじゃったの。もう続けられないって」
▲市場で働くおばぁ。市場の人達は人情味がある。
東京の人々の淡白な空気とは異なり、人情というものがこの街に残っている事を再確認するリュウ。
「あのソーキそば屋ってどこでしたっけ?」と多少興奮気味に尋ねるリュウ。
「…実はね、あそこの店、たたんじゃったの。もう続けられないって」
結
 以前、訪れた時には気付かなかったが、牧志公設市場の老朽化や、衰退化が目につくようになっていた。
リュウはその街の現状をカメラに収めようと何度もシャッターを切る。
市場の現状を知りながらも、カメラに写る街の人々は生き生きとしていて、活気に溢れていた。リュウの心は段々と穏やかになっていく。
沖縄出発の朝。
リュウは、再度肉屋のおばちゃんを尋ねた。滞在中に取り溜めた写真を見せる。
「この街の発展の為に、ここを舞台にした映画を撮るからおばちゃんの店はたたまないでよ」
リュウはそう約束を告げて、沖縄の街を後にした。
帰りの機内。リュウはパソコンに向って映画の構想を練っている。
以前、訪れた時には気付かなかったが、牧志公設市場の老朽化や、衰退化が目につくようになっていた。
リュウはその街の現状をカメラに収めようと何度もシャッターを切る。
市場の現状を知りながらも、カメラに写る街の人々は生き生きとしていて、活気に溢れていた。リュウの心は段々と穏やかになっていく。
沖縄出発の朝。
リュウは、再度肉屋のおばちゃんを尋ねた。滞在中に取り溜めた写真を見せる。
「この街の発展の為に、ここを舞台にした映画を撮るからおばちゃんの店はたたまないでよ」
リュウはそう約束を告げて、沖縄の街を後にした。
帰りの機内。リュウはパソコンに向って映画の構想を練っている。
監督紹介&過去実績
 島田雅史
1991年神奈川県生まれ。東京造形大学在学中より監督作品を中心に映画製作現場に参加し、出演、制作、助監督などを経験。現在も映画、PVなどの現場を踏みつつ、自主製作映画を手がけている。高校の友人との対話を描いた「友人との時間」ヒロシマをテーマにした「H/2」を製作。家族との関係、労働と幸福をテーマにした映画「家族のありかた」が2014年1月末に完成予定。
2013年9月・・・・・・第18回 ながおか映画祭出品
「橙と群青」監督:赤羽健太郎
現在・・・・・・・・・・・・映画「家族のありかた」監督:島田雄史 製作中
島田雅史
1991年神奈川県生まれ。東京造形大学在学中より監督作品を中心に映画製作現場に参加し、出演、制作、助監督などを経験。現在も映画、PVなどの現場を踏みつつ、自主製作映画を手がけている。高校の友人との対話を描いた「友人との時間」ヒロシマをテーマにした「H/2」を製作。家族との関係、労働と幸福をテーマにした映画「家族のありかた」が2014年1月末に完成予定。
2013年9月・・・・・・第18回 ながおか映画祭出品
「橙と群青」監督:赤羽健太郎
現在・・・・・・・・・・・・映画「家族のありかた」監督:島田雄史 製作中
過去実績
2011年 制作「友人との時間」 2012年 制作「H/2」支援金用途
制作費6万円(小道具・ロケ地使用料など) 機材費3万円 渡航費3万円 滞在費3万円 ーーーーーーー 合計 15万円制作スタッフ
監督:島田雄史 リュウ役:島田雄史 ケイ役:オーディション予定 エキストラ/ボランティアスタッフ:牧志公設市場のみなさま制作スケジュール
2014年1月・・・脚本推敲、街調べ 1/31~・・・・・・オーディション、ロケハン 2/3~・・・・・・・脚本改稿、リハーサル 2/8、9・・・・・・東京パート撮影 2/10・・・・・・・・沖縄入り 2/11~16・・・・沖縄パート撮影 2/17~・・・・・・編集 2/28・・・・・・・・完成最後に
この映画は私が数年前、沖縄に自転車で向った旅の体験をもとに構成しています。いわば、私は沖縄の“訪問者”でしかありません。ですが、その訪問者の視線で沖縄の現状を撮影し、魅力を再発見出来れば幸いです。 Director’s Statement 今年の二月、私は自転車で東京 から沖縄に向って走り出した。 今、思うとその衝動の根元に何があったのかわからない。退屈した日常からの逃避行なのか、または自分の死に場所を探していたのか?記憶に乳白色のフィルターが掛けられたかのように、 旅立った時の気持ちを思い出す事が出来ない。 今となっては、そのような物が旅の本質なのかもしれないと思う時がある。 何日間か自転車を漕ぎ続けて辿り着いた那覇の街。
国際通りの賑わいや、南国独特の人との触れ合いやすさ。達成感とも相まって心地よい時間の流れに身を任せていた。けれども、そういつまでも旅行気分に浸れるわけではない。
現実に引き戻されると、帰りの移動費と、残り僅かのお金しか持っておらず、その日は仕方なく寝袋にくるまって公園で一夜を過ごす事に。
まだ、夜も早かったので遠くから街の賑わいが微かに聞こえてくる。
「このままこの街で生きていくのもありかもなぁ〜」そう思いながら、寝袋に包まっていると公園の入口でぽつんと佇むおばちゃんがいる。
ちょっと不気味に感じて身体を起こすと、そのおばちゃんが段々と近づいてくる。
背は150あるか、ないかで、お世辞にも綺麗とは言えないジャケットを羽織っている。
恐怖心を感じながらも、逃げる訳にはいかず、視線を合わせないように遠くを眺めているふりをしていたら、そのおばちゃんは私の目の前まで近づいてきて、こういった。
「…お腹、空いているか?」
確かにその日の朝は、リュックに詰めてあった餅をコンビニのお湯でやわらかくして食べただけの食事だったから、満腹なわけではない。
「…はい」
恐る恐る、返事をしてみる。
「…お前さん、ソーキそば食べるか?上手い店あるんだよ」
「…でも…」
「…いやっ、本当安いから、おごってあげるよ」
申し訳ない気持ちと、久しぶりのまとまった食事を食べられるありがたさを感じながら、荷物をまとめてそのおばちゃんについていくことにした。
夜の賑わいが残る国際通りを抜けて、中央市場の路地へと入っていく。
ここは戦後、闇市として発展した名残で、今も商店の人々の助け合いのもとに成り立っている。
ぐいぐいと進んでいくおばちゃんの背中を追いかけ、しばらくして辿り着いたのがカウンター席が数個しかない小さなソーキそばや。
店の暖簾もなく、シャッターを開けたらすぐ目の前がカウンターという店の構造で、中にはおっちゃんが、一人ぽつんと新聞を読みながら丸椅子に座っている。
「やべっ、失敗したかな」と、気の優しそうなおばちゃんに着いて来たのを後悔しつつも「おごってもらえるんだから、そんな事、思っちゃダメだろ」という気持ちを抱きながら、とりあえずカウンター席に座る。
「おいっ、連れて来たで、お客さん!!」
新聞紙から一切顔を見せない店のマスターに向っておばちゃんが声を掛ける。
マスターは無愛想に目も合わさず、新聞紙を折り畳んで、慣れた手つきでなべに麺を入れる。見回すとこの店にはメニューがない。ソーキそばだけしか置いていないのだろうか。
そばが出来るまで、隣に座ったおばちゃんと話をした。聞くところによると、おばちゃんは近くで肉屋をやっているとのこと。最近は国際通りの賑わいの為かあまり店の状況は良くないと嘆いていた。そのおばちゃんにも、自分と同じ位の息子が居て、今は東京で暮らしている。自分がその息子のように思えて、なんだか可哀想になって声を掛けてくれたとの事だった。
そうこうしていると、ドンブリいっぱいに入ったソーキそばがカウンターの上に二つ並べられる。
「はい、二つで600円」
「…600円!!」私は心の中で呟いた。
「こんなに麺やソーキが入っていて、一杯300円って!!…本当に大丈夫だろうか?」
そうこう思いつつも、見た目はシンプルでとても良い香りが漂っている。おばちゃんに箸を渡されて、恐る恐る麺を啜る。
「…うまい!!」
深いだしの香りと、歯ごたえの良い麺。次にソーキを口に運ぶ。とても柔らかく、味も染みて、思わず微笑んでしまった。
「美味しいですね!!」
おばちゃんに話しかける。「当たり前でしょ、ここは戦後からずっと変わらない味で商売してるんだから」
おばちゃんは得意げな顔で、息子に似た自分が美味しそうにソーキそばを食べるのを嬉しがっていた。店のマスターは、自分たちに話しかける訳でもなく、事が済んだように、また丸椅子に座って新聞を読み始める。
あんなにも美味しい麺類を食べたのは初めてだった。しかも300円という安さ。不思議な巡り会いで出会えたおばちゃんに感謝の気持ちを抱きながらその夜は、別れを告げた。
翌日、教えてくれたおばちゃんの肉屋に行ってみた。そこは話しで聞いていたように、 人気がなく、寂れたような雰囲気だった。自分が美味しそうにソーキそばを食べている姿を微笑ましく眺めていたおばちゃんの姿とは違って、どこか物寂しそうだった。そのおばちゃんと軽く話しをしてから、気になって、ソーキそばの店にも行ってみた。その日もマスターは新聞紙を広げて、丸椅子に座っている。あんなにも美味しいソーキそばなのにお客さんが誰一人として居なかった。
それから数日して私は東京に戻りました。
あの街でそのまま暮らしてしまおうか迷ったのですが、あの心優しいおばちゃんやソーキそばの味をどうにか人々に伝える事は出来ないか?
こんな自分でも、何か人の為に出来る事があるんじゃないのか?
そう思ってもう一度、東京の街に戻ってきました。
今回の制作でその思いを実現させたいと考えています。
どうぞあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。
何日間か自転車を漕ぎ続けて辿り着いた那覇の街。
国際通りの賑わいや、南国独特の人との触れ合いやすさ。達成感とも相まって心地よい時間の流れに身を任せていた。けれども、そういつまでも旅行気分に浸れるわけではない。
現実に引き戻されると、帰りの移動費と、残り僅かのお金しか持っておらず、その日は仕方なく寝袋にくるまって公園で一夜を過ごす事に。
まだ、夜も早かったので遠くから街の賑わいが微かに聞こえてくる。
「このままこの街で生きていくのもありかもなぁ〜」そう思いながら、寝袋に包まっていると公園の入口でぽつんと佇むおばちゃんがいる。
ちょっと不気味に感じて身体を起こすと、そのおばちゃんが段々と近づいてくる。
背は150あるか、ないかで、お世辞にも綺麗とは言えないジャケットを羽織っている。
恐怖心を感じながらも、逃げる訳にはいかず、視線を合わせないように遠くを眺めているふりをしていたら、そのおばちゃんは私の目の前まで近づいてきて、こういった。
「…お腹、空いているか?」
確かにその日の朝は、リュックに詰めてあった餅をコンビニのお湯でやわらかくして食べただけの食事だったから、満腹なわけではない。
「…はい」
恐る恐る、返事をしてみる。
「…お前さん、ソーキそば食べるか?上手い店あるんだよ」
「…でも…」
「…いやっ、本当安いから、おごってあげるよ」
申し訳ない気持ちと、久しぶりのまとまった食事を食べられるありがたさを感じながら、荷物をまとめてそのおばちゃんについていくことにした。
夜の賑わいが残る国際通りを抜けて、中央市場の路地へと入っていく。
ここは戦後、闇市として発展した名残で、今も商店の人々の助け合いのもとに成り立っている。
ぐいぐいと進んでいくおばちゃんの背中を追いかけ、しばらくして辿り着いたのがカウンター席が数個しかない小さなソーキそばや。
店の暖簾もなく、シャッターを開けたらすぐ目の前がカウンターという店の構造で、中にはおっちゃんが、一人ぽつんと新聞を読みながら丸椅子に座っている。
「やべっ、失敗したかな」と、気の優しそうなおばちゃんに着いて来たのを後悔しつつも「おごってもらえるんだから、そんな事、思っちゃダメだろ」という気持ちを抱きながら、とりあえずカウンター席に座る。
「おいっ、連れて来たで、お客さん!!」
新聞紙から一切顔を見せない店のマスターに向っておばちゃんが声を掛ける。
マスターは無愛想に目も合わさず、新聞紙を折り畳んで、慣れた手つきでなべに麺を入れる。見回すとこの店にはメニューがない。ソーキそばだけしか置いていないのだろうか。
そばが出来るまで、隣に座ったおばちゃんと話をした。聞くところによると、おばちゃんは近くで肉屋をやっているとのこと。最近は国際通りの賑わいの為かあまり店の状況は良くないと嘆いていた。そのおばちゃんにも、自分と同じ位の息子が居て、今は東京で暮らしている。自分がその息子のように思えて、なんだか可哀想になって声を掛けてくれたとの事だった。
そうこうしていると、ドンブリいっぱいに入ったソーキそばがカウンターの上に二つ並べられる。
「はい、二つで600円」
「…600円!!」私は心の中で呟いた。
「こんなに麺やソーキが入っていて、一杯300円って!!…本当に大丈夫だろうか?」
そうこう思いつつも、見た目はシンプルでとても良い香りが漂っている。おばちゃんに箸を渡されて、恐る恐る麺を啜る。
「…うまい!!」
深いだしの香りと、歯ごたえの良い麺。次にソーキを口に運ぶ。とても柔らかく、味も染みて、思わず微笑んでしまった。
「美味しいですね!!」
おばちゃんに話しかける。「当たり前でしょ、ここは戦後からずっと変わらない味で商売してるんだから」
おばちゃんは得意げな顔で、息子に似た自分が美味しそうにソーキそばを食べるのを嬉しがっていた。店のマスターは、自分たちに話しかける訳でもなく、事が済んだように、また丸椅子に座って新聞を読み始める。
あんなにも美味しい麺類を食べたのは初めてだった。しかも300円という安さ。不思議な巡り会いで出会えたおばちゃんに感謝の気持ちを抱きながらその夜は、別れを告げた。
翌日、教えてくれたおばちゃんの肉屋に行ってみた。そこは話しで聞いていたように、 人気がなく、寂れたような雰囲気だった。自分が美味しそうにソーキそばを食べている姿を微笑ましく眺めていたおばちゃんの姿とは違って、どこか物寂しそうだった。そのおばちゃんと軽く話しをしてから、気になって、ソーキそばの店にも行ってみた。その日もマスターは新聞紙を広げて、丸椅子に座っている。あんなにも美味しいソーキそばなのにお客さんが誰一人として居なかった。
それから数日して私は東京に戻りました。
あの街でそのまま暮らしてしまおうか迷ったのですが、あの心優しいおばちゃんやソーキそばの味をどうにか人々に伝える事は出来ないか?
こんな自分でも、何か人の為に出来る事があるんじゃないのか?
そう思ってもう一度、東京の街に戻ってきました。
今回の制作でその思いを実現させたいと考えています。
どうぞあたたかいご支援をよろしくお願いいたします。