皆さん、こんにちは。「Adoption for Happiness = アダプション・フォー・ハピネス(幸せになるための特別養子縁組)」プロジェクト発起人のネルソン聡子です。今回、特別養子縁組が「特別」ではなくなる社会を目指し、養子縁組に関する海外のドキュメンタリーや当事者へのインタビューなどを見てもらいたいと考えプロジェクトを立ち上げました。これは、自分自身が養子を迎えた時にいろいろと感じたことがきっかけとなっています。
ぜひとも映像作品の翻訳費、配信費、配信用ウェブサイト制作費、初年度の運営費にご支援を頂きたく思います!運営体制が整ったら、このウェブサイトを使って特別養子縁組制度や里親制度などに関する映像配信の他、関連書籍の紹介、翻訳出版書籍の販売、関連情報の発信を行い、イベント開催もできたらと考えています。最後までお読みいただけると嬉しいです。
★配信権獲得作品★
「I'll see you later」トレーラー(英語版)
クラファンが成功しましたら、こちらにも字幕をつけます!
養親が養子に迎えた子どもを育てる中で、産みの親も子どもの人生の一部として存在する養子縁組=オープンアダプション。オープンアダプションを経験した養子、養親、産みの親の言葉を通して、養子縁組のあり方を描いている。
★配信権獲得作品★
「I am a secret」のアンドリュー・カンテッラ監督からのメッセージ
母親と息子、娘の3人家族。彼らの中で養子じゃないのは息子だけ。母親も養子当事者、妹もインドから養子として迎え入れられている。「2人(母親と妹)にとって、養子であるとはどういうことなのだろう。」 この問いの答えを知るため息子はカメラを回し始め、家族だからこその距離感で母親と妹の胸の内に迫っていく作品。
本プロジェクトはAll-or-Nothing方式で実施します。目標金額に満たない場合、計画の実行及びリターンのお届けはできませんので、ご支援・拡散のほど、どうぞよろしくお願いいたします!
目次
-------------------------------------------
【1】このプロジェクトで実現したいこと
・養子を迎えたら「おめでとう!」と言ってもらいたいんです!
・「養子に出す/養子を迎える/養子になる」が、特別ではない社会にしたいんです!
【2】そのためにどうするの? 支援したら何ができるようになるの?
・多くの人に養子、養親、産みの親の「生の声」を届けたい!
・そのために養子縁組に関する海外のドキュメンタリー、当事者のインタビュー映像に日本語字幕をつけて配信します。
【3】どんな作品を配信するの?
・「産みの親の声」「養子の声」「養親の声」「制度の話」をテーマにしたドキュメンタリーやインタビュー映像を考えています。
【4】プロジェクト立ち上げのきっかけ
・特別養子縁組の手続き中、直面した数々の困難。
・日本における子どもの養子はたった1%なんて…。
・「養子に出す/養子を迎える/養子になる」は隠すべきこと?
・特別養子縁組に対するネガティブなイメージを払拭したい!!
・人々が未来に希望を抱ける「これからの選択」としての、特別養子縁組のイメージ構築へ
---------------------------------------
【1】このプロジェクトを通して実現したいこと
養子を迎えたら「おめでとう!」と言ってもらいたいんです!
海外の友人などに「養子を迎えることにしたの」と言うと「おめでとう!」と祝福してくれます。一方、日本の友人などに同じことを伝えると、何か奥歯に物が挟まったような… そっけない反応になることが少なくありません。悪気がないことは分かっていますが、やはりこの違いは大きいなと感じています。特別養子縁組は「子どもが幸せになるための制度」だということ、それをもっと広めていきたいです!
「養子に出す/養子を迎える/養子になる」が、特別ではない社会にしたいんです!
私が娘と電車に乗り、隣に座った年配の女性と話をしていた時のことです。話の流れで私が娘を養子縁組したと話すと、その女性は「あなた、とても立派ね」と仰いました。サラッと出てきた言葉ですが、私は違和感を覚えたのです。この方は私を褒めてくださったのだと思います。ですが、養子を迎えることは「立派なこと」で「普通じゃない」と思われているというのが、もどかしく感じました。養子に出す、養子を迎える、養子になる。これが普通の出来事として受け入れられる、それぞれがより生きやすくなる世の中にしたいと思います!
【2】そのためにどうするの? 支援したら何ができるようになるの?
多くの人に養子、養親、産みの親の、生の声を届けたい!
まずは興味を持ってもらうこと。それは制度や仕組みについてもそうですが、「関わっている当事者の声を聞くことが、人が興味を持つきっかけになるのではないか?」と思っています。ですが、日本では声を上げる当事者はまだあまりいません。最近になり、養子を迎えたことを公にする方も出てきていますが、その数は圧倒的に少ないのが現状です。そこで、養子縁組(海外では「特別」というくくりがありません)が日本より盛んな海外のドキュメンタリーや当事者へのインタビューを発信して、「特別養子縁組」について多くの人に知ってもらいたいと考えました。

養子縁組に関する海外のドキュメンタリー、当事者のインタビュー映像に日本語字幕をつけて配信します!
養子縁組の当事者「養子、産みの親、養親」の生の声が伝わり、人々がインスピレーションを得たり、そこから気づきが生まれたりするようなドキュメンタリーやインタビュー映像を配信します。
海外の映像にこだわったのは、プロジェクトメンバーが映像字幕翻訳者(日本語字幕を制作する翻訳者)だということもありますが、映像には「人々の心にダイレクトに訴えかける力が」あり「見た人それぞれが解釈する余白がある」からです。
また、今の時代、映像はスマホがあれば「すぐに」「気軽に」見られます。この「気軽さ」で、養子縁組というものを知るきっかけを作りたいと思います!
 image by Freepik
image by Freepik
【3】どんな作品を配信するの?
「産みの親の声」「養子の声」「養親の声」「制度の話」を中心とした、様々な角度で作られた映像を見てもらえるようにと考えています。

今回(初年度)は、約10作品の配信を予定しています!現時点で映像制作者から配信権を頂いている作品は7作品です。現在、他の作品も引き続き交渉を進めていますので、配信権が得られた作品を続々UPしていきます!
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【テーマ1】アダプション(養子縁組)、オープンアダプションの取り組み
オープンアダプションは、文化や制度の違いなどもあり、その概念自体が日本では浸透していません。オープンアダプションでは、子どもを養子に出した後も産みの親と育ての親が交流を続け、時には子どもと一緒に過ごすこともあります。産みの親は養親のプロフィールなどを見て、子どもの将来や幸せを考えながら養親を選ぶことができ、産みの親と養親が直接的または間接的に関わり合いながら養子縁組の手続きを進めるのが特徴です(団体にもよります)。オープンアダプションには色々な形態がありますが、子どものアイデンティティ形成や出自を知る権利が大切になっている今、これからの将来、日本でも議論されていくのではないでしょうか?
★配信権獲得★
「I'll see you later」

養親が養子に迎えた子どもを育てる中で、産みの親も子どもの人生の一部として存在する養子縁組=オープンアダプション。オープンアダプションを経験した養子、養親、産みの親の言葉を通して、養子縁組のあり方を描いている。当事者が養子縁組を前向きに捉えている姿が印象的で、日本における養子縁組に関する考え方にインスピレーションを与えるであろう作品。海外で数々の映画祭に出品、賞も受賞している。(55分)
受賞歴:
2021 Impact DOCS Award Winner, 2021 Better World Film Festival Winner, 2021 Life Fest Award Winner for Best Feature Documentary
公式出品:
Central Alberta Film Festival, Calgary Independent Film Festival, Ottawa Canadian Film Festival, Toronto Lift-Off Film Fest, Film For Peace Festival, Mosaic Film Festival, Triumphant Film Series, Mosaic Film Festival, International Social Change Film Festival, and others.

★配信権獲得★
「I am a secret」

母親と息子、娘の3人家族。彼らの中で養子じゃないのは息子だけ。母親も養子当事者、妹もインドから養子として迎え入れられている。「2人(母親と妹)にとって、養子であるとはどういうことなのだろう。」 この問いの答えを知るため息子はカメラを回し始め、家族だからこその距離感で母親と妹の胸の内に迫っていく。「パズルのピースがいつも欠けている感じがする。」「一つのピースを見つけても、また次のピースを見つける作業。これは一生続いていくもの。」こう話す母親と妹の会話からは、養子縁組というものが人の一生に影響を与えていくものだと分かる。作品を撮ったのは、若手の映画プロデューサーのアンドリュー・カンテッラ。アメリカの映画祭で高い評価を受けた「One night in Tokyo」の製作総指揮を務めている。(11分)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【テーマ2】10代の養子縁組
養子縁組を考える人のほとんどが新生児を望みます。愛着形成のためでもあると思いますが、ある程度の年齢を超えると、そのまま施設で過ごし18歳になったら自立せざるを得ない現状があります。ティーンエイジャーは多感な時期でもあり愛着形成が難しいと思われることも多いですが、18歳で社会にある意味「放り出されてしまう」ことも問題となっている今、10代の養子縁組にも焦点が当たるといいなと思います。
「Take a Chance on Me」(交渉中)

10歳から里親に預けられ2度の養子縁組に失敗。その後は誰も彼を欲しがらず施設で暮らしていたダリエンは、家族を見つけることを諦めていた。しかし、ある若いカップルが一緒に暮らそうと言ってきたのだ。養子になるためにもう一度新しい里親の元で暮らすのか、それとも、このまま養護施設で過ごし18才になると同時に1人で生きていくのか。ダリエンは決断を迫られていた。ダリエン自身、そしてダリエンの養親へのインタビューを中心に構成されている。(34分)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【テーマ3】養子当事者の声
養子に迎えられた当事者が考えていることって? これは、養親であれば誰もが知りたいと思うことではないでしょうか。養子縁組は成立すれば終わりではありません。養子縁組をされた子どもたちにとって(養親と産みの親にとっても)、生涯を通して向き合う事実なのです。最近では「子どもが出自を知る権利」も議論され始めましたが、日本ではまだまだ「子どもの声」を聞くことがまれです。養子として迎えられた子どもたちの気持ちや葛藤などの生の声に耳を傾けてみませんか?
映像を提供してくれるのは、イギリスで最も大きい養子縁組団体のひとつである「PAC-UK」。特に10代や産みの親に対するサポートに注力しており、その取り組みはイギリス国内のみならず世界各国から注目を集めています。
★配信権獲得★
「Messages for Adoptive Parents from Adopted People」

10代~成人した養子当事者たちが自分たちの過去を振り返り、これから養親になる人たち、すでに養親で子どもを育てている人たちへメッセージを伝える短編作品。「喪失とトラウマ(LOSS AND TRAUMA)」「恥じる気持ち(SHAME)」「アイデンティティ(IDENTITY)」「異なる人種間での養子縁組(TRANSRACIAL ADOPTION)」「誠実さと透明性(HONESTY AND TRANSPARENCY)」といった様々なテーマをもとに、当事者たちが素直な気持ちを語っている。(26分)

★配信権獲得★
「Voices of Adopted Teens」

10代の養子縁組の当事者たちが集まり、街行く人への養子に関するインタビューを見ながら、自分たちの気持ちを話し議論していく作品。「養子になるって、どんな気持ち?」「養子の子どもは、生きるうえで不利だと思う?」「10代の養子当事者たちは、産みの親についてどう考えていると思う?」などの質問に対する一般の人の考えを聞いて、養子当事者たちはどう考えるのだろうか? イギリスの支援団体が制作したこの作品は、養子縁組を希望する親や学校の教員に対する研修の場でも活用されている。(17分)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【テーマ4】産みの親の声
養子へ出すということ自体に対する社会のネガティブな認識や、産みの親をサポートする制度自体が整っていないことなどから、産みの親の存在にフォーカスが当たることはまだまだ少ないのが現状です。ですが産んでくれた人がいなければ、養子を迎えることもできません。産みの親がどんなことを考えている/考えていたのかを知ることは、子どもたちのためにも必要なことではないかなと思います。
★配信権獲得★
「Emma’s Adoption Story」

産みの親のエマ。17歳の時に妊娠し子どもを養子に出した経験が語られたショートインタビュー。高校生で妊娠した時の気持ち、実際に養親に託す前の気持ち等を話しながら、養子縁組という選択について振り返る。「妊娠してると分かった時は、興奮するとか嬉しいとかじゃなく、何かに打ちのめされた感じがしたし怖かった。」「でも、人生最高の瞬間のはずなのに、自分に子どもができたことが恥ずかしくガッカリするなんて…。」 交錯した感情の中、彼女が養子縁組を選んだ背景とは? そして、養子縁組を選んだ先に彼女が見つけたものとは?(12分)

「The 48 Hours Until Legal Adoption Signing」(交渉中)

アメリカ テキサス州では、出産してから48時間経過し初めて子どもを養子に出すことができる。若くして妊娠をしたドミニクは産む前から子どもを養子に出すことに決め、子どもの養親になる夫婦も決めていた。そしていざ出産。病院には養親となる夫婦も訪れ、生まれたばかりの子どもと交流を始める。希望に満ちた養親と産みの親との交流、それぞれが抱える心の葛藤、そして48時間後 –––– 。養子縁組とは誰のためなのかを改めて考えさせられる作品。(22分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【4】プロジェクト立ち上げのきっかけ
特別養子縁組の手続き中、直面した数々の困難。
このプロジェクトは、私、ネルソン聡子の経験がきっかけです。子どもは欲しかったものの自然なかたちでは恵まれず不妊治療を開始しました。ですが年齢の壁、高額な治療費(当時は保険適用外でした)、頻繁な病院通いによる体力的な疲れ、成果が出なかったときの精神的なショックなどがあり、結局1年で不妊治療をやめました。
その後、しばらくして夫の母親(フィリピン人)から「フィリピンで養子に出したいと言っている親がいる」と連絡を受け、私たち夫婦はもちろんすぐに「Yes!」と返事をしたのです。
最初はフィリピンで養子縁組を成立させようとしたのですが、法律上の問題によりできませんでした。ですが、せっかくのご縁を諦めるわけにはいかないと情報を集めたところ、子どもを日本に連れてきて日本で養子縁組成立を目指す方法があることを知りました。そして、唯一サポートを申し出てくれた国際行政書士の指導のもと、最終的には27種類もの書類をフィリピン大使館に提出し、子どもを入国させることができたのです。その後すぐに家庭裁判所への申し立て行い、優秀な弁護士、そして行政書士の方のおかげで2023年12月に特別養子縁組は成立しましたが、その手続きの間、特別養子縁組に対するサポートが整っていない現実にいくつも直面しました。
例えば、同居届けを出しても外国籍である子どもは公的な健康保険の対象外でした。また、養親を対象とした研修を受けたいと児童相談所に相談しても「里親として登録するわけではないから」と受けられず、市役所に相談しても「こちらにはあまり情報が…」と歯がゆい対応でした。とても親切にはしてくれたのですが、必要な届け出の数ばかり多く、私が欲しい情報やサポートを得ることはできませんでした。
日本における子どもの養子はたった1%なんて…。
少し古い資料ですが、こちらに日本とアメリカ「養子縁組の構成比較」の図があります。これを見て私は愕然としました。なんとアメリカでは成年養子(家名や家業の継承や相続を目的として行われる養子縁組 )がゼロ!! 一方の日本は成年養子が70%近くもあり、他児養子(特別養子縁組はここに該当)は1%なのです。

《養子縁組の構成の日米比較》出所:森口千晶「日本はなぜ子ども養子小国なのか」井掘・野口・金子編『新たなリスクと社会保障』、第3章、東京大学出版会、2012年
(一橋大学ウェブマガジンより)
また、こちらは国の人口に対する特別養子縁組(海外では養子縁組)の成立人数を示した表です。これを見ると日本での成立数が諸外国と比べて圧倒的に少ない事実が分かります。
*表の参考資料:里親及び特別養子縁組の現状について(厚生労働省資料より)

「養子に出す/養子を迎える/養子になる」は隠すべきこと?
望まない妊娠をした女性たちが誰にも相談できず、孤独を感じながらひとりで出産し赤ちゃんを死なせてしまうという悲惨なニュースが後を経ちません。ニュースなどでは母親が加害者となっていますが、これは母親一人の責任ではなく、そういう状況に母親たちを追い込んでしまっている社会の責任だと思うのです。子どもは実親が育てなくてはいけない、学生時代に妊娠するのは恥ずかしいこと… こういう社会の雰囲気では、悲惨なニュースは決して減りません。このプロジェクトを通して、産みの親に、子どもを養子に出すという選択肢があることを知ってもらいたいと思います!
また、日本では「血縁関係がある=家族」というイメージがまだまだ根付いています。そのため、養子を迎えてもその事実を周りや養子自身に伝えない養親の方もいらっしゃいます。ですが、それは養子にとっては決していいことではありません。養子であることを隠されていた=自分は隠されるべき存在なんだと思ってしまいますし、「自分はどこから来たのか」という出自について知らないとアイデンティティの形成ができません。何かぽっかり穴が空いたまま一生を過ごしていくことになるのです。
産みの親も、養親も、そして養子も、それぞれが自分の選択/自分の置かれた境遇を前向きに捉えることが、幸せに生きていくことに繋がると信じています。配信する映像作品は当事者の生の声が詰まっています。それぞれの迷いや葛藤もありますが、そこには希望を持って生きる姿があります。私たちが配信する映像を見て、「養子に出す/養子を迎える/養子になる」ことを隠すのではなく、1人でも多くの人が、その選択や境遇を前向きに受け入れることができればと思っています。
特別養子縁組に対するネガティブなイメージを払拭したい!!
こうして海外と日本とを比較したり、日本で起こっていることや自分の経験を振り返ってみると、特別養子縁組に対するイメージがネガティブなものとして根付いていると感じます。ですが、これらの制度に関する正しい情報や生の情報(当事者:養親、養子、産みの親の声)に触れる機会が一般的にはないのが現状です。特別養子縁組は、「子どもが幸せになるための制度」なのに、そういう認識が日本に広まっておらず、勝手なイメージだけが先行してしまっている・・・
「この現状を変えたい!!」 そう強く思いました。私は、自分の娘が成長していく過程で養子であることに引け目を感じてほしくありません。産みの親は子どもを捨てたのではなく、養子に出さざるを得ない事情があったのです。養子に出すのは子どもの幸せを思ってのことであり、その逆ではありません。特別養子縁組は子どもが幸せになるための制度であると認識できれば、養子である子どもたちが前を向いて生きていく一助となるはずです。
人々が未来に希望を抱ける「これからの選択」としての特別養子縁組へ
日本ではネガティブなイメージがある一方、海外では状況が異なります。海外では、特別養子縁組の形態が複数あり(海外では「特別」という言い方はしていません)、当事者(子ども、産みの親、養親)への継続的な支援や当事者同士がつながる場所作りなども積極的に行っています。また、当事者たちが自分の経験を顔を出して発信することも海外では稀なケースではありません。そのため、海外の事例や当事者たちの実際の声を日本に紹介することを通して、特別養子縁組に対するネガティブなイメージを払拭するとともに「養子に出す/養子を迎える/養子になる」ことに希望や幸せを見い出せるような状況を作っていきたいと思っています。
プロジェクトメンバーの紹介
こちらがプロジェクトメンバーです!
 ネルソン聡子
ネルソン聡子
現在、夫と養子に迎えた娘の3人暮らしです。長い道のりを経て、養子を迎える決断してから1年4ヶ月後、無事に特別養子縁組が成立しました。その過程で日本が抱える様々な問題に直面し、「社会の問題」と「自分の仕事(映像字幕翻訳)」を繋げて何かできることはないか…と模索した結果、プロジェクトの立ち上げに至りました。保育士をしていた経験もあり、子どもの環境(人的・物的)には非常に興味があり、また課題も感じています。主な翻訳作品はこちらからご覧いただけます。

土居恵理
北海道出身、山口県在住の英日字幕翻訳者です。字幕担当作品に『メイドの手帖』、『ハサン・ミンハジの愛国者として物申す』などがあります。作品を見た方から「希望を持っていいんだと思えた」「楽しみながら学べた」など感想をいただくことがあり、映像の持つ力を日々感じています。
昔から洋画や海外ドラマが大好きなのですが、海外作品を見ていると90年代、2000年代から幸せになるための選択肢の1つとして「養子縁組」が登場します。それを見ていた私自身もポジティブなものとして受け止めていました。このプロジェクトを通して同じポジティブな感情が広がればと思っています。
リターンについて
(スマホでご覧の場合、リターンの詳細は本ページ最下部の説明をご参照下さい)
(管理画面では支援者の氏名が英数字の羅列になってしまい、氏名が表示されません。そのため、リターンを購入して頂く際には、ぜひメッセージ内にお名前をご記載ください!)
《配信作品を選んで見られます》リターン!
3,000円:配信作品が1本視聴できます。
5,000円:配信作品が3本視聴できます。
7,500円:配信作品が5本視聴できます。



《全配信作品を見られます+セミナーにご招待》リターン!
15,000円:全配信作品視聴+セミナー✕1へご招待(1購入につき1名)

《全配信作品を見られます+セミナーにご招待》リターン! ★団体にオススメ★
30,000円:全配信作品視聴+セミナー✕1へご招待(1購入につき3名まで可)
50,000円:全配信作品視聴+セミナー✕2へご招待(1購入につき5名まで可)
70,000円:全配信作品視聴+セミナー✕3へご招待(1購入につき7名まで可)
セミナーは、海外の専門機関の方を招き下記のテーマでの開催を予定しています。
①セミ・オープンアダプション、オープンアダプションの取り組みに関して
②当事者に対する継続的な支援に関して
③当事者の体験談 *当事者を招き、その方(方々)の話を聞く機会です。
*逐次通訳付き
*参加するセミナーは、後日①②③からご自由に選択できます。
*すべてのセミナーは2025年12月末までに行う予定です。
*オンラインでの開催になりますが、当日ご参加できない方には後日視聴できるURLをお送りいたします。



《上映会ができます》リターン!
100,000円:上映会用の権利(2作品)
200,000円:上映会用の権利(5作品)
300,000円:上映会用の権利(全作品)
*上映の規模は問いませんが、作品によってはあまり大きい画面ですと画質が荒くなる可能性もございます。その点、ご了承ください。



ーーーーーーーーご注意ーーーーーーーー
携帯やスマートフォンでは、各リターン内容詳細は最後の「募集方式について」の後に出てきます。
スケジュール
3月〜:配信映像作品の権利交渉
5月:クラウドファンディング開始
7月 :クラウドファンディング終了
8月上旬 〜10月下旬:プラットフォーム構築
9月上旬〜10月下旬:映像作品翻訳
11月上旬〜下旬:配信準備
12月上旬:プラットフォームOPEN、映像配信開始、リターン発送
資金の使い道
実費
○翻訳費:63万円
○字幕の焼付け・編集作業費:10万円
○PR費:12万円(チラシ作成、CAMPFIRE経由での宣伝費)
○プラットフォーム構築費:8万円
○雑費・予備費:5万円
○配信プラットフォーム利用費(Vimeoを予定):5万円
○専門家のセミナー開催費(支援者へのお礼)10万円
○CAMPIFIREへの手数料(17%):40万円
初年度の運営費
○プロジェクト管理・事務作業費:4万円✕10ヶ月分=40万円
○PR作業費(宣伝に関する執筆等):2万円✕10ヶ月分=20万円
○海外とのコミュニケーション費:2万円✕10ヶ月分=20万円
最後のメッセージ
このプロジェクトを立ち上げるきっかけを、私の娘がくれました。娘には自分の境遇を卑下することなく生きてほしいですし、私や娘、そして私たち夫婦に娘を託してくれた産みの親と同じ方々が世の中にはたくさんいると思います。日本の特別養子縁組の現状を考えると私がしてきた経験は小さなものですが、この経験が、ライフワークとなるこのプロジェクトを与えてくれました。養子を迎える/迎えた養親の方々、養子として新しい家族に迎えられた方々、自分の子どもを養子として託した産みの親の方々の幸せを後押しするためのプロジェクトに、ぜひ皆様の力をお貸しください!ご支援の程、どうぞよろしくお願いいたします。
Q&A
【視聴を希望する作品は、リターンの購入時に選ぶの?】
現在、配信権を交渉中の作品がまだございます。そのため、クラウドファンディングの目標が達成された後に、全作品の中から視聴する作品をお選び頂けます。
【いつまでに視聴すればいいの?】
ご購入するリターン(作品数)によって期間が異なります。各リターンページに「視聴可能期間」が記載されていますので、そちらをご確認下さい。
【セミナーはオンラインで実施するの?】
はい、セミナーは海外とつなぎオンラインで実施する予定です。オンライン開催当日に参加できない方には、後日アーカイブをお送りいたします。
【セミナーではどんな人が話すの?】
セミナーでは、海外の養子縁組斡旋団体や支援団体の専門家を招き、自国での取り組みについてお話頂く予定です。海外の実践を聞くことで、日本の取り組みを見直したり発展させたりすることを目的としています。
<募集方式について>
本プロジェクトはAll-or-Nothing方式で実施します。目標金額に満たない場合、計画の実行及びリターンのお届けはございません。
最新の活動報告
もっと見る
予告編に字幕をつけました!
2025/11/07 15:22こちらの作品の予告編に日本語字幕をつけました!これも、皆様の引き続きのご支援・応援のおかげです。どうもありがとうございます。現在はこちらのインスタよりご覧いただけます。https://www.instagram.com/p/DQtthxOj04S/近日中にBeyond usのHPにもUPいたしますので、ぜひチェックして頂ければと思います。下記の3つのSNSで発信を続けておりますため、フォローやいいね!をお願い致します!インスタグラム:https://www.instagram.com/beyond_us08/X:https://x.com/beyond__usnote:https://note.com/beyond_us来年中には、今ある作品を世に出したいと思っておりますため、もしまたよろしければ、ご支援頂けると大変嬉しく思います。現在、総額「8万円」の寄付を頂いております!諦めずに続けていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします! もっと見る
「Beyond us」として再始動いたしました!
2025/09/01 10:401年ぶりの投稿となります!まずは、改めまして、ご支援や応援をしてくださり、本当にありがとうございました。昨年の7月末にクラファンが終了しましたが、その間に新しいメンバーも増え、9月より新体制で月1回のミーティングを重ね、この度「Beyond us」というプロジェクト兼 団体名で再スタートを切ることになりました!「Beyond us」は、「既存の(私たち自身の)価値観を乗り越えていく」という意味が込められています。クラファン開催期間中、養子縁組に直接関わる方々にも多くのご支援や応援を頂きましたが、障害のある子どもを育てておられる方々、社会の中で「生きづらさ」を感じている方々や、その周りの方々も、このプロジェクトに共感し応援の声を寄せてくださいました。クラファン終了後にメンバーと振り返りを行う中で、養子縁組以外の社会問題にも目を向け、大手の配給会社ではない、私たち翻訳者だからこそ見いだせる作品を日本に紹介していくべきではないか、ということを話し合いました。そして…「世の中に埋もれている世界」に光を当てていく。知名度ではなく「今、届けたい」と思える物語たちに目を向け、誰かの人生にそっと光が灯るような作品を紹介していくことを軸に、再出発を図ることにいたしました。今年の1月くらいからWebsiteの作成に着手し、やっと「Beyond us」のWebisteも完成いたしましたので、ぜひ御覧くださいませ。https://admin373374.wixsite.com/beyondus/about-1映像に日本語字幕をつけ配信する、という活動スタンスは変わっておりません。配信権を獲得している養子縁組関連の作品も、引き続き、寄付を募りながら作品に字幕をつけ配信をしていく予定です。クラファンの時のようなリターンはないのですが、500円〜寄付ができるように設定をいたしましたので、もし可能でしたら、ぜひご寄付を頂けますと嬉しく思います。何かご不明点、疑問点などがございましたら、Beyond usのメール(beyondus.japan@gmail.com)までご連絡を頂けますと幸いです。息の長い活動にしていきたいと思っておりますので、今後とも、応援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。ネルソン聡子 もっと見る
映像の一部に仮字幕をつけました②!
2024/07/27 14:40昨日に引き続き、こちらの作品にも仮字幕をつけました!イギリスの養子縁組斡旋・サポート団体が制作した、養子たちへのインタビュー映像です。「あの時、こうしてほしかった」「これは、こうすべきじゃない」「もし今から養子を迎えることを考えるのであれば…」など、養子当事者の赤裸々な声を集めた短編作品で、養親の方や、養子縁組を検討されている方などには、本当にヒントがたくさん詰まっています。こういう作品を、どんどん日本に紹介していきたい…そう強く思っています。ぜひご覧ください!https://youtu.be/qV0bPSWhEMA?si=a5GQGzYWVnidByvk作品概要:「Messages for Adoptive Parents from Adopted People」(原題) 10代~成人した養子当事者たちが自分たちの過去を振り返り、これから養親になる人たち、すでに養親で子どもを育てている人たちへメッセージを伝える短編作品。「喪失とトラウマ(LOSS AND TRAUMA)」「恥じる気持ち(SHAME)」「アイデンティティ(IDENTITY)」「異なる人種間での養子縁組(TRANSRACIAL ADOPTION)」「誠実さと透明性(HONESTY AND TRANSPARENCY)」といった様々なテーマをもとに、当事者たちが素直な気持ちを語っている。(26分) 映像を提供してくれるのは、イギリスで最も大きい養子縁組団体のひとつである「PAC-UK」。特に10代や産みの親に対するサポートに注力しており、その取り組みはイギリス国内のみならず世界各国から注目を集めています。残り2日となりました。お気に入りに登録をして頂き、ずっと応援をし続けて頂き、本当にありがとうございます。あと2日、最後までどうぞよろしくお願いいたします! もっと見る
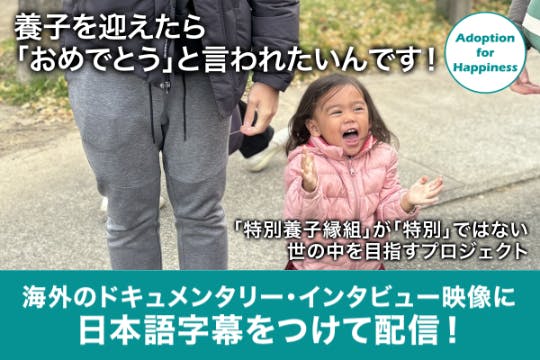

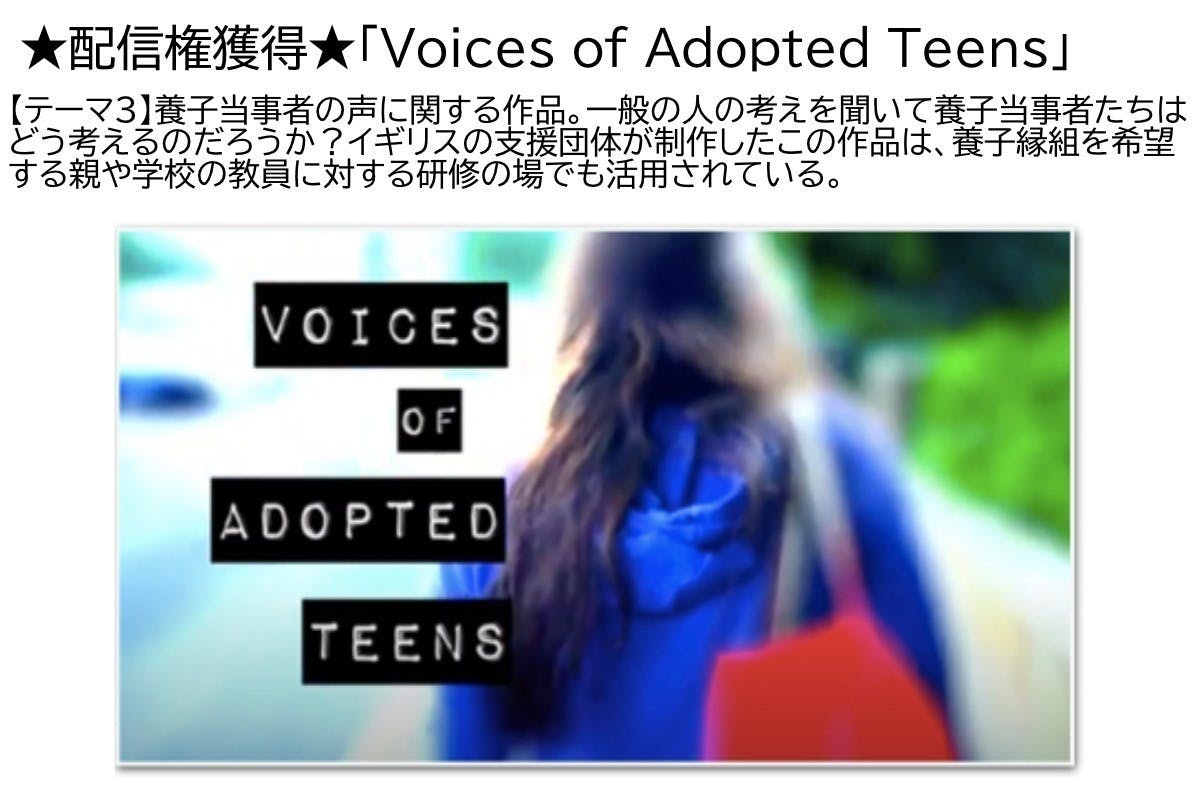

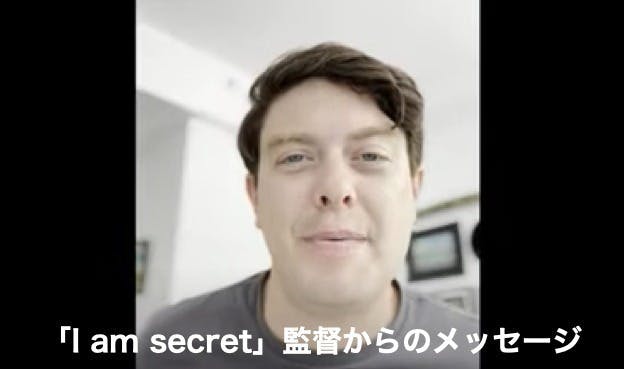









コメント
もっと見る