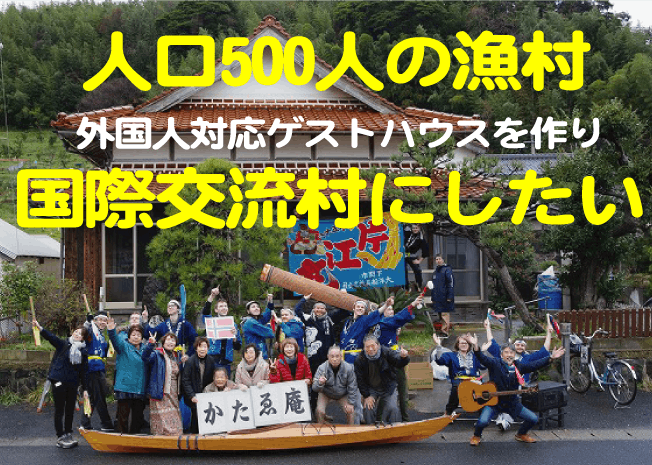2019/06/27 19:31
ノンフィクション「だからあれだけ行ってはだめだと言っていたのに」
https://faavo.jp/shimane/project/3698/report/23853#pj-single-nav
この続きを支援者の方だけにと、以前お約束してましたので、
もしよければ読んでください。
ここからそのノンフィクションの続きです。
まだ読んでない方は先に上のリンクをご覧ください。
大波に飲まれ、海底近くまで沈んだ時に、息子が行ったある行動が、
おそらく生還につながったのではないかと思います。
波に飲まれ、海中の底に行った、と言っていました。
これは、おそらくいつものように潜る時の体制になったのではないかと思います。
つまり水面に対して直角に体がなったと。
おそらく生還につながったのではないかと思います。
波に飲まれ、海中の底に行った、と言っていました。
これは、おそらくいつものように潜る時の体制になったのではないかと思います。
つまり水面に対して直角に体がなったと。
そして、そのまま息を止め、体を動かさないでいた。
そうすると何もしないと浮かんできます。
ひょっとしたら、その沈んだ後、体を大の字にしてたかもしれません。
しばらく、その状態から浮き上がるまで待ったと思います。
そして、やらなかったことが泳ぐこと。
浮かび上がって、背浮きの状態で、顔だけ出て、呼吸を確保。
その時に体が大の字になってたのではと想像します。
なぜか。
日ごろから、私は、海岸で大の字になって
何もせず浮かぶことがすきで、よくやっていました。
子どもたちもそれをまねてやってました。
子どもたちもそれをまねてやってました。
イギリスなんかではこの星の形で、着衣水煙の指導をしてると聞いてます。
このことは、何もしないでも浮くことを子どもたちは経験上知っていたのです。
また、子どもたちは泳ぐことよりも潜ることを先に覚えました。
そして泳げるようになると深く潜る時には、水面に対して垂直にアプローチすることが
最適だと経験していました。
海に飲み込まれ、海底にまで行ったといっていたことから、
いつもの姿勢になったのではないかと思います。
そして海に落ちなかった、陸にいた子どもたちの行動は、
息子の名を呼んで「こうせい君頑張れ」と言ってたようです。
これを思い出しながら書いてる段階で、あることに気が付きました。
それは、以前そのことを聞いた時には、そんな声をかけるよりも大人の人に助けを求めに
行ってくれたらよかったと思っていました。
しかし、この息子の状態で、岸がどちらか、顔をあげなければ確認できなかったのではと推測します。
もし、顔を上げたなら間違いなく、沈んでしまったと思います。
そして声がする方向へ向けて少しづつ手首で水をかいて近づこうとし、水の流れも運よく陸に向かい、そこで声をかけた子どたちに奇跡的に到達し、陸に上がることができたと思います。
直接見に行ってないので、推測です。
あとは海の神様が守ってくれたんだと、思い出すたびにその幸運を片江の神に感謝してます。
その翌年、小学校行事として、着衣水泳を実施します。また10年以上前までやっていた片江湾の東の海岸から西の海岸までの横断遠泳大会を復活。
その時に着衣水泳でお世話になったのが、サポートメンバーの片江のてつとさんです。
そして、漁協は遠泳大会に全面的に協力していただきました。サポートメンバーの太さんやらが漁船を出して、
万が一の救助船としてコースの途中途中に配置していただきました。
その後、この着衣水泳は、次男の転校先の川津小学校でも校長に紹介しました。
今は、毎年その着衣水泳を行っていると聞いています。
川津小学校は、60年ほど前に船が遭難して沈没、それにのっていた就学旅行の小学生の多くが亡くなった悲惨な過去があります。毎年就学旅行に行く前には、救命道具のつけ方を学んでいました。そこに着衣水泳が加わったことの意味は大きいと思います。
そして、先週昼食の時にぼーっとテレビを観ていましたら
NHKの昼のしまねのニュースにてつとさんがでていました。
着衣水泳の指導者として。
UG