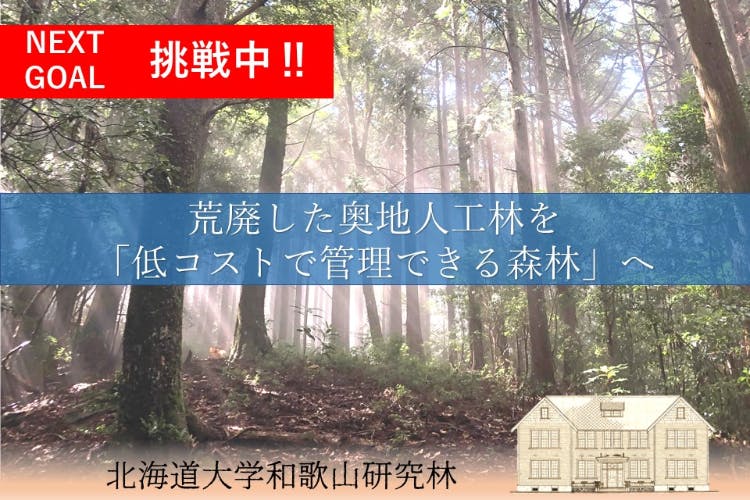こんにちは。あっという間に桜前線も通過してしまい、早くも新緑がまぶしいこの頃ですがいかがお過ごしでしょうか?まだ暫く遠方への外出は難しいかもしれませんが、春は意外にも近くで見つけることが出来るかもしれません。花粉も収まってきたことですし、近所を散歩するのも良いかもしれませんね!
 冬眠から出てきたカエル
冬眠から出てきたカエル
さて今回は早速話題の方に入ってまいりたいと思います。今回のテーマは「木質バイオマス発電」です。既にご存じの内容も多いかもしれませんが、普段はあまり聞く機会のない問題点など、皆様にとって新たな発見があれば幸いです。どうぞお読みください!
これからのエネルギー
ところで皆様はここ数年、「聞く機会が増えた」と感じる言葉はありますか?ご職業や専門分野、住んでいる地域によっても異なってくるかもしれませんね。ですがどの人も共通して 、「持続可能性」という言葉は聞く機会が増えたと感じているのではないでしょうか?2015年の国連サミットで2030年までの持続可能な開発のための目標(SDGs)が採択されてからは、その頻度もさらに増えているような気がしますね。 SDGsの目標
SDGsの目標
このSDGsには大きく17の目標があり、その内容は貧困やジェンダーといったものから、気候変動、産業の発展など多岐に渡っています。その中の一つ、7番目の目標に「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」というものがあり、クリーンエネルギー技術の開発が進められてきました。クリーンエネルギーとは温室効果ガスや大気汚染物質を放出しない、環境に配慮した方法で生産されたエネルギーのことで、太陽光発電や風力発電などは分かりやすい例です。そして、このクリーンエネルギーの一つに「木質バイオマス発電」が数えられています。
木質バイオマス発電の考え方
木質バイオマス発電とは、燃料に化石燃料を用いず、樹木由来の物質を燃料として燃やし、タービンを回して発電する方法です。木を燃やす際には当然、二酸化炭素が発生します。しかし、排出した炭素は植物が光合成により固定するので、差し引きゼロになるという理論によって、木質バイオマス発電がクリーンエネルギーに数えられています。また、太陽光発電や風力発電と異なり天候に左右されないことも注目されています。
 バイオマス発電の考え方
バイオマス発電の考え方
燃料には木屑や廃材まで様々なものが利用されています。林業関連では、これまで使い道が無く捨てられていた枝葉や末端材などの林地残材や、間伐材等の有効利用法としても期待されています。実際に、林野庁によると、木質バイオマス発電所の増加に伴い、2017年にはエネルギーとして利用された間伐材・林地残材等の量が前年比で37%も増加しているそうです。間伐材による収入が見込めると、林業の中間収入が発生することになるので、林業の活性化につながる可能性があります。また、間伐の収益化によって適切な管理を促せる可能性もあります。このような点から、木質バイオマス発電は、単にクリーンエネルギーとしてだけではなく、林業活性化のきっかけとしても期待されているようです。
 和歌山研究林の木工場で発生したおがくず
和歌山研究林の木工場で発生したおがくず
燃料の調達に課題
このように二酸化炭素の排出量が実質0と考えられ、林業の活性化にも期待されている木質バイオマス発電ですが、一方でいくつか問題点が指摘されています。特に太陽光電池や風力発電と異なり、木質バイオマス発電には燃料費がかかるため、燃料の安定供給が課題となっています。ビジネスとして電気を販売するためには、販売価格を他の発電方法と同程度まで下げ、競争力を確保する必要があります。そのためには、燃料となる木質バイオマスを安く大量に買い集め、大量に発電しなくてはなりません。しかし、国内から生産される木質バイオマスは未だ安定供給ルートが確立されていません。そのうえ間伐材や林地残材は、立木が残った林内を搬出しなくてはならず作業効率は低いうえ、形が不揃いなので体積がかさばり搬出コストが高くついてしまいまい、外材に対し圧倒的に優位な立場を築けません。その結果やや高くても、大量に安定供給が可能な輸入チップやペレットが主燃料となってしまい、2018年時点での木質ペレットの自給率はおよそ2割まで低下してしまいました。 
FIT制度
この厳しい状況でも木質バイオマス発電所の事業が進められている背景にはFIT制度があります。FIT制度とは再生可能エネルギーを一定期間、一定の価格で買い取る制度です。経営の見通しを立てやすくすることで、技術開発中で生産コストの高い再生可能エネルギーを普及させることを目的としています。このFIT制度において、木質バイオマス発電による電力は、他の再生可能エネルギ―よりも比較的高い価格が設定されていました。 しかし、このFIT制度には適用期限があります。北海道立総合研究機構林産試験場の古俣寛隆氏らの研究 によると、国内の一般的な木質バイオマス発電所の多くは、FIT適用期間終了後、利益を上げるのが難しくなると予測されています。制度終了後、自立して電力ビジネスを行うためには、間伐材の安定供給のために郎網整備を進めたり熱利用の促進(後ほど説明致します)したりすることが重要になります。
 FIT制度
FIT制度
他にも諸々の課題が…
また、木質バイオマスの輸入依存はそもそもの「クリーンさ」も危うくしてしまいます。海外から原料を調達するには当然、船で輸送する必要があり、木質チップを燃やす際に発生する量以上の二酸化炭素を排出してしまいます。このようにサプライチェーン全体で環境影響評価を行うことを、ライフサイクルアセスメントと呼び表面的な評価にならないように注意が必要とされています。また、木質チップ生産者が環境に配慮した森林・林業経営を行っているのか否かも、注目すべき点です。第三者認証を進めていますが詐称が疑われるなど、運用が今一歩信頼しきれない状況で、トレーサビリティの確保が急がれています。
 ライフサイクルアセスメントの考え方
ライフサイクルアセスメントの考え方
カスケード利用
バイオマス燃料に特化した森林施業が行われていることも、カスケード利用という観点から疑問の声が上がっています。カスケード利用とは、初めに資源を最も付加価値の高い状態で利用し、古くなったりやや品質が低い材は別の方法で利用していく、という考え方です。例えば木材ですと、切り出してきた木を付加価値の高いまま利用する方法として、建材や家具材などがあります。時間が経過し、それらの材が廃材になるとチップにして加熱圧縮し、パーティクルボードなどになります。それも使い古されると、木質バイオマスの燃料として利用されるという流れが、カスケード利用の観点では理想とされています。
 カスケード利用のイラスト
カスケード利用のイラスト
この利用方法では、切った直後に木質バイオマス燃料として燃やしてしまうよりも、樹木が吸収固定した炭素を長期間維持できます。そのため、樹木の炭素貯蔵効果を最大限発揮させるためには不可欠な考え方です。ところが、大規模バイオマス発電所の需要に応えるため、バイオマス燃料に特化した森林経営が行われると、樹木が吸収した炭素を短期間で放出してしまうことになり、樹木の機能を活かしきれていません。そのため本来は、製材過程で発生するおがくずや建材の廃材、未利用だった間伐材など、既に下位のカスケードに位置する木質バイオマスを利用するのが理想的です。
鍵は熱利用?
さて問題点をつらつらと書いてきましたが、じゃあ木質バイオマス発電に未来は無いのかというとそうではありません。しかし、普及には「発電」だけでなく「熱利用」を改善する必要があります。バイオマス発電は本来エネルギー効率(投入したエネルギーに対し変換後に回収できるエネルギーの割合。バイオマス発電の場合バイオマスの持つカロリーに対し発電された電気エネルギーの割合。)が30%と低くなっています。一方で、ボイラー効率(燃料のエネルギーのうち水蒸気に変換された割合)は8割となっており、熱利用を進めることでバイオマス燃料の真価が発揮できるとされています。
 現在のバイオマス発電
現在のバイオマス発電
熱電併給
どういうことかというと、現在は木質バイオマスを燃やすことで得られた水蒸気の全てを、発電タービンを回すために使ってしまっています。ところがそれではエネルギーのロスが大きく、エネルギー効率が落ちてしまいます。そこで、水蒸気の全てを発電に回すのではなく、水蒸気の持つ熱を木材の乾燥など他の用途で使うことで、全体としてエネルギー効率を上昇させることが出来るのです。このような方法を熱電併給(コージェネレーションシステム)と呼びます。
 熱電併給
熱電併給
しかしながら、日本では国内FIT制度の仕組みが原因となり、この熱電併給が積極的に行われていません。日本のFIT制度は総合的なエネルギー効率ではなく、発電量に対して制度が適用されており、発生したエネルギーを全て発電に回した方が経営が良くなるためです。欧州では総合的なエネルギー効率に対して適応される制度があり、熱電併給が進んでいるので、日本は制度の見直しが必要かもしれません。
今後、バイオマス燃料で熱の消費を賄うことには、脱炭素化を進めるうえで非常に重要になってきます。 国際的な自然エネルギー政策ネットワーク組織REN21が2018年に行った、エネルギーが最終的にどのような形で利用されたかを調べた調査では、全体の48%が熱分野で利用されていました(電力は20%)。つまり、エネルギーの脱炭素化を進めるには電気利用だけではなく、熱利用に関する脱炭素化も進める必要があります。そこで電力だけでは活かしきれないバイオマス燃料に活路が見いだされ、長期的に間伐材の需要が維持されれば、林業にとっても明るい話題になるかもしれませんね。
長くなってしまいましたが、今回はこれで終わりです。最後までお読みいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。
参考資料
・Renewables 2018 Global Status Report, REN21
・古俣 寛隆, 石川 佳生, 柳田 高志, 久保山 裕史 2019 FIT調達価格の変動による木質バイオマス発電事業の経済性評価
・日経 2018/12/11 バイオマス発電8割動かず 林業人手不足、燃料輸入頼み
・日経BP 2020/8/26 稼働の6割、認定の9割が「輸入」燃料、「バイオマス白書2020」
・日経BP 2020/9/30 FIPの制度設計スタート、「基準価格」はFITと同水準
・日経XTEC 2019/10/18 「バイオマス発電はFITに合わない」、バイオマス産業社会ネットワーク・泊みゆき理事長に聞く
・林野庁 平成29年度 森林・林業白書 第1部第IV章第3節木材利用の動向(4)木質バイオマスのエネルギー利用
・林野庁 令和元年度 森林・林業白書
・資源エネルギー庁 バイオマス白書2020 1. FIT制度におけるバイオマス発電の現状と経緯
・資源エネルギー庁 バイオマス白書2020 2 森林バイオマスの持続可能性
・経済産業省 資源エネルギー庁 ホームページ 固定価格買取制度 閲覧日2021年4月15日
・林野庁 木質バイオマス発電事業の概要