皆さん、はじめまして。中西謙介と申します。

奈良県月ヶ瀬の梅農家に生まれ、自動車メーカーで研究開発の仕事に従事した後、梅作りへの情熱と小さな使命感で実家に戻り、専業で梅作りをはじめて4年が経ちました。
現在、7,000㎡(東京ドーム0.5個分)ある梅畑では、南高梅、紅映、白加賀など計10種類の品種を育てており、生梅の他にも、梅干しやジャム、シロップなど梅を加工した商品も手作りしています。
月ヶ瀬は梅林の郷と呼ばれ、江戸時代から続く梅の名所。今でもその景色はとても美しく、日本政府が最初に指定した名勝の一つです。梅作りは未だ生産者の残るこの場所ですが、「烏梅(うばい)」を作る農家は私たち家族の一軒のみ。月ヶ瀬だけではなく全国を見ても私たちは烏梅を作る最後の、唯一の農家になってしまいました。このクラウドファンディングを通して、烏梅のことを皆さんに少しでも知っていただき、烏梅作りを日本に残すための美味しい応援をして頂けたら嬉しいです!
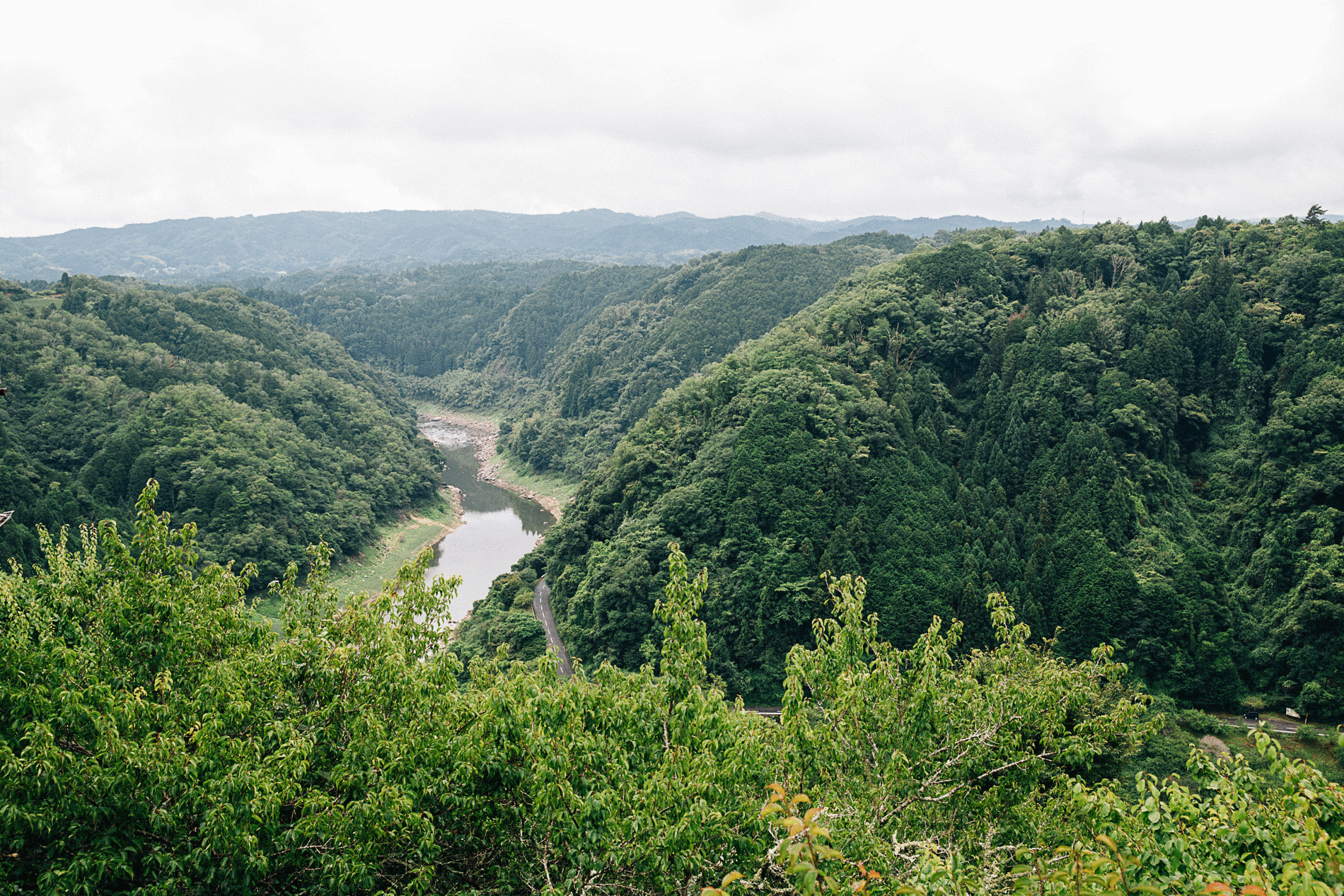
 皆さんは烏梅(うばい)という名前を聞いたことがありますか?烏梅は中国から遣唐使が持ち帰ったものの一つで、梅の果実を伝統製法で燻製にしたもの。漢方薬の原料として、また染料として日本で1300年の歴史があります。当時から薬として胃腸や肺、風邪や咳・熱の症状に効くと言われてきました。また、キク科の植物「紅花(べにばな)」と合わせることで鮮やかな紅色の染料ができることから、化学染料のない時代に欠かせない材料として重宝されていました。衣類用の繊維を染めるのはもちろん、口紅や頬紅にも使用され、歴史の中で日本女性を彩った「色」でした。
皆さんは烏梅(うばい)という名前を聞いたことがありますか?烏梅は中国から遣唐使が持ち帰ったものの一つで、梅の果実を伝統製法で燻製にしたもの。漢方薬の原料として、また染料として日本で1300年の歴史があります。当時から薬として胃腸や肺、風邪や咳・熱の症状に効くと言われてきました。また、キク科の植物「紅花(べにばな)」と合わせることで鮮やかな紅色の染料ができることから、化学染料のない時代に欠かせない材料として重宝されていました。衣類用の繊維を染めるのはもちろん、口紅や頬紅にも使用され、歴史の中で日本女性を彩った「色」でした。
 当世美人合踊師匠 画:国立国会図書館デジタルコレクションより
当世美人合踊師匠 画:国立国会図書館デジタルコレクションより
 奈良県の月ヶ瀬地域では700年前から烏梅を作り続けていて、私は烏梅農家の10代目。烏梅作りの最盛期には月ヶ瀬にも400軒以上の烏梅農家がいたとされていますが、明治期に西洋から安価な化学染料が輸入されると烏梅の需要は激減。さらに戦時中の食糧難のなかで腹を満たさずお金にならない烏梅農家は次々と消えていきました。
奈良県の月ヶ瀬地域では700年前から烏梅を作り続けていて、私は烏梅農家の10代目。烏梅作りの最盛期には月ヶ瀬にも400軒以上の烏梅農家がいたとされていますが、明治期に西洋から安価な化学染料が輸入されると烏梅の需要は激減。さらに戦時中の食糧難のなかで腹を満たさずお金にならない烏梅農家は次々と消えていきました。
当時は「終戦後の食糧難の時代になぜこんな時にそんなことをしているのか?」などと、変人だと言われることもあったそうです。しかし、中西家の先祖代々受け継がれている「(天神さんをお祀りするつもりで)売れても売れなくても梅を焼け」という言葉。歴史を残すために、そして伝統的な染色家の想いにも応えるために、烏梅を作り続けた先祖の想いが今も引き継がれ、私たち家族の原動力にもなっています。
 1970年代 中西家の烏梅作り
1970年代 中西家の烏梅作り


燻蒸中は24時間、つきっきりで温度調節をするため、ひとときも気が抜けません。年に一度、烏梅を作る数週間はその年で一番気合の入る時期です。時間をかけて出来上がった烏梅は、紅花と掛け合わせることで、烏梅の酸と紅花の持つ色材が反応し、鮮やかな紅色の染料になります。これを「紅花染め(べにばなぞめ)」と呼びます。近年では、手に入りにくくなってしまった烏梅の代わりに、紅花とクエン酸を使用する染色家の方もいらっしゃいますが、発色の鮮やかさ、透明感は烏梅を使ったものとは大きな違いがあります。
 紅花(べにばな)
紅花(べにばな) こんなに鮮やかな紅色に染まります
こんなに鮮やかな紅色に染まります
烏梅を使用して衣類用生地の染めを行う染色家は、現代でもまだ僅かに残っているものの、口紅や頬紅に烏梅を使用すること自体が過去のものとなってしまいました。
しかし、歴史を学ぶうちに、現在は作られていない紅花と烏梅から本物の口紅を復活させてみたいと考えるようになりました。食品だけでなく肌に直接触れる化粧品も成分の見直しが行われ始めている昨今だからこそ、アレルギーを持つ方や敏感肌の方へ向けた、低刺激で安全、更には環境にも優しい口紅の可能性を改めて感じています。
 伝統工芸品として当時作られたものが僅かに残っている口紅。
伝統工芸品として当時作られたものが僅かに残っている口紅。
理由は未だ解明されていませんが、紅花の赤色の色素は乾くと美しい玉虫色に変化します。
紅花と烏梅の口紅は当時から伝統工芸品として大切にされてきました。これまで先人たちの強い想いで守ってきた烏梅作りを後世に残すため、伝統と文化の継承のためにも紅花と烏梅だけを使ったオーガニックの口紅を復活させたいです!
また月ヶ瀬地域には耕作放棄地がたくさんあるため、そこで新たに紅花の栽培を始めたいと思っています。この口紅プロジェクトを地域と連携しながら活性化させることで、伝統産業を再生させ、烏梅という文化を継承しつつ、森を守っていくことにも繋がっていく。地域に還元できる、そんな新しい循環を作ることを大きな目標としています。
春から夏の時期は、梅の収穫や烏梅の製造など農家としての仕事があるため、冬場のオフシーズンを上手に使用し、商品化を進めていきたいと思っています。まずは、商品開発に取り組むための工房設備の着工、化粧品の商品化やデザイン等を、固めていきたいと思っています。
目標としては、2022年の秋には口紅の試作を開始し、2023年の春頃には、口紅製作拠点の完成です。そして、その後、商品の完成を目指します。
「日本最後の烏梅作りを残したい。知られざる梅の魅力を伝えたい。」その気持ち一心でスタートした一世一代の口紅製作。一時的な施策ではなく継続したプロジェクトになるよう、完成のクオリティを高めるため、原料の泥紅を安定供給できる工房施設を作り、化粧品の商品化やデザインなど、それぞれ専門家や専門工場と一緒に開発にすることで、長期的に育てていけるような魅力的な商品づくりを目指します。紅工房では泥紅の生産、烏梅、梅食品の開発のほか、烏梅染体験が出来る設備を設け、地域に人が訪れるきっかけの1つになれたらと思います。今回は、その体制を整えるための先行投資として、クラウドファンディングを行わせていただけたらと思いました。
もちろん資金としてのサポートもですが、これを機に烏梅の存在を知り、私たちの取り組みに共感して仲間になってくれる人がいたら嬉しいな、とも思っています。
 支援者の皆さまへお送りするリターンは、ぜひ召し上がっていただきたい、私たちが月ヶ瀬で作る昔ながらのすっぱい梅干しです。
支援者の皆さまへお送りするリターンは、ぜひ召し上がっていただきたい、私たちが月ヶ瀬で作る昔ながらのすっぱい梅干しです。
 食生活や食の嗜好の変化によって市場の梅干しはだんだんと甘く、塩気が少なくなってきたように感じますが、「塩分カット」や「甘口梅干し」がどのように作られているか知っていますか?梅干しは塩を一定の比率使用することで保存が利くように仕上げます。なので塩分カットや甘い梅干しは塩で漬けた後に塩分を抜いたり、加糖したりして作っていきます。その過程で梅自体の養分やエキス分も一緒に抜けてしまうので、どうしても少し味気ない味わいになってしまいます。さらに塩分が抜けた分、保存が利くように防腐剤などの添加物を使用するため、本来であれば塩だけを使った保存食である梅干しに結果としてたくさんの添加物が足されてしまうのです。
食生活や食の嗜好の変化によって市場の梅干しはだんだんと甘く、塩気が少なくなってきたように感じますが、「塩分カット」や「甘口梅干し」がどのように作られているか知っていますか?梅干しは塩を一定の比率使用することで保存が利くように仕上げます。なので塩分カットや甘い梅干しは塩で漬けた後に塩分を抜いたり、加糖したりして作っていきます。その過程で梅自体の養分やエキス分も一緒に抜けてしまうので、どうしても少し味気ない味わいになってしまいます。さらに塩分が抜けた分、保存が利くように防腐剤などの添加物を使用するため、本来であれば塩だけを使った保存食である梅干しに結果としてたくさんの添加物が足されてしまうのです。
私たちは昔ながらのすっぱい梅干し作りを続けていて、梅と紫蘇、塩だけを使って、昔から食卓に並んでいた酸味の強い、台所の桶で保存されていたあの頃と同じ味わいを守り続けたいと思っています。私たちの畑には10種類以上の様々な品種の梅の木が生きています。古い品種で「城州白(ジョウシュウハク)」という長生きの木だと樹齢200年以上のものも!古い品種や、ぽってりと柔らかい実が人気の「南高(ナンコウ)」など新しい品種、様々なものを育てています。品種によって酸味や食感、味わいは大きく異なります。味のプロでなくても面白いくらい違いがわかるので、ぜひ食べ比べて好みの梅を探してみて欲しいです。
白ごはんや、お茶漬けはもちろん、お肉や茹で野菜と合わせておかずにも。梅干しサワーにしても美味しいですよ。スッパ〜!!と口をすぼめて目を瞑って、みんなで楽しく食べてもらえたら嬉しいです。





生まれてからずっと私の家には家訓のように「(天神さんをお祀りするつもりで)売れても売れなくても梅を焼け」という先祖の言葉がありました。自然とその言葉が私の真ん中にいつもあって、自動車メーカーで仕事をしている時も、いつかは梅作りに、実家に帰るんだという意識がありました。それは小さな使命感のようなものかもしれませんが、私自身が「烏梅を世の中に残したい、歴史と伝統のある烏梅だからこそ何か面白いことができるのではないか」と明るい可能性を信じていたように思います。
烏梅農家がどうして・・・?と思われてしまいそうな「口紅」の復活プロジェクトですが、作り方や歴史を文献を読んで学んでいくうちに心からワクワクしている自分がいました。家業である梅、烏梅を使ってこんな気持ちになれたこと、そしてそれをサポートしてくれる仲間がいることに感謝しています。
ここまで読んでくださった皆さん、本当にありがとうございます!
梅や烏梅の魅力を知ってもらう、それこそが「烏梅を後世に残す」ためにまずは必要なこと。このページを読んで興味を持っていただけたら、それこそに意味があると思っています。ぜひ我が家の自慢のすっぱい梅干しを食べて、烏梅や口紅に想いを馳せていただけましたら何よりの幸せです。

最新の活動報告
もっと見る
全国大会に向けたクラウドファンディング
2026/02/06 23:30クラウドファンディングで目標到達出来ればにっぽんの宝物コンテストの全国大会に出場します。日本最後の烏梅を、次の舞台へ。― 全国大会への挑戦は、皆さんと一緒に決めたい ―はじめまして。奈良・月ヶ瀬で1300年の歴史を持つ梅の加工品「烏梅(うばい)」を受け継いでいる、梅古庵の中西謙介です。現在、この技術を継承しているのは、私たち梅古庵一軒のみとなりました。烏梅は目立つ存在ではありません。それでも、確かに日本の歴史と暮らしの中で生きてきた営みです。■烏梅とは ― 過去から今へ続く役割烏梅は、完熟した梅を蒸し焼き、燻製と天日干しを重ねてつくる、千三百年以上前から続く梅の加工品です。遣隋使によって薬として奈良に伝えられ、日本最古の医学書『医心方』には、身体を整える薬として記されてきました。現代では、その知恵を受け継ぎ、烏梅は薬膳茶として、人の暮らしに寄り添う存在になっています。日々を健やかに巡らせるための、支えとして。一方で烏梅は、染めの世界でも重要な役割を果たしてきました。延喜式にも記される紅花染めでは、発色と色とめを担う、欠かせない存在です。その色は、晴れの場や祈りの場を彩ってきた、高貴な色でした。明治以降、化学染料の普及によってこの技法は一気に姿を消していきました。それでも今なお、格式を重んじる場や、千年単位の時間を生きる場所では、変わらず使われ続けている色があります。■ このクラウドファンディングについて今回のプロジェクトは、目標金額を達成した場合のみ成立するAll or Nothing方式で実施します。そしてもうひとつ、私自身が大切にしたい目標があります。それは、50名の共感者とともに次の一歩を踏み出すこと。烏梅は、大量生産できるものではありません。だからこそ「共感してくれる人の数」をこの挑戦の指標にしたいと考えています。■ 目標達成後、全国大会へ挑戦します地域の隠れた逸品を発信する舞台「にっぽんの宝物グランプリ全国大会」ありがたいことに、出場のお声がけをいただきました。この舞台に立つ目的は、賞を取ることではありません。まだ知られていない烏梅という文化を、全国へ届けること。目標を達成し、多くの方と想いを共有できたなら、全国大会という次の舞台へ進みます。■ 吉野杉の新しい器に入れた、特別な烏梅今回お届けする烏梅は、奈良・吉野の杉を使った新作の特別容器に入れてお届けします。木を使うことは、見た目の美しさだけではありません。・プラスチック使用量の削減・CO₂を吸収してきた木材の活用・吉野の森の循環を守ることにつながります。そして器づくりには、木工だけでなく多くの職人の技術が関わっています。烏梅という存在を残すことは、そうした職人の営みを未来へつないでいくことでもあります。■ リターン内容吉野杉の新作容器入り 烏梅1個 6,980円(税込み、送料込み)1300年前から受け継がれてきた製法そのままに、梅の果実を蒸し、燻し、干し、長い時間をかけて作り上げています。自然素材だけで生まれる深い黒。今だけの特別なかたちです。■ なぜこの挑戦を、皆さんと進めたいのか烏梅を全国へ発信するために、今回、新しい舞台へ挑戦しようとしています。けれど、その一歩を支えてくれるのは、大きな数字ではなく、顔の見える一人ひとりの存在だと感じています。烏梅は大量生産することで続いてきたのではなく、季節の火を見守り、その価値を受け取ってくれる人たちの存在が、次の一年を支えてくれていました。今回も、ただ賞を目指すのではなく「共に進もう」と思ってくださる気持ちの重なりを大切にしたいと考えています。共感が重なった先に、全国へ踏み出す意味が生まれる。そう信じて、この挑戦を始めます。■スケジュール クラウドファンディング募集締切 2026年2月20日 にっぽんの宝物グランプリ全国大会エントリー 2026年2月21日 にっぽんの宝物グランプリ全国大会 部門大会 2026年2月28日 にっぽんの宝物グランプリ全国大会 総合 2026年3月1日■ 最後に私の家には、代々受け継がれてきた言葉があります。「天神さんをお祀りするつもりで、売れても売れなくても梅を焼け」それは、経済活動のためだけではなく、自然への感謝や祈り、日々の営みを大切にする心を忘れないための言葉だと思います。烏梅を未来へ。森と職人の循環を次の世代へ。烏梅は脇役であり、大きく主張する存在ではありません。静かに火を守り続けてきた先人たちがいました。その火を、もう少し先へ。もしこの営みに共鳴していただけたなら、この小さな挑戦の仲間になっていただけたら嬉しいです。リンク(キャンプファイヤー)https://camp-fire.jp/projects/926635/view#クラウドファンディング#キャンプファイヤー#烏梅#紅花染め#梅古庵 もっと見る
写真家倉家eto修司さん
2026/01/30 20:19写真家 倉家eto修司さんによる密着撮影が始まりました。2年程かけて撮影してもらう通称冷静と情熱の大陸プロジェクト@photo_k_e_shyuji写真1文部科学副大臣の小林茂樹氏と写真2春日大社の参道燈籠写真3春日大社正式参拝㈲恵夢経恵寿の藤森社長さんと写真4春日大社正式参拝の御神酒写真5奈良の食文化研究会の新年会会場写真6NHKの料理対決番組に出場した奈良の食文化研究会の会長は最初烏梅を使った鍋で勝負したいと打診あったので烏梅鍋を試作しその試作の様子もNHKに撮影してもらってたのにその後の幹部さん達の試食会で烏梅鍋却下され別の饂飩鍋で本番に出場された経緯あって会員で唯一負けろと思ってたのに見事に全国優勝され祝勝会で何か述べろと言われたので敗戦の弁を述べている横に優勝トロフィーを持った会長が満面の笑みで絡む写真7奈良の食文化研究会の新年会で挨拶#写真家#春日大社#食文化#烏梅#梅古庵 もっと見る
大豆栽培と薬膳味噌作りコース
2026/01/22 22:155月に一粒の大豆を蒔くところから始まった大豆栽培と薬膳味噌作りコースの一年は、夏は雑草と向き合い、水をやり、枝豆になり、やがて11月には大豆として収穫。そして1月、育てた大豆を生麹、天日塩と合わせ、秋田杉の味噌桶へ仕込みました。秋田杉の味噌桶をつくる職人さんも、年々少なくなってきています。けれど杉の桶には発酵に欠かせない菌が住み着き、使い続けることでその土地、その家ならではの味が育ちます。桶を使い継ぐことは、道具を守ることでもあり、発酵文化を守る事だと感じています。仕込んだばかりの味噌はまるであずきバーのようでまだ味噌の味はしません。けれど一年寝かせるだけで、驚くほど深く、おいしい味噌へと育っていきます。大豆を育てるところから始めるからこそ感じられる醍醐味は、ランチには羽釜で炊いたお米のおにぎりと味噌汁、烏梅鍋、梅にゅう麺。月ヶ瀬の素材を味わいながら、楽しく育て、仕込む一年のワークショップでした。植物の命をいただくこと。土に触れ、季節の移ろいを感じること。一粒の大豆が芽を出し、葉を伸ばし、花を咲かせ、何倍もの実となって還ってくる農耕民族の知恵と強さを、体で学ぶ一年でした。来年も、この循環をともに楽しむ仲間が増えますように。#大豆#栽培#薬膳#味噌作り#梅古庵 もっと見る


















コメント
もっと見る