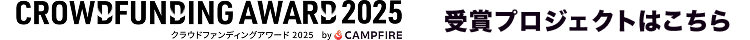quazero – カゼロウ
今沢カゲロウ ルワンダ滞在目撃録9
(現地ガイドが目撃したことを書き記しています)
ガイドをしていると横にいながら説明をしたり、少しだけ斜め前を歩き振り返りながら話をするという場面が多くなる。
居るようで居ないようで居る関わり方が、訪問者本人がルワンダを捉える視界を邪魔しないことにつながっていると感じているからだ。
そういう日々の中で、何かのタイミングでカゲロウさんと対面に座り話をする機会があった。
ルワンダ滞在前半のときだ。
発言の節々で、顎を下げ、眼鏡の上縁を越えてぐっと押し込めるように視線を投げる。睨むともまた違った独特の視点の置き方が、今沢カゲロウらしい切れ味を助長していた。
自信の現れにも見える一方で、何かを自信で覆っている現れにも見えた。
そのリズムに慣れてきたとき、私はなぜ今回密着取材をしたいとおもったかを話し始めていた。
到着前に「密着取材をしたい」ということだけお伝えし、それ以上に詳しく説明せずとも、トントンとOKを頂いてしまっていたのだ。
ガイドとして様々な方をお迎えしていると、その都度その都度新しいルワンダを発見できる。
こちらに住んでいて、慣れきってしまって、知っているつもりになっていたこの国のことを、いつも更新してくれるのは、訪問者の目から見たルワンダ像だ。
バックグラウンドも違う、価値観も違う、かつて訪れてきた国も違う、生活している環境も違う、これから目指すことも違う、何を大切にしているかも違う、それぞれの人たちから聞かせてもらえるルワンダの印象を受け取るたびに、全く違う国のことを見つけたような嬉しさがあった。人の数だけルワンダがある。
ああ、そう見えているのか。そう感じているのか。
「その人の目になって、その人のこころに成り代わって、世界を見てみたい、そのことを記録してみたい、そうおもったんです。それで、今回ガイドを行いながらルワンダ滞在中の密着取材をさせていただきたいとお願いしました」
いつもの、上縁を越えた刺すような視線は飛んでこなかった。
可視化できる長さの沈黙のあと、伏目のまま聞こえてきたのは
「私のこころを追体験するのは厳しすぎます。耐えられないと思う」
「一言でいうなら、苦悩と自己否定の連続でした」
大衆的ではないジャンルの音楽を続けていくにはそれ相応の覚悟が要る。
聞き手のニーズに合わせていくよりも、こちらが表現したいことが圧倒的にあり、それに共鳴したり引き付けられてしまう人を絶やさないこと。
そのためにはその圧倒性の手触りがいつも存在している必要があったし、それが更新され続ける必要があった。
中学生でギターを手に取り、しばらくしてベースに出会ったときに「より身体に近い楽器だ」と直感的におもった。
そこから独学で訓練を重ね続け、来る日も来る日も弾き続けた。実験的なこともたくさんした。
オリジナリティを逞しく積み上げ、それはベース奏者になる過程というよりも己になる過程に近かったようにおもう。
大学4年間は一度もお昼ご飯を食べなかった。毎日毎日食堂の前で演奏をしていたからだ。
たまに混ざってくる人がいた。たまに隣でパフォーマンスをしてくる人がいた。
誰も長く続かなかった。
結局一人で始め、一人で最後まで続けた。
在学中にプロデビューし、卒業後もそのままベーシストとして活動を続ける。
独自性をさらに強固にし、独学、蓄積、独学、蓄積の繰り返しをした。
ベースを手にしたそのときから今沢スタイルが立ち上がり、その上にどんどん今沢スタイルを塗り重ねていった。
あまりの突飛さに国内では批判が相次ぎ「そんなのベース演奏じゃない」「おとなしくバンドの一員で弾いていればいいのに」「アンサンブルを下支えするものなのに目立ちすぎ」等々、今沢スタイルが許容されることなく、拠点を海外に移した。
どうして理解されないんだろう、なぜ伝わらないんだろうの連続に苦悶する時期もあり、そこから距離を置くための選択だった。
海外での活動を始めたときも、活動開始たった数日後にいい顔をしながら近づいてきた人に騙されすっからかんになる。
路上パフォーマンスやカセットーテープ手売りなどを続け一日一日を文字通り切り抜けるようにして生き延びた。
その後軌道に乗り、世界規模のショーにも度々招聘されるようになる。気づくと誰が付け始めたか分からないBASSNINJAのニックネームが広まり、独自性がさらに開花していった。
2010年
積み上げてきた今沢スタイルと共に、満を持して南インドツアーに向かう。
グラミー賞受賞者の打楽器奏者ヴィック・ヴィナヤクラムと、その息子との共演のためだ。
深く息を吐く。
意を決したように空気を吸い込み、静かに口をひらく。
「こてんぱんにされました。演奏家として全ての自信を喪失しました。」
「あんなにベースと一体化していると信じて長年活動してきたのに、あの場にいた誰よりも、私は楽器から遠かった。私だけ身体から楽器が生えていなかったのに気づいてしまった。」
「音楽と身体の溶け具合が全員圧倒的だった。私だけ全くついていけなかった。セッションをしたときも、曲によっては私だけソロを回してもらえなかった。ベースはそもそもソロ用の楽器でないという判断のもとだったかもしれないが、それでも悔しかった。」
共演相手は幼少の頃から家庭環境的に英才教育を受け、確固たるリズム感を身につけているのは分かっているが、それを差し引いたとしても、そのダメージを回復させる薬にはならなかった。
真っ白になり途方に暮れた状態で帰国。
帰国直後に、まだ何も報告していない人から「で、これからどうするの?」と言われハッとする。
基礎をやろう。
ずっとやってきていなかった、基礎をやり直そう。
ベースを始めて27年目。
はじめて人に音楽を習うことを決意する。
敬慕する音楽理論家の門を叩き、徹底してクラシックからはじめた。
違う、もっとこう、そうじゃない、それではだめだ、こうしなさい
今まで言われたことのないフレーズのなかに自ら飛び込み、4年間ひたすら地道に習い続けた。
「そうするしか無かったんです、あの圧倒的な違いを見てしまってからは。」
自身のスタイルで最初からやってきた人が、この決断をするのはどれほどのことだったか。
積んでは壊し積んでは壊しの繰り返しを自分の力で行ってきていたが、これが最大の壊しだったのではとおもう。
自分の力だけでは行けない距離に自分を運ぶために、壊すことも自分以外の力を借りる必要があった。
自分に影響を与える物を自分で選んでいては、都合の良い自分にしかなれない、とはある音楽家の言葉だ。
知り合って2ヶ月。
彼のライブすら見に行ったことがない、ギターとベースの違いもよく分かっていない素人の私が、新しい世界を作る音楽の誕生に立ち会うには情報があまりにも少なすぎた。
それを察してか、「過去は振り返らない」と言い切るカゲロウさんが、時間を使って丁寧に自らのこれまでを共有してくれた。
 歩きながら素材を探す
歩きながら素材を探す
 そこかしこにインスピレーションのもとが
そこかしこにインスピレーションのもとが
 ルワンダの伝統二弦楽器Iningiri(イニンギリ)の試奏
ルワンダの伝統二弦楽器Iningiri(イニンギリ)の試奏
カゲロウさんと話をしていて、ある特徴に気づく。
「中華料理でなにが好きですか?」と聞くと
「多くの人が好むようなエビ、ホタテとかにあまり興味はないです」
「音楽の業界でこれからどう進んでいくんですか?」と聞くと
「管理される、自由がきかないのは嫌なので、事務所に所属することはないでしょうね」
「回鍋肉が好きです」や
「これからもフリーでいきます」ではなく、
取らない選択肢の話を先にする。その後に核心に迫っていく。
そういうなかで
「これからどんな未来を作るんですか?」と聞いたときは
「ベースで新しい世界をつくります」
そう明確に、力強く、取る選択の方を放った。
眼鏡の上縁を越える目線ではなく、まっすぐに、私にではなく、私を通り越したはるか先を見据えて。
ベ ー ス で 新 し い 世 界 を つ く る
それはベースの世界の話ではなことは確かだ。
世界の世界の話だ。
ご本人は「進化」ということばをよく口にするが、その変容と日々の姿を見るにつけ、それは帰還に見えてくる。
どんどん自分に戻っていき、その根にある原動力に近づいていく。
近づいて近づいて原動力そのものに成ったときに、どんな世界が溢れ出すのだろうか。
今沢カゲロウが存在しなければ、この世に存在しなかったもの。
それをもうすぐ耳にできる。

(文・写真:masako kato)