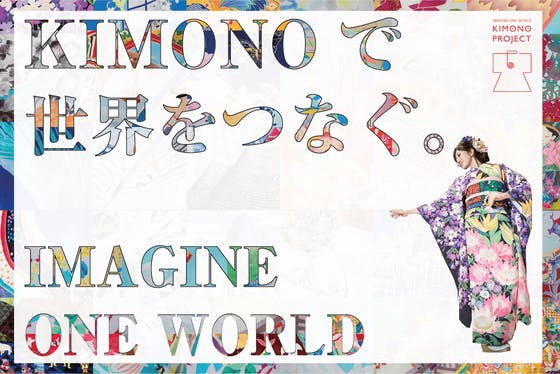■幸せの国ブータン
ブータン王国は、 世界で唯一チベット仏教を国教とする国家であり、 南アジア、インドと中国の間にある、日本の友好国です。
数年前に国王夫妻が来日された時の報道を目にしたときに、国王夫妻の凛々しいお姿と、 その高貴な立ち居振る舞いに心から感動を覚えました。
ブータン王国は1989年より日常着として公の場での民族衣装の着用を国民に義務付けた国としても有名です。 国民総幸福量を高めることを国家目標に掲げ、物質文明にとらわれない指針は世界に大きな反響を与えています。
また、男性の民族衣装「ゴ」は呉服の語源ともされ、伝統の織物や染織においては、 古来よりの技術を今に伝える宝庫と言われています。 アジア最初の国にブータンを選んだのは、染織の先進地で、その歴史的価値を広く紹介したいという想いからです。
■日本一の染め元の歴史
ブータン王国のKIMONOの製作を行ったのは、京都の老舗「千總」。 創業1555年、武田信玄と上杉謙信が川中島の合戦を行った弘治元年に、 法衣商を室町三条で営んだことが千總の歴史の始まりです。
友禅の技法が開発された元禄時代はもちろん、近代においては明治期に、日本画家に着物の下絵を描かせることにより、 明治以降の着物のデザインに大きな影響を与えました。海外的な視点も鋭く、パリやブリュッセルの万国博覧会では、 数々の賞牌を獲得し、日本の染色の技術の高さを世界に示すなど、業界における功績は数えきれません。
また、常に「新たな美」を追求し、アールヌーボー、型友禅、最近では友禅染めのサーフボードの製作、 世界的なデザイナーとのコラボによる友禅掛け軸の製作など、 時代の最先端を駆ける先駆者として確固たる地位と名声を誇っています。 その千總にして初めての挑戦が「国をテーマにしたKIMONO」でした。
■温故知新のデザイン
ブータンを製作するにあたり、デザインの基本に置いたのが「古典」です。
江戸時代の小袖には、着物全体を大きく取り分けて、 掛けた時と着た時の印象の違いを楽しむ文様も数多くあります。 そこで、ブータンの国旗に描かれている「龍」に着目して、 寛文時代の取り方を参照しながらデザインの製作が進められました。
国旗に描かれている赤と黄の配色は、この国の好みを端的に表していることから、 これを地色として、中心に大きく龍をシルエットで描く着想が浮かびました。 その際に、絞ったようにみえる友禅「友禅疋田」で龍を描き、ブータンの力強さを表現しました。 また、絣の織物が特徴であることに着目して、伝統的な織物の文様を染で表現し、仏教にゆかりの深い「唐草」の文様を、できるだけブータンの国花である芥子の花に近づける工夫を凝らしました。 また、世界で唯一ブータンにのみ生息するブータンシボリアゲハという蝶を、 ブータンの国民の皆さんへの敬意として描くことにしました。

■京友禅の教科書
千總の仕事は、まさに京友禅の教科書と言えます。
図案が完成すると、千總専属の染匠である「木村染匠」と工程の打ち合わせに入り、 図案→下絵→糸目→糊伏せ→地染め→色挿し→蒸し→水洗→金彩→刺繍 といった職人の構成がきまります。
京都の友禅は分業制であり、それぞれの仕事に卓越した職人が、 単に図面通りの仕事を行うだけでなく、図案の持つ意図や出来上がりのイメージを、 それぞれの工程で共有しつつ、 更によくなるように自分の領域において工夫を重ねるところに最大の特徴があります。
即ち、つぎの工程へと進めば進むほど「進化」しながら完成に近づくのです。
その全体のディレクターが木村染匠であり、 統括するプロデューサーが千總ということができます。



■浮かび上がった、ブータンの龍
着装時には全体を見ることはできませんが、衣装掛けに掛けて見るとブータンの象徴である龍がどっしりと中心に描かれ、 ブータンを護り導いているかのようです。
また、赤や黄の色もアジアンなテイストの彩色になっており落ち着きのある華やかな全体の印象に大きく寄与しています。
ブータンの力強い生命力や躍動感をあらわす「唐花」の文様は、上前と肩にデザインの中心を置き、刺繍や金箔によって飾られています。
ブータンシボリアゲハもブルー系の濃淡を用いて描かれていて、 全体をまとめるアクセントになっています。
世界的に貴重な素晴らしい国「ブータン」を敬意をもって創作された作品となっています。

■ブータン 帯
製作者 西村織物 伝統工芸士 井上久人
技法 手織佐賀錦
佐賀錦は、元々旧肥前国鹿島藩の御殿女中に受け継がれた織物で、 大隈重信の肝いりによりロンドン万博(1910年)に出品され高く評価されたことから、 その後も高級な織物として現在に至るまで帯地に使用されています。
今回は、博多に現存する数少ない手織の技術を生かし、ブータンの帯地の作品に挑みました。
ブータンはチベット仏教の影響が強い敬虔な仏教徒の国であり、 また、男性の民族衣装である「ゴ」は呉服の語源とも言われています。 そんな、ブータンの寺院の装飾文様から取材を行いました。 佐賀錦の特徴は、網代のように金箔を経糸の代わりに張って、 緯に金糸や金箔を織り込んでいくことから、 必然的に市松や斜め45度の斜線にそった文様が織り上げやすいという点にあります。
そこで、タイル状にちりばめられた寺院の文様に注目し、 赤と青の色を中心に佐賀錦の金色を活かしたデザインが完成しました。
博多織の伝統工芸士「井上久人」氏は、80歳に至る佐賀錦織のベテランですが、 ここ20年近くは、現存するデザインを繰り返し織ることに従事してきたために、 当初は新柄への挑戦にためらいも感じていました。
しかし、今回のプロジェクトの真意を理解したうえで、 新たなデザインへの挑戦をしてくださいました。
井上氏曰く「一見、単純に見える市松の文様を正確に織り上げることは想像以上に 困難でした。強く打ち込めば四角がひしゃげてしまい、打ち込みが甘いと長方形になってしまうところが最大の難関 でした」
数度にわたる試し織の中で、金地に載った青や赤の彩を調節することで、豪華な振袖の上にも十分に合せられる帯の製織に成功しました。

織上がりは、見た目以上に薄手で軽く柔らかいもので、この質感こそ手織ならではのものといえます。
また、糸使いの妙によって、ブータン古来の絣の雰囲気さえ感じ取ることができ、 物質文明としての進歩以上に、幸せを追求するブータンの人々にも受け入れていただけるような織上がりに成功したと思っています。 大きな竜と国旗の色に彩られたKIMONとの相性も抜群です。