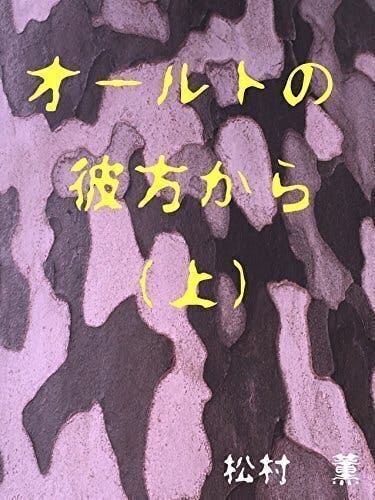今日は、SF「講義 地球人史(第十二回)」の冒頭をお送りします。 さて、三ヶ月続いたこの講義も今日で終了じゃの。テストもみなよくできておったぞ。これが終わったらあとは体験して確かめるのじゃ。では始めようかの。 最近と言ってもいいが、五百年前からの科学の大進歩は生命進化に起きたカンブリア大爆発になぞらえ、科学のスーパーノヴァと言われているな。ん? どこが最近なのかって? 過去の出来事は起きてしまえば一瞬に感じるものなのじゃよ。まあ聞きなさい。それは人類が火星に移住を始めた頃から起き始めたのじゃ。物理学や医学、情報科学に宇宙工学と数え上げればきりがない。 たとえば、ヒッグス粒子の発見から暫く物理学者はダークマターと重力子の発見に躍起になっていた。四百八十年前、月に建設したハイパーハドロン衝突型加速器(HHC)により、まず重力子が発見され四百五十年前についにダークマターと重力子が同じものだということが分かったのじゃ。これにはコンピュータの発達の寄与するところが大きかったな。 これが発見されてから、まさにエネルギー革命が人類を席巻したのじゃ。ん? 何がってか。確かに諸君の生きている今では全てが当たり前だと思うのは当然じゃ。騒音が全くないのは昔はありえないことじゃった。人類は重力子を発見して以来一世紀以上を費やし、重力を制御する方法を見つけたのじゃ。 さあ、それからは滝壺に向かって落ちていく水のように変化が加速した。まず、エンジンが消滅したな。次いでモーターの仕組みが変わったのじゃ。名前こそ重力子エンジンというが、吸入-圧縮-燃焼・膨張-排気というサイクルを繰り返すわけではない。地上を車輪で進む必要がなくなった。そう、乗り物は全て浮遊しながら移動できるようになったというわけじゃ。推進力は車体の周囲の重力バランスを崩すことで得られるから音も出なければ移動もスムーズじゃな。ほら、このあいだ講義した空飛ぶ円盤の話があったじゃろ。不思議な飛び方をするというあれじゃが、恐らくそれも似たようなメカニズムなんじゃろうの。 ついでに宇宙開発の話をしようかの。重力子エンジンの発明はロケットや宇宙エレベーターを不要の物にした。宇宙船の速度は現在最も速いもので光速の九十パーセントまでじゃな。限りなく高速に近づけることもできるようじゃが、そうするとそのうち様々な原子が衝突してくるからの。それを防ぐ方法はまだ出来ておらんのじゃよ。とは言え、太陽系全体を探査することは可能になった。船も重力子エンジンのおかげで巨大なものが航行できるようになったぞ。トラディショナルパークに聳えておる赤い塔があるじゃろ。近年手入れが大変になったそうじゃが、あれは東京タワーと言っての、電波塔じゃったな。ちょうどあれくらいの長さの船が今ではスタンダードじゃな。 火星も移住後ずいぶん人口が増えたな。当初はそうするつもりはなかったのじゃが、今は太陽-地球ラグランジュポイント5の位置にスペースコロニーが三棟浮かんでおる。そう、太陽と地球を結んだ線から六十度の地球の公転軌道と交わる位置じゃな。地球の後を追うように自転しながら公転しておるよ。直径十キロメートル、長さ二十キロメートルの円筒の形のものじゃな。一棟につき十万の人が住んでおる。電力は宇宙空間に広げた太陽光発電パネルから得ている。クリーンじゃろ。水は月から運び込んだ。植物はコケ類から始め広葉樹まで全面積の五十パーセントを覆うようにしている。水草も豊富じゃぞ。光合成をし酸素を作り出しておる。ここ百年の話じゃ。