「草の葉ライブラリー」は小さな出版革命に踏み出した
「草の葉ライブラリー」は今から三十年前に、雑誌「草の葉」ならびに単行本刊行を目的に、営利事業としてではなく一隅を照らすボランティア活動として創立しました。爾来、農夫、工房主催者、建築家、ガレージ運営者、タクシードライバー、精神科医、翻訳家、書店員、主婦、珈琲屋店主、詩人、出版人、編集者,作家、画家、保育園創設者、塾教師、大学教授、劇団創立者、美術館創立者、学校設立者、牧場経営者などすぐれた識見と思想をもつ人々と仕事をしてきました。そしていま「誰でも本が作れる、誰でも本が発行できる、誰でも出版社が作れる」という小さな活動に踏み出しました。

たった一冊の本が世界を変革していくことがある
本は売れなければならない。売れる本だけが価値をもたらす。売れる本によって本を作り出す人々の存在が確立されていくからである。これがこの世界を絶対的に支配している思想でありシステムであり、したがって数十部しか売れない本は価値のない本であり、数部しか売れない本はもう紙屑同然のものということになる。しかし本というものは食料品でも商品でも製品でもなく、まったく別の価値をもって存在するものであり、たった数部しか売れなかった本が、数十万部を売った本よりもはるかに高い価値をもっていることなど枚挙にいとまがない。ベストセラーなるものの大半が一読されたらたちまちごみとなって捨てられるが、たった五部しか売れなかった本が、永遠の生命をたたえて世界を変革していくことだってある。
この視点にたって創刊される「草の葉ライブラリー」は、たった数部しか売れない本に果敢に取り組み、独自の方式で読書社会に放っていく。荒廃して衰退していくばかりの読書社会に新たな生命の樹を打ち立てる本である。閉塞の世界を転覆させんとする力動をもった本である。地下水脈となって永遠に読み継がれていく本である。
一冊一冊手作りの出版のシステムを確立していく
これら数部しか売れない本を読書社会に送り出していくために、その制作のシステムを旧時代に引き戻すことにした。旧時代の本とは手書きだった。手書きで書かれた紙片が綴じられて一冊の書物が仕上がる。その書物を人がまた書き写し、その紙片を束ね、表紙をつけて綴じるともう一冊の書物になった。こうして一冊一冊がその書物を所望する人に配布されていった。
この手法を現代に確立させるための最上の道具がそろっている。その作品をコンピューターに打ち込み、スクリーンに現れる電子文字を編集レイアウトして、プリンターで印字し、簡易製本機で一冊の本に仕立てる。簡易製本機、これは驚くべき発明である。この機器が登場することによってだれも本が作れるようになった。その工程はすべて手作りである。その一冊一冊が工芸品のように制作される。
大量印刷技術によって、複雑なる販売流通によって、売れる本しか刊行しない、売れる本しか刊行できない現代の出版のシステムに反逆するシステムである。この旧時代的手づくり工法によって、真の価値をもった作品が新たな生命力を吹きこまれて一冊の本となって読書社会に送り出される。新しい時代を切り開く出版のシステムの誕生である。
読書社会に新しい地平を切り開くクラウドファンディング
長い苦闘の果てに書き上げた作品が、本となって読書社会に投じられるまで何段階ものハードルがあり、そして実に複雑なルートを通さねばならない。晴れてその本が書店に並べられたとしても、その本を手に取る人はゼロで、したがってその本は二三週間で返本される。ごみ同然となったその本は裁断され焼却される。これが今日の出版の現実である。この現実を切り開かんと、いま全く新しい出版のシステムが登場した。クラウドファンディングである。大望を抱く者が、しかしその大望に取り組む資金のない者が、社会に人々に助力を求めるシステムである。
草の葉ライブラリーはこのシステムによって、一冊一冊が読書社会に投じられていく。複雑な流通システム一切なしである。リターンにクリックされた購入者のもとに草の葉ライブラリーから発送される。出版システムの革命である。
生命の木立となって時代とともに成長していく草の葉ライブラリー
現在の出版のシステムは、その本を読書社会に投じたらそれで完了である。一度出した本を再編集して投じるなどということはめったに行われない。出版社は絶版の山を築いていくばかりである。大地を豊かにする名作がこうして捨てられていく。ゴッホの絵がなぜいまなお脈々と生命をたたえているのか。それは繰り返し彼の絵が展示されるからである。なぜモーツアルトの音楽がいまなお人々に愛されるのか、それは繰り返し演奏されるからである。生命力をたたえた本は、繰り返し新しい世代に向けて発行していくべきなのだ。「草の葉ライブラリー」は新しい編集、新しい体裁によって繰り返し刊行されていく。その時代の生命をその本に注ぎ込むことによって、その本は時代ともに成長していく。これらの活動はwebサイトの「noteウオールデン」に二百本近いコラムやエッセイとなって植樹されている。
草の葉ライブラリー
手作りの本。
貧弱な体裁の本だと思うのか。
出版革命を先導する
製本機「とじ太くん」によって
造本される本は
素朴だが美しい。
荒廃していく読書社会に
新しい地平を切り拓いていく本だ。
「草の葉ライブラリー」が
魂をこめてつくりだす
一冊一冊は
生命の木立となって
時代とともに成長していく。
このサイトに、何百万とアクセスされている「youtube」の動画を植え込んでいますが、これは違法ではありません。この土地に植え込まれても「著作権者」の権利は確保されていて、私たちがそのサイトを訪れるたびに「著作権者」に加算されていきます。もともと「youtube」の根源の思想は、その動画を拡散させ、世界中の人々に共有してもらうことにあるのです。草の葉ライブラリーはこの思想を共有するということです。
いまやウエッブサイトは、圧倒的に画像や動画の世界になっています。文字だけのサイトは敬遠されます。長い文章などはすべてスルーです。こういう世界で本の真価を人々に伝えるにどうしたらいいのか。そこで編み出したのが、長い文章の一部を切り出し、音楽と融合させるという試みです。音楽が言葉に流れ込み、言葉が音楽に流れ込んでいく。言葉と音楽を共振させ、訪問者の豊かな想像力にゆだねるのです。

「草の葉ライブラリー」は「CAMPFIRE」に第一弾「ゲルニカの旗 南の海の島」を、そして第二弾「かぐや姫」を投じました。この本を手にして読了された人々の声。

手作りの本ということで、いったいどんな本なのだろうかと疑心半分に注文してみたが、作り手の魂がこもったズシリと心に響く美しい本だった。
なによりも内容が素晴らしい。四つのストーリー、どれも驚くべきストーリーです。新鮮な果実が心のなかではじけていく。
手づくりの本、新しい時代をつくる本だと思います。「一冊の本が世界を変革することがある。小さな出版革命はやがて大地に広がっていく」って、本当にそんなことを強く予感させます。私もこんな本をつくりたい。

「ゲルニカの旗」の小学生たちのいじめが半端じゃない。しかし今でも子供たちはこんないじめ方をしている。もっと激しく、もっと陰険に。それはゆがんでいく日本の社会の反映でもある。
学級崩壊したクラスに新しい先生がやってくる。私もこういう先生に出会いたかった。そしたら私の人生はまったく違ったものになっていただろう。
吉永先生の授業は素晴らしい。私もこういう授業をしてみたい。私の目標ができた。
「ゲルニカの旗」は実際に起こった事件らしい。大人たちの争闘に巻き込まれた小学生は、苦しみながら成長していく。スペインを訪れて、実際にピカソの「ゲルニカ」の前に立ち、新しく生きていくと覚醒していく倉田佐織にしびれた。

「最後の授業」は、中学三年生の瀧沢君は納屋で首をくくって自殺する。瀧沢君は家族に美しい遺書を残していた。その美しい遺書を篠田校長は貧しい幼稚な遺書だと言った。いったいこの校長はどんな教師なのか。
伝統ある中学校で起こった中学生の自殺事件。マスコミに連日報道されて日本中が怒りで湧きたっていく。日本の教育はここまで腐敗しているのかと。
校長先生は、体育館に全校生徒を集めて、最後の授業をします。なぜ瀧沢くんの遺書が貧しく幼稚な遺書かといった意味があきらかにされていきます。生徒たちからすすり泣きの声が上がります。わたしもまたすすり泣いていました。
篠田校長は、瀧沢君に作文を書かせるために、四百枚の原稿用紙をリュックサックにいれて、北アルプスに登っていく。

そして今日改めて、最後のお作「南の海の島」を四度目、拝読し終えることができました。夜を徹して寝床で読了。あれこれ反芻しつつ寝就くことができませんでした。これはすごい作品だなと、深くうなずかずにはいられませんでした。
あれこれ思いました。何で作者はあの素晴らしい人間たち、飛鳥を、その母佐保子を、次いでその夫琢磨を、飛鳥の兄数馬を殺してしまったの! なんでだ、なんでだと私の中で、三度読んでも納得できない大きな違和感のかたまりが、打ち消し得ぬままにしっこっていたのでした。そして四度、私は否応なくねじ伏せられてしまったのです。これが世の中の不条理というもの、否定し得ることのできない究極の姿として受け入れる他はあるまい──。私の鼻血はそれなのだ。
これは傑作というしかない。私はそう思うばかりでした。
でも、インドに向かって出ていく私、「そして、今度は君がインドにくる番だな」。ちぎれんばかりに手を振って別れていく樫山と私。最後にはもののみごとに、希望が、希望の星が輝いている。読者は救われるのだ。すごい物語を、心からありがとうございました。

「かぐや姫」を一挙読みです。これは驚愕するストーリーです。本当に鎌倉時代に生まれた円空という人がこの「かぐや姫」を書いたのですか。
「かぐや姫」を作った高畑勲さんが、もしこの本を読んだら、この作品をアニメ化しただろう。高畑勲さんに読んでもらいたかった。
貧しい村の青年と恋に落ちたかぐや姫は、なんて愛らしいのだろう。かぐや姫が月に帰っていく場面で私は号泣してしまった。
ああ、これは驚くべき物語だ! 平安時代に生まれた「かぐや姫」と、鎌倉時代に生まれた「かぐや姫」は、永遠に残っていく。
四人の皇子たちが劇的に崩壊していくなか、石作りの皇子は、四十年かけてかぐや姫との約束を果たすのだ。この皇子の崇高な美しさに感動でふるえた。
「かぐや姫」をうちの劇団で舞台化したいと思います。

そして「草の葉ライブラリーの第三弾は、山崎範子著「谷根千ワンダーランド」と、高尾五郎著「クリスマスの贈り物」、さらに第一弾で投じた「ゲルニカの旗 南の海の島」をもっと密度の濃い三分冊、「ゲルニカの旗」「最後の授業」「南の海の島」にして投じます。そして圧倒的な評価を得た「かぐや姫」の六作品です。これらの作品を別のシーンから紹介する場面を活動報告に、さらに「noteウオーデン」に打ち込みます。「noteウオーデン」を訪問してください。
谷根千ワンダーランド 山崎範子

スナック美奈子での五日間
新聞配達の後を追う
怒涛の配達与太日誌
蔵の活用法を考えよう
事務所所探しの顛末
サトウハチロウ特集の最後
谷根千編集後記傑作選
獄窓の画家 平沢貞通のこと
D坂シネマの夜が更けて
奥本大三郎さんと千駄木を歩く
どこにでもいる少年岳のできあがり
生き物飼い方
地蔵になった哲学者
愛しの自筆広告
いま、私の目に見える景色
印刷所の男たちが版下を谷根千に変身させる夜
ステンドグラスのある風景
山崎範子の奥に見えてくるもの
‥‥‥‥‥‥
等々、四十編のエッセイ、ルポ、コラムが編まれている。
怒濤の配達与太日誌
12月25日
午後4時45分、『谷根千』56号できあがる。団子坂マンションに仕事場が移ってから、納品作業には屈強な足腰が必要なのだが、その労働は三盛社にオンブにダッコ状態。「腰が痛い」「息が切れる」「脚がよたる」といいつつ八千冊の『谷根千』が壁のように積み上げられる。外はもう薄暗く、配達開始は明朝と決め、台帳整理を急ぐ。納品書・領収書に判をおし、請求書を書く。いつもながらのドロナワ作業。夜、ニュージーランドに出奔中の十七歳の友人が突然遊びにきて、「えっ、おばちやん、クリスマスにも働いてるの?」
12月26日
未明、時計屋を営む姉より電話。息子が急性虫垂炎で手術するのだが身動きがとれない、たかが盲腸の手術なんだから勝手にやってくれと医者にいったが、親族の付き添いと、もしものときの輸血要員が必要だと説得された。ついては「おまえ、午前中病院にいってくれ、ちょうどB型だし」と懇願される。実は、人にはいえぬ弱みを姉に握られ頼みを断れず、『谷根千』の配達を気にしながら川口へ向かった。病室へ入り「叔母です」と担当医に挨拶。手術前に「剃毛します」と剃刀とシャボンを持ってきたかわいらしい看護婦に、甥は「自分でやります」とカーテンを閉め悪戦苦闘、シーツを紅く染めた。手術は順調に済み、昼すぎにお役御免。睡眠不足のまま午後から配達。谷中銀座の武藤書店で「年の瀬だというのに静かなもんだねえ」と声がかかる。今回は根津特集。これまで何かとストレートな反応(つまり苦情など)が多い根津のこと、心なしか配達の手が震える。
12月27日
気温は低いが、風もなくまあまあの配達日和。朝一番で自転車を走らせる。新年を前にして谷中墓地は墓参りの人で賑やかだ。あの世の人にもこざっぱりと新年を迎えてもらおうという、その心づかいがうれしい。昨年の夏の終わりに亡くなった三原家の高尾重子さんを偲んで『谷根千』を読んでくださる方もあり。上野桜木の桃林堂で屠蘇散を、東大前のニイミ書店でのし餅をいただく。正月が近い。とっぷり陽が暮れたころ、駒込のフタバ書店に到肴。ここの本揃えはユニークで主張がある。今回入口には、「店長が選ぶ今年のベストテン」コーナーが新設され、堂々とコメント付きで並べてある。おお、その十冊のうち六冊までがわたしの今年のベストテンと、一緒じゃないか、こんなに気のあう人は初めてだぞ、と思いながら一位に輝く未読の『ビート・オブ・ハート』(ビリー・レッツ著、文春文庫)を買って帰った。
12月28日
朝、本郷から神保町へ向かう。本郷通りの棚澤書店のおじさんが店頭ではたきをかけている。ここの建物は明治三十八年にはすでに建っていたという立派な出桁造りで、最近、建物を見にくる人が多くなったんだそうだ。「みんなが見てくれるから、今までは月に一度の掃除を、週に一、二回拭くようにしているんだ。ほら看板もきれいでしょう」という。今日は年賀状書きで大忙しとのこと。落第横丁にあるペリカン書店の品川力さんは腰を痛めて臥せていらした。神保町すずらん通りのアクセス(地方小出版流通センターの本屋さん)で、百冊の包みをドサツとおろす。ここの棚を物色するのは毎度の楽しみで。本日の掘り出しものはA5判の雑誌「中南米マガジン」五百円。ラテン音楽の紹介雑誌だが、中米料理店の店当てクイズ、ラテンの心を持つ女シリーズなどヘンナ記事も多い。『谷根千』とサイズも薄さも同じこの雑誌は、匂いも同じで見るからにマイナー、思わず創刊号から最新の四号までを購入。夕方、12月26日に閉店した小石川の児童書の店ピッピで最後の清算。この小さな書店と谷根千は、手を取り合って仕事をすることはなかったが、お互いの存在が支えで、見ている方向はいつも一緒だったと思う(少なくとも私はそうだった)。ピッピ最後の営業日は満員の大盛況で、閉店時間が迫るとカウントダウンが始まり、ゼロのかけ声で写真のフラッシュがいくつもたかれたんだそうだ。私を含めたこれだけのファンが経営難の力になれなかったのが淋しい。
PM10時、夜の店の配達に繰り出す。昼間は開いていないスナックや居酒屋に『谷根千』を置いて回る。大晦日まで頑張んなくちゃ、というのと今晩で今年は終わり、という店が半々くらいか。
千駄木の居酒屋兆治に行くとマスターが一人酒。朝七時までやっているこの店は十二時すぎから混んでくるという。「この間TVの取材でなぎら健壱がきたよ。谷中銀座の鳥肉店の小林さんと。すずらん通りの惣菜店のキョシさんとうち。うちのお汁粉サワー・青汁サワー・味噌汁サワーが珍しくてうまいからってさ」という。「ちょっと気持ちの悪い飲み物ですね」と私。
夜の本郷に写植カバが鳴く
A五判四十八頁、ペラペラのこれが雑誌「谷根千」の基本型。創刊号は八頁。二号目でグンと飛躍して三十二頁。そして四十号、四十八号とジワジワと厚くした。三十六号「学童疎開」の特集で思いが余り五十四頁。四十号の十周年特集は編集人三人のくだらない懐占談を載せて七十二頁になった。基本の一・五倍。たとえば、いつも十五軒分自転車にのっけていたのが、十軒分しか積めなくなる。広告の数も増えてホクホクしていたところに、割増の写植代と印刷代の請求が届く。雑誌を厚くするとはこういうことだ。
谷根千の文字は写植。文京区本郷のスマイル企画という写植屋さんで打ってもらっている。「打って」というのは正確ではないな。数年前から電算写植だからワープロのようにキーを「叩いて」文字を入力していく。そして藤間さんが編集機で改行や文字の大きさ、書体を指定してくれる。
さあ、ゲラがでた。ゲラというのは校正刷りのことで、活字を組んで入れる長方形の箱(galley)の名からきたのだった。ちょっと脱線するけど、今から二十年ほど前に精興社印刷の青梅工場を見学した。原稿を見ながらキーを叩き、叩かれて穴のあいた紙を機械に入れると、その先から新しい活字がポンポン作られて並べられていくのを見た。活字作りが機械化されている横では、あの鉛でできた小さな活字の、しかも裏返しになった字をひとつひとつ拾っている文選の人がいた。抬った文字を版面にきっちりと並べる植字の人がいた。私たちは振り仮名をルビと呼ぶけれど、これも活字の大きさで七号(五・五ポ)のことをイギリスではルビーと呼び、それが振り仮名に使う大きさだからなのだとこのとき教わった。本作りには、あの重たい鉛の入った箱を並べてゆく作業が必ずあると思っていた。が、谷根千を作るとき、目の前には写植しかなかったような気がする。
話を戻さなくちゃ。ゲラが出ると原稿と突き合わせて校正をするが、書いた人間と直す人間が同じなので非常に心許無い。そこで小野寺さんに校閲をたのみ、そのほかに編集人三人で読み合わせをする。三人がゲラを手元に置き、回り持ちで読むのを目で追い耳で聞く。「その人はそんな話し方はしない」「ぜんぜん意味わかんないよ」「この話ホント?」なんて、原稿書くときにどうにかして欲しいこともここで直す。「この漢字心配」 「ここで改行しよ」 「アンタの文章〈ネ〉が多いから三つくらい削ろう」「この話〈だそうだ〉くらいにしておいた方がよくない」など。
朝から仕事場に籠もり、留守電にして玄関に配達中の札を下げる。コーヒーをガボガボ飲み、昼ごはんも適当につまみながら、読む。読みながら、聞きとりの語り手のことを話す。取材したときの失敗も話す。腹立ったことも話す。嬉しかったことも話す。Oが突然語り手の声色を使って読みはじめるから、腹をかかえて笑い転げる。一転この密着した時間に、日頃のウップンを晴らすべく、お互いの欠点をあげつらってデスマッチを繰り広げることもある。
夕方、いつも時間切れ。残りの読み合せを超スピードで片づけ、真っ赤になったゲラを持ってスマイル企画に走るのだ。編集機の画面を見ながら赤字を直す藤間さん。直っているかどうか初校と再校ゲラを突き合せ、今度は素読み。「素読トハスットバシテ読ムコトナリ」谷根千。このあたりは急げ急げの大合唱で、できあがったときの赤っ恥がわかっちゃいるけどいつもこうなる。
再校または三校で校了。編集されたフロッピーが動物園のカバほどの大きさの黄色く四角い写植出力の機械にかけられる。
「グィーン、ガシヤ、ガシヤ。グウィーン、ガシヤ。……グィーン、ガシヤ。グィーイーン、ガシャガシヤ」これが黄色い出力カバの鳴き声でけっこう大きい。機械なのに音は不規則で、グィーンというところが「この字はどこかな」、ガシヤは「お、ここだ」に聞こえる。だから難しい字を探すときは「どこかな、どこかな、あれ、ないな、あったあった」風に「クィーンクイーン、……グィィーン、ガシャガシヤ」となるのだ。
生き物の飼い方
「犬猫等の家畜の飼育」禁止の賃貸マンションに住んでいる。古くて狭いが、「子ども可」の物件が他に少ないためか、近所にもジャリジャリ子どもがいる。わが家にはイモリ、ハムスター、金魚、メダカ、鈴虫がいるが、これくらいのものだと何もいわれない。それとベランダを勝手に寝床にしている不法侵入猫が三匹。
以前にも種類の違うハムスターがいた。子どもが同級生に二匹もらって、押入れに隠してたが、ガサゴソの音で発覚。飼うことにした。近所の子どもたちが、ハムスターと遊びに毎日どっとやってきた。よく食べ、よく眠り、よく動き、かわいかったけど、ある日、転んだ子どもの下敷になって内臓破裂。目玉が飛びだし、見ている間に死んだ。
子どもたちはシーンとして、泣き出すのもいる。しかたないので、飛び出た目玉を押し込めて、近くの公園に埋めた。子どもたちは「さらば友よ」を合唱した。
内臓破裂でハムスターが死んだ晩、残ったもう一匹は相棒を探して、一晩中巣の中をカサカサ歩きまわった。翌日からは巣の一隅に踞り、絶食をはじめた。好物のキャベツもヒマワリの種もカステラでさえも食べなかった。絶食をはじめて一週間くらい経った頃、動かないハムスターに触れると死んでいた。同じ公園の隣の場所に埋め、また「さらば友よ」をみんなで歌った。
「ハーちゃん(餓死した方)は、ムーちゃん(事故死の方)がとっても好きだったんだね」
「うん、死ぬほど好きだったんだ」
「さみしかったんだよ、ほかに仲間がいないから」
「話し相手がいないもんね」
「あたしたち遊んであげたのにね」
「でも、ハムスターじゃないものね」
子どもたちは、このハムスターの死にしばらく感動していた。
同じ頃、うずらを二羽飼うことになった。おまつりのクジに当たって、鳥カゴとエサ付きでもらってきたのだ。数カ月すると毎日卵を一個づつ産むようになったので、五日分溜めては食べた。飼いはじめて一年半くらいした頃、一羽が猫に連れ去られた。うずらの首を銜えてゆく猫の姿が窓の外に見えたが、追いかける気になれなかった。
残ったうずらがキキキキイとうるさく鳴く。あんまりうるさいので家の中に入れるが、それでもキキキキイと鳴き続ける。大家から苦情の電話がくる。鳥屋に持っていこうと話した朝、うずらがいなくなった。その朝、エサをやったのは誰か? エサの扉をわざと開けたままにしたのか? 追究する気もないまま、うずら事件は終った。
メダカが一挙に孵化したことがある。小さな黒点のついた透明なのがウヨウヨ泳ぐ。毎日毎日体が大きくなる。水草さえ入れておけば、エサを忘れても元気に育つ。だいぶ大きくなった頃、池で捕ったクチボソの小さいのをメダカの水槽に入れた。翌朝、メダカは水に浮き、クチボソ三匹が悠悠と泳ぎながら死体をツンツンとつついている。
結局、別にしてあった親メダカ四匹を残して、その年孵化したのは全滅した。
子どもたちはさっそくクチボソを池に追い返し、「メダカー同の墓」と割りぱしに書いた。メダカには「さらば友よ」は歌わない。
山崎範子の奥に見えてくるもの
「谷根千に終刊の日が」を草したのが、二〇〇九年であるから、それから十二年の月日が流れ去ったが、いまだに山崎範子の本は世にあらわれてこない。そこで草の葉ライブラリーでの登場である。彼女が「草の葉」に投じたエッセイ、そして地域雑誌「谷根千」に書き込んだコラムやルポを拾い集めて、時系列ではなくランダムに組み立ててみた。すでに遠くに去りつつある時代に書かれた文章であり、いずれも短文であり、その分量も二百五十ページにすぎない。しかしこの一冊のなかに山崎範子の本質というものが縫い込められている。彼女がどのように生きてきたのか、そしていまなお何をめざして生きているかが。
「谷根千」という小さな季刊雑誌から森まゆみという読書社会のスターが誕生したが、その影に隠れている山崎範子の存在を多くの人に知ってもらいたいと、『note』というウェッブサイトに、彼女のエッセイやコラムやルポをいくつか打ち込んだが、その中の一つに「日本最大の編集者」とタイトルをつけてみた。掛け値なしに山崎範子にそういう冠をのせるのは、この本を手にした人にはうなずかれるだろう。
「谷根千」は、谷中、根津、千駄木という地域に発行される百ページにも満たぬ小雑誌だが、発行されるまでにはさまざまな膨大な作業がある。取材からはじまって、原稿を書き、写真を収集し、それを割付していく。さらに毎号、百近い店舗から広告をとってくる営業活動があり、刷り上がってまるで壁のように積み上げられる一万部もの雑誌を、店頭販売してくれる三百近くもの書店や商店に、自転車の荷台に「谷根千」を山と積みこんで配布していく。
自転車操業のなか、精神活動、肉体活動、営業活動、奉仕活動、イベント活動、社会活動、金銭活動、子育て活動、内部争乱活動と、その全身をフル回転させ、時代の底に沈んでいくような町を見事よみがえらせていったのだ。こういう活動を二十五年も営々として展開していった山崎を「日本最大の編集者」と名付けたっていいではないか。
彼女はまた斬新な言葉を紡ぎだす一級のコラムニストであり、エッセイシストでもある。この本のなかに三編の「生き物の飼い方」があるが、こんな生き物の飼い方を描いた人は誰もいない。あるいは冒頭に編んだ「スナック美奈子での五日間」は、『note』につぎのような前文を書いて打ち込んでみた。
「これは極上のルポである。山崎範子のコラムニストとしての、あるいはエッセイシストとしての才気がほとばしっている。スナック稼業を、美奈子ママの人生を、その店に集う人々をとらえる視点の深さ、そして文章の構成力。たとえば、修業する目的が三つあるとして、冒頭でその二つの目的を書くが、三つ目は伏せられている。その三つ目が最終日に明かされるのだ。そのシーンにであったとき、私たちの心のなかに鐘が鳴り渡る。たった五日間の体験だが、山崎範子の柔らかい心と、繊細な感受性と、それを確かなタッチと文章力で描くこのルポは、短編小説のように仕上がっている。読む者を幸福にさせる」
クリスマスの贈り物 高尾五郎
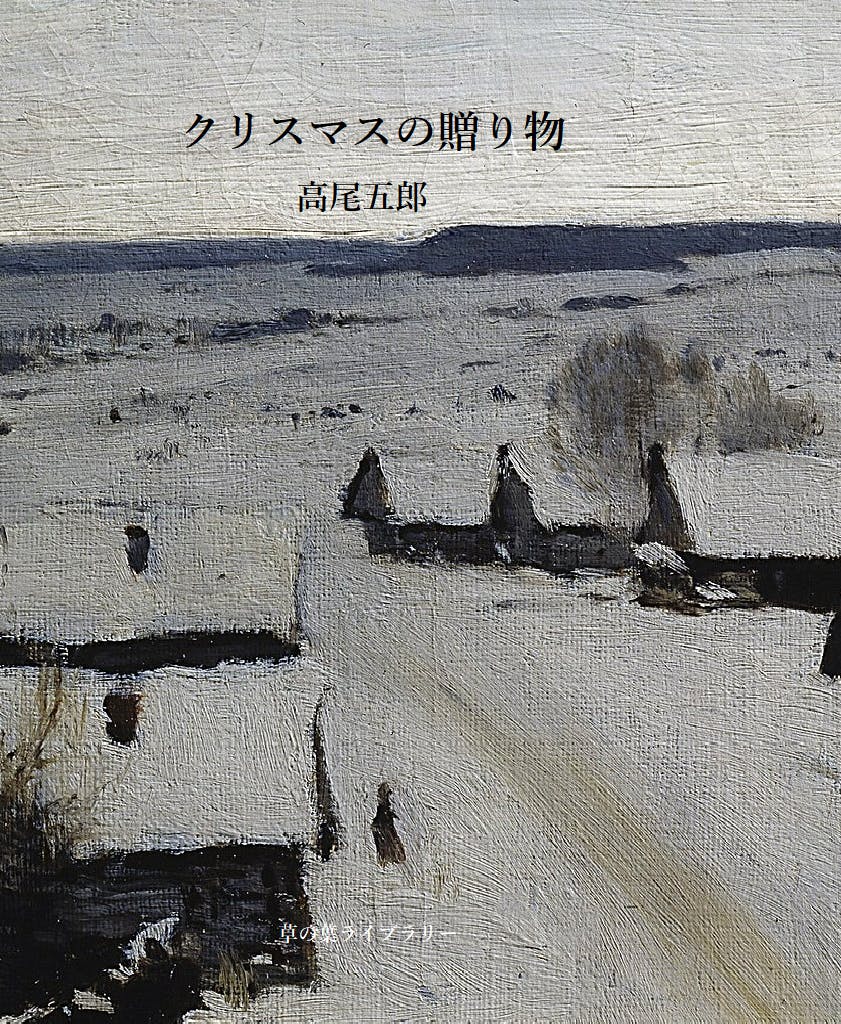
イエロー・ブリック・ロード
日本の川下り
北風号の冒険
決闘
クリスマスの贈り物
ようこそ、ピーターラピットの国へ
風と雲のアジテーターと日本のテロリスト
青い海、青い島
クリスマスの贈り物
私の朝ははやい。四時に起きなくてはいけないのだ。まだ人々が眠りについている町のなかを自転車をとばして販売店にむかう。私の受持ちは荏原五丁目から六丁目にかけて五十軒。全部を配り終わるのが七時半ごろだった。それから急いで家にもどると、ご飯をたべて学校にいく。そしてまた午後、学校から帰るとすぐに販売店にいく。タ刊を配らなければならないのだ。 新聞配達って、雨がめちゃはげしく降っている日とか、この間のようにどかっと雪が降った朝などちょっと大変だけど、仕事そのものはたいしたことはない。それよりも一番つらいのは、なにかいつも時間を気にしていなければいけないというか、いつも時間にしばられているということだった。放課後なんかも友達とおしやべりに熱中していても、すぐに時間がたって、
「あ、大変、もう時間だ!」
と言って、大急ぎで家に帰るのだ。
夜もまた見たいテレビが九時からとか十時からとかにある。それを見たいと思うけれど、明日また四時に起きなければならないと思うと、ついがまんしてしまう。だから新聞が休みの日などは、ああ、明日は休みなんだと思うと、からだの底からにこにこしてしまうのだった。
私がどうして新聞配達などはじめたかと言うと、一年生のとき、ともえちゃんという子と同じクラスだった。放課後、みんなでぺちゃくちゃと話していたら、突然ともえちゃんが、いま何時、いま何時って騷ぐので、みんなで職員室の前にある時計をみにいった。すると四時だったのだ。ともえちゃんはいま私がよくやっているように、
「あ、大変、時間だ!」
と叫んであわてて帰ろうとする。私はどうして時間なのときいたら、なんでも最近配達する人がいなくて、私がバイトで新聞を配っていると言った。
そのとき私は突然、ともえちゃんに、私にもそのバイトさせてと言ったのだ。そしてその日のうちに、ともえちゃんのお父さんに会って、新聞配達することにきめてしまった。
その夜、仕事から帰ってきた母に私は言った。
「私、あしたからアルバイトするから」
母はその意味がよくわからなかったからか、軽くうけ流すかのように、
「なんのバイトするわけなの」
「新聞配達の」
母ははじめて事態の大きさに驚くと、
「どうしてそんなことはじめるの。そんなことできないわよ。あなたはまだ中学一年生になったばかりでしょう」
「でも、ともえちゃんだってしてるんだから、私にだってできるわけよ」
母はそのときなんだか急に顔をくもらせたかと思うと、その目に涙をにじませている。私の家には父がいなかった。父は三年前になくなったのだ。だから私の家は、母がパートで働いているお金で生活をしている。だからなのか母はしめった声でこう言った。
「私の家は貧乏だけど、でもまだよっちゃんに働いてもらうほど、おちぶれてないと思うけど」
私はなんだか母を悲しませまいと、あわてて言った。
「そうじゃないのよ。ほら、お父さんの美術館の話」
「うん、うん」
「あれって、ものすごくお金がかかるでしょう。私もいまからお金をためなくちゃいけないと思うのよ。ともえちゃんの話をきいて、ああ、そうなんだ、もう私にだって、お金をかせげるんだってことに気づいたわけだから」
それは母と私と妹、つまり私の一家の夢だった。どこか森のなかに小さな美術館をつくるというのが。
でもそのとき私がアルバイトをしたいと思ったのは、やっぱりなんといってもお小遣いがほしかったからだ。中学生ともなるといろいろとお金がかかる。シャーペンとか、手帳とか、ノートとか。もちろん洋服だとかCDとか。原宿なんかにいくと買いたいグッズがいろいろとある。でもそんなことは母にたのめないことだから、やっぱり自分でバイトする以外にないと思っていたのだ。
でも私がその新聞配達のバイトではじめてお金をもらったとき、それははるかにお小遣いの範囲をこえていたから、みんな母に差し出すと、母はそのお金を貯金してくれた。その貯金通帳の口座名が、
《黒木俊雄の美術館をつくる会》
となっていた。
そのとき母はしみじみとした口調で言った。
「毎日の生活がきりきりまいでそんな余裕がなかったけど、よっちゃんのおかげでとても現実的になったわね。なんだかほんとうにできるように思えてきたわ」
すると妹までも、
「あたしもお姉ちゃんみたいに中学生になったらバイトするから」
「そうね。東京じゃとても無理だけど、どこか小さな村の森のなかならば土地だって買えるし。この通帳、私たちの希望ね。ありがとう、よっちゃん」
そうなのだ。それは私たち一家の勇気なのだ。
私の父は無名のままに倒れた画家だった。わずか三十八歳の命だった。その早すぎる死が、父にとってどんなにくやしく無念だったかということが、いまでも鮮やかに思い出すことがある。
イエロー・ブリック・ロード
その埠頭には赤煉瓦の倉庫が四つ五つと建っていて、その倉庫棟の前を通る道路もまた煉瓦が敷きつめられていた。高層ビルディングが次々と立っていくなか、そのあたりは古い時代の古い時間がたちこめているようだった。煉瓦通りを抜けると広場にでる。その広場の奥には全身をガラス張りにしたレストランが建っていた。建物の半分を海にのせていて、そのテラスから海に向かって長い桟橋を突き出している。その桟橋には白や青や黄色や赤にペイントされた幾隻ものクルーザーが停泊していた。そのあたりは煉瓦通りとはちがったなにか近未来といった景色が広がっていた。
そのレストランの前の広場は、都会の穴場というか忘れられた三角地帯というか、いつも空いているのでぼくたちが野球をするときは、
「イエブリにいこう」
「うん、イエブリだ」
と言って自転車をとばしていくのだ。イエブリとぼくたちがその広場を呼ぶのは、そのレストランの名が《イエロー・ブリック・ロード》で、それをちょん切ってつなげたわけで、それはぼくたちを解放させる、ぼくたちだけにしか通用しない、なかなかクールな呼び方だと思っているのだ。とにかく馬鹿ママたちが、学習塾とか、水泳クラブとか、ピアノとか、英会話塾とか、あっちこっち入れるもんだから、ぼくたちの毎日は忙しい。だからそんなものを蹴飛ばして、みんなそろってイエブリにいくときは心が燃え立つのだ。
そしてそれはぼくだけのことかもしれなかったが、ちょっと体があつくなる。というのはイエブリにいく途中、不思議なことにいつもシェパードをつれた外人の女の子と会うのだ。すごくかわいい子で、ぼくたちとすれちがうとき、その子は春のような笑顔でハーイと声をかけてくる。雄太とか、健治とか、守とかはその子に出会うと、ハローとか、ジスイズペンとか、ジスイズガイジンとか言っていたが、そのうちジスイズオマンコとかジスイズキンタマとか言って下品にガバガバガビガビ笑うので、ぼくはとてもはずかしかった。もしその子が日本語をわかっていたらなんて思うだろうって。そんな気持ちでちらりとその子をみる。するとその子はバラのような笑顔をぼくに、もっとここを強調すると、ぼくだけに送ってくるのだ。
その日もまた野球をやろうというみんなの気持ちが燃え立って、学習塾とか、水泳クラブとか、そろばんとかをそれぞれ蹴飛ばしてイエブリにいくことになった。ところがぼくは宿題を忘れ、その罰で掃除当番にさせられ、下校するのがみんなより遅くなってしまった。そんなことに時間を潰されたことが悔しくて、その時間をとり戻そうと全力疾走で家に帰ると、ランドセルをベッドに叩きつけ、グローブやボールやバッドをディバックに投げ込み差し込み、カラコラムGTのギアを最上段にぶちこんでイエブリに向かった。ぐんぐんと飛ばして、天王州橋を渡り、寺田倉庫橋を渡り、若潮埠頭橋を渡り、赤煉瓦の倉庫通りを曲がろうとしたときだった。目の前に突然シェパードが飛び出してきた。両輪のブレーキをかけ素早く避けようとしたが、ハンドルを切りすぎて路上にどっところがってしまった。
「あ、大丈夫!」
と女の子が悲鳴をあげた。あの子なのだ。ぼくは痛みよりもその子のことが気になったから、ずきっと痛みが走ってきたが、
「平気、平気、ぜんぜん平気」
「あ、血がでてる。たいへんだわ。痛そうね」
その子はポシェットのなかからハンカチをとりだし、血がにじんでいる膝小僧のあたりにあてようとした。ぼくはまた「平気、平気、ぜんぜん大丈夫」と言って、倒れたバイクを引き起こした。
「ねえ、これ使って。これ、あなたにあげるわ」
いつもお父さんが言っている男は我慢だということもあるし、その子には格好よくみせたいと思ったから、
「大丈夫だよ、こんなの怪我のうちにはいらないから」
と冗談ぽく言ってカラコラムGTにまたがると、その子を振り切るようにぺダルをこいでいた。
北風号の冒険
この恐怖のどん底のなかで、そのときハンスは突然、この村につたわる歌を思い出すんだ。それは何世紀もの昔のことだよ。この島の漁師たちがものすごい嵐にまきこまれたときの話なんだ。悪魔そのものの濃柑のウルトラマリンディープが叩きつけてきて、もうだれもが海の藻屑となって消えるにちがいないって思ったらしい。そのときだれともなく歌を歌いはじめたんだ。恐怖を迫い払うように、のどが破れるばかりの大声で、歌を歌ったんだ。するとだよ、嵐のうなりの底から、女の声が聞こえてくるじゃないか。その声はだんだん大きくなって、彼らの歌にあわせるように歌うんだ。美しい声で、まるで天使のような声で、漁師たちががなりたてる歌にあわせて歌ってくるんだ。漁師たちはそのとき思ったそうだ。ああ、おれたちはとうとうあの世に召されていくんだってね。あの天使の歌声は、おれたちをあの世に引き連れていく声なんだってね。そう思いながらも、その女と歌っていると、あたりがだんだん明るくなり、波のうねりもおだやかになり、いつしか風もエメラルドグリーンになっていった。七人の漁師たちはその歌で救われたのさ。その歌を歌うことで、嵐の海を乗り切ったんだな。その歌がそのときハンスにひらめいたのさ。ハンスももちろんその歌を知っていた。小さい頃からおじいちゃんにいやというほど聞かされて育ってきたからな。ハンスもまた伝説の漁師たちのように、恐怖を追い払うように大声で歌いはじめたのさ。
風は気まぐれ、おいらの船は風まかせ
あんたが暴れた海は、
おいらの女房よりたち悪い
ああ、退散だ、退散だ
ハンスは恐怖を追い払うように大声で歌ったんだ。何度も何度も、声がかれるばかりになあ。するとだよ、あんた。すると、大波のむこうから、ものすごい風のうなりの奥から、歌が聞こえてきたんだ。それは伝説の話にあった女の声ではなく、何十人何百人もの人間が合唱するのが。風は気まぐれ、おいらの船は風まかせって歌うだろう、すると風のなかから、波のむこうから、何十人何百人もの合唱がかえってくるんだ。あんたが暴れた海は、おいらの女房よりたち悪いって歌うと、そっくりそのままの歌が何十人何百人もの合唱となってな。わしはものすごく元気になってその歌を歌いつづけたんだ。
風は気まぐれ、おいらの船は風まかせ
あんたが暴れた海は、
おいらの女房よりたち悪い
ああ、退散だ、退散だ
そしたらだ、そしたらだよ。起こったんだ、とんでもねえことが起こったんだ。海は依然として荒れ狂ってくる。風もさらに激しくなった。もうヨットはきりきりと悲鳴を上げている。万力になれとばかりに握りしめている舵は、ハンスをはじき飛ばさんばかりだ。しかし、そのとき、ヨットがふわりと浮いたんだ。巨大な波にもちあげられたんだ。ああ、もう終りだ。次にどっと海の上に叩きつけられる。ハンスの人生も終りだと思ったものだ。しかしなんということだ。ヨットは叩きつけられるどころか、ぐんぐんと空に舞い上がりはじめたじゃないか。空を飛んでいるんだ。ヨットが空を飛んでいるんだ。一杯に張った帆は、風をとらえぐんぐんと空に舞い上がっていくんだ。ハンスは何度も思ったさ。これが死ぬということか。人間はこうして天国にのぼっていくのかって。しかしこれは夢ではない。天国にのぼっているのでもない。たしかにハンスのヨットは空を飛んでいるんだ。海面がどんどん離れていく。さかまく波が、うねる波がだんだん遠くなっていく。ヨットは風をうけてどんどん高度をあげていくのだ。雲が走っている。その雲のなかにヨットは突っ込んでいく。一瞬あたりが真っ白になった。そこを突き抜けたとき、真っ青な空が見えたんだ。下をみると大海原だ。なんとヨットは空を走っているんだ。
青い海、青い島
父と私の二人だけの食事。いままでそれはもう賑やかな食事風景だったので、このはげしい落差は最初のうちはとても寂しかった。でもいまではこういう落ち着いた食事もいいものだと思うのだ。父はちょっと静かな人でいつも新聞を開いている。父が無口なぶん、私がおしゃべりだったから、なかなかいいバランスがたもたれているのかもしれなかった。
私は父になんでも話す。もう話しだしたらちょっと止まらないばかりなのだ。そんな私の話を父はビールをすすりながら開いた新聞の向こうで聞いている。
「ねえ、お父さん、今日ね、理科の先生があの人の話をしたよ」
「あの人って」
と父は広げた新聞の向こう側から言った。
「芦沢奈津子さんの」
「ふうむ、それで、どんな話をしたんだ」
「すごくほめるのよ、あの人は熱帯雨林を守った人だとか、破壊されていく自然を今でも第一線で守っている人だとか、鈴木先生はすごくその人のことをほめるけど、私はちょっと違うんじゃないって思ったわけ」
「どう違うんだい」
「つまり芹沢さんは、セブ島とかいう所にいくために家庭を捨てたわけでしょう、鈴木先生は捨てたと言ったよ、愛する人を捨て、生まれたばかりの子供を捨てたって、その捨てたという言い方にもすごくひっかかったけど、一番ひっかかるのはその人の生き方なのよ、その人がセブ島にいって、消えていく熱帯雨林を守るというならば、どうして結婚なんかしたわけ、どうして子供なんかつくったわけ、家庭を捨てていくならもともと結婚なんかしなければよかったでしょう、生物学者として地球を救いたかったら、結婚なんかしなければよかったのよ、だけどその人は結婚してしまった、そしたらその人が一番忠誠を誓わなければならないのは結婚した人にでしょう、二人の間に生まれた子供にでしょう、そうじゃない、お父さん、一つの家庭を守れない人にどうして地球が守れるわけ、私はそう思ってしまうのよ」
私のちょっと熱い口調に、父は新聞をおき、びっくりしたように私をみつめていた。そんな父に私は言った。
「お父さんは、このことをどう思うわけ?」
父はちょっと呆然としたような視線を宙にはわせていたが、やがてなにかを決心するかのようにばさりと新聞をたたむと、ちょっと待ってくれと言って立ち上がり、食堂から出ていってしまった。なかなか戻ってこないので、どうしたのだろうと思っていると、父はミカンのダンボール箱を両手にかかえて戻ってきたのだ。そしてその箱をテーブルにおくと、私に言った。
「これはお母さんからきた手紙なんだ、お母さんの手紙がこのなかに全部入っている、こんなものをいままで大事にとっておいたのは、もちろんぼくのためである、過去にこだわるのはよくないことだけど、円(まどか)が生まれたときのぼくたちの歴史がいっぱいこのなかに詰まっているからね、この歴史はたしかにぼくたちのものだったんだ」
ふだん父は、私の前でぼくなどという言い方はしなかった。なんだかその言い方がとても新鮮だった。それはきっと青春の思い出が、父を青年のように若くしたからかもしれなかった。父は言った。
「しかしお母さんの手紙を、こうして大事にとってきたのはもう一つの理由があった、それはいつかそのときがきたら、円にこの手紙を読んでもらおうと思っていたのだ、どうやらそのときがきたようだね、お母さんはいっぱいお父さんに手紙を書いてくれた、これを全部読むのは大変だけど、でもきちんと読んでくれるね」
南の海の島 高尾五郎
南の海の島
豆腐屋
靴屋
私が友保坂嘉内、私を棄てるな
南の海の島
その遠く隔てた距離のために、卒業してからたしか二年目か三年目に一度東京で会ったきりだった。しかし年賀状とか、あるいはちょっとした近況のやりとりは続けていたのだ。ところが三年前、ひどく謎めいた、なにかただならぬ手紙をよこしたあと、ぷつりと音信を断ってしまった。それは私とだけではなく、彼と親しくしていた共通の友人にたずねても同様な返事がかえってきたから、私たちの前から姿を消さなければならない、なにかただならぬ事件といったものが、彼の身の上に起こったのかもしれないと思ったりした。
実際、その手紙は謎めいていた。分校をつぶしたとか、子供を殺してしまったとか、一家を虐殺したとか、村をつぶしたとか、ぼくは裏切り者だとか、この罪を永遠に許さないといった言葉が書かれていたのだ。しかしそれ以上のことはなにも書かれていない。いったい村をつぶしたとはどういうことなのか、子供を殺したということはどういうことなのか、一家を虐殺したとはどういうことなのか、私は二度ならず三度まで手紙をしたためたのだが彼からの返事はなかった。
そんな彼のことがずいぶん気になっていて、幾度か彼の住む島を訪ねようとしたが、飛行機をつかっても最低一週間、もし海が荒れて船が欠航でもしようものなら二週間近くの休暇を覚悟しておかねばならない。そんな長い休暇をとるには一大決心を要することで、なかなかふんぎりがつかずにずるずると時を重ねていたのだ。
ところが今年の賀状の束のなかに、彼の賀状もまじっていた。それを手にしたとき、どんな事態に見舞われたのかわからぬが、彼は再び立ち上がったと思った。彼は挫折することや絶望することを禁じられた男だった。挫折や絶望のなかにではなく、理想のなかに倒れるためにこの世に放たれた男だったのだ。
彼の賀状ほどうれしいものはなかった。というのはその年が終わろうとする十二月の半ばに、四年という長かったのか短かったのかわからぬ結婚生活にピリオドを打って、私は離婚したのだ。私と彼女を引裂いた亀裂はもうずいぶん前から走っていて、そのピリオドはいわば私たちの解放であったのだが、離婚という現実にいざ直面してみると、やはり十分すぎるほど打ちのめされた。そんなときはるか遠方より思いがけない、しかし私が一番会いたかった男からの便りは、光のない洞を徘徊しているような私には、なにか一つの救いのような意味をもっていたのだ。

ちょろちょろと燃える火のなかに木端を投げこんだ。夜はからりと冷えこむのだ。新しい薪がぱっと燃え上がった。そのときひょいと倫子が私たちの前に現れた。私はちょっとぎょっとなって身構えたが、それは樫山も同じだったようだ。彼女は角材の切れ端を拾ってきて、私たちのかたわらに置くと、そこに座りこんだ。
「ねえ、樫山さん。訊きたいことがあるのよ。村上さんの話、聞いたかしら?」
「村上さんの話って?」
と樫山はおうむがえしにたずねた。
「あの高台の土地を売ったという話、どうやら本当らしいわよ」
「そういう話があるというだけだと思うけどな」
「だから樫山さんは甘いって言うのよ。このところ毎月のようにお年寄りたちが鹿児島の病院に出かけていくけど、おかしいと思わないの。本当は病院なんかにいくんじゃないのよ。あの人たちの息子や娘がそこで待っているからなのよ。各地から家族を集めて、その席にお金を積みあげて、あっという間に印鑑を押させてしまうのよ。敵は馬鹿じゃないのよ。敵のやり方は私たちが考えているよりずっと巧妙で狡滑なのよ」
「そのこともちらりと聞いたよ」
「だったらどうして手を打たないわけ。どんどん切り崩されていくのよ」
「しかしそれは結局、島の人たちの問題だと思うんだ」
「そんな呑気に構えてていいわけ」
「だからといって、どんな手を打てばいいんだろう。いまはぼくたちにはなにもすることができないと思うんだ」
「あなたはもう樫山教になっているじゃない。あなたはもうこの島の宗教なのよ。みんなあなたの信者じゃないの。あなたがいうようにみんな動くじゃない。だからいまのうちなのよ。いま手を打たなければ手遅れになるわよ。もうお金が飛び交っているんだから。あの土地はいくらで売ったとか、あそこはいくらで売るとか。この島の人たちは、もうそんな話しかしなくなってしまったのよ」
「君はまったくおかしいよ」
「そう、おかしいの。それはあなたがおかしいからよ。私にはあなたがわかるの。あなただってちゃんとわかっているくせに。企業に土地を売ったらどうなると思うの。どんなことされると思うの。あなたがしようとしていることとは別のことをはじめるんだわ」
そして倫子は私を指さした。とうとうその矛先が私にむけられるのかと思ったが、そうではなかった。「この人と同じ船で帰ってきた工藤のおじいさん。帰ってきてからずいぶん様子がおかしいらしいのよ。急によそよそしくなって、寄合いにもでなくなって、なんだか島を出るなんていっているらしいのよ。このあたり一帯の土地はあの人のものでしょう。あの人が土地を売ったら、私たち全員ここからでていかなければならなくなるわね」
樫山はなんだか打ちのめされた人のようにうつむいてしまった。そんな彼をさらに苦しめるように、「でも誤解しないで欲しいわ。私はあなたに反対するわよ。あなたは幻なんだから。この島が分裂したって、私たちが解散したって、この島がお金でよごれたって、私は反対するわ」
彼女は立ち上った。そして火を背にしてよろよろとよろけながら、踊るようにあざ笑うようにこう言ったのだ。
「あなたは幻なの。あなたは幻に向かって歩いている幻の人なのよ。あなたを追いかける人は、みんな谷底に転落するの。あなたはみんなを谷底に転落させる気なんだわ」
それは愛の言葉なのだろうか。もしそうだとしたら、なんというはげしい言葉なのだろうか。人をひと突きにするほどのはげしさだ。そのはげしい言葉は私の心にも突き刺さってきた。

毎朝、馬や牛の世話をしたあと、わずかな時間を学校に寄って、オルガンを奏でることを日課としていたのだ。それは彼にとって祈りの時間なのだろう。無心にしかしなにか一心にオルガンを弾いている彼の姿をみて、彼が十五のときにイエスに出会ったという話をもう私はげらげらと笑わないだろう。その奇妙な話を次なる事実によって認めなければならないのだ。イエスと出会ったことは幻ではなかったことを証明するために彼は生きているのだという事実によって。
かつて彼は聖書を剣のように構えた戦闘的なキリスト教徒だった。百人もの人間を巻き込んでちょっとした運動を起こしたとき、たしかにもう一つの太陽として輝やこうとしたのである。青春のエネルギーというのはいつも外にむかってほとばしる。だからこそ自我をギラギラとひからせなければならなかったし、聖書だってあんな乱暴な読み方をしなければならなかったのだ。あふれほとばしる青春の情熱がめざすものは愛と理想の王国である。人間は強くなければならない。強ければ強いほど理想の国は近いのである。
しかしいま彼のオルガンは外にではなく、彼の内部にむかって奏でられているように思えた。それはどこにでもころがっている挫折とか絶望がそうさせるのではない。神之島での敗北や、この島でのさまざまな軋轢や障害は彼を強くしたのである。彼のような人間には、失敗とか敗北はそういう現れ方をするように思えた。久しぶりにみる彼は、大学時代のように自信をみなぎらせている男ではなくなっていた。語る言葉はどことなく力がなく、その物腰もまたどことなく弱々しかった。倫子のはげしい愛の告白にうろたえる彼や、青年会での始終開き役にまわっている姿を目のあたりにすると、彼のなかでなにかが変わってしまったように見えたものだ。事実、彼は自信を失っていたし、彼の心は揺れていた。しかし私はその弱々しさのなかに、その揺れる心のなかに土のなかに深くはっていく根をみるのだ。土のなかに深く根がおりていれば、風に吹かれる草のように揺れればいいのである。多くの人間を巻き込むことも、はげしく動きまわることも、自己をいたずらにひからせることも必要ないのだ。
彼の聖書もまたそのオルガンのように彼の内部にむかっているように思えた。結局、人間にはたった一つのことだって実現することができないと彼は言った。だとしたらいったい彼のような人間は、どこにむかって歩いていけばいいのか。どこまでいっても不毛の荒野ではないか。だからこそ神の手が必要なのかもしれなかった。失敗という種を神の手にゆだねるための、幻というかたまりをもった自我を救いだすための神の言葉が。
南海丸は予定通りやってきた。あの若者たちも、小学生や中学生たちも、そして島の人たちも私を見送りにきた。はしけに乗る前に私はもう一度樫山に声をかけた。
「今度は、君がインドにくる番だな」
「そうだな。きっといくよ」
「おれもあの大陸でなにかをはじめていくよ」
「うん、そうだね、まったく」
樫山の目に涙がにじんでいた。そんな彼を見る私もまた涙腺がうるうるとなった。
南海丸は島に向かって幾度か汽笛を鳴らすと、ゆっくりと島を離れはじめた。突堤を子どもたちが船を追いかけるように走っていた。樫山もまた手を大きく振りながら走っている。突堤の先端にたどり着いた彼らは、ちぎれんばかりに手を振り、声を限りに叫んでいた。私もまた彼らの姿が見えなくなるまで手を振った。
この日、黒い雲が島を重く覆っていた。なにやらその景色は樫山たちの前方に横たわっている重々しい苦悩のようにみえた。そしてそれはまた私の前方に横たわる雲であるかもしれなかった。

豆腐屋
野口辰雄は四時に目が覚める。その時間は正確であって、柱にかかっている振り子時計が四時を告げる直前に、布団の上で半身を起こしているのだ。するとなんだか彼の起床にうながされてしかたなく振り子時計が、ボン、ボン、ボン、ボンと鐘を叩くかのようだった。商店会の寄り合いや、同業者の会合などがあって床に就くのが深夜になっても、彼が目覚めるのは四時だった。一日として四時の鐘を叩く振り子時計に遅れをとったことはなかった。五十年続けてきたその習慣が、彼の肉体の中に目覚まし時計のような正確な時刻を刻みこんだのだろう。
床から起き上がると、彼らが土間と呼んでいる作業場におりる。十畳ほどの空間に、水槽やコンロや炊飯竈が行儀よく並んでいる。四十年続けた作業である。手順は毎日きまっている。その作業を辰雄が行い、則子は彼の仕事を手伝う。野口豆腐屋の豆腐はそういう体制で出来るものだと辰雄は思っていた。しかし七年前、辰雄が交通事故にあった。豆腐や揚げ物を荷台のボックスに入れて行商するのだが、その行商中に車と接触してしまったのだ。交差する裏通りでの軽い接触事故だったが、しかしどっと道路に投げだされた辰雄は右腕を骨折してしまった。しかし野口豆腐屋は一日として休むことはなかった。則子がたった一人で豆腐を作りつづけたのだ。だれよりも辰雄はそのことに驚いたものだ。
七時には店のシャッターを上げて、ポリエチレンのボトルに入れた温かい豆乳を並べる。この暖かい豆乳を求めて、足を運んでくる客がいるのだ。近隣に住んでいる何十年来のお得意さんたちだった。このお得意さんたちも歳をとり、六十、七十になってしまった。毎朝、シャッターを上げると同時にやってくる吉江ばあさんはもう八十五歳である。キャリァカーで体を支え、弱った足を引きずるようにやってくる。しかし声は元気だ。そしていつも陽気だった。
「はあい、ババアは元気だよ」
「そうよ、おばあさん、いつだって元気印よ」と則子が応じる。
「あんたのところの豆乳に、元気だよって書いておきなさいよ」
「ついでに、くたばらねえ豆乳だよってか」
と奥から辰雄が茶々を入れた。
「そうよ、八十五までくたばらないってさ。ここにちゃんとした見本がいるんだから。あんたね、それって誇大広告じゃないよ」
「広告にするんだったら、九十ってところだな。九十歳までくたばらない豆乳だってさ。だから、あと五年はがんばってもらわなきゃあ」
「あんた、あと五年であたしをくたばらせるわけかい、冗談じゃないよ、あたしは、百歳までくたばらないよ、百歳まで生きてやるんだからね、あんたのところもがんばって、店をたたむなんて考えないでよ、なんでも、ニューヨークじゃ豆腐がはやってんだって、テレビでやってたけど、ダイエットすると動物性たんぱく質がすごく不足するから、ダイエットって野菜とかそんなものを食べて、肉を取らないだろう、肉を食べなくなると、動物性タンパツク質がへって、それが体にいろいろと悪影響がでるから、それで豆腐を食べるらしいのよ、それがさ、あんた、あっちの人のやることは大胆というか、気持ち悪いっていうかさ、豆腐にシュロップかけたり、ジャムをぬって食べるらしいんだよ、それがセレブなんだって、そうやって食べるのが流行ってんだって、だからさ、あんた、アメリカで流行ってることは、すぐに日本でも流行るからさ、日本のギャルたちもダイエットやるからって、豆腐を買いにくるようになるのよ」
芳江ばあさんは物知りだ。一日中テレビと対面しているためか、セレブだとかギャルだとかいった現代語もちゃんとその会話に登場してくる。毎朝、芳江ばあさんは豆腐屋にやってきて、そんな会話を野口夫婦とすることが日課となっていた。
「あ、雪が降ってきたよ」
「あら、ほんとう。寒いわけね。おばあさん、今日は暖かくして、風邪ひかないようにね」
「はいよ、まあだだよだからね。あんたたちだって、まあだだよなんだからね」
辰雄も七十を三つ越え、則子もまた七十の大台にのってしまった。彼らも十分に歳をとったのだ。彼らもまた決断しなければならない時期にきている。四十年続いた店をたたむという決断を。辰雄はこのところしきりにそのことを考える。いろいろと複雑な問題がこんがらがってからみつき、そのことを考えないわけにはいかないのだ。その問題は辰雄と則子だけで交わされる内輪の話だったが、しかし何十年来のお得意さんたちには二人の胸のうちをお見通しだった。芳江ばあさんは野口豆腐屋の行く末を本気で心配しているのだった。
靴屋
そんな彼にやがて縁談が持ち込まれるのだ。商店街に医院を構える歯医者の夫人からで、もうその縁談相手の女性と会うセッティングまでしていた。そしてこの商店街のボス的存在である野田家具店の野田夫妻から二件も。二人の子供夫婦と一族経営する野田家具店はこの商店街でもっとも大きな店舗で、この店舗を経営する野田夫妻からは、まるで彼らの親族にされたかのように篤史は愛されていた。だから彼らが持ち込む縁談は真剣で、とりわけ二件目などはその話を結実させようと熱く迫ってきた。しかし篤史はその二件ともまったく心を動かさなった。即刻その場で断るのだ。それはまったく取りつく島がないといった反応だった。
その野田夫妻から三件目の縁談が持ち込まれるのだが、それはそれまでの話とちがって、彼の存在を揺さぶるひとつの大きな事件だった。その発端は土曜日の昼下がりだった。一人の女性が彼の店を訪れた。その女はドアを押して店舗に入ってくるなり、
「ああ、ビバルディ!」
工房に優雅に流れている旋律にその女性は感嘆の声を上げた。
「ビバルディがこうして一日流れているんですか」
「ええ、まあ、そうです」
「ああ、なんて幸福なお仕事なんでしょう、ビバルディを聞きながらお仕事ができるなんて、前からこのお店、気になっていたんですけど、とうとうきました、ああ、ビバルディですよね」
そして工房内を見渡して「たくさん道具とか機具があるんですね、ちょっと拝見してもいいですか」といって、手にしてきた紙袋をテーブルに置くと、カウンターの横から工房内に入ってきた。そして一点一点の工具や機具の説明を求めるのだった。
「三台のミシンは、それぞれ違っているんですか」
「ええ、それは作業によってそれぞれ別の用途があるんです」
「これはなんていう機械なんですか」
「フィニッシャーと呼んでいます。皮革を切ったり、削ったり、磨いたり、そぎ落としたりともっとも頻繁に使う機具です」
「これはなんですか、ずいぶん変なものがありますね」
「これはドライヤーです。強力に熱風で皮のたるみとしわを伸ばしたりするんです」
「ああ、たくさんのナイフ、ナイフが壮観ですね」
「ぼくらは包丁ってよんでいます。皮きり包丁ですね。毎日の作業はいつも包丁研ぎで終わるんですよ、ときには二時間とか三時間、砥石でごしごし研いでいます」
「複雑な工程がいっぱいあるんですね、そのいくつもの工程を通って、棚に展示されている紳士靴が誕生するんですよね、ちょっとお靴を見せていただけますか」
篤史はその棚から靴を取り手渡すと、その人は掌で爪先から踵まで愛撫するかのように撫で、靴の中に手を差し込んだ。そしてその靴の中からなにか聞こえるのてばないかとその靴を耳に当てたのだ。
「ああ、ビバルディ! この靴のなかからビバルディが聞こえてきますよ」
こんな奇妙なことを言われたのははじめてことで、篤史は意味不明の感嘆の声を上げていた。
「だって一日中、ビバルディの音楽が流れているんでしょう、この靴のなかにもビバルディが染み込んでいるはずですよ」
こうして狭い工房内を一巡して、接客のために置いてあるテーブルのところに戻ってくると、その女性はテーブルに置いた紙袋から二足の靴を取り出した。高品質のハイヒールとローヒールだった。ローヒールはイタリア製だった。篤史は手にしただけで修理箇所がわかり、瞬時にその作業の工程を組み立てる。ハイヒールの方はヒールの交換だった、彼らがソールをよぶ靴底に張り替えが必要だった。作業の工程表に目を落としながら、四日ほどかかりますがと篤史が伝えると、平日は残業があってこれないので一週間後の同じ土曜日に取りにくるというのがその人の返事だった。それでビジネスは成立した。するとその人はまた奇妙なことを言った。
「ここでしばらくビバルディを聞いていてかまいませんか」
「ああ、どうぞ」
「質問ばかりしてごめんなさい、おとなしくしていますから、どうぞお仕事をなさって下さい」
彼は作業にとりかかった。しかしその女性のことが気になる。テーブルの奥にソファーが置いてある。彼女はその左の端に深く座り、やや顔をあげて頭を壁面にあずけ目を閉じている。なにか流麗に流れるビバルディに、その全身をゆだねているかのようだった。その女性は美人というわけではない、しかし気品があり深い知性をその相貌にたたえている。
生涯に一千近く作曲されたというビバルディサウンドがつぎつぎに流れていく。ヴァイオリンとビオラとチェロの弦が奏でる宇宙。ビバルディはこの三つの弦を多様多彩に織りなして革命を起こしたのだ。弦が飛翔する。弦が風を奏でている。木の葉が舞い散っていく。渓流がその葉をさらっていく。麦畑はもう刈り取られた。落穂拾いをする農婦たち。間もなく冬将軍がやってくる。イタリアで紡ぎだされた中世のサウンドが、品川の小さな工房のなかに、ときには切なく、ときには悲しく、ときには優雅に、ときには暗く、ときには悪魔のように流れていく。
そのとき彼は見た。その人の閉じた目から涙が頬にすべり落ちていくのを。その人は掌でその涙を拭っている。しかしまた新しい涙が頬に流れてくる。その涙をまた指先で拭っている。篤史はその一瞬その女性に恋に落ちた。一瞬で恋に落ちたことなどはじめてのことだった。
最後の授業 高尾五郎
最後の授業
吉崎美里と絶交する手紙
大雪の日のゼームス坂
二発の弾丸
最後の授業
これは北アルプスの麓に広がる安曇平という地のある町でおこった出来事です。すでにみなさんはその町の名前を知っていますね。あれだけ騒がれた事件ですから。ですからその町の人々にはとてもつらいことですから、その町の名をA町としておくことにします。その町の名をつけた中学校もまたやはりA中学校としておきますが、この中学校は信州教育と尊敬をこめてよばれる数々の実践活動を生みだしていった古い輝かしい歴史をもった学校でした。この中学校に通う瀧沢隆君という中学生が、自宅の納屋で首を吊って自殺するという痛ましい事牛がおこったのでしたね。
残念なことに、まるで流行のように、子供たちがあちこちで自殺しています。子供たちの自殺があまりにも頻繁に起こるので、いまでは新聞記事にもなりません。しかしこの隆君の自殺事件はちがっていました。連日にわたって新聞もテレビも週刊誌も、なにかヒステリ一をおこしたと思われるばかりの騒ぎ方でした。どうしてこんな騒動に発展していったかといいますと、その事件を取材するためにつめかけた地元記者たちが、その学校の校長先生を取り囲んで、
「隆君は遺書を残していますが、この遺書を先生はどう思われますか?」
とたずねたのです。その学校の校長先生は篠田政雄といいましたが、そのときその篠田校長は、なにか吐き捨てるように、
「こんな貧しい遺書で死ぬなんてあわれです」
といったのです。驚いた記者たちは、
「貧しいですか?」
「貧しくて幼稚な遺書です」
「幼稚なんですか?」
「これが幼椎でなくてなんなのでしょうか。こんな幼稚な遺書で死んでいく子供はあわれにつきます」
校長先生はさらに取材を続けようとつめよる記者たちをかきわけて、逃げ込むように校門に消えていったのですが、そのときその一部始終をテレビ局のクルーが音声とともにしっかりと録画していたのです。その映像とその会話が、各テレビ局に配信され、日本中にそのシーンが、それはもう繰り返し繰り返し放映されていったのでした。
翌日の新聞も一斉にこの事を報じました。社会面を二面もつぶし、さらに社説までにとりあげて、校長先生の言動をはげしく非難するのでした。凄まじいのはテレビでした。昼のワイドショーで、夕刻のニュースショーで、さらには深夜のニュース番組で、いずれもトップニュースとしてこの事件を報じるのでした。

篠田校長にたいする取材はすさまじいばかりでした。学校はもちろん自宅まで大勢のマスコミの取材者たちが、二十四時間張り込んでその姿を捕らえようとするのでした。
隆君の葬儀が三日後に行われましたが、そのときも大変な騒動でした。篠田校長が車から降りてくると、何十人もの取材者がどっと襲いかかるように校長先生を取り囲み、マイクをつきたて、それぞれが質問をぶつけるのでした。なにかそれは獲物に襲いかかるハイエナといった光景でした。ようやくその取材者たちの群れから抜け出して祭場に入っていくと、一斉に険しい視線が校長先生に向けられるのでした。
校長先生が焼香する番がきました。そのとき親族のなかから突然猛々しい声が飛んでくるのです。隆君の叔父さんでした。
「お前なんか、焼香する資格なんてない!」
そして激昂したその叔父さんは、校長先生のところに飛んできて、校長先生の胸倉をぐいとつかむと、「お前なんか帰れ、ここにくる資格はない!」
この興奮した叔父さんを、隆君のお父さんやお母さんが、必死におしとどめて席に引き戻しました。
校長先生は焼香台の前に立つと、隆君の遺影を見つめました。美しい笑顔です。少年の輝きがこぼれるばかりの笑顔です。校長先生は両手をあわせて、ずいぶん長く黙祷していました。そして焼香をおえると、遺族の列にむかって頭をさげ、退場しようと歩み出したとき、今度は隆君のお母さんが立ち上がって校長先生を呼びとめ、校長先生の前につつと歩みよるとこういいました。
「校長先生。先生はいま隆にどんな言葉をかけて下さったのですか」
「‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥」
「まさか、幼椎な貧しい遺書を書いて死んで、あわれだとおっしゃったのではありませんね」
「‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥」
「隆は校長先生をとても尊敬していました。校長先生はちょっとちがう、校長先生はちょっとすごいって。なにがちがうのか、なにがすごいのかわからないいい方ですが、でも隆にとってそのいい方は、最高のことを表現するいい方だったのです。隆はそんなにも校長先生を尊敬していたのです。その尊敬していた校長先生に、貧しい幼稚な遺書を書いたものだ、あわれな死に方をしたものだといわれて、どんなに悲しい思いをしているでしょうか。若くして無念のなかで死ぬと、その魂はいつまでも成仏できずあたりをさまよっていると聞きます。隆の魂はいまこのあたりにいるのです。隆の魂はまだ生きています。立派な遺書だった、美しい遺書だったなんていってもらうつもりありません。でもあの子はあの子なりに力いっぱい書いたのです。ですから校長先生、力いっぱい書いた遺書なんだね、力いっぱい生きたんだねって、隆の前でいって下さいませんか」
しかし校長先生はただ軽くお母さんの前に頭をたれると立ち去りました。この様子を固唾をのんで見守っていた参列者から、この非情な校長先生に怒りの声が投げつけられました。
「学校が子供を殺したんだ!」
さらにはこんな怒号も飛びました。
「お前たちは殺人者なんだ!」
そして参列者の怒りが頂点に達したかのように、参列者の一人が折り畳みの椅子を校長先生に向かって投げつけるのでした。
そのシーンを沢山のテレビ局のカメラが、さまざまな角度から一部始終とらえていました。そしてまた一斉にそのシーンがありとあらゆるチャンネルで流されるのでした。篠田校長にたいする非難はすさまじいばかりでした。なにか日本列島が一大ヒステリーをおこしたかのような騒動になりました。マスコミの攻撃は教育委員会や文部科学省に校長を処分せよと迫り、さらにはこの事件はいじめによる殺人事件だから、警察はただちに捜査を開始せよという論調になっていくのでした。

篠田校長には二人の子供がいました。長女の庸子さんはいま松本の小学校の教師をしていました。次女の加奈子さんは東京でした。大学の三年生で、彼女もまた先生になろうとしていました。この一家は先生一家なのです。
庸子さんも大学は東京でしたが、卒業するとやっぱり信州が好きでしたからこの地に戻ってきたのです。よほど教育採用試験の成績がよかったのか、あるいは屈指の名校長といわれる父親の七光のせいか、彼女が最初に赴任したのは松本市内の小学校でした。
まだ先生になって三年目なのに、子供たちから愛されるとても評判の高い先生でした。それはちょうど三時間目の算数の授業をしているときでした。教頭先生がなにやらあわてた様子で教室の引き戸を開けて、庸子先生を廊下に呼び出すと、
「篠田先生、なんだかお宅で、大変なことがあったらしい。いま電話が入っているんだが、ちょっと出で下さい」
と耳打ちしました。授業を教頭先生にまかせて、胸騒ぎする庸子さんは小走りに職員室に飛んでいきました。受話器をとると、
「篠田庸子さん?」
とたずねてきました。女性でした。
「はい。そうですが」
「実はお父さんが自殺なさってね。いまさきほど、お亡くなりになりましてね……」
「えっ、自殺ですか!」
「そうです。自殺です。鴨居に首を吊ってね」
頭のなかはもう真っ白になり、力という力が抜け落ちて言葉がでません。すると突然、、ははははと野卑な笑い声が、庸子さんの耳に弾き飛んできました。
「驚いたでしょう。嘘ですよ、嘘。だけどさ、あんたのお父さんは、そうしてもいいんじゃないんですか。校長先生やってんでしょう。校長先生ってそうやって責任をとるもんでしょう。子供が一人死んだんですよ。隆君はいってみれば、あんたのお父さんが殺したようなもんじゃないの」
これほど悪質ではありませんでしたが、実はこういういやがらせの電話はもう自宅に毎日のようにかかってくるのでした。朝、昼、夜となく。そればかりではありません。深夜にだれかが石を投げこんで、二階の窓ガラスが粉砕されました。闇からの攻撃は篠田校長だけでなく、家族までに向けられているのです。
庸子さんはこの不快な電話を切ると、青ざめたままクラスに戻ってきました。授業の続きをはじめましたが、クラスがとてもざわついています。もう勉強する雰囲気でありません。でも庸子先生はなにかいやなことをぬぐい去るためにも、むきになって授業を組み立てようとしました。しかし子供たちはなかなかな集中しません。あちこちでざわざわと私語が起こります。とうとう庸子先生は、声をあらげました。「どうしてなの。どうして先生のいっていることをちゃんと聞いてくれないの。最近のあなたたちはおかしいわよ」
最近、本当にクラスの様子がおかしいのです。それまで築かれてきた友情と信頼にあふれたクラスが、なにかどんどん壊れていくように思うのでした。そのことを庸子先生は子供たちに投げかけました。すると一人の子供が、
「先生はいつ校長先生の話をしてくれるんですか。いつかきちんと話してくれるといったでしょう」
その発言は子供たちの胸にたまっていたものに火をつけました。教室はもう騒然となりました。
「うちのお母さんがいってたけど、どうしてあやまらないのかって。校長先生はあやまるべきだって」「うちのお母さんも子供が一生懸命に書いた遺書を、幼稚な遺書だなて馬鹿にする校長は許せないっていってたけど」
「隆君のお母さんがさ、涙をながしてさ、隆の遺書をほめてやって下さい、校長先生、お願いです、隆の遺書をほめてやって下さいっていってんの、全然無視してさ」
「そうそう、そのあとバシッと椅子が飛んできてよ」
「あの椅子をぶん投げたオヤジ、面白かったよな。責任をとれ、責任をとれ、校長としての責任をとれって、叫んでさ」
ひょうきん者の聡君という子が立ち上がって、もう何十回となく放映されたそのシーンを演じると、子供たちはどっと笑いました。
いま庸子先生のクラスの子供たちの最大の関心はそのことにあるのでした。あの事件が起こってからクラスが急激に落ち着き失い、なにか先生と子供たちの信頼の関係がゆらいでいったことは、庸子先生はとっくに気づいていました。だからいつかこの事件のことを話さねばならないと思っていたのです。しかし子供たちにいったいどう話せばいいのでしょうか。
庸子先生はお父さんがわかっていました。お父さんがなぜかあのような発言をしたのかもわかっていました。ですから子供たちにそのことを説明しようと思えばできるのです。しかしいま子供たちの関心はそんなことでなく、テレビから受けた情報による、いってみればテレビ的な関心でした。隆君をいじめて自殺させた五人組はどうして逮捕されないのかとか、隆君の遺書を貧しく幼稚だといった校長先生はいつクビになるのかとか、クビになったとき退職金はもらえるのかとか。テレビが植えつけたそんな関心には一言もふれたくないと庸子先生は思っているのです。
有明の自宅まで、幾通りもあるのですが、この日は安曇野の風景をいまなおよく残している山麓線を通りました。ずいぶん遠回りですが、なにか落ち込んでいく気分を吹っ切りたいと思ったのです。
有明の町に入り、赤松の立ち並ぶ一角に篠田家がありましたが、庸子先生はあたりを警戒しながら車を走らせます。というのは、いまでもマスコミの取材者が飛び出してきて、カメラのフラッシュをたいたり、マイクを突き出してくるからです。一時は大変な騒動でした。何十人ものマスコミの取材者たちが自宅を取り囲んでいたのです。彼らの取材は家族にまでむけられ、庸子先生が学校から自宅に戻ってくると、どっと何十人もの取材者に襲撃されたこともありました。ようやくそんな嵐のような騒動も過ぎ去りましたが、しかしいまでも狼のように潜んでいる取材者がいて、家族の姿をみると襲撃してくるのです。幸いこの日はだれも張り込んではいませんでした。ただいまと玄関に入ると、妹の加奈子が奥からばたばたスリッパの音をたてて飛んできました。

吉崎美里と絶交する手紙
これまで私にとって君は美里だったけど、君と絶交するために吉崎と呼ぶことにする。もう私たちの関係って遠くはなれてしまって、いまさらこんな絶交の手紙を書いたってなんの意味ないことだと思ったりするけど。あと半年もすれば卒業で、吉崎とも永遠の別れだし、それまで私は黙ってたえていればいいことだとも思う。けれども、いま吉崎にこの手紙を書かなければ、私はこの先一歩もすすめない。受験はどんどん迫ってくる。塾にいってもまったく勉強できず、このままではなにか自滅していくばかりで、この手紙を書いて心の整理をつけるというか、自分の気持ちにけりをつけたいと思うのだ。
吉崎とは五年生になって、はじめて一緒のクラスになった。最初は親しく話しかけることもなく、たがいに距離をおいたぎこちない関係だったけれども、でも私にとって吉崎はいつも気になる存在で、だから吉崎の前に出るとどことなく緊張していた。そんな吉崎が私のなかで圧倒的な存在になっていったのは、例のいじめ事件だった。
いじめなんて少しもめずらしいことではなく、それはいつも私たちのまわりに存在する日常のことだけど、そのいじめがひときわ派手に騒がれたのは、木村信長というなにかいじめられる体質そのものをもった個性と、それに木村の家庭にその究極の問題があった。それは吉崎もまたするどく指摘したことだけど。信長はいじめられると何倍も誇張して家族に訴える。すると区議会議員である父親が、学校に怒鳴りこんできて、庄司先生だけでなく、校長先生や教頭先生までつるし上げるみたいに攻撃する。区議会議員だから教育委員会などに顔がきき、そこからも締めつけられるから、心やさしい庄司先生は次第に顔が引きつっていって、この先生は危ないなとみんなに思わせたのだ。そしたらとうとう私たちの予感が的中する日が来てしまった。
その朝、教室に入ってきた庄司先生の顔は青ざめ、なにか心が壊れる寸前だと思わせた。いつも微笑みをうかべているおだやかな顔つきが、その朝は鬼のようになっているのだ。そしてヒステリックに、いきなり怒鳴りだした。あなたたちは、クソガキだわ、何度も何度もいじめはやめなさいって言ってるのに、その約束をすぐ破る、あなたたちは人間性などひとかけらもないクソガキだわ。クソガキ! クソガキ! クソガキ! と叫びながら出席簿で教卓をばしばしとたたいた。いじめ問題に苦しむ庄司先生は、それまで幾度となく私たちを強く叱ったことがあるけど、クソガキなんてののしりの言葉を浴びせたり、出席簿で教卓をばしばしたたくなんて光景ははじめて目にすることだった。
先生、狂ってるよ、とだれかが言った。それで教室に笑い声がおこったが、庄司先生のその朝の突然の乱心といった光景が、なんだか私たちにはちょっとおかしかったのだ。湧きおこった笑いの渦に庄司先生は、さらに混乱し、さらに乱心して、今度は声をたてて泣き出した。あなたたちは人の苦しみがわからないのね、あなたたちはどんなに人が苦しんでいても、小馬鹿にしたように笑って、それでまたいじめるクソガキだわ、クソガキ! クソガキ! クソガキ! とまた三度叫ぶと、もう今日は勉強なんてどうでもいいの、これから自習時間にするから、反省の作文を書きなさい、工藤さん、鳥取君、あとはあなたたちクラス委員の責任よと叫ぶと、教室から飛び出していった。
それから庄司先生はしばしば学校を休むようになった。朝になると体調がおかしくなり、それでも学校にいかなければと家を出るけど、激しい腹痛に襲われてトイレにかけ込んでしまうらしい。なんでもそれは不登校症候群という病気で、これは子供だけにかかる病気だと思っていたけど、この種の病気にかかっている先生は、日本中にあふれているなんてことを私たちははじめて知った。
大雪の日のゼームス坂
この稿を起こすにあたって、私は久しぶりにこの曲を聞いたが、涙がはらはらと落ちて仕方がなかった。私はもちろんドイツ語はわからない。しかしそこでなにが歌われているか諳んじている。ヘルマン・へッセの詩をテキストにしていたシュトラウスは、この最後の曲にアイヒェンドルフの詩を使うのだ。
苦しいときも、うれしいときも
私たちは手に手をとりあって歩いてきた、
さすらいの足を止めて、いま私たちは
のどかな田園がひろがる丘の上でやすらう
私たちの前に、谷々がおちこみ
空はしだいに暮れかかっている
二羽のひばりが、夕もやのなかを
高く、高く、飛翔していく
こっちへおいで、さえずるひばりたちよ
まもなく眠りの時間がやってくる
こんなにさびしい景色のなかで、
私たちははぐれないようにしよう
おお、このひろびろした静かな平和
夕映えが深々と世界を染めていく
歩いてきた旅の疲労が、私たちに重くのしかかる
もしかしたら、これが死なのだろうか
私の妻は意識が混濁したなかで、しきりに右手で何かを訴えるようにしていた。私はその手の動きがわからなかった。意味のわからぬままその手を握ると、彼女は深い安息につつまれるようにして逝ったのだ。あの謎はこういうことだったのだろうか。はぐれないように私の手を求めていたのだろうか。彼女がはぐれるのではない。彼女はいまわのきわのなかにありながら、なお私を案じていたのだ。彼女はまさしく私の分身のような存在であった。彼女に出会っていなければ、おそらく私は私とならなかっただろう。それと同じように、私は彼女にとってよい夫であったのだろうか。
ヘッセの詩にも生の輝きに織り成すように、落ち葉に、夕闇に、夏の終りに、夜に、眠りに死の影が濃厚に宿っている。その生と死のおののきを音楽がいっそう深く染め上げていく。シュトラウスは言葉と音楽を魔術的色彩のなかで融合させたのだ。「英雄の生涯」や「ツアラストラはかく語りき」などの交響詩、「薔薇の騎士」や「サロメ」などのオペラ群を創造してきたこの作曲家の創造力が最後に到達した、まるで沈みいく太陽が西の空をこの世のものとは思えないばかりの荘厳さで染めていく夕映えの揮きといった、まことに見事としか言い様がない作品なのだ。
私はこの曲に出会ってから長いこと心にひめていたことがあった。シュトラウスにならうわけではないが、私もまた八十という年を迎えたとき、最後の四つの小説というものを手がけてみようと思っていたのだ。作家たちはある年齢に達すると自分の人生といったものがひどく気になるのか、しきりに自伝めいたものを書きはじめていく。しかし私はそのことをきっぱりと拒んできた。作家の人生などというものは、実にとるにたらないつまらないものなのだ。日常の大半を机にむかってワープロを叩き込んでいるだけの人生だった。そんな人間の自伝が面白いわけがない。事実作家の自伝といったもので、これはと思ったものはほんの数えるほどしかない。作家にはもっと書かねばならないことがあるのだ。その思いはいまでも変わらないのだが、しかしこのシュトラウスの曲をおりにふれて聴くたびに、わが人生を主題にした最後の四つの小説というものを手がけたいという誘惑は、私のなかでずうっとくすぶっていたのだ。
八十年という人生を振り返ってみるとき、たしかに人には節目といったものが存在する。竹のようにくっきりとした輪郭というものがあるわけではないが、ある一つの出来事、ある一つの出会い、ある一つの体験がなるほど人生のなかに、あるときは奔流のように襲い、またあるときは微妙な波をつくりながら流れ込み、その人の一生を決定していく。そんな節目にも似た出来事のなかから、私は四つの主題を選び出してみるのだ。すなわち私の少年時代のこと、放浪を続けていた青年時代のこと、かろうじて私というものを打ち立てることができた四十代のこと、そしてふたたび闇のなかをさ迷っていた五十代での出来事を。そしてシュトラウスがなしたように短い物語のなかに私の最後の歌を託してみるのだ。
ゲルニカの旗 高尾五郎

ゲルニカの旗
珈琲亭「白鯨(モービィ・ディック)
高く、高く、より高く
ゲルニカの旗
年が明けた三学期の最初の日、五年三組の教壇に新しい先生が立った。その先生はにこにこしながら私たちを見回すと、
「なるほど、これが名高き五年三組なんだなあ、さあて、ぼくの自己紹介からはじめようか……」
といってチョークをとり、黒板に《吉》と書き、《永》と書きかけたとき、だれかがトマトを黒板に投げつけた。トマトはびしゃっと音をたてて炸裂した。私たちもびっくりしたが、先生は、
「ウム………」
と絶句して、砕け散ったトマトを見下ろしていたが、
「君たちの歓迎のメッセージっていうわけかな、面白いメッセージだなあ、だけどまずぼくの名前をちゃんと書かせてくれよ」
といってまた黒板に《永》という字を書き終え、《和》と書き、《雄》という字を半分書きかけたとき、またトマトが投げつけられた。今度のトマトは派手に飛び散り、その滴が前の席の女の子たちにまで飛んできて、女の子たちがきあゃっと悲鳴をあげた。
「なるほどなあ、こういう自己表現の仕方というものがあるんだね、なかなか痛快だなあ、このトマトを投げたのはだれなんだい、こっちのトマトは、多分そのあたりからカーブ回転で飛んできたんだろうね、こっちのトマトは、こちら側からシュート回転で投げられたんだろうか、さあ、いさぎよくだれが投げたか手を挙げてくれよ」
しかしだれもが黙りこんでいる。すると先生はさらにこういった。
「みんな、誤解しないでくれよ、手を挙げてくれといっているのは、このトマトを投げた子を叱るなんてことじゃないよ、ぼくはその子を尊敬する、だって先生っていうのはいってみればクラスの権力者だよね、クラスの隊長であり、君たちの点数をつける怖い司令官みたいなものだ、その権力者にトマトを投げつけるなんて、まさに英雄だ、ぼくはその英雄に親しく挨拶をしたいんだよ、よくやってくれたなあってね」
私たちはなにがなんだか訳がわからなかった。いったいこの先生は何者なのだという思いだった。すると先生はさらにこにこして、
「じゃあ、仕方がないね、二人の英雄が名乗りでるまでぼくたちはじっと待つことにしょう、なんとしてもまずぼくはクラスの英雄に敬意を表したいのだ」
この笑顔はいったいなんなのだ。その笑顔の裏側におそろしい人間が隠されているのではないか。なにか途方もないおそろしいことをたくらんでいるのではないか。この先生が私たちには不気味だった。
終業のチャイムがなった。どっと廊下に飛び出した隣のクラスの子供たちがあげる騒音が、沈黙した私たちの教室に流れこんできた。静まり返ったこの教室でいったいなにがあったのだろうと、隣のクラスの子供たちが窓からのぞきこんでいた。
二時間目の始業のチャイムが鳴った。それでも私たちは沈黙したままだった。先生もまた黙って待っている。とうとうその張りつめた緊張に耐えられなくなったのか、野中君が立ち上がって言った。
「先生、ぼくがやりました」
「そうか、とうとう名乗ってくれたね、ありがとう、それで、こちらのシュート回転のほうはだれかな?」
すると石塚君が立ち上がって、
「先生、ぼくもしました」
「うん、君か、二人ともよく名乗りでてくれたね、君たちに大切なことを教えてもらった、ぼくはまるで自分のクラスだといった顔をして、この教室に入ってきた、しかしこのクラスは君たちのものなんだね、君たちがこの教室の主人なんだ、だからまず君たちから自己紹介をするのが筋道なんだな、そのことを君たちふたりは教えてくれた、ありがとう」
と先生はいって、なんだか舞台にたった俳優みたいに、
「さあ、権力者に怒りのトマトを投げつけた我らの英雄よ、ここに立って君を語りたまえ、君の怒りと希望を語ってくれたまえ、まずは野中からだな」
野中君は、ええっといって尻込みしていたが、先生に何度もいわれると恥ずかしそうに黒板の前にいくと、
「ええと、ぼくはいま、トマトをカーブ回転で投げた野中重雄です」
クラスにどっと笑いが起こった。カーブ回転というところが本当におかしかったのだ。その明るい笑い声は、このクラスに起こったはじめての、なにか信頼と希望の笑い声のように私は思えた。
「待て、待て、待ってくれ」
と席に戻ろうとする野中君を、先生は呼び止めた。
「それではだめだ、そんな自己紹介で終わらせないでくれ、君はもっと自分のことを語らなければだめだよ、そうだね、一人の持ち時間を一分間としょうか、一分間、なんでもいいから話してもらうことにする、好きなタレントとか、好きな食べ物とか、ゲームとか、家族のこととか、将来どんなことをしたいとか、どんな人になりたいとか、なんでもいいから一分間、話してもらう、野中にはぼくからとくに注文がある、どうしてトマトを投げたのかってことを話してくれないかなあ」
すると子供たちから手が上がった。
「話せなかったらどうするんですか」
「そのときは黙って立っている、沈黙もまた重要な表現だからね」
「一分を越えたらどうなるんですか」
「ああ、大歓迎だよ、話したければ何分でも話していいんだ」
「夜まででもいいんですか?」
「もちろんだよ」
「明日の朝まででもいいんですか?」
「ああ、いいね、そうなったら最高だ」
と先生はさらににこにこしていった。
こうして一人一人が教壇の前に立って自己紹介をしていった。最初は好きなテレビだとか、好きな食べ物とか、好きなゲームとかいったことを話していたが、次第に学校のこと、クラスのことを話す子のほうが多くなった。
「……それと、いまの学校は、ちょっとおかしいというか、変というか、ぼくは好きになれません、それとクラスとかも、ちょっと荒れているというか、乱れているというか、好きではありません」
と話したり、
「……クラスのことですけど、いまこのクラスははっきりいって荒廃しています、このクラスはぜんぜんクラスではありません。もっとちゃんとしたクラスにしてみたいと思うけど、どうしたらそんなクラスができるか私にはわかりません」
と話す子も出てきた。
私の番になった。私も最初は、好きな食べ物とかいったことを話していたが、しかし私がいまここで話したいことはそんなことではなかった。話したいことがいっぱいある。叫びたい言葉がいっぱいある。私はとうとうそのことを切り出していた。
「……私はいまとても苦しんでいます、学校にくることが毎日とても怖くて、それで朝になると、お腹とか頭とが痛くなったりして、学校にくるのがとてもつらいんです、でもここで休んだら、ずうっと休んでしまうと思って、毎日学校にきています、でもこんなに学校にくることがつらくて怖いことだって、いままでそんなことを一度も思ったことはなくて、どうしてこんなふうになってしまったのかっていつも思います、それまで学校にくるのが楽しくて楽しくて、風邪をひいてどんなに熱があっても学校にきました、でもいまはつらくて……」
と話していった。しかしそこまでしかいえなかった。教室はシーンとなって、重い沈黙がどんどん重くなり、なにかみんなの視線が痛いばかりに突き刺さってきた。本当のことをこの教室ではいってはいけない、これ以上自分のことをさらしたら私はさらに傷つき、もっと惨めになると思い開きかけた心をそこで閉ざしてしまった。

私たちはその問題を話し合いたいのにまたそういって追い返されてしまった。いつもこうしてはぐらかされてしまう。こういう校長先生の態度に私たちはいよいよ敵意を深めていくのだった。
ゲルニカが完成した。そして最後の制作委員会が開かれた。その会議には六年担任の四人の先生と教頭先生も同席した。ゲルニカをどうするのか、どのように展示するのか、吉永先生がその問題について説明した。
「ゲルニカをどのように展示するか、先生たちは真剣に話し合ってきました、そして最後の結論が出たからそのことを報告します、ゲルニカは卒業式に飾ります」
ときっぱりと先生がいった。そのとき子供たちから、やったといった歓喜の声が上がり、パチパチと拍手が起こった。それほどうれしかったのだ。しかしその笑顔もだんだん曇っていった。その話はこう続けられていったからだ。
「卒業式に飾ることは決まりました、しかし正面にではなく、会場の後ろにゲルニカを貼ったパネル板が置かれます、正面のステージではありませんが、しかしゲルニカは後ろから君たちの姿をしっかりと見守ります、君たちはゲルニカに見守られて卒業していきます、そういうことになりました、そういう方法でゲルニカを展示します」
卒業式がやってきた。その朝、卒業式の会場となる体育館に入っていくと、ステージの上に日の丸が飾ってあった。ずらりと椅子がステージに向かって並んでいる。生徒の席があり、その背後がPTAの席だった。その華やかな式典の片隅にゲルニカが置かれてあった。まるでみんなの目から隠すように体育館の片隅におしやられていた。そのゲルニカをみたとき、私の目に涙がにじんでくるのだった。あんなに情熱をこめて、あんなに膨大な時間をかけて、あんなに希望に燃えて描いていったゲルニカが、こんな片隅に、こんな卑屈に、こんなにしょんぼりと置かれている。なにが私たちの卒業式を見守っているだ。
卒業式がはじまった。司会をする教頭先生がいった。君が代斉唱、全員ご起立をお願いしますと。みんながどどっと立ち上がった。私も立ち上がった。しかしそのとき私は叫んでいたのだ。
「私は歌えません。私は君が代は歌えません!」
そしてすとんと席にすわると、三組の子供たちもどどっと座っていった。式場にざわめきが起こった。吉永先生がびっくりして私たちの席まで飛んできた。しかしどうすることもできない。もっと驚愕していたのは教頭先生だった。なにかその様子はパニックに陥ったといった風だった。そのピンチを音楽の先生が救った。ピアノが奏でられると、体育館にはなんだか気の抜けたような君が代が斉唱されたのだ。
私たちの卒業式は、卒業生の一人一人の名前が呼ばれると、校長先生の前に進み出て卒業証書を受け取る。そしてマイクの前に立って感謝と決意の言葉を述べることになっていた。
「倉田佐織さん」
とうとう私の名前が呼ばれた。私は立ち上がり、校長先生の前に進みでて、両手で卒業証書をもらった。マイクの前に立つと私は校長先生をひたとみつめていった。
「校長先生、どうしてゲルニカを、ステージの正面に飾ってくれなかったのですか、私たちは何度も何度も校長先生にお願いしました、しかしとうとうゲルニカを飾ってくれませんでした、ゲルニカは私たち六年生全員が、この小学校でのたくさんの思い出をこめて描いていったのです、この六年間は楽しい思い出ばかりではありませんでした、苦しくて心が夜のように暗いときがありました、朝がもうこないのではないかと思うほどのどん底がありました、だからゲルニカは遠い国でおこった悲惨な事件の絵だと思えませんでした、私たちの心がちぎれていました、私たちの心が叫んでいました、私たちの心が救いを求めていました、だからゲルニカは私たちの心の歌だったのです、私たちの希望の旗だったのです、その私たちに心の歌を歌わせないで、どうして君が代だけを歌えというのですか……」
「わかった、わかった、もうやめろ!」
と鋭い怒号が私を突き刺すように飛んできた。そしてそれを契機にPTAの席から一斉に野次と怒号が上がった。
「お前はもう引っ込め、君が代が歌えないのは日本人じゃない!」
「神聖な卒業式を汚すな!」
「引っこめろ、その子供を引っこめろ!」
大人たちがこのような激しい憎悪の野次を浴びせたのは、君が代斉唱のとき私が君が代を歌えませんと叫んで着席してしまったからだ。大人たちを私に注目していたのだ。野次と怒号はどんどん激しくなって、体育館はなにか騒然となっていく。そのとき吉永先生が立ち上がり、PTAの席にむかって、野次を制止するように両手をふりおろしながら叫んだ。
「みなさん、静かに聞いて下さい、子供の声を静かに聞いて下さい、お願いします、子供の声をまず静かに聞いて下さい」
しかしさかんに制止する先生の声を打ち消すように、さらに野次と怒号は激しくなる。その野次は吉永先生にも向けられていった。
「お前のような教師が子供を駄目にするんだ!」
「責任をとれ、こんな子供をつくりだした責任をとれ!」
「教育長、この先生を懲罰にかけなさい!」
いよいよ激しくなる野次と怒号のなかでおびえながらも、しかし私は最後までいいきった。
「ゲルニカは、ゲルニカは、ゲルニカは私たちの心の歌だったのです、私たちの希望の旗だったのです、その私たちの心の歌を歌わせないで、どうして君が代だけを歌えというのですか、私たちの希望の旗を後ろにかくして、どうして君が代だけを飾るのですか、私はこのような卒業式をぜったいに認めたくありません、子供の声や叫びを拒杏する校長先生のような人に、私はぜったいになりたくありません、私はいま強い怒りと悲しみをもって卒業していきます」

翌日はどんよりと曇った日だった。私の頭のなかもどんよりとした雲がかかっていた。小さなレストランで朝食をとり、ホテルをでて通りを歩き出すと、時差ぼけの幕がきれいにすっきりと晴れていった。私はすでにこの町がどのように構成されているか地図でたっぷりと調べてあった。ゲルニカが展示されている芸術センターは、カルロス五世広場にある。その広場にでるには何通りもあるが、どんなに遠回りしても三、四十分の距離だった。私はプラド通りから五世広場に向かうことにした。
その大通りを歩いているとき、私のなかにまた秀雄のことが、あふれるばかりに噴きだしてくるのだった。この道を秀雄の指に私の指をからませて歩くはずだった。噴水も、木立も、建物も、すべてスペインなのだ。スペインの風景のなかを私は歩いている。それなのに私は秀雄の影を追っているのだった。
その建物はソフィア王妃芸術センターと名をつけていたが、その優雅な名称とはほど遠いなにか官庁か病院を思わせた。しかし一歩館内に踏み込むと巨大な絵画の群れがどっと私に襲いかかってきた。その絵画の洪水におぼれまいと、館内の案内地図をたよりにわきめをふらずに進んでいった。私はまずゲルニカの前に立たなければならなかった。ゲルニカを見るためにはるばるとやってきたのだ。
「ああ、とうとうきた」
と思い、
「ああ、これなのか」
と思いながら、私はゲルニカの前に立った。愛と憎しみのゲルニカだった。私はその絵をすべてそらんじていた。その直線、その曲線、その光の当て方、その影の作り方、その手、その体、その顔。悲しみをたたえて立っている牛。その下で死んだ子を抱き上げ絶叫している母親。牙をむいた馬。その馬体に描かれた刺のような無数の毛。炎のなかで手をあげて泣き叫ぶ女。窓から突き出した女の手に握られたランプ。その横にある太陽。太陽のなかのもう一つのランプ。異常にふくらむ膝を持つ女。腕を切り落とされて横たわる兵士。折れた剣を握りしめているその手から小さな草が生えている。
ゲルニカは激しい絵だ。爆撃の音、叫び声、切り裂く音。しかしそのときゲルニカは、ひっそりと、つぶやくように、私のなかに言葉を送り込んできたのだ。ゲルニカから逃げるな、ゲルニカを剥がすな、ゲルニカを胸に貼りつけて生きよ、と。そしてそのとき突然、ゲルニカ裁判とは私の裁判ではなかったのかという思いが駈け抜けていった。
私はゲルニカ裁判を捨てるためにこの絵の前に立ったのだ。私の足にからみつき、私の青春に立ち塞がり、私の人生を崩し、私の飛翔をさまたげ、私の未来にいつも暗雲として覆いかぶさり、私をしばりつけていた。私はゲルニカ裁判を憎み、こんな裁判をひきおこした吉永先生を憎んだ。私はいつもそこから立ち去ろうと思った。私はこんな裁判にとらわれない自分の人生を生きようと思った。私が私になるのは、この裁判を捨てたときだと思っていたのだ。
しかしゲルニカ裁判とは私の裁判ではなかったのか。卒業式のあの日、私は君が代を歌えませんと叫んで着席した。六年三組の子供たちもみんなざざっと席に座ってしまった。伴奏がはじまり君が代が歌われたが、私たちのクラスはだれも歌わなかった。それを先導したのは私だった。そしてそのあとの決意表明のとき、私はその卒業式を非難した。するとPTAの席から、猛然と野次と怒号が上がって、厳粛な式典はめちゃめちゃになった。その行為を引き起こした犯人は私だった。教育委員会が憎んだのは私だった。教育委員会が処分したかったのは私だった。しかしそのとき倉田佐織はまだ十二歳だった。子供を戒告処分などできない。だからそのかわりに吉永先生が犠牲山羊になったのだ。それがゲルニカ裁判の真実の姿ではなかったのか。
そうなのだ。ゲルニカ裁判とは私の裁判だったのだ。私はその事実からいつも逃げようとしていた。そんな私をもっとも鋭く見抜いたのは秀雄だったかもしれない。秀雄はいった。君の人生はコピーじゃないか。コピーすることが生きることだと思っているんじゃないかと。ずるずると大学院に入ったのも、とうていその力がないのにレイチェル・カーソン研究のまねごとをしょうとしたのも、みんな自分から逃れるためのコピーなのだと。そういえば、あんなに深く秀雄を愛しながら、彼との人生を踏み出せなかったのも、コピーする人生から抜け出せなかったからだ。いつでもほんとうの人生は彼方にあって、その彼方にある道を歩きだしたときから私の人生がはじまると思っていた。そうではなかった。ゲルニカにとらわれていたこの人生が私の人生だったのだ。
ゲルニカ裁判とは、私のあの行為が犯罪であるかないかの闘争だったのだ。十二年にもおよぶ三度の裁判で、国家の下す判決はいつでも有罪だった。最後の審判も有罪だった。私は犯罪者になった。ゲルニカから逃げるなということは、この事実から逃げるなということなのだ。ゲルニカを生きよということは、国家が私に下した犯罪者だという印を、胸に張り付けて生きよということなのだ。
私はそのとき自分の言葉を取り戻した。私は私になった。
珈琲亭・白鯨(モービィ・ディック)
老人が珈琲亭・白鯨に姿を見せるのはいつも木曜日だった。昼さがりのがらんとした店に入ってくると、窓側に設置された長いカウンターに椅子に座る。その窓から外の景色が望見できるのだ。JRの車輌基地に何本もの引き込み線が敷かれ、そこに待機中の車両が停車している。その敷地の右方には、赤煉瓦の建物が時代に取り残されたように立っていた。しかしその建物はいまでも現役で、そのなかで車両を点検したり、修理したり、解体したり、組み立てたりしているのだろう。老人がこの店に姿を見せるのは、毅然と立っているその赤煉瓦の建物を眺めるためかもしれなかった。
珈琲亭の前の道路の向こう側はすとんと切り落ちた崖になっていて、その崖下を特急、急行、各駅停車の電車がひっきりなしに往来する。電車が走り込んでくるたびに、老人の視線はその電車を幼児のように追っていった。老人はそれらの景色を眺めながら、コーヒーを一口また一口とすすり少半時を過ごすと、店のオーナーに「おいしかったよ、これで一週間は大丈夫だ、珈琲亭のコーヒーは私の精力のもとだからな」と声をかけると、オーナーもまたいつもの通りのせりふを投げ返す。「一週間どころか、あと十年は大丈夫ですよ。渡辺さんは私らの目標だから、百歳まで頑張ってもらわなきゃ」。珈琲亭のオーナーもまた来年還暦を迎える立派な老人だった。老人が珈琲亭に姿を見せるのは、こんな冗談を交すためだったかもしれなかった。
また木曜日がやってきた。珈琲亭のウエイトレス役を担っているオーナーの曾孫が、水を運んできてオーダーを取る。しかしこの日、彼女は紙袋を手にしていて、オーダーを取る前に老人に、
「あの、クジラ絵本クラブというところの人が、これを渡辺さんに渡してくれって頼まれたんですけれど」
「クジラ絵本クラブ?」
「ええ、クジラ絵本クラブって言ってました、わけがあって珈琲亭にはこれないけど、渡辺さんに渡してくれって」
奇妙な話だった。クジラ絵本クラブなんて聞いたこともない。老人は首を傾げ、怪訝そうに紙袋の中をのぞいてみた。《写ルンです》という簡易カメラと、ピンクの封筒が入っていた。その封筒のなかには、同じピンク色の便箋と手の切れるような紙幣が入っていた。いよいよ不審を募らせて、便箋に目を落とした。そこにまるっこい文字がスキップでもするかのように記されていた。
《渡辺謙作さん。はじめておたよりを差し上げます。クジラ絵本クラブは渡辺さんを『過去をめぐる旅』に送り出し、そこで写真を撮ってきてもらうというプロジェクトに取り組むことになりました。一方的な決定で、一方的なお願いですか、どうかクジラ絵本クラブに力を貸して下さい。もしこのプロジェクトを引き受けて下さるのなら、まず渡辺さんが生まれた池桜の村にいって、ぱちぱち写真を撮ってきて下さい。《写ルンです》を同封してあります。このカメラはただシャッターを押すだけでいいのです。往復のチケット代、それに現地の宿泊費用など少なくて申し訳ありませんが、それも同封してあります。旅から帰ってきたら《写ルンです》をこのテーブルにおいて下さい。ではよろしくお願いします。クジラ絵本クラブより》
高く、高く、より高く
潮沢族の歴史と文化と戦争と愛の記録
トンビが、言葉を持っている鳥だということを、あなたは知っているだろうか。トンビたちにも人に劣らぬ長い歴史があり、その歴史を彼らもまた絶えることなく語り継いでいる。不幸なことに人間にはその言葉がわからない。しかしもしあなたが彼らの言葉を聞き取り、その長大にして雄大な歴史に耳を傾けたいと思うならば、一つの方法を教えよう。松本から島々線に乗換えると、二両編成の電車が安曇平をのんびりと走り、二十分ほどで終着駅である島々につく。改札を抜け、駅舎を出て、畔道をたどっていくと、北アルプスの懐から流れこんできた梓川にぶつかる。とうとうと流れるその川の堤をゆっくりと下っていくのだ。むろんそのときあなたは、この地を歩いていかねばならない。車に乗ってどうして鳥の歌が聞こえようか。降り注ぐ陽光を浴び、もし雨ならば雨に打たれ、もし風が吹いていたら風を満身に受けて歩いていくのだ。
梓川にかかる倭橋を渡り、サラダ街道に入っていく。辺り一面果樹園であったり、トウモロコシ畑であったりする。その広大な田園地帯を歩いていくと、梓村から北アルプスの山麓沿いに巡る道に出る。この道を土地の人々は山麓線と名づけたが、赤松の森や田畑を縫うこの美しい道をのんびりと歩いていくのだ。安曇村から堀金村ヘ、穂高町から松川村へと抜け、さらに大町へと入っていく。大町を抜け、国道十六線を下っていくと仁科三湖と呼ばれる三つの湖に出会う。最初の湖が木崎湖で、その湖畔をそぞろ歩き、小さなかわいい中網湖を眺めながら国道を通り、さらに青木湖をぐるりと一回りする。
その湖を回遊すると、再び松本方面に足を向けるのだが、今度は、安曇野をはさみこみ、アルプスの峰々と向き合って連なる、こんもりとした山並み沿いを通る明科大町線という県道を歩いていく。走る車がうるさければ、田畑を縫いながら歩くとよい。池田町に入るとどこからともなくハーブの香りが漂ってくる。この町には、日本で最も美しい美術館が、小高い丘の中腹に立っているが、その美術館を訪れると安曇野が一望できる。道はやがて明科町に入ると犀川にぶつかる。あなたはようやく潮沢一族の国の玄関に立ったことになる。
月日をかけたその流浪のなかで、あなたの全身が次第に野生的になり、大地の匂いをかぎとり、草や木立の生命のささやきも、かすかに感じられるようになっていくと、はじめて鳥の歌が聞き取れるようになってくる。うねうねと流れる犀川を渡り、潮沢の国深くはいりこみ、たとえば岩州山の岩山に立って空を見上げるとき、もしあなた運がよければ、悠然と飛翔している一羽のトンビに出会えるだろう。風介という名前をもつトンビに。彼は人の年齢に換算したら八十近い老鳥ということになる。しかしその飛翔はたくましく、彼はいまでも六千メートルの高度まで飛翔することができる。風を愛撫し、宇宙をたゆたうように、のんびりと飛翔するその翼に刻みこまれている言葉は深い。民族の悲劇の歴史を、この鳥は深く刻みこんでいるのだ。
もちろん、トンビ語なるものを聞き取ることができるには、何十年もかかる。しかし安曇野を回遊したあなたには、少なくともトンビ語を感じとる体質ができつつあるのだ。もともとあなたが、トンビの言葉を聞き取りたいという思いに駆られたのは、あなたの心がひどく痛んでいたからにちがいない。恋に破れたとか、仕事につまずいたとか、あるいは大切な人を失ったとか、生きる意味がわからなくなったとか。ともあれそんな人生の重大な岐路に立ったあなたは、新しい再生の道をもとめて安曇野に旅だったはずなのだ。風のそよぎに心がふるえ、月の光にさえ痛みを感じとるばかりに、心が繊細で柔らかくなければ、烏たちの言葉は聞き取れない。
もし風介にあなたが出会えたら、そして彼があなたの存在を認めてくれたら、彼はあなたにも以下のような物語を語るはずだった。潮沢一族の挫折と敗北の歴史を。そしてその敗北の底から立ち上がって雄々しく戦い、再び一族の国家を打ち立てていった輝かしい歴史を。
かぐや姫 高尾五郎
はじめの章 おはなしの家
一の章 貧しい村
二の章 五人の皇子たちの求婚
三の章 石上皇子
四の章 車持皇子
五の章 大伴御行
六の章 阿倍皇子
七の章 石作皇子
八の章 帝
九の章 籠売り娘
十の章 紙づくり工房
十一の章 月に帰るかぐや姫
新編竹取物語の作者、円空
はじめの章 お話のおうち
ここから車で、一時間も走れば明科という村にでるけんど、そこに明科神宮寺というお寺さんが建っているんだわ。その神宮寺の裏にある土蔵から最近になって、
『三浦家新編竹取物語』
という古文書が発見されたんよ。歴史をひもとけばわかることだけんど、三浦家というのは鎌倉時代に、三浦半島に興隆した一族なんだわ。頼朝が鎌倉に幕府を開いて以来、幕府をささえてきた豪族であったけんど、宝治元年に、いわゆる宝冶の乱で、三浦一族は法華堂にたてこもって、一族五百余名がことごとく自害していく。そのときその乱が起こる直前に、三浦家再興の時のために三浦家所蔵の文書などを、はるか信州の地にまで運んできたという言い伝えがあったんよ。明科神宮寺もまたその一族が建立したものであるといわれてきたんだけど、そのことがその文書の発見によっても裏付けられたということになるんだわね。
その古文書は、信州大学の小山先生の手によって、解読されていったんだけんど、おばさんは小山先生とは昔からのお友達だったもんで、その解読作業に加えてもらったんよ。毎週のように小山先生はこの「お話のお家」にやってきて、一行一行の解読の成果を説明してくれるんだけんど、それはもうぞくぞくするばかりの興奮の日々だったわね。それは大変な物語なんだわ。なによりも驚いたことは、なんとその物語には、お母さんが指摘した、かぐや姫が月の世界で犯した罪がなんであったかという謎が、それは見事に解き明かされているんだわ。なにかこの物語は、あの謎の一行に光をあてるために、書かれたのではないかと思われるばかりなのよ。ということは、なんと八百年も前の鎌倉時代に、お母さんや私たちと、同じことを考えていた作家が、いたということになるわね。
竹取物語を面白くしているのは、かぐや姫に求婚した五人の皇子の冒険譚といったもんだけんど、その冒険というものが、どれもこれもこすっからいんだわ。嘘をついたり、偽装したり、山中に身を隠したりと、その頃の貴族の実態を暴いているといえば、それなりの意味があるんだろうけんど、まあけちくさい人物ばかり。ところが、この神宮寺で発見された竹取物語には、五人の皇子たちが、人間の苦悩もった人物として描かれているんよ。彼らが背負ってしまった悲劇には、なにやらシェクスピアの劇のような深さがあるんだわ。そうして皇子たちを実際に、海ヘ、陸ヘ、砂漢ヘと旅だたせている。そのことがこの物語を、宇宙的規模にしているんだわね。
五人の皇子の物語のなかで、最後に登場するのが、石作皇子という皇子なんだけんど、この皇子が長い放浪の旅を終え、瓦礫の山にぬかずいて、慟哭しながらいう台詞があるんよ。その場面で、おばさんも思わず慟哭してしまったのは、この物語がまさに、人間の苦悩というものを彫り込んでいるからなんだわ。おばさんだけじゃないわよ。きっとこの物語を語る語り手たちのだれにも、この皇子の苦悩の魂がのりうつって、だれもが慟哭しながら、その台詞をいわなきゃあならんだろうさ。
そうしてこの新しい竹取物語を、さらに魅力的にしているのが、原典にはない永吉という若者を登場させたことにあるんよ。竹取物語はもともとが貴族たちの物語だったんだけんど、この鎌倉時代の作者は、貧しい竹採り村の若者を登場させることによって、庶民の物語にしてしまったんだわ。永吉を登場させることによって、かぐや姫は人々に愛される姫になったともいえるわね。永吉に愛されるかぐや姫はなんて愛らしいんだろう。だからこそ姫が月に帰っていくシーンが、一層ドラマチックになっているんよ。
どうしてこんな作品が八百年も眠っていたんだろうね。もしこの物語が鎌倉時代に、いいえ、室町時代でも、江戸時代でもいいわ、その頃、世にでて広く読まれていたら日本の文学は、もっとちがったものになっていたんだろうと思わせるばかりの作品なんだわ。
あんたさんの入学のお祝いに、贈り物をせなゃあならんといろいろ考えたけんど、おばさんは貧乏だから、高いもんなんて買えんのよ。そんなものよりもね、あんたさんの手紙をもらったときから、もうその贈り物はこれしかないって思っていたんだわ。この新しく発見された「竹取物語」を、あんたさんにお話してみようってね。あんたさんの前で、八百年も眠っていた物語をいまその封印をといて、はじめてお話してみようって。これから日本の民話を研究しようするあんたさんのために、そしてあんたさんのなかでしっかりと生きている私の大切なお友達のためになあ。
五の章 大伴御行
やがて海は、船長がいった通りになった。まるで船を吹き飛ばさんとするばかりのものすごい風が、吹きつけてきた。波もわさわさと荒れ狂い、もう船は木の葉にようにきりきりと舞うばかり。このままでは危ない。このままでは船は粉々に打ち砕かれる。どうすればいいのだ。どうしたらこの窮地を抜けだせるのか。この船には四十人もの人間をのっている。これらの人間を守らねばならぬという強い使命感をもった船長は、操舵不能、遭難確実、もはや天に祈る以外にないという絶望的境地に達すると、柱にしがみついている大納言のもとにいくと、その大納言の足にがっしとしがみつき、
「大納言様、もはや神にすがる以外にありませぬ。この嵐は神にそむいたむくいでございますよ。神の化身であられる龍を捕らえにいくなどという魂胆をもたれた大納言様に、怒りの鉄拳をふりおろしているのでございますよ。はやく、はやく、その魂胆をお捨てください。そうしなければ、この船は真っ二つになりますぞ。はやく、はやく、天にむかって、大納言は間違っていた、大納言をお許して下さい、大納言は二度と龍を捕らえにいくなどという魂胆はもちませぬと叫びなされ!」
と船長は懇願する。しかし大納言は、そんな船長をけりつけて、
「なにをぶちぶちいっておるのだ。そんなことがいえるか。恐れるな。こんな嵐など、いまに鎮まるのだ。突き進め、真っすぐに突き進め!」
と叫ぶのだが、もう突き進むどころではない。やがて船がすとんと波の底に落下したと思ったら、なにやら巨大な山のような波がやってきて、船は岩にたたきつられたように木端微塵に砕け散ってしまった。
海中でぐるぐるとこねくりまわされた大納言は、やっとの思いで海上に頭をつきだし、そこにあった柱にしがみついた。荒れ狂う海はなおもはげしく、大納言はもう必死にその柱にしがみついているだけだった。それはどのくらい嵐の海にもまれていたのだろうか。荒れ狂っていた海も次第に鎮まっていき、空をおおっていた黒い雲もふきとんでいって、あたりにやわらかい光がもどってきた。その船には四十人もの人間がのっていたが、いま生き残っているのは大納言ただ一人だった。嵐は残る三十九人を海の藻屑としてしまったのだ。
大海原を漂っている大納言に、そのときまるで一筋の光が差し込むように、ある思いがふうっと走ってきた。わしはだまされていたのかと。まさか、まさか、そんなことはあるまい。これはあの女が仕組んだ罠だというのか。まさか、まさか。いや、そうなのだ、そうにちがいないのだ。わしはあの女の仕組んだ罠にまんまと落ちたのだ。だいたい首に五色にひかる珠をつけた龍などがいるわけがないのだ。なぜそのような単純なことに、わしは気づかなかったのだ。あの女こそ化け物だったのではないのか。あの女こそ首に五色の珠をつけた妖怪だったのではないのか。ああ、なんということだ。どうしてこのことに気づかなかったのだ。嵐の海が、この馬鹿者を目覚ましてくれた。この愚か者はやっと目が覚めた。
くそ、くそったれめ。わしはくたばらんぞ。くたばってなるものか。生き延びてやるぞ。どこまでも生き延びてやるぞ。あの女を真っ二つにしてやるのだ。それまでわしは断じてくたばらんぞ。そんな大納言のはげしい思いとは別に、嵐の去った海は平穏そのものだった。ふと前方をみると、そこに緑の島が横たわっているではないか。
その島はまったくの無人島だった。しかし湧き水のでる泉があり、南国の木立ちがたっぷりと果実を実らせている。自然のめぐみにみちあふれた島だったのだ。しかしたった一人で無人の島で生きていくには、やはり強い生命力というものがなければならなかった。絶望の底に落ちたとき、人の心を支えるものは夢とか希望であった。夢や希望があるからこそ、人はどんな苦難も乗り切れることができる。しかし人はまた復讐せねばならぬというはげしい憎悪をもつことによっても、そのどん底を乗り切っていけるのかもしれない。南海の孤島で、大納言が一人で生き延びてこられたのも、姫に復讐せんとする怒りと憎悪にあったのだ。
二年にもおよぶ無人島の暮しも、とうとう最後の時がきた。その島はちょうど唐の国に渡ったり、あるいはまた日本の国に渡るための一つの指針にもなっていたものだから、よく船はその島の近辺を通っていくのだ。しかしそのたびに大声で叫んでみるが、なんの応答もなかった。しかしその日の船は違っていた。たまたま大納言が食事をとるために浜辺で焚き火をしていた。その火に気づいて船が、まっすぐに島をめざしてきたのだ。
幸か不幸か、その船の最後の寄港地が、難波の港だったから、大納言は二年もにおよぶ流浪の旅から、難波の地に戻ってきた。船からおりると、大納言はまっすぐに竹採り村にむかった。都の自分の館に戻る前に、成し遂げねばならぬことがあるのだ。あの嵐の海で決意したこと、南海の孤島で彼を支えていたことをまず成し遂げねばならないのだ。
最後の峠をこえて村に入り、姫の館がみえてくるころには、もう大納言の体は、なにか憤怒の血でわきたつばかりになっていた。門前に馬をつけると、大声で門を開かせ、門が開かれると馬蹄の音もけたたましく前庭にかけこみ、ひらりと馬からおりると、屋敷のなかにずかずかと押し入っていく。そして応対にでてきた爺さんにむかって、
「姫を、ここにつれてこい。あの悪女をつれてこい!」
「これはまた大納言様、いったいどうなされたのでございますか」
「とぼけるな。龍はこの御殿にいたのだ。わしはてっきり龍とは唐の国に住んでいるものだとばかり思っていた。ところがそうではなかったのだ。龍はこの御殿にいたのだ。首に五色の珠をまいた龍とは、かぐやなる女そのものだったのだ。そいつをここにひきずりだしてこい。わしが一刀両断にしてくれるわ」「な、な、なんということをおおせられます」
「このような化物を、この世にのさばらせておくわけにはいかぬ。ただちにここに連れてまいれ」
もう爺さんは仰天しておろおろするばかり。
「ええい。もうお前などに用はない。そこをどけ」
どんと爺さんをつきとばすと、爺さんはくるくると四回転もして、庭にどすんと転落していった。つもりにつもった憤怒をはきださんとする大納言は、
「化物退治にきたのだ。化物を叩き斬る!」
とわめきながら、回廊をどどどどっと足音も荒く、姫の館に乗り込み、姫の部屋に一気に押し入らんとした。ところがその部屋の前に、ぴたりと婆さんが座っていたのだ。
「どけ、どけ、そこをどけ。ばばあ、お前も斬られたいのか」
「お静まりくだされ。見苦しいではございませぬか。大納言様ともあろうお方が、下々のものになんという無礼をお働きになるのでございますか」
「無礼なのはどちらだ。男たちをさんざにもて遊び、あっちにいけ、こっちにいけと、口からでまかせの難題を投げつけては、奈落の底に突き落とす。そんな化物を飼っているお前たちこそ、天にもそむく非道人ではないか。わしはお前たちが飼っているその化物を討ち取りにきたのだ」
「なりませぬ。この部屋にはたとえ大納言様といえでも、一歩も入れませぬ。もし押し入るというのなら、この私をお討ちなさいませ」
「どけ、どけ。お前などに用はない」
「こんな田舎のばばあでございます。私を斬って、そなたさまのお心がやすまるなら、さあ、私を斬って下され」
ときっと大納言を見据えて婆さんはその声を発した。その毅然たる態度に大納言は一瞬ひるむ気配をみせたが、しかし怒りの炎となっている大納言にはもはや火に油だった。
「こいつは驚いた、化け物屋敷に人間がいたというのか、いやいや、そうではあるまい、お前もまた姫に劣らない化け物なのだ、おれに斬られまいとすばやく人間に姿をかえた化け物だ、よおし、お前のいうとおりだ、お前を叩き斬ってやる、一刀両断にしてお前のなかにいる妖怪を征伐する、覚悟しろ!」
といって刀を降り上げ、婆さんの面上に降り下ろそうとしたその一瞬、ぴかっとあたりが光って、
ズドドドドドン!
と、それはものすごい爆音とともに雷が大納言めがけて落下した。大納言の黒焦げになった死体が、なんと松の枝にひっかかっていた。この大納言はどこまでも激しい人物だったということになる。
十一の章 月に帰るかぐや姫
とうとうその七月十五日がやってきてしまった。
噂というものはいつの時代でもまたたく間に広がっていくものだ。七月の十五日に、かぐや姫を奪いとりに月から大軍が攻め寄せてくるという噂はもう国中に広がっていて、あちこちの村や町から、はたまた都から何千何万という人が竹取りの村におしかけてきた。そして姫の御殿がみえる山の上や、畑や、楠や、柿の木や、橋の上や、家々の屋根や、鎮守の森や、神社の鳥居といったさまざまな場所に陣取って、いまかいまかとまちわびているのだった。月から攻め寄せる大軍を、朝廷からくりだされた三千の武者たちが迎え撃つ。その壮大な戦闘をみないわけにはいかないのだ。
日が落ちていくと、あたりの闇が次第に深くなっていく。そして空にぽっかりと月が浮かびあがった。その月ははちきれんばかりの満月だった。あわただしく騎馬が走ってきてはまた走りさっていく。あちこちで部隊を動かす指揮宮の声が鋭く飛び交う。
「橘卿の部隊百騎は、東の門に移動せよ!」
「加賀少将磨下の三十部隊は、西の屋根にとりつけ!」
「四百の歩兵は、東南の広場をかためよ!」
いよいよ戦闘がはじまる。何万という人々をのみこんだ村は、嵐の前の静けさで、なにか怖いばかりに緊迫していく。人々は首が痛くなるのをがまんしながら一心に空を見上げているのだった。
すると、無数にきらめく星空のなか、四っ、いや五っの星が、くっきりと光の尾をひいている。それは流れ星ではなかった。流れ星ならばすうっと消えていく。しかしその星々は消えるどころか、いよいよ光度を強くして村にむかってくるのだ。
「あれだ!」
「きたぞ!」
「月から、大軍団が攻め寄せてくるぞ!」
という叫び声が、村の畑に林にひろがっていく。その星々の輝きはいよいよ強さをましていく。それはすごい速度で地上にむかって落下してくることだった。村を埋め尽くした大観衆はもう驚きで声もでない。ただぽかんと口をあけてその光の群れを見上げているばかりだった。なかには両手をあわせて一身に祈っている人たちもいる。
その光の群れがぐんぐんと村の上空に迫ってくると、やがて満月がその星々の全貌をくっきりと浮かびあがらせた。それは船のかたちをした雲で、その雲の船が、その全身を光で飾っているのだ。巨大な一隻の船をかこむように、四隻の雲の船が前後左右に配されている。その雲の船団から放たれる光の美しさは夜に輝く虹のようだった。人々は突如上空にあらわれたその雲の船の美しさに、魂さえも奪われるばかりだった。
しかし兵士たちは戦わねばならなかった。月からの船団を撃退しなければならなかった。ようやくわれにかえった部隊の指揮宮は、声をかぎりに、
「全軍戦闘体制につけ。敵はまもなく攻め寄せてくるぞ!」
「矢をつがえよ!」
「弓をひけ、射程距離にはいったら発射せよ!」
「恐れるな。恐れることなく敵を打ち倒せ!」
命令が次々に下っていく。
そのとき一番大きな雲の船がゆっくりと地上におりてくると、その巨体をかぐや姫の御殿の前に広がる畑のなかにぴたりと着陸させたのだ。朝廷軍の指揮宮たちはいっせいに声を放った。
「あの船を近づけるな!」
「放て、矢を放て! あの船の胴を打ち抜け!」
御殿の前庭で、屋根で、土塀の上で警護している何百という武者たちが、いっぱいに引きしぼった矢を放とうしとした。すると、なんということだろうか。
ぷっぷっぷっぷっという音が闇のなかを走っていくと、武者たちの悲鳴がいっせいに上がった。
「あっ、弦が切れた!」
「おれの弦も切れた。どういうことだ!」
「弦が切れた。矢が打てぬ!」
屋根や土塀の上に張り付いた兵士たちは、へなへなと座りこんでしまった。するとまた馬上の指揮官が叫んだ。
「刀を抜け。敵を一歩も近づけるな!」
地上にいる部隊も、屋根に上がった兵士たちも一斉に刀を抜こうとした。ところがまた、
「刀が抜けぬ!」
「刀が錆ついたように鞘をはなれぬ!」
「なんということだ、これはいったいどうしたというんだ!」
御殿を警護する三千の武者たちの武器が、いまやことごとく使えなくなっていたのだ。
姫の御殿の前におりたった巨大な雲の船。その旗艦を援護するように四隻の船がぴたりと空中で停止している。その雲の船々から放たれる美しい光は、なにか戦闘の意欲というものを、奪い取る力がひめられていたのかもしれない。もうそれから兵士たちは、だれ一人として戦うという気持ちなどなくなっていたのだ。
三千の兵士と数十万の群衆が、魂を奪われてしまったかのように見守るなか、その船の扉が開いた。そしてその扉から、月の使者たちがぞろぞろと出てきたのだ。
使者たちは広い甲板にずらりと並ぶと、その中央に立つもっとも高き位の人と思われる月のお方が「日本の国に人々よ」と語りかけてきた。その声は村じゅうに響き渡っていった。重々しい、しかしあたたかく柔らかい声が。
「日本の国の人々よ。その蔵にとじこめられているお方は、わが月の姫君であられる。その姫君は愛という心を失っていたために、罰としてそなたの国にお預けになられた。しかし姫はとうとう愛の心を取り戻した。よって月に帰還されるお許がでたものである。その姫をいまわれらはお迎えにきた。わが月の姫君に、愛という心を取り戻してくれた貴国の友愛に、わが月は深甚なる謝意を表するものである。これがわが月の王のご伝言でござる」
そしてその月の使者は、姿などみえぬ姫にむかって、なにかありありとその姿をみているかのように、「さあ、姫。お帰りの時です。姫の罪は許されました」
その使者がひと差し指を御殿にむけると、その指先からぱあっと光の束がとんで、開じていた東門の閂がばしりと折られると、その重い扉がぎいっと開き、かぐや姫をとじこめていた蔵の何重もの錠前もぱちぱちとはじきとんで、その蔵の扉もまたぎいっと開いていった。
そしてそこから現れたかぐや姫のなんという美しさ。いまや地球の人ではなく月の人となったからなのか、その全身から光があたりに放たれている。蔵をでた姫は、呆然と立ち尽くしている爺さんと婆さんの前にくると、深々と頭をたれ、
「お爺さん、お婆さん、長いことありがとうございました。とうとう月に帰る日がやってきました。お爺さんとお婆さんを心のなかにしっかりと抱きしめてあの国に帰っていきます。たとえ遠く離れていても、お爺さんとお婆さんは、私の心のなかで生きております。どうかいつまでもお元気でいて下さい」
と姫の挨拶をうけると、二人はよよよと泣き崩れていくばかり。姫は別離の悲しみをふりきるように雲の船にむかって歩きはじめた。
リターン
谷根千ワンダーランド 山崎範子

- A5版 264ページ
頒布価 2300円
クリスマスの贈り物 高尾五郎
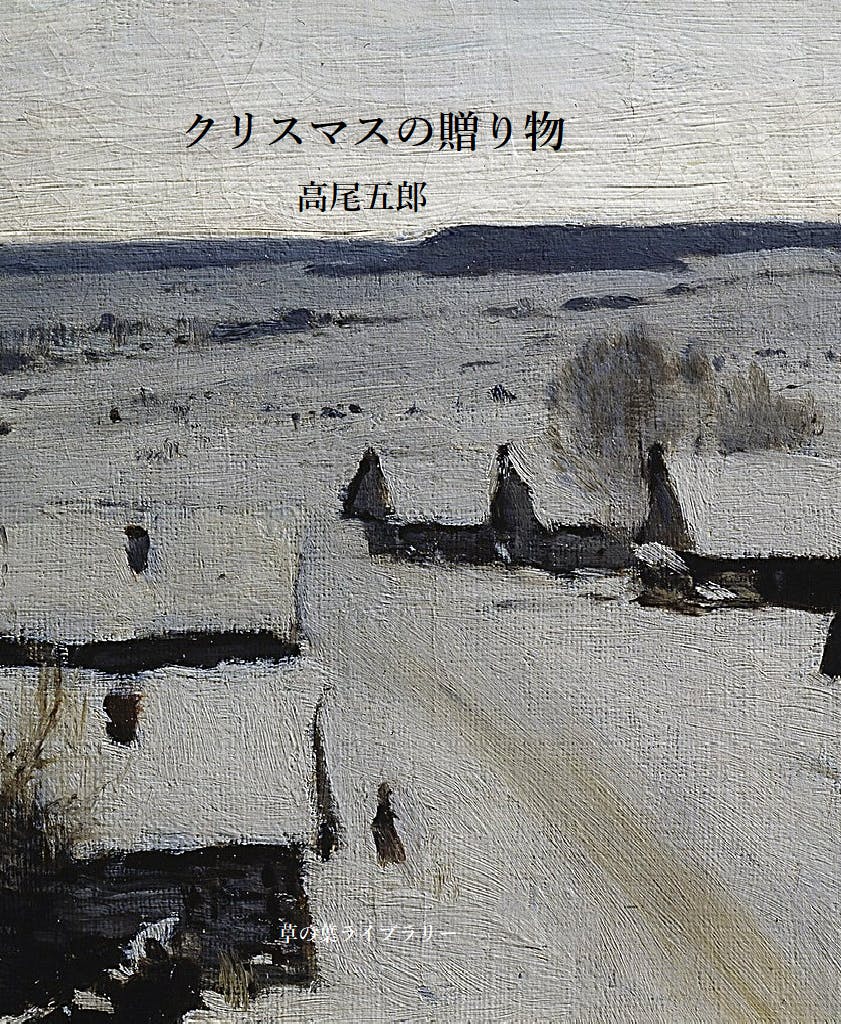
- A5版 262ページ
頒布価 2300円
最後の授業 高尾五郎

- A5版 258ページ
頒布価 2300円
ゲルニカの旗 高尾五郎

- A5版 252ページ
頒布価 2300円
南の海の島 高尾五郎

- A5版 254ページ
頒布価 2300円
かぐや姫 高尾五郎

- A5版 234ページ
頒布価 2300円

資金の使い道について
「草の葉ライブラリー」が刊行する本はすべて手作りです。膨大な時間をかけての編集作業がなされた本の版下版が、コンピューターに打ち込まれています。その本のご注文があると、一ページごとにプリントアウトして、裁断され、製本機で一冊の本に綴じられます。一冊一冊が手作り作業で造本されます。したがって「草の葉ライブラリー」の本づくりは、一つの工芸品を生み出す作業に似ています。一冊当たりの経費の内訳、
編集制作費 24パーセント
紙代、インク代、製本代 40パーセント
著者印税 10パーセント
クラウドファンディングの手数料 20パーセント
リターン者への送料 6パーセント 370円
制作のスケジュール
2021年7月 制作開始
8月 制作完成
9月 リターン者へ送付

最新の活動報告
もっと見る
大切なことは、到着することではなく、どこを目指して歩いていくかなのだ
2021/07/14 21:23アン・リンドバーグが見えてくる 須賀敦子がこの地上から去ってからすでに二十年近い月日が流れてしまったが、須賀さんと結ばれている精神の紐帯というものを私はいよいよ強く感じるのだ。私が須賀敦子という存在を知ったのは、ある雑誌に連載されていたアン・リンドバーグについて書かれたエッセイに目を投じたときだった。アンは夫のリチャード・リンドバーグと極東に向かって飛び立つ。しかしシリウスと名付けた単発機は千島列島で不時着するのだ。そのときの様子を描いたアンのエッセイに、須賀さんは心奪われ、いつか自分もこのような文章を書ける人になりたいと思うのだ。日本はアメリカと大戦争を勃発させた。須賀さん、中学生のときのことである。 それから数十年後に、再びアン・リンドバーグと対峙することになる。そのあたりをちょっと長めに、須賀さんのエッセイから転載してみる。これは山崎範子の本質に向かっていく行程でもある。《さらに時間が経って、まったく関係のない調べものをしていたときに、アンの最初の著書の表題が、『北から東洋へ』"From North to Orient"だということを知った。これこそ、かつて私を夢中にさせたあの千島での不時着陸のときの文章がのっている本に違いないとは思ったけれど、それも手に入れる方法をもたないまま、また月日が流れて、私は大学を卒業し、フランス留学から帰って、放送局に勤務していた。ある日、友人がきっときみの気に入るよ、と貸してくれた本の著者の名が、ながいこと記憶にしみこんでいたアン・モロウ・リンドバーグだった。この人についてならいっぱい知っている。『海からの贈物」というその本は、現在も文庫本で手軽に読むことができるから、私の記憶の中のほとんどまぼろしのようなエッセイの話よりは、ずっと現実味がある。手にとったとき、吉田健一訳と知って、私はちょっと意外な気がしたが、尊敬する書き手があとがきでアンの著作を賞讃していて、私はうれしかった。もしかしたら、戦争中に読んだあの文章も、おなじ訳者の手になったのではなかったかという思いがあったが、そのころの私はそういうことをきちんと調べる習慣をもっていなかった。一九五五年に出版された『海からの贈物』は、著者が夏をすごした海辺で出会ったいろいろな貝がらをテーマに七つの章を立てて、人生、とくに女にとって人生はどういうものかについて綴ったもので、小さいけれどアンの行きとどいた奥行のある思索が各章にみち美しい本である。たとえば、つぎのような箇所を読むと、ずっと昔、幼い日に私を感動させたあの文章の重みが、もういちど、ずっしりと心にひびいてくる。「今日、アメリカに住んでいる私たちには他のどこの国にいる人たちにも増して、簡易な生活と複雑な生活のいずれかを選ぶ贅沢が許されているのだということを幾分、皮肉な気持になって思い返す。そして私たちの中の大部分は、簡易な生活を選ぶことができるのにその反対の、複雑な生活を選ぶのである。戦争とか、収容所とか、戦後の耐乏生活とかいうものは、人間にいや応なしに簡易な生き方をすることを強いて、修道僧や尼さんは自分からそういう生き方を選ぶ。しかし、私のように、偶然に何日間か、そういう簡易な生活をすることになると、同時に、それが私たちをどんなに落着いた気分にさるものかということも発見する」「我々が一人でいる時というのは、我々の一生のうちで極めて重要な役割を果たすものなのである。或る種の力は、我々が一人でいる時だけにしか湧いてこないものであって、芸術家は創造するために、文筆家は考えを練るために、音楽家は作曲するために、そして聖者は祈るために一人にならなければならない。しかし女にとっては、自分というものの本質を再び見いだすために一人になる必要があるので、その時に見いだした自分というものが、女のいろいろな複雑な人間的な関係の、なくてはならない中心になるのである。女はチャールズ・モーガンが言う、『同転している車の軸が不動であるのと同様に、精神と肉体の活動のうちに不動である魂の静寂』を得なければならない」(新潮文庫) 半世紀まえにひとりの女の子が夢中になったアン・モロウ・リンドバーグという作家の、ものごとの本質をきっちりと捉えて、それ以上にもそれ以下にも書かないという信念は、この引用を通して読者に伝わるであろう。何冊かの本をとおして、アンは、女が、感情の面だけによりかかるのではなく、女らしい知性の世界を開拓することができることを、しかも重かったり大きすぎたりする言葉を使わないで書けることを私に教えてくれた。徒党を組まない思考への意志が、どのページにもひたひたとみなぎっている。》撃墜されたサンテグジュペリも見えてくる そして、雑誌連載の次の号に、須賀敦子の存在が私のなかに決定的な痕跡を残すエッセイを載せるのだ。サンテグジュペリのことが書かれていたのだ。ここでもちょっと長めの転載をしてみるのは、これもまた山崎範子の精神の投映していくものだから。《最初は、『星の王子さま』はなんだか子どもの本みたいなものを、と不満だったのが、読みすすむうちに、きらめく星と砂漠の時空にひろがる広大なサンテグジュペリの世界に私たちは迷いこみ、すこしずつ、深みにはまっていった。いや、迷っていたのは、クラスで私ひとりだったかもしれない。それまでに読んだどんな話よりも透明な空想にいろどられていながら、人間への深い思いによって地球にしっかりとつなぎとめられたサンテグジュペリの作品は、他にも読むべき古典がたくさんあるのをながいこと私に忘れさせるほど、夢と魅惑に満ちていた。 飛行家のアン・リンドバーグが書いたものに揺りうごかされ、いつか自分もこんなものを書けたらと思ったのは、十二、三歳のころだったけれど、それからまた六、七年たって、ふたたび私の心をつよく捉えたこの作家が、これまた飛行家というのは、それにしてもどういう偶然だったのか。 ジグザグのように歩いてきたながい人生の道で、あのとき信州にもっていったサンテグジュペリの本のうち、『戦う操縦士』だけが、どんなめぐりあわせだろう、傍線・付箋だらけになってはいるが、まだ私の手元にある。黄ばんだ紙切れがはさまった一二七ページには、あのときの友人たちに捧げたいようなサンテックスの文章に、青えんぴつの鈎カツコがついている。「人間は絆の塊りだ。人間には絆ばかりが重要なのだ」 もうひとつ、やはりこの本で読んだ、私にとって忘れることのできない文章がある。人生のいくつかの場面で、途方に暮れて立ちつくしたとき、それは、私を支えつづけてくれた。いや、もうすこしごまかしてもいいようなときに、あの文章のために、他人には余計と見えた苦労をしたこともあったかもしれない。若いひとたちにはすこし古びてみえるかもしれないけれど、堀口大学の訳文をそのまま、引用してみる。「建築成った伽藍内の堂守や貸椅子係の職に就こうと考えるような人間は、すでにその瞬間から敗北者であると。それに反して、何人にあれ、その胸中に建造すべき伽藍を抱いている者は、すでに勝利者なのである。勝利は愛情の結実だ。……知能は愛情に奉仕する場合にだけ役立つのである」》 そしてこのエッセイはこう結ばれていく。《サンテグジュペリが、ドイツ軍に占領されたフランスの解放をねがって、北アフリカで軍事行動に参加中、一九四四年、偵察飛行に出たまま行方不明になったという話が私の意識を刺しつづけた。自分は中学生だったとはいえ、戦争中なにも考えることなく罩事政権のいうなりになっていたことが口惜しく、彼のような生き方への憧憬は年齢とともに私のなかでつよくなった。行動をともなわない文学は、というような口はばったい批判、理論ともいえないような理論を友人たちと論じてすごした時間を、いまはとりかえしたい気持だし、自分は、行動だけに振れたり、文学にとじこもろうとしたり、究極の均衡(そんなものがあるとすれば、だが)に到るのはいつも困難だった。自分にとっては人間とその運命にこだわりつづけることが、文学にも行動にも安全な中心をもたらすひとつの手段であるらしいと理解するまで、ずいぶん道が長かった。『戦う操縦士』とともにもう一冊、おそらくはフランスに留学する直前に買った、ガリマール書店版の『城砦』が本棚にある。ページも、そのあいだに入れた手製の栞も、茶色に古びているけれど、あるページには濃いえんぴつで、下線がひいてあった。「きみは人生に意義をもとめているが、人生の意義とは自分自身になることだ」 さらに、表紙の裏にはさんであった封筒には、だれかフランス人が書いたと思われる授業料のメモらしい数字と名前の下に、あのころの私の角ばった大きな字体で、サンテグジュペリからの言葉が記されていた。「大切なのは、どこかを指して行くことなので、到着することではないのだ、というのも、死、以外に到着というものはあり得ないのだから」》アン・リンドバーグを描いたエッセイ「葦の中からの声」と、このサンテグジュペリを描いたエッセイ「星と地球のあいだ」を読んだ私は、須賀敦子に挑戦の矢の矢を放つのだ。 もっと見る
芸術家と共存する街づくり
2021/07/09 03:10芸術家と共存する街づくり塩谷陽子著「ニューヨーク──芸術家と共存する街」はもう十年も前に出版された本だが、ここに書かれていることは少しも古くなく、むしろこの本で指摘されていることはいよいよ日本と日本人は切実な問題として迫ってくる。日本の芸術は健在のように見える。あらゆる領域の芸術世界にスターが生まれ、さかんに興隆しているように見える。しかしそれはある一部のある特殊な例に過ぎない。その作品が売れてそれだけで食べていける芸術家は、それこそほんの一握りであって、大多数の芸術家は彼の作り出す作品だけでは食べていけない。大多数といったが、例えば、この日本には本物の画家はどのくらい存在しているのだろうか。少なく見積もっても一千、いや、そんな数ではなく、隠れキリシタンならぬ正体を隠した画家は数万人にのぼるかもしれない。私のいう本物の画家とは、絵を描くことで人生を貫こうと決意している人のことである。彼らはたとえその生涯に一枚の絵が売れなくとも画家であることをやめないだろう。彼らは神の声を聞いたのである。あなたはこの仕事を生涯をかけてやり抜きなさいと。それがあなたの天職なのだと(英語で天職をcallingという)。そういう本物の画家が、おそらくこの日本には確実に数十万人存在しているのだ。数十万という数は少しも驚く数ではない。人間はパンだけでは生きていけない。魂のパンもまた同様に食べていかねばならない。芸術家とはこの魂のパンを作る人たちのことである。一億二千万人の胃袋に食を提供する人々が、この日本には数百万人必要なように、一億二千万人の魂に作品を提供する芸術家は数百万人必要なのだ。農業者が数百万人存在するように、画家が数百万人存在しても少しも不思議ではない。芸術家を育てる街にさまざまな領域の芸術がある。音楽、映画、文学、演劇、ダンス、絵画、彫刻と。それぞれの領域でスターが生まれる。彼らの作品は売れ、その公演活動はいつも満席になり、何度もマスコミに登場して世の脚光を浴びる。しかしそんな彼らの背後に、何万何十万という本物の芸術家が存在しているということに、私たちの社会はもう気づくべきなのだ。彼らの作品は売れない。懸命に創造を続けるが、しかし一作も売れずにその生涯を終えるだろう。大半の芸術家がそうである。私たちの社会は、そんな彼らをけっして芸術家などとはいわない。彼らは人生の落伍者であり、敗北者なのだ。売れない芸術などに人生を浪費した屑であり、人間失格者なのだ。屑になりたくなかったら、さっさと撤退して、真面目なまともな社会人になれということになる。塩谷氏はこのことを鋭く提起しているのだ。どんな時代にも、どんな社会にも、芸術家は生まれる。芸術を天職とせよと天の声を聞いた芸術家が、今日もまたあちこちで誕生する。この日本には本物の芸術家は、数十万人、いや、ひょっとすると数百万人の数にのぼるかもしれない。社会はそんな彼らの存在を認め、芸術家として生きる権利を彼らに与えよということなのだ。これはどういうことなのか。塩谷氏は説明の導入としてエイズ患者のことを例に出しているが、社会が芸術家を向ける視線とエイズ患者に向ける視線が相似するからなのだろう。例えば、あなたの息子が高校を卒業すると、これからプロのバレーダンサーを目指して生きていくと決意表明したら、あなたの家庭は混乱するだろう。あなたの娘は美大を卒業して、画家になろうと毎日だらだらと、さっぱりわけのわからない絵を描いている。女の子だから、それはあなたの許容範囲だが、ある日その娘が、売れない彫刻家と結婚すると宣言したら、あなたの家庭は大混乱に陥るだろう。見識のあるあなたにしてからそうなのだから、日本の社会が芸術家に向ける視線は、さらに険しく、彼らが近辺に存在することさえ嫌悪するのだ。売れない芸術に人生を浪費している彼らは、人間の屑であり、人間失格者なのだ。こういう社会に「芸術家は、現代社会の中で、芸術家として生きる権利がある。だからその権利を守ってやる必要がある」という思想が、さらには「芸術は、教育や福祉とまったく同じに、コミュニティーが責任をもって扱う課題だとみなすべきものである」という思想を植え込んでいくにはどうしたらいいのか。建物ではなく人間に投資するこの新しい思想を打ち立てるために、ニューヨークの人と街で展開されているさまざまな活動がこの本で紹介されている。それらの活動を私の住む品川の街に引き寄せてみるとき、例えばこういうプロジェクトが組み立てられる。いま学校の教室がたくさん余っていて、廃校になる学校さえあるが、それらの空き教室や廃校になった学校を、芸術家たちに低料金で貸し出し、アトリエや練習場として使ってもらうといった取り組みである。あるいは廃業になった工場や倉庫や店舗がいたるところにあるが、それらの建物を行政が借りて、芸術家たちのアトリエとして提供していくといった取り組みである。町や村がその地域に文化を起こそうと、巨額の資金を投じて音楽ホールを建てたり、美術館を建てたりする。しかし文化とは建物が起こすのではない。建物にいくら巨額の資金を投じたって、文化など起こるわけがない。文化とは人間が起こすものであり、その地域に文化を起こしたかったら、文化を起こす人間に投資すべきなのだ。品川区にもたくさんの文化施設がある。すでに一千人を収容できるホールが大井町に、五百人を収容できるホールが荏原町に立っている。いまこの二つのホールは、たんなる貸しホールとして存在しているが、これからの時代、それぞれのホール専属の楽団や劇団やバレー団を養成していくべきなのだ。品川にはオーケストラだって、バレー団だって、劇団だって数多く存在している。彼らの公演活動を援護していく新しい思想に立った文化政策である。 もっと見る
生命の樹となって成長していく絵画
2021/07/04 18:41生命の樹となって成長していく絵画 二〇〇八年の九月から十月にかけて葉山の海岸に立つ神奈川県立近代美術館で秋野不矩(ふく)展が組まれた。その展覧会に足を運んだ私は、展示室に入りその最初に展示された絵に釘づけになった。こういう体験はひさしぶりだ。こういう出会いをしたくてさまざまな展覧会に足を運ぶが、たいていは空振りで、なにか徒労の時間を費やしたといった思いになるのだが、しかしその「朝露」と題された日本画は私を釘づけにした。その母の像は背中だけ、横顔さえ見せていない一時期、明治という新しい時代に、岡倉天心たちが起こした芸術運動を小説にしようと、天心のもとに集まってきた画家たち、横山大観や菱田春草や下村観山などの絵をずいぶん熱心に見て回ったことがある。しかし次第に彼らの絵のフラットさ──画面を平面的に造形していく手法に、物足りなさを感じるようになっていった。画面が大きくなればなるほど、空間処理の部分がより広くなり、その主題とする平面的な絵は、いよいよ空疎といわないまでもフラットになる。油絵は絵の具を重層的に塗りあげていく。遠近法を駆使して、光と影の陰影を深くして立体的に造形していく。そんな油彩画のもつ重量感や存在感に比べるとき、平面的に画面を造形していく日本画はどうもフラットに映るのだ。その「朝露」もまた対象を平面でとらえる典型的な日本画だった。朝顔の蔦が花をつけて竹格子を這っている。その朝顔を背景にして、下駄を履いた和服姿の若い母親が、幼児を抱いて立っている。縦二メート七十センチ、横一メートル六十センチの画面である。しかしこの絵はフラットではない。画面は気品をたたえ、豊かさにあふれ、濃密な存在感がある。母子像をヨーロッパの画家たちもたくさん描いていくつもの名画があるが、この「朝露」はそれら油彩で描かれた歴史的名画に少しも劣らないばかりの感動を観る者に与える。母親が抱いている幼児は、母親の肩越しにこちらを向いている。その母親の像は背中だけ。彼女は横顔させ見せていない。画面に描かれているのは、黒に近い濃紺の和服に、ネイブルスイエローというのか枯葉色の帯をきりりと締めた後姿なのだ。しかし見る者にこの女性のやさしさや、強さや、英知や、凛とした意志がみえてくる。画家は子供を抱いた母親の背中を描くことによって、その女性の内部を描いているのだ。それはまた画家自身の内部を描きだすことだった。この絵が放つ、高さと、深さと、気品と、決然たる強い意志。白い画面に立ち向かう画家の高い志を描いている絵なのだ。カタログを見ると二十五歳の作とある。秋野はその若さですでに完璧と思えるばかりの日本画の技量を確立していたのだ。インドが創造力と想像力を爆発させたその初期の作品のあとに、がらりと変貌した子供や若者たちを描いた絵が並ぶ。同じ画家仲間と結婚して子供が次々生まれ、その子育てに奮闘していた時代の作品である。子どもたちは少年少女になり、やがて青年になっていく。彼らの成長する姿を描いたそれらの絵は、若くして確立したいわゆる風雅な日本画のスタイルを、なにやら完全に放擲してしまっているような絵だ。彼女の三十代、四十代、五十代、そして六十代の作品がほとんど展示されていないからただ推測するのみだが、だれよりも彼女は日本画のもつ限界に気づき、その限界を突き破ろうと血まみれの格闘をしていたのではないのだろうか。油彩画のもつ存在感と生命力を岩絵の具でいかに造形していくのか。少年たちを描いたそれらの絵にその苦闘の痕跡がとどめられているように見えるのだ。その部屋を抜けると展示会場は一気にインドを描いた世界に入っていく。彼女は五十五歳のときに、インドの大学に客員教授として招聘されるのだが、その一年間のインドでの生活が彼女の絵画を劇的に変貌させていく。それは変貌と呼ぶべきものではなく、大きな魂と破格の技量をもった彼女はインドと出会うことでとうとう解放された、あるいはインドという大地が彼女を救い出したということかもしれない。彼女の内部でくすぶり続けていた創造と想像のマグマが吹き上げ、圧倒的な黄色の世界を作り上げていったのだ。縦一メートル四十センチ、横三メートル六十センチの大画面である。黄濁した河面は黄金に染まり、その濁流のなかを家族であろうか、十二、三頭の水牛が大河を渡っている。水牛は角しか水面に出していない。画面を占めるのは圧倒的な大河の流れである。この大画面はフラットではない。存在感と生命力がみなぎっている。この絵はもはや日本画という範疇でとらえる絵ではない。これこそ秋野が目指してきた世界だった。若くして日本画のスタイルを確立し「朝露」や「姉妹」や「紅裳」のような傑作の森をつくりだした。しかしそのとき同時に誰よりも深刻に日本画の限界に直面したのであり、その限界を打ち破らんと苦闘してきた長い年月があった。「渡河」はその苦闘の果てに出現させた世界だった。力を秘めた絵画は見る者に対決を迫る。見る者の精神に衝撃をあたえ、魂までも揺さぶる。カタログをみると一九九八年作とある。なんと秋野八十六歳にして取り組んだ作品である。膨大な作品が火災で灰になってしまった秋野不矩の全貌を伝えんとするその回顧展に、画家がもっとも苦闘したであろう三十代、四十代、五十代、そして六十代の作品がほとんどない。いったいこの欠落は何を意味するのか。その疑問はカタログをみて腑に落ちた。二度も火災に会っているのだ。最初の火災に見舞われるのは六十三歳のときである。そのとき彼女の作品が一瞬にして灰になってしまったのだ。家や家財が焼け落ちたのはあきらめがつく。しかし彼女の生命そのものであった作品群がことごとく灰になってしまったことに、彼女はどれほどの衝撃をうけたであろうか。さらに六十六歳のときに二度目の火災にあって、ここでもまた作品が失われた。創造はつねに破壊することからはじまっていく。それまでの創造を打ち破らなければ新しい創造は生まれない。この火災は彼女にそういう決意をさせたのであろうか。これでさばさばした、ここから新しい出発だと。秋野はその火災こそ、彼女の画業を結実させていく新しいスタート地点に立ったと思わせるばかりだ。事実、葉山の美術館での一大回顧展は火災後の作品がしめることになる。この回顧展はまた次のことを私たちに気づかせる。彼女は若くして名声を確立していたのに、その絵がほとんど売れていない、彼女は本質的に売れない画家であったという事実に。「朝露」は二十代半ばに描いた傑作である。その時代に会場に展示されている「朝」「姉妹」「砂上」「紅裳」といった傑作の森を作り出している。それらの作品をいま私たちが見ることができるのは、その絵が売れていたからである。売却されて、売却された場所に展示されていたり所蔵されていたりした。だからその絵を私たちは見ることができる。しかし三十代から六十代までの作品はほんどと展示されていない。おそらく私たちを魅了するいくつもの大作や、珠玉のような小品の群れがあったに違いない。しかしそれらの絵はほとんど売れなかったのだ。売れない絵は自宅に所蔵しておく以外にない。二度の火災がそれら膨大な作品群をすべて灰にしてしまったのだ。なんという損出であろうか。彼女の絵と彼女の画家としての存在が、ようやく画壇という小さな世界から広く社会に認められていくようになるのは、八十歳を超えたあたりからである。そして九十歳のとき文化勲章を受ける。彼女は一躍時の人となりマスコミの脚光をあびていく。そのときから彼女の絵は飛ぶように売れていったのだろうか。インドの大地を描いた大作群が破格の値で売られて、それらの絵がさまざまな場所で展示されたり所蔵されたりするようになったのだろうか。いまカタログを見るとき、展示会場に展示された作品群の所蔵先は、そのほとんどが浜松市秋野不矩美術館蔵とある。ということはその大作群もほとんど売れていなかったことを語っていることである。彼女もまた売れない画家の一人だった。生命の木となって成長していく絵画秋野の六十代までの作品は二度の火災でことごとく焼失してしまった。二度あることは三度あるものだが、スプリングラーなどが完備した彼女の美術館が誕生することによってその心配もなくなった。その作品は何重にも警護されて、展示室に展示されたり所蔵庫に保管されたりしている。これで残された彼女の絵はひとまず安全に次の時代に引き継がれていく。彼女の絵が見たくなれば、いつでもその辺境の地に立つ美術館を訪ねればいいのだ。しかしそれでいいのだろうか。彼女の絵はその小さな美術館にひっそりと閉じ込めておいていいのだろうか。大半の画家たちの作品は、作者があの世に去ると死蔵されるか忘却の底に捨てられる。それは時代をにぎわしたベストセラー作家の作品だってその例に漏れない。しかし秋野の絵はちがう。彼女の絵はぐんぐんと成長していくのではないのだろうか。木立が年輪を刻みこんで、その幹をいよいよ太くさせ、超然と何百年と生き続けるように。生命力をもった絵画は歴史とともに成長していくのだ。私はその会期中に二度ほど葉山の美術館に足を運んだが、入場者の大半が高齢者たちだった。なるほど九十三歳まで力みなぎる創造を続けた秋野の絵に高齢者たちは魂がふるえるほど感動する。しかしその感動は青年たちこそ体験すべきことではないのか。自分の信じた道をあきらめずに歩いて行けと。どんな苦難にもうろたえることなく自分の道を歩いて行けと。彼女の絵は大望を抱く青年たちを力強く励ますに違いない。子供たちだって彼女の絵の前に立つべきではないのか。絵を描くとはきれいに美しく描くことではない。絵を描くとは自分を表現することなのだ。白い紙の上に思いのままに自分を表現する。どんなに下手でもいい。そんなことは問題ではない。そこにしっかりと自分が表現されている絵こそ絵というものなのだ。彼女の絵は子供たちに絵を描かせる力を与えるはずだ。インドに行きたいという声が聞こえたすぐれた芸術がなぜ時代とともに生き、歴史とともに成長していくのか。それはその芸術の前に立つ人々の魂の波動や血液がその芸術の中に流れ込んでいくからなのだ。それは音楽を見ればよくわかる。バッハはなぜ現代に脈々と生きているのか。モーツアルトやベートゥヴェンがなぜ日々新しくなって私にたちのなかに流れ込んでくるのか。それは彼らの音楽が、常に新しい時代の新しい世代の演奏者によって新生の血液を流し込まれるからだ。演奏者たちだけではない。コンサートに足を運び、ラジオやCDでその演奏に聴くおびただしい人々の魂の律動がまたその音楽に流れ込んでいく。バッハやモーツァルトやバートゥエベンは常に新しい。永遠の生命をたたえて人類の歴史を生きていく。それは絵画だって同じことだ。セザンヌやゴッホの絵の前にいつの時代でも無数の人々が立ち、その人々の生命の律動や新生の血液がその絵に流れ込んでいく。秋野の絵はインドにいきたいと、ささやき、うめいていないだろうか。インドを描いたその大作群をインドの人々に見てもらいたいと。彼女の画家としての魂はインドと出会うことで解放された。インドが彼女を救い出したのである。彼女の絵がインドに渡りたいと迫るのは当然のことだった。そのささやき、そのうめき声をたしかに聞きとった秋野不矩美術館のスタッフは、その声を実現すべく奮闘すべきなのだ。美術館の運営を担うスタッフの仕事は、所蔵する絵を管理し保管し展示するだけではないのだ。所蔵庫に絵を眠らせることは死蔵することにつながる。それは作品の生命の呼吸を止めてしまうこと。秋野の絵はぐんぐんと成長を続けている、そしてインドに渡りたいと叫んでいるのだ。ならば美術館のスタッフは、インドの主要都市、ニューデリーの、カルカッタの、カラチの美術館を巡回する展覧会に取り組むべきなのだ。インド各地の都市を巡回した彼女の絵は、インドの人々を虜にするだろう。するとその成功は世界から注目を浴び、競って彼女の絵が世界各地の美術館から招聘されるだろう。パリで、ロンドンで、ベルリンで、上海で、そしてニューヨークで彼女の大規模な回顧展が開かれる。彼女の絵は日本画という領域を打ち破った絵画だった。彼女の絵は国境を越えて成長していく木立である。秋野不矩は世界の人々に愛される《FUKU AKINO》となる日がやがてやってくる。「渡河」が百七十億円で売却されたさらにこういう現象もおこっていく。世界各地の美術館から秋野不矩の絵を譲ってくれないだろうかと打診される。その話を具体化させる使者たちもやってくる。それらの動きを察知した画廊主たちも暗躍しはじめ、やがて秋野の絵はニューヨークやロンドンのオークションにかけられ、高額な値がつけられて売られていく。新しいポリシーをもつ秋野不矩美術館長は、とうとう彼女の最高傑作である「渡河」もオークションに出してしまった。その絵にいったいどのくらいの値がつけられるのだろうか。二〇〇六年にジャクソン・ポラックの「NO5」が百七十億円という値で売却された。「渡河」もまたそのくらいの値がつくだろう。なにしろ世界の《FUKU AKINO》である。そんな値がついてもおかしくない。かくて「渡河」は売却されて海を渡ってしまった。こういう決断をした館長に、猛烈な批判が巻き起こるにちがいない。秋野不矩美術館は商売を始めた。秋野の最高傑作を売り払ってしまった。秋野芸術を冒瀆する行為である。天上にいる秋野は嘆き悲しんでいると。しかしそうだろうか。むしろ秋野は会心の笑みを浮かべているのではないのだろうか。最後には勝つと生きてきた彼女の作品群が、かくも高額な値で売られ、世界に広がっていくなど想像することさえできなかったが、しかしこれでようやく自分のしたかった次なる事業に取り組めると。館長はこの秋野の声を聞きとっていたのだ。手にした百七十億円でなにをはじめるのか。芸術家たちを援護するための秋野不矩財団をつくるのである。売れない画家たちに奨学金を出したり、作品を買い上げたり、彼らの作品を世に送り出すシステムをつくったりと、苦闘する彼らを援護する財団である。百五十億円もの資金があれば、千人の若い画家たちを援護できるだろう。秋野は教育者でもあった。若い画家たちを育ててきた半生でもあった。芸術家は次の時代の芸術家たちを援護していかねばならない。もし自分の絵が高額で売却されたら、その金は若い画家たちを援護する資金にすべきなのだということを覚知していたはずである。館長は彼女のそんな声をたしかに聞きとったから、断固として「渡河」を百七十億円で売却したのだった。 もっと見る
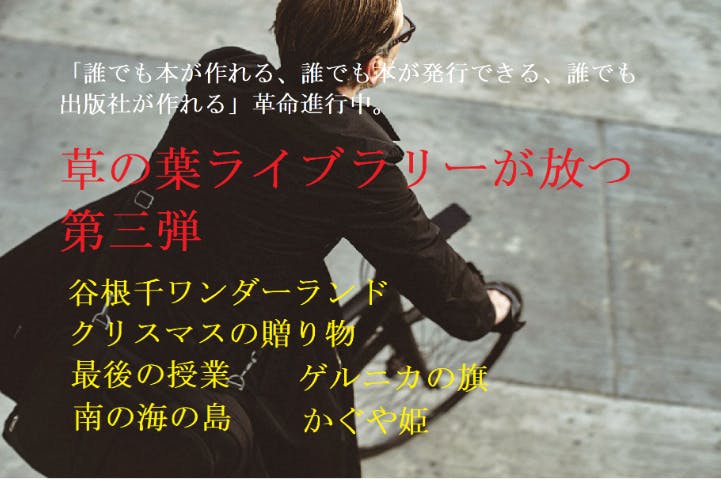


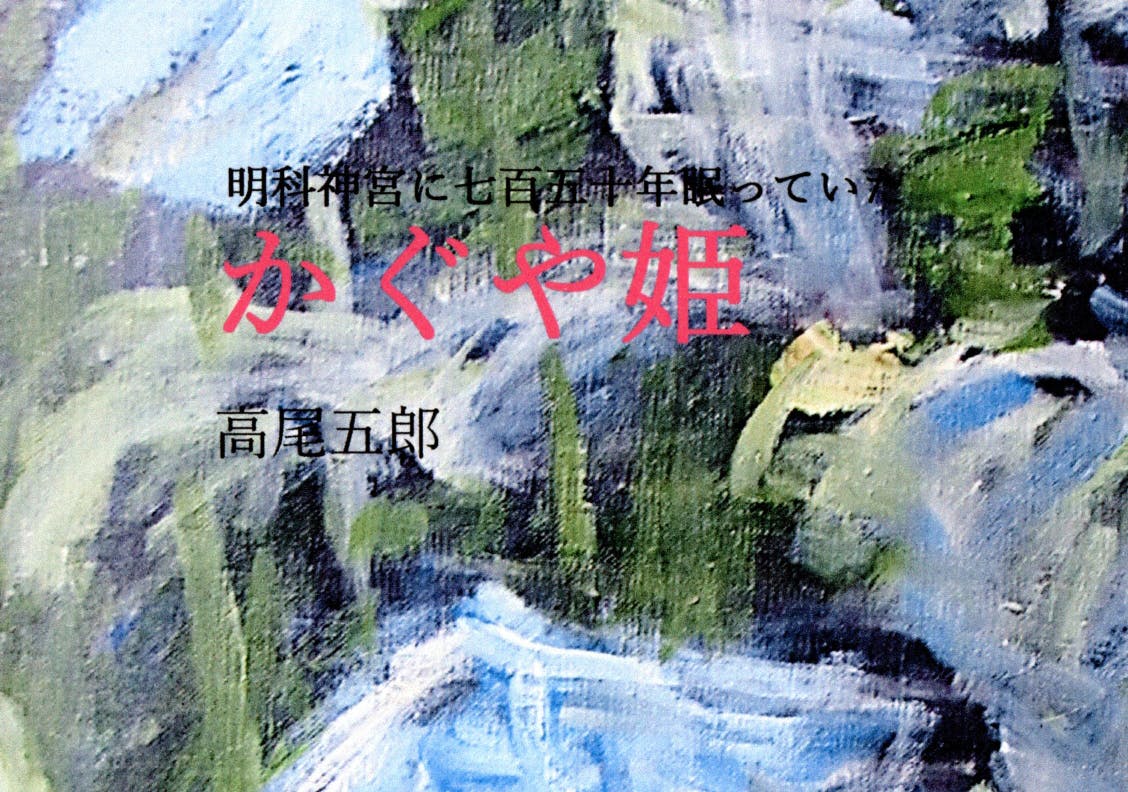












コメント
もっと見る