誰でも本が作れる
誰でも本が発行できる
誰でも出版社が作れる革命
草の葉ライブラリーは、たった数部しか売れない本に果敢に取り組み、独自の方式で読書社会に、毎月、一冊、また一冊と投じていきます。閉塞した社会に新たな生命の樹を打ち立てる本です。地下水脈となって永遠に読み継がれていく本です。
売れる本しか刊行しない、売れる本しか刊行できない現代の出版のシステムに反逆する、旧時代的な手づくり工法によって、真の価値をもった作品が一冊の本となって誕生します。そしてクラウド・ファンディングによって、その本を真に欲している人に手渡されていきます。
「誰でも本が作れる、誰でも本が発行できる、誰でも出版社が作れる」革命によって「誰でも本が作れる、誰でも本が発行できる、誰でも出版社が作れる私塾」が誕生した。

高尾五郎著 山に登りて告げよ
悲劇のどん底に投げ込まれる弘。分校の存在理由に苦しむ智子。風雲急を告げる長太。三人はどこに流れていくのか。小さな人間の小さなドラマを、三十六の短編に積み上げて描く現代の叙事詩。その第三部。

第一章 手の素描
この手紙があなたの手に渡る頃には、ぼくはニューヨークにいるはずです。ソーホーの安ホテルに泊まって、部屋探しに明け暮れているでしょう。やっと本物の芸術家の魂をつくりだすことに挑戦する時間を持つことができたということでしょうか。当分のあいだ日本に戻らないつもりです。十年、いや二十年、いやひょっとするとぼくはもう永遠に日本にはもどらないかもしれません。この国を捨てて、かの国でぼくの樹を打ち立てるという覚悟で新天地に渡っていきます。
第二章 愛の挨拶
ぶらりと分校を訪ねてきて智子や子供たちに鮮烈な印象を残した茜は、それから一週間ほどしてまたぶらりとあらわれ、また一日中、子供たちと遊んでいった。明日もまたきてよねと子供たちの熱い声に送られて、その日は別れるのだが、しかしその翌日にも次の日も姿をみせず、もう茜はこないとみんなあきらめていたら、またぶらりとあらわれる。その間隔がだんだん短くなって、とうとう茜は分校に入学した。
第三章 健太
健太の家は、国道の裏に立っているマンションのなかにあった。階段をあがって三階にあるその部屋にいってみると、ドアから健太の弟が姿をみせて、親はいないと言った。どこにいってるかも分からないと言うのだ。親が子供にぴたりと貼りついて、その一挙手一投足まで見張られている家庭の子供たちもつらいが、またこういう底なしの放任家庭も問題だなあと弘は思うのだった。
第四章 She not goes does to school
英語は希望を語る言語であった。愛を歌う言語であり、嘆きや悲しみ怒りの叫びをあげる言語であった。小さき者たちが、圧制の帝国から立ち上がる抵抗の言語であった。英語というものは誇り高き民族の言語であったのだ。中学校の授業によって、ひたすらけちくさい言語におとしめられていたその英語を、洋治は長太の仕組んだその授業によって、その力と生命を蘇らせたのだ。
第五章 北海道遠征
明彦たちを送り出すと、七人はテレビの前にすわりこんで第一回の遠征を記録したビデオを見ていた。するとそこに正憲がやってきた。はげしい雨のなかを、学校が終ってかけつけてきた彼の全身は、びしょ濡れだった。彼はけわしい顔を智子にむけて、けわしい声で言った。
「こいつら、なにやってんですか」
第六章 復讐は私のする仕事
来る日も来る日も悶えのなかにあった。子供団がどんなに深く彼の生命のなかに根をのばしていたかを知るのだった。苦しかった。どこかでこの苦しみから抜け出したかった。彼は聖書を手にしていた。そしてある言葉を探していた。以前その不思議な言葉に触れたことがあったが、そのときその言葉がよくわからなかった。しかしなにかひどくひっかかる言葉だった。その言葉はロマ書のなかにあった。
第七章 ガレージコンサート
彼の横に愛が座っている。彼がずうっと夢みた愛が座っているのだ。彼の胸はなにか恋人の隣りにすわったようにどきどきしている。彼はしきりにその手をのばそうとしていた。そのかわいい手を握りろうとしていた。彼はおそるおそる手をのばした。拒絶されるかもしれなかった。しかしその手は逃げなかった。その小さな手もまた長太の手を求めるように、しっかりと握りかえしてくるのだった。
第八章 父と子
分校に入学すると、みんなの前で、自己紹介することになっていた。横田貴之は、両手でピースのサインをつくり、ひょうきんさを全面にだして、みんなの受けを狙うかのような挨拶をした。「……それと趣味とかですが、そういうのはあんまりなくて、ファミコンとかするけど。それから、あんまり趣味には関係ないけど、むしゃくしゃしたときには妹をぶっとばすとか、おやじとかおふくろをバッドでぶんなぐるとか……
第九章 山に登りて告げよ
弘は思った。なぜ宮沢賢治はかくも童話にこだわりつづけたのか。彼は詩人だった。難解な詩を書きつける詩人だった。文明論や農業論を書き上げる力も持っていた。宗教文学だって書ける力量を持っていた。しかし彼は童話を書き続けた。それはおそらく童話こそ文学の核心だったからにちがいない。芸術の核心であり、人間の魂の核心がそこにあるからだった。
透明な風が吹き渡る──服部みずほ
「ゼームス坂物語」の一部と二部から私はたくさんのフレーズをノートに写しました。子供たちの姿を見失ったとき、教師としての自信を失った時などによくそのノートを開き、そのフレーズを指でなぞるように味わいます。教師の姿勢や、教育のあり方を根源的ところで問いかけてくるからです。
第三部もまた魅力的な子供がたちがたくさん登場してきますが、なかでも茜さんってなんて素敵な少女なのでしょうか。本当に透明な風が吹き渡っていきました。望月先生に次々に襲いかかる悲劇。もう息も止まる思いでした。弘さんはこの悲劇の底からどのようにして立ち直っていくのでしようか。現代という時代に翻弄される三人。しかし押し寄せる荒波に真っ直ぐ立ち向かい、新しい道を切り開いていこうと英雄的な戦いをする三人。これはまさしく現代に叙事詩です。第四部が待ち遠しく仕方がありません。(小学校教師)

高尾五郎著 最後の授業
伝統ある公立中学校に通う三年生の瀧沢隆君が、自宅の納屋で首を吊って自殺した。遺書を残しての覚悟の自殺だった。この遺書を、瀧沢君の通う中学校の篠田政雄校長は、「貧しい幼稚な遺書です」といった。なぜ篠田校長は、瀧澤君の書いた遺書ほ貧しい幼稚な遺書だと言ったのか。日本の教育の核心に迫っていく名作である。

これは北アルプスの麓に広がる安曇平という地のある町でおこった出来事です。すでにみなさんはその町の名前を知っていますね。あれだけ騒がれた事件ですから。ですからその町の人々にはとてもつらいことですから、その町の名をA町としておくことにします。その町の名をつけた中学校もまたやはりA中学校としておきますが、この中学校は信州教育と尊敬をこめてよばれる数々の実践活動を生みだしていった古い輝かしい歴史をもった学校でした。この中学校に通う瀧沢隆君という中学生が、自宅の納屋で首を吊って自殺するという痛ましい事牛がおこったのでしたね。
残念なことに、まるで流行のように、子供たちがあちこちで自殺しています。子供たちの自殺があまりにも頻繁に起こるので、いまでは新聞記事にもなりません。しかしこの隆君の自殺事件はちがっていました。連日にわたって新聞もテレビも週刊誌も、なにかヒステリ一をおこしたと思われるばかりの騒ぎかたでした。どうしてこんな騒動に発展していったかといいますと、その事件を取材するためにつめかけた地元記者たちが、その学校の校長先生を取り囲んで、
「隆君は遺書の残していますが、この遺書を先生はどう思っていますか」
とたずねたのです。その学校の校長先生は篠田政雄といいましたが、そのときその篠田校長は、なにか吐き捨てるように、
「こんな貧しい遺書で死ぬなんてあわれです」
といったのです。驚いた記者たちは、
「貧しいですか?」
「貧しくて幼稚な遺書です」
「幼稚なんですか?」
「これが幼椎でなくてなんなのでしょうか。こんな幼稚な遺書で死んでいく子供はあわれにつきます」
校長先生はさらに取材を続けようとつめよる記者たちをかきわけて、逃げ込むように校門に消えていったのですが、そのときその一部始終をテレビ局のクルーが音声とともにしっかりと録画していたのです。その映像とその会話が、各テレビ局に配信され、日本中にそのシーンがそれはもう繰り返し繰り返し放映されていったのでした。
翌日の新聞も一斉にこの事を報じました。社会面を二面もつぶし、さらに社説までにとりあげて、校長先生の言動をはげしく非難するのでした。凄まじいのはテレビでした。昼のワイドショーで、夕刻のニュースショーで、さらには深夜のニュース番組で、いずれもトップニュースとしてこの事件を報じるのでした。
いったいこの事件をマスコミはどのように報じていったのでしょうか。そのあたりをある日の昼のワイドショーを子細に再現してみましょう。いかに日本中がすさまじい騒動の嵐につつまれたかがわかろうというものです。
まずその画面に重々しい悲しみの音楽がながれて、隆君の遺書が写し出されます。その遺書を声優が悲しみをこめて読んでいきます。
「お父さん、お母さん、由香、それとぼくの大好きなおじいちゃんおばあちゃん。ぼくが死ぬことをゆるしてください。ぼくはもう生きていくことはできなくなりました。もうつかれました。とても生きていく力はありません。HYSFNにもうぼくはつきあえません。ぼくはもう二度ほど死ぬ目にあっています。二年のときは日本海で死ねといわれたし、またこのあいだの台風のあと犀川横断のときも死にそこないました。だんだんバツゲームもひどくなって、今度はT先生の部屋をおそうなんてぼくにはできません。ぼくはHたちにつきあうのはもうつかれました。ぼくはいままで六十万たまっています。いつかぜったいに返そうと思っていましたが、返せなくなってごめんなさい。お父さんとお母さんにはいろいろと感謝しています。由香はぼくのぶんまでお父さんとお母さんを大事にして下さい。おじいちゃん、おばあちゃん、いつまでも元気でいてください。ぼくはみんなが大好きでした。ぼくが死ぬことをどうかどうかゆるしてください」

高尾五郎著 実朝公暁
実朝は殺された。しかし彼の詩魂は、自分は自殺したのだというのかもしれない──小林秀雄
健保七年(一二一九年)の一月、実朝は暗殺された。この事件の謎は深い。実朝を暗殺した公暁が、いかなる人物であったかを照射する歴史資料が、無きに等しいところからくる。しかし『吾妻鏡』をなめるようにあるいは穴の開くほど眺めていると、この公暁がほのかに歴史の闇のなかから姿をみせてくる。
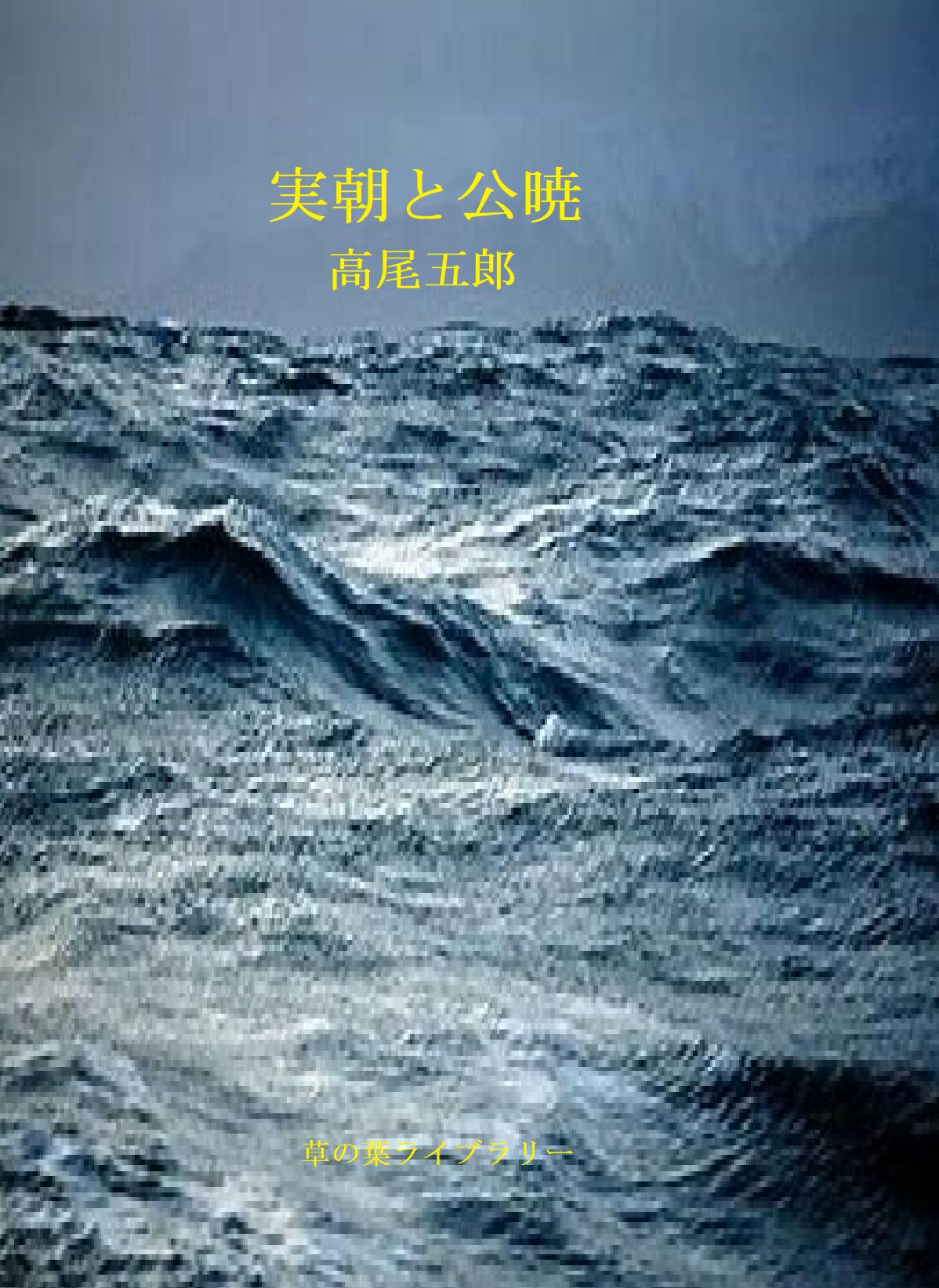
序の章
源実朝は健保七年(一二一九年)正月二十七日に鶴岡八幡宮の社頭で暗殺された。この事件の謎は深い。フィクションで歴史を描くことを禁じられている歴史家たちにとっても、この事件はいたく想像力をかきたてられるのか、その謎を暴こうと少ない資料を駆使して推論を組み立てる。しかしそれらの論がさらに謎を深めるといったありさまなのだ。それもこれも、実朝を暗殺した公暁がいかなる人物であったかを照射する歴史資料が無きに等しいところからくる。
しかし鎌倉幕府の公文書とでもいうべき『吾妻鏡』を、なめるようにあるいは穴の開くほど眺めていると、この公暁がほのかに歴史の闇のなかから姿をみせてくるのだ。というのもこの『吾妻鏡』のなかに「頼家の子善哉(公暁の幼名)鶴岡に詣でる」とか「善哉実朝の猶子となる」といったたった一行のそっけない記事が記されていて、それもすべてを並べたって十行余にすぎないが、しかしそれらの一行一行の奥に隠された公暁の生というものに踏み込んでいくとき、そこから公暁はただならぬ人物となって現れてくるのだ。
それは歴史学者たちが好んで描く、実朝暗殺は幕府の重臣たちの権力闘争であったとか、北条一族が権力を握るために公暁に暗殺させたとか、公暁が狂乱の果てに起こした刃傷沙汰だったといったことではなく、なにやら公暁なる人物が、主体的意志をもって時代を駆け抜けていった事件、公暁が公暁になるために──すなわち鎌倉に新しい国をつくるために画策した事件であったという像が、ほのかに歴史の底から立ち上ってくるのだ。
したがってこの謎に包まれた事件に近づいていくには、暗殺の首謀者である公暁を、どれだけ歴史のなかから掘り起こしていくかにある。もし公暁に生命を吹き込むことに成功したとき、私たちははじめてこの歴史の闇のなかにかすかであるが、一条の光を射し込ましたということになるのであろう。

リターン

高尾五郎著 山に登りて告げよ A4版 300ページ
頒布価2500円 送料370円

高尾五郎著 最後の授業 A4版 220ページ
頒布価2000円 送料180円
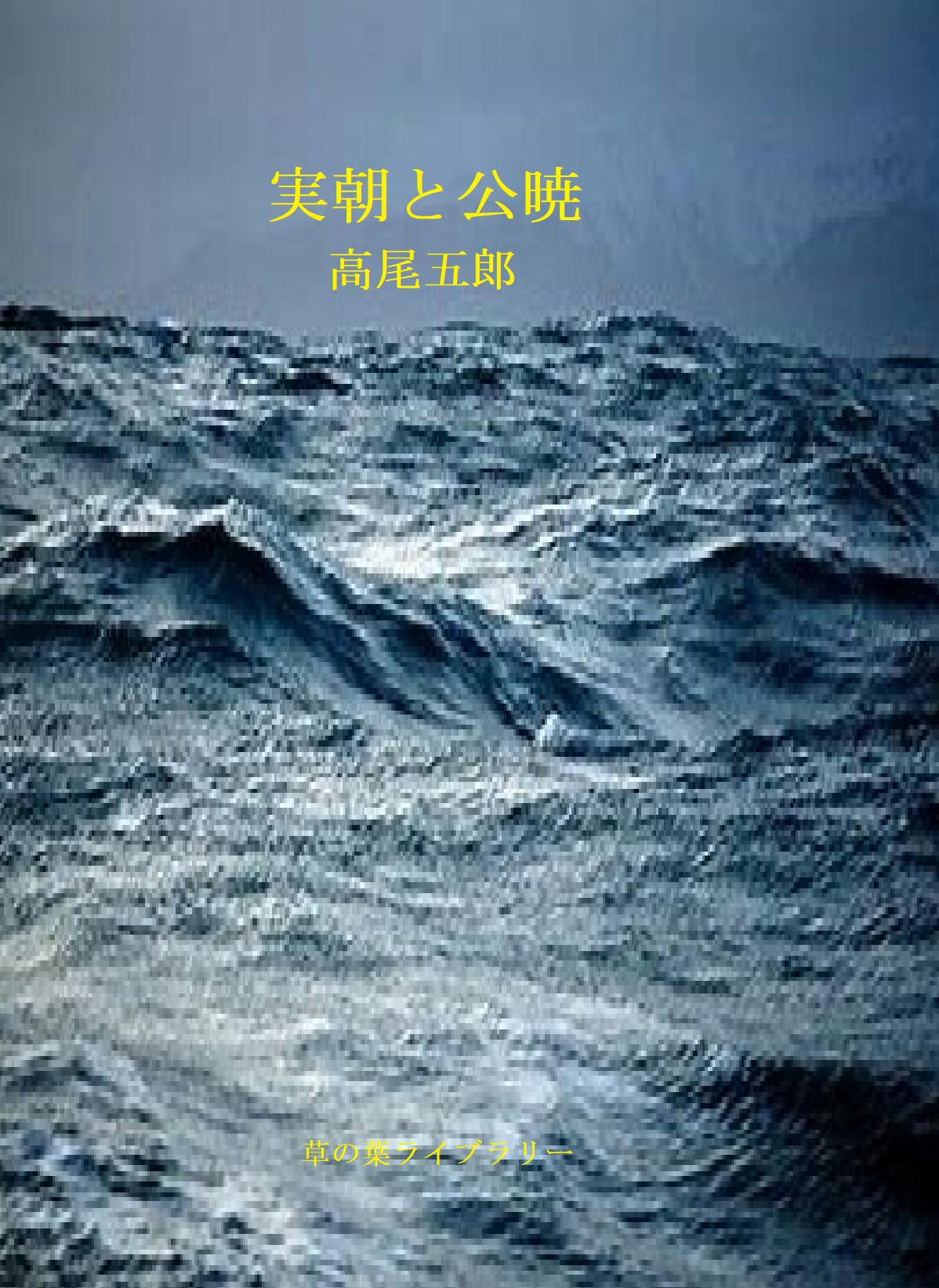
高尾五郎著 実朝と公暁 A4版 300ページ
頒布価2500円 送料370円
集めた支援金の用途と内訳
CAMPFIRE手数料
草の葉ライブラリーの本の製作費
著者への印税
 画像キャプション
画像キャプション
誰でも本が作れる
誰でも本が発行できる
誰でも出版社が作れる革命
毎年おびただしい本が刊行される。それらはすべて採算が取れると踏んで刊行されるのであって、少なくとも数千部、さらに数万部の大台にのせ、あわよくば数十万部を目指し、その究極の目標がベストセラーである。本は売れなければならない。売れる本だけが価値をもたらす。売れる本によって彼らの存在が確立されていくからである。これがこの世界を絶対的に支配している思想でありシステムであり、したがって数百部しか売れない本は価値のない本であり、数十部しか売れない本は紙屑のようものであり、たった数部しか売れない本は鼻くそみたいに本ということになる。
しかし本というものは、食料品でも、商品でも、製品でもなく、まったく別の価値をもって存在するものであり、たった数十部しか売れなかった本が、数十万部を売った本よりもはるかに高い価値をもっていることなどざらにあり、数百万部のベストセラーなるものの大半が賞味期限がきれたらたちまちごみとなって捨てられるが、たった五部しか売れなかった本が、永遠の生命をたたえて世界を変革していくことがある。
この視点にたって創刊される草の葉ライブラリーは、たった数部しか売れない本に果敢に取り組み、独自の方式で読書社会に放っていく。荒廃していくばかりの読書社会に新たな生命の樹を打ち立てる本である。閉塞の世界を転覆させんとする力動をもった本である。地下水脈となって永遠に読み継がれていく本である。これら数部しか売れない本を読書社会に送り出していくには、数部しか売れない本を発行していくシステムを確立しなければならないが、これは簡単なことだ。その制作のシステムを旧時代に引き戻せばいいのだ。グーテンベルグが開発した活版印刷が登場する以前の時代の本づくりに。
出版のシステムを旧時代の手作り工法に
旧時代の本とは手書きだった。手書きで書かれた紙片を綴じて一冊の書物とした。その書物を人がまた書き写し、その紙片を束ね、表紙をつけて綴じるともう一冊の書物になった。こうして一冊一冊がその書物を所望する人に配布されていった。この手法ならば売れない本を発行するシステムが確立できる。作家たちが膨大な時間とエネルギーを投じて仕上げた作品を、コンピューターに打ち込み、スクリーンに現れる電子文字を編集レイアウトして、プリンターでA四紙の裏面に印字する。それを二つ折して中綴じホチキスで止めると一冊の冊子──ブック──が出来上がる。その工程はすべて手作りである。その一冊一冊が工芸品を作り上げていくかのように、その本を注文した購読者に送付されていく。
大量印刷技術によって、採算をとる経済によって、多層なる販売流通によって、売れる本しか刊行しない、売れる本しか刊行できない現代の出版のシステムに反逆する、古代的な手づくり工法によって、真の価値をもった作品が新たな生命力を吹きこまれて一冊の本となって誕生する。そして二十一世紀の初頭、アメリカに誕生したクラウド・ファンディングによって、その本を真に欲している人に手渡していくのである。
生命の木立となって成長していく草の葉ライブラリー
現在の出版のシステムは、その本を読書社会に投じたらそれで完了である。一度出した本を再編集して投じるなどということはめったに行われない。出版社は絶版の山を築いていくばかりである。大地を豊かにする名作がこうして捨てられていく。
ゴッホの絵がなぜいまなお脈々と生命をたたえているのか。それは繰り返し彼の絵が展示されるからである。なぜモーツアルトの音楽がいまなお人々に愛されるのか、それは繰り返し演奏されるからである。生命力をたたえた本は、繰り返し新しい世代に向けて発行していくべきなのだ。新しい編集がなされ、新しい体裁によって繰り返し刊行されていく。新しい時代の生命をその本に注ぎ込むことによって、その本は時代ともに成長していく。


最新の活動報告
もっと見る北の果て、一人生きる、漁師92歳
2023/05/17 15:00北の果一人いきる 漁師 92歳 北海道礼文島人里はなれた島にある集落があります。暮らしているのはたった一人。浜下福蔵さん、91 歳。漁師として海とともに生きてきました。長いあいだ福蔵さんが続けてきたことがあります。自然への想い、消えいく故郷(ふるさと)の記憶を詩に残す。「自分の命がある限りといえば変だけどなあ、命があるから書けるのよ」夏風に負けずに咲いた花の美しさあの花は何と言う力強いものがあった俺もあのようにして生きたい日本海にうかぶ礼文島。人口およそ2700人。漁業がさかんな島でした。福蔵さんが暮らす鮑(あわび)古丹は強い風と荒波が打ち寄せる島の北端にあります。5月「ああ、風あるなあ」福蔵さんは91回目の春をむかえました。毎日自宅前の高台から海を見下ろします。「いやあ、今日もまだ吹いてる、明日は南東の風っていうだろうなあ」鮑古丹に生まれ育ち漁師となって70年あまり。杖が手放せなくなった今も毎日浜に出かけます。「これ、浜下さんの船ですか」「そうそう、うちのもんだ」今、鮑古丹の浜を使うのは、福蔵さんと離れて暮らす息子夫婦だけになりました。「カモメが一羽もいないと思ったら、いないはずだわ、食べる物がねえんだ、こんな食う物がねえところにいるわけねえな、なぜおれはいるんだ。不思議なくらいだ」水揚げも少なく、物寂しい島、かつては活気にあふれていました。明治から昭和にかけて、鮑古丹はニシン漁でにぎわいました。「ニシン漁にさ、青森とか秋田とか、百人ぐらいきたよ、にぎやかだった、話せば数かぎりなくあんけど、すばらしいところだった」父親のあとをつぎ、中学卒業後漁師になった福蔵さん。以来、鮑古丹の海とともに生きてきました。今、一つの歴史を閉じようとしている鮑古丹。最後の住人となった福蔵さんは、鮑古丹をかたちにしてきました。漁師日記と名づけた日々の記録、天気や海の様子、大自然に営みを書き続けてきました。「何日、何日、強風、何の風だって、それから(漁師日記を書いてから)、おれの一日がはじまるのよ」日記のあとから必ず書くのが詩です。長い時は二時間以上、納得いくまで書き続けます。「この部屋に入ったときは、なにも考えてねえんよ、こう外さ見て、太陽が光ったり、曇ったり、それについて書く。単純に発想するように心を運ぶ。ああ、今、太陽が光った」福蔵さんは、太陽の輝きを笑顔と感じました。太陽の笑顔、美しい俺も笑顔の 鮑古丹「どういう形で残るがわからないけど残したい。残したいから書く,自分の命がある限りと言えば変だけど、命があるから書ける。だけんども、字がついていっているかどうかはわからねえな、自分はおとろえてるからなあ、それでも書きたいんだなあ、うむ」浜に人影がありました。福蔵さんの長男裕司さんと、その妻の陽子さんです。五キロほど離れた別の集落で暮らしています。「タコ漁、きょう仕掛けて、明日揚げるのよ」毎年親子三人で操業していたタコ操業ですが、福蔵さんの姿がありません。「今年も行く行くと張り切っていたけど、足腰の回復が遅れているみたいで」実はこの春先から福蔵さんの足腰は悪化していました。この日も、夫婦が網を仕掛けている姿を高台から見守るしかありませんでした。翌朝。4時。福蔵さんは大きな決断をしました。「漁、行きますか?」「行かない、もう自分はダメだ、寒さがきついし、動作が鈍くてもうダメだ、波のあるときは、体かわさねばならねど、それもできない、漁師が沖に行けねえことはつらいことだなあ、みんな行くけど自分にはもういけない、朝早く起きて、海を見て、みんなと会話して、操業してたから、悔しくないと言えないけど、やっぱりさみしい」沖に向かったのは、息子夫婦だけでした。この日に境に福蔵さんは船に乗ることはありませんでした。大切なしてきた鮑古丹の海を息子夫婦に託しました。沖は強風操業注意漁師、君の大漁を祈るタコ漁を仕掛けた息子夫婦の船が浜に戻ってきました。水揚げが気になる福蔵さんが゛浜におりてきました。「どうだ、大漁か?」「タコ一杯だな。ソイはいつぱい入ったけど」「ソイは入った?」「ソイとタラかな」自宅に戻った福蔵さんは、詩を書き始めました。息子夫婦に言葉を送ります。祈る心に 二人を想え明日も働く北漁場大漁祈り 海を見るこの鮑古丹は美しい長い人生 輝けそして、福蔵さんは、漁をあきらめた自分自身への言葉も書きました。漁師の出漁出来ないのがさみしい働いた海と別れるゆくのが心に代わり 涙降る「さみしいとか、なんとか、もう度を超えてしまった、きようまであの船から降りたことはねえもん、三人でやった、なんぼ頑張っても自分の体はこれ以上動かない、動かそうと思っても動かない、詩をかくとなんとか、モノに例えて書いているけんど、本当の気持ちはそんなもんじゃねえよ、ああ、泣いた、泣いた」福蔵さんの目からもぬぐってぬぐっても涙があふれでてきます。 もっと見る世界一の翻訳の技
2023/05/15 06:00世界一の翻訳の技圧倒的な英語の襲撃を、翻訳者たちは烈しい気迫と情熱で立ち向かっていき、その英語をことごとく日本語のなかに取りこんでいった伝統は、今日でも脈々と引き継がれていて、外国語を翻訳する力、とりわけ英語を翻訳する力は群を抜いているのではないだろうか。アメリカやイギリスで出版された話題作やベストセラーは、ことごとく翻訳されて日本の読書社会に登場してくる。私たち日本人は世界のベストセラーが、瞬時に母国語で読める国に住んでいるのである。翻訳者がその原文に取り組むとき、記述が論理的に展開されていく本──政治や経済や科学技術や学術関係の本の翻訳は比較的容易なはずである。水は酸素と水素で成り立っているという論理が展開されている本ならば、その文章を機械的に即物的に日本語に転換していけばいいのである。ところが磨きに磨いて書き上げられたエッセイや小説や詩などはそうはいかない。それらの本は数式的に即物的に訳することができない。なぜならその文章には涙や怒りや祈りといった人間の感情のさざなみだけでなく、あたりの景観──光や影や風や空気や騒音や静寂が、さらにはその時代や歴史が縫い込められているからである。多様多彩な言葉の糸で織りこまれた布を、日本語の布に移し替えるのは容易ではないのだ。だからどんなに練達した翻訳者でも、その本のあとがきに「果たしてこの美しい原文が訳されたかどうか、はなはだこころもとない」と嘆くことになる。しかし日本の翻訳者たちは、これらの本を鍛え上げた技を駆使して、その原文の行間に、あるいはたった一行の文章の奥にただよわせる光や風や匂いや音までを、繊細微妙に日本語に織り込んで読書社会に送り出してくれる。さらに幸運なことに、日本人の琴線に触れる名作が新しい翻訳者によって新生の生命を吹き込まれて、繰り返し何度でも読書社会に登場してくる。このような国もまた世界に例をみない。原文と訳された日本語を交互に読むとき、読まなくともただ眺めているだけでも、ある不思議な現象がおきていくことに読者は気づかれたことがあるだろうか。そこに言葉の音楽が生まれるのだ。あるときはチェロソナタになり、あるときはバイオリンソナタになり、あるときはバイオリンとヴイオラの弦楽二重奏曲になって聞こえてくる。さらにその翻訳が三つ四つ五つとあると、そこで奏でられる言葉の音楽は、あるときはピアノ三重奏曲となり、あるときは弦楽四重奏曲となり、あるときはクラリネットが加わるクラリネット五重奏曲になって、私たちを豊穣な時間のなかに誘いこんでいく。 もっと見るその事件の四日前
2023/05/11 02:30その事件の四日前 文部科学省は政府官庁の建物が林立する端に立っているが、官庁ビル一ののっぽビルだった。初等中等教育局長室は二十七階にある。テニスコート一面ほどの広さだ。寺田洋治は八時過ぎにその部屋を出る。朝は八時前に局長室に入っているから、十二時間勤務したことになる。部屋を後にするとエレベターホールに向い、ノンストップのエレベターで地下三階に下り、送迎車専用の玄関に出る。そこで局長専用車に乗り込む。それが寺田の退庁するときのルーティンだった。 彼は夜の会食が嫌いだった。夜の街にくり出すことがさらに嫌いだった。会食の必要があるときは昼食時に組み込んだ。彼を料亭などに呼びつける政治家たちには、早朝なら空いています、先生のお話になりたいその複雑な問題は、頭脳明晰な早朝にこそふさわしいと応じる。 局長室付きの秘書事務官が、ねずみ色の封筒を携えて彼についてくる。エレベターは地下三階に下りていく。エントランスホールを出ると、彼を送迎する黒塗りの専用車が滑り込んでくる。秘書官がドアをあけ、携えてきた封筒を寺田に手渡すと、寺田はありがとうと言い、車に乗り込み、専属の運転手に「お願いします」と声をかける。官僚というピラミッド社会の階段を駆け上がっていく官僚たちは、次第に下位の階級に住む人間たちにぞんざいに振る舞うようになるが、洋治は威張ることはない。しかし彼の人格は単純ではない。むしろ複雑な人物だった。 車は地下から地上にあがり首都高速に入る。秘書官が洋治に手渡した封筒には、その日に発行された文科省に関連する新聞や雑誌記事のコピーがファイルされている。そのファイルを取り出して、さあっと目を通していく。それが彼のなすべき一日の最後の仕事だった。 その日のファイルが分厚い束になっているのは、この日に発行された週刊誌がいずれも、間もなく国会に提出される「初等・中等教育の教育課程に関する新教育指導要綱」を取り上げているためだった。いずれもどぎついタイトルで下半身的刺激を煽ろうとしている。それだけの安っぽい空っぽの記事だからざっと一瞥するだけだった。そんなファイルのなかで彼の手が止まった新聞記事があった。ある官僚の熱く長い戦い(一)翻訳ソフトの開発 今国会に提出される「改訂教育指導要領」は、現行の教育制度を根底から変える革命といえるだろう。中学と高校の全生徒にパソコンが支給され、教科書が廃止になり、ノートも筆記用具も不要になる。さらなる大改革は英語である。これまでの英語の授業は教師が教科書にそって英文の解釈や文法を教えていた。こういう授業もまた完全に追放される。 改訂指導要領による英語の授業は英会話中心で、一対一の対話、グループを組んでディスカッション、さらにはデベイトが行われたりする。教師の役割も一変する。教師はもはや授業の主役ではなく、会話レッスンの進行役、あるいはそのレッスンの管理人といったことになる。文法を教えることこそ英語教育の根幹であり、本道であると主張する英語教師たちからは、英語教育の破壊だと怒りと抗議の声が上がっている。 さらに激しい論議をよんでいるのは、英語の授業時間が拡大されたことである。これまで国語と同じく週三日の三時限授業だったが、新指導要綱では英語が突出して週五日の五時限授業、さらに土曜日の選択授業に英語を選択すれば週六日も英語の授業になる。日本の教育は英語中心になる、これでは日本語が滅んでいくという非難の声も湧きあがっている。 しかし文科省は大改革に向けて舵をきった。そこには一人の官僚の熱く長い戦いがあった。初等中等教育局長の寺田洋治である。文科省が巨大な船体の舵をきるまでの寺田の半生を三回の連載で追ってみる。 寺田は東京で生まれるが、その年に物理学者だった父親が東大からプリンストン大学に転任したため、彼はボストンで成長していく。一家が帰国したのは寺田が十三歳のときだから典型的な帰国子女だった。帰国子女の多くが日本語に苦しむが寺田は二つの異なった文化をバランスよく成長していったようだ。そして中学三年生のとき、今日の英語改革の素地をつくったといわれる「草の葉メソッド」による授業に出会う。 翻訳ソフトをベースにした授業である。ところが当時の翻訳ソフトの性能は、実用にほど遠い未完成品だった。そのことが物理学者の血が流れる寺田の科学的探究心に火をつけたようだ。東工大に入ると翻訳ソフトの開発に打ち込み、そのソフトが完成すると会社を立ち上げ、《オディセイ/ODYSSEY》という商品名で世に投じる。翻訳ソフトの革命と賞賛されるソフトだった。翌年にはその会社を大手のコンピューターメーカーに数十億円で売却している。 若くして寺田は巨額の金を手にするのだが、彼が選択したのは官僚の道だった。当時、官僚になるには国家試験合格者だけだったが、その年から学長推薦者を採用するというルートが取り入れられた。寺田はその新制度によって文部科学省に入省した一期生だった》 その記事は毎朝新聞の朝刊に載った記事だったから、今朝出勤途上の車のなかで目を通していたが、あらためて読んでみるとずいぶん安直に仕立てられたものだと思った。新聞記者はもともと情報を打ち込む人種だから、事件だって、社会現象だって、人間だってこの程度のとらえ方しかできないのだろう。それはそれでいいがこの記事には三つの間違いがある。 帰国子女が日本に戻ってきたとき日本に溶け込むことに苦労するものだが、寺田はそのことに苦しまなかったと書かれている。なるほどこの記事を書いた新聞記者はそのことを彼に問いかけてきた。しかし洋治はポーカーフェイスに徹してただ軽くクビを振った。彼は他者に弱みを見せない。苦しければ苦しいほどポーカーフェイスで耐え抜く、そういうタイプの人間だった。もしこの新聞記者が洋治のこのような性格を見抜き、ポーカーフェイスの内部に踏み込んできたら、多少は彼の実像を捕える記事になっていたかもしれない。 異国で成長してきた子供が、突然、言葉や文化や生活の異なって国に投げ込まれて戸惑わない子供がいるのだろうか。彼はまず猛烈ないじめに出会った。そのいじめに対抗するために必殺の一撃を習得するために空手道場に通った。その必殺の一撃とは、相手の攻撃から逃げるように避けるように体をかがめて一回転させ、右足を蹴り上げ、踵を相手の顔面に叩き込む──回し蹴りだった。道場から帰宅してからも庭に立てた柱に必殺の回し蹴りを叩き込んだ。そしてついにその日がきた。中学一年生の回し蹴りだったが、相手は三メートルも吹き飛んでいた。その一撃でいじめはばたりと止んだ。 彼をさらに苦しめたのは日本語だった。彼の第一言語はすでに英語になっていたから、彼の中学時代は日本語を第一言語にしようとした戦いの日々であった。言葉に鋭敏な少年だったからその戦いは深刻だった。偏頭痛に苦しめられ、アスピリンづけになっていた。そんな変調をきたすほどに追い詰められていた彼を救ったのが、中学三年生のときに出会った「草の葉メソッド」方式による英語の授業だった。 それまで二つの異なった言語の争闘は、彼の頭の中、あるいは彼の肉体の中で行われていた。それがその授業によって翻訳ソフト上で行うようになったからだった。偏頭痛が消えていった。アスピリンから解放された。分裂していくかのようだった精神や肉体が統一され、いわゆるバイリンガルとしての自己が形成されていった。彼が翻訳ソフトの開発に打ち込んでいったのは、いわばバイリンガルとしての人格を形成していくことでもあったのである。 開発した翻訳ソフトを大手ITメーカーに売却して、若くして数十億円という巨額の金を手にしたと書かれているくだりがあるが、このくだりも正しい記事とはいえない。なるほど彼が開発した翻訳ソフトは九十億で売却された。しかしその九十億は霞と化して消え去ったのだ。そのソフトを売却するための小さな会社を設立した。そのとき同じ東工大の研究室にいた手塚という男が、その事業の経理担当者になっていて、金の出納はすべて彼に委ねていた。 手塚は統計確率論を打ち立てようと研究室に在籍していたが、彼の体質は研究者ではなく、新しい企業を打ち立てたいという野心がつねにうずいていた。洋治が起こした会社もこの手塚によって主導されて、その会社が九十億円で売却されたのもこの男のビジネス的手腕によってだった。そんなことからも売却した九十億円は手塚によって管理されていたのだが、彼はその資金をひそかにインターネット取引に注ぎ込んでいった。もっとも危険なバイバイゲームで金を獲得できる商品取引に。 その世界はクリック一つで十億、二十億という金を稼ぎだせる世界だった。それは同時に一瞬にして百億、二百億を失う世界でもあった。手塚がひそかにその世界に手を染めていったのは、彼が編み出した統計確率論の実践に乗り出したのかもしれない。しかしそこは統計確率論などが通用する世界ではなかった。五十億を失い、六十億を失い、七十億円を失っていく。いよいよ追い詰められいく現実から逃れようと、競馬場、競艇場、競輪場に日毎に繰り出し、はては香港やマカオまで飛んでギャンブル漬けになって、地獄の底に転落していった。そしてマカオ近郊の森のなかで額に拳銃を撃ちこんで自殺した。こんな顛末があったことなど洋治はだれにも話したことはない。いまだにその真実を封印したままだった。 もっと見る



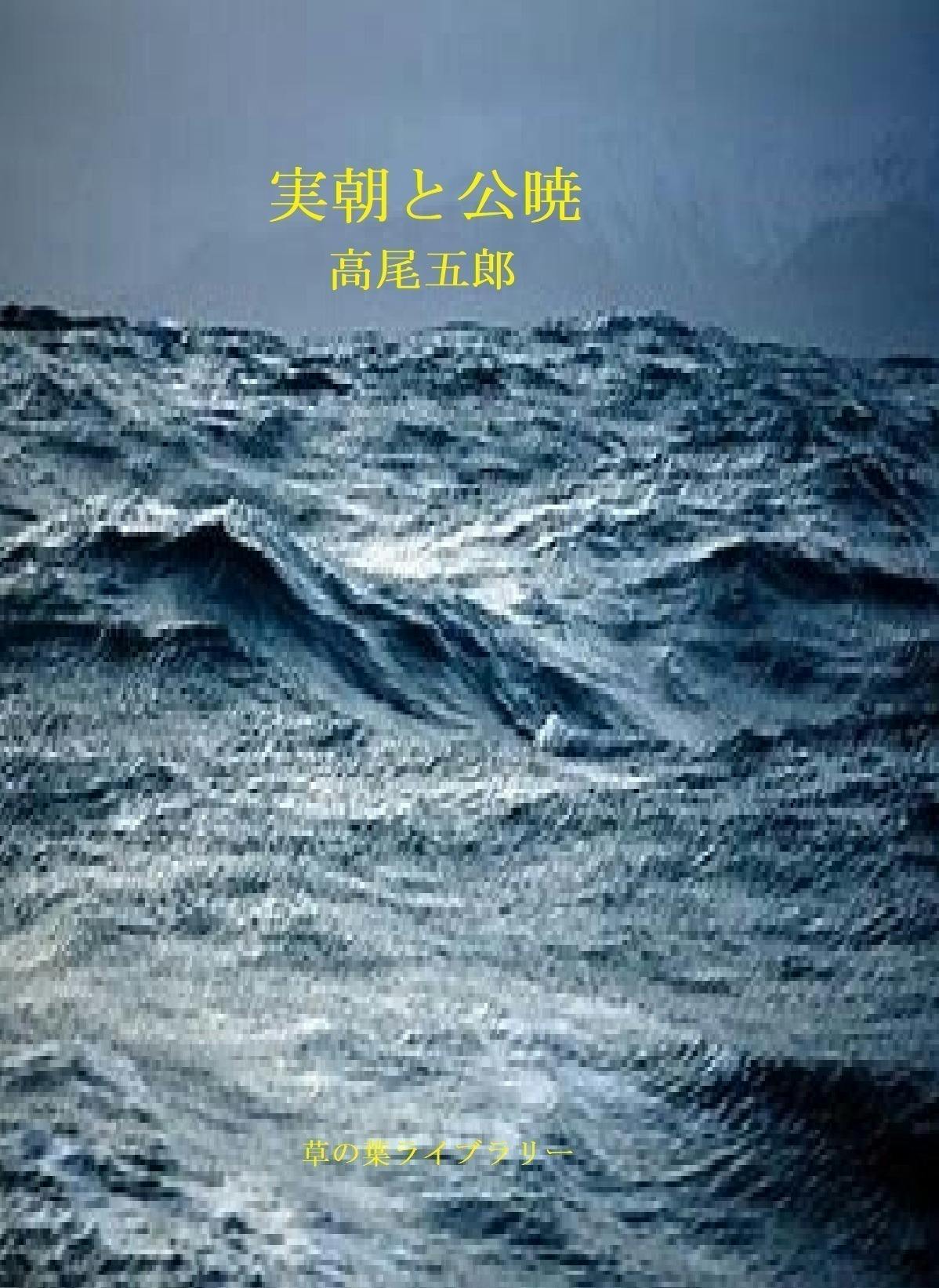








コメント
もっと見る