
ヤマタノオロチを巡る旅、第3回目です。
安田登(能楽師)が書きます。
▼斐伊川とオロチの旧跡のつながり
ヤマタノオロチ神話を辿って、奥出雲、雲南を巡ってきましたが、すべて斐伊川(ひいかわ)流域でした。
さらにここから下って行った出雲市周辺にもオロチの旧跡があります。ところが、それらの旧跡は突然、斐伊川を外れるのです。オロチ=斐伊川氾濫説においてはむろんのこと、オロチ=たたら一族説でもオロチの本体は斐伊川です。斐伊川を離れてのオロチ説話というのは考えにくいのです。
と思っていたところ、斐伊川の流れが江戸時代に大きく変わっていたことを知りました。今の斐伊川は宍道湖に注いでいますが、寛永年間の川違えまでは神門水湖(神西湖)を通って海に流れ込んでいました。
となれば、すべてのオロチ旧跡は斐伊川にあることになります。ひと安心です。
とはいえ、出雲市周辺のオロチ旧跡群も、ここはここでひとつの物語を完結させています。
どうもヤマタノオロチ神話は、斐伊川の上流・中流・下流でそれぞれ物語を完結させているようなのです。
▼重層する神話と「鬼の舌震」伝説

奥出雲では、同一の平面に時間や系譜を超えたいくつかの神話や神々が掛詞のように重層的に重なっていました。また、オロチの旧跡は土地ごとに独立しています。
これは、物語の原型としてのヤマタノオロチ神話があり、それが川の上流・中流・下流によって、それぞれ違った受け止め方をされながらも、同一の神話として享受されてきたからなのでしょう。
さすが神話世界は、縦(時間)と横(空間)とが複雑に錯綜しています。
などと考えていると、雲南に「鬼の舌震(したぶるい)」という、なんともそそられる名所を見つけました。
寄ってみると、奇岩・奇石とその間を流れる渓流が織り成す自然の絶景です。ここは斐伊川の支流にあり、ヤマタノオロチの神話とは直接の関係はありませんが、『出雲国風土記』にはこの地にまつわる神話が載っています。
恋山(したいやま)の伝説です。
この土地(阿伊の村)に坐します玉日女命を、和爾(わに)が恋い慕い、川を上って来ていました。ところが玉日女命は川を石で塞いでしまったので、和爾(わに)は恋い慕いながらもヒメに会うことができなくなってしまいました。これによって山の名が「恋山」になり、「わにの恋(した)ふる」が「鬼の舌震」になったというのです。
この物語は確かにヤマタノオロチの話とは違いますが、しかし何となく似てもいます。
稲田姫はタマヒメとなり、オロチがワニに変わってはいますが、異類が乙女を求めるという点では共通しています。ともに処女を異類に生贄として差し出す儀礼の神話化のように思われます。
▼因幡の白兎と大国主命
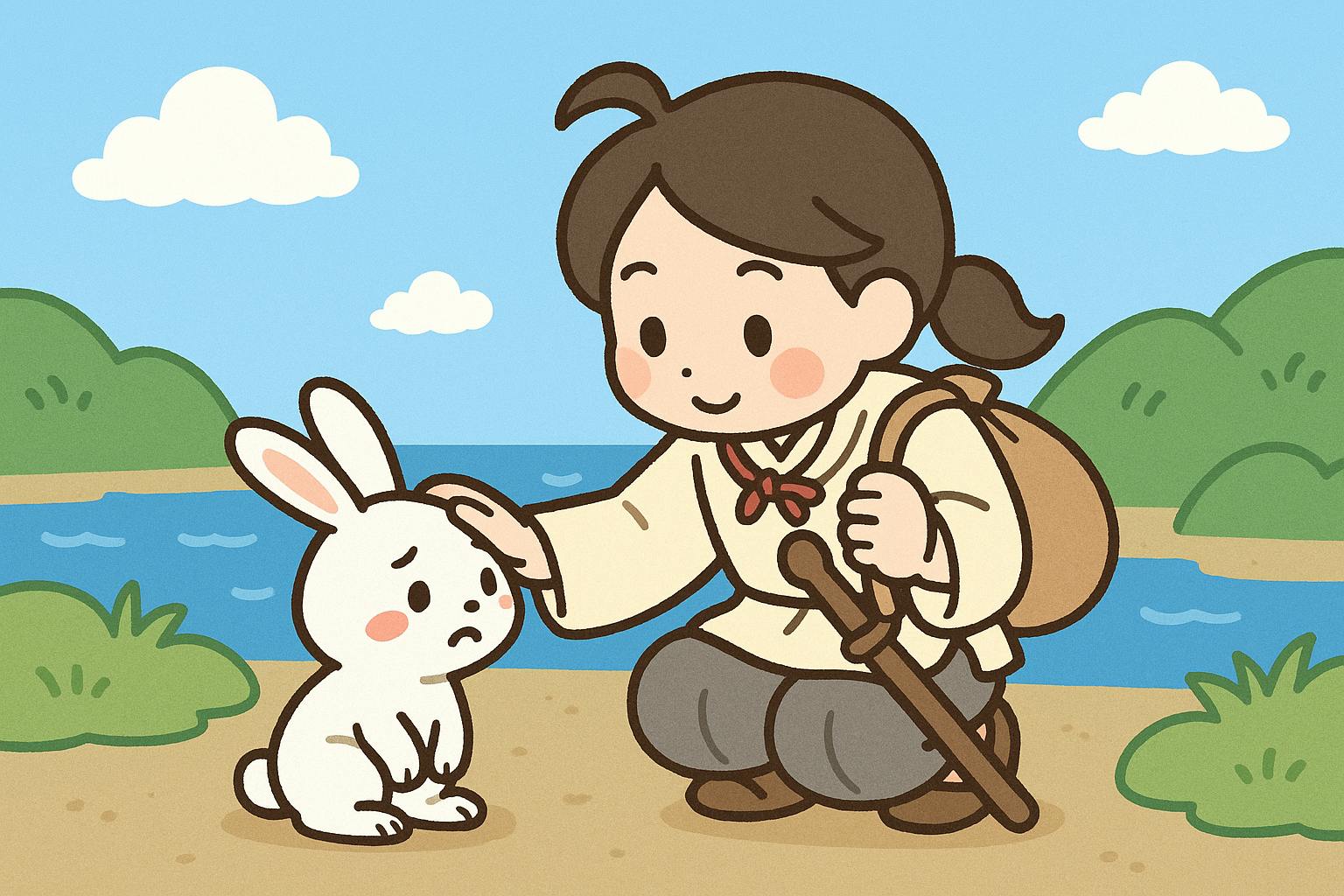
ワニということで思い出すのは「因幡の白兎」の話ですが、ここで絵本や童謡でも知られる「因幡の白兎」を紹介しておきましょう。
出雲の神である大国主命(おおくにぬしのみこと)は、兄神たちの荷物をすべて持たされて旅をしています。兄神たちは因幡の八上比売(やがみひめ)と結婚をするために、出雲から因幡まで旅をしていたのですが、一番若い弟にすべての荷物を持たせていたのです。
小学校のとき、みんなのランドセルを持たされるとか、そんなことありますね。
さて、重い荷物を持たされた大国主命は、ひとり遅れて歩いていました。
すると、そこに泣いている白兎がいました。
「なぜ、泣いているの?」と大国主命が聞くと白兎は説明します。
私は隠岐の島に住んでいて、因幡の国へ渡ろうと思ったのですが、海を渡る方法がありませんでした。そこでワニをだまして「数を数えるから並んで」と言い、背中を飛び移って海を渡りました。
ところが最後に「だましたんだよ~」と言ってしまい、怒ったワニに皮をはがされてしまったのです。
そこに大国主の兄神たちである八十神(やそがみ)の行列が通りかかり、「海水を浴びて、風に当たって寝ていろ」と教えてくれ、その通りにしたら体中が傷だらけになったのです、というのです。
大国主命は、「それは違うよ。川の真水で洗い、蒲(がま)の穂を敷いて寝ていなさい」と教えたので、その通りにした兎は元気を取り戻しました。
白兎は感謝し、「八十神たちは因幡の八上比売と結婚はできず、あなた(大国主命)が結婚するでしょう」と予言しました。この兎は菟神(うさぎがみ)になりました。
▼神話を「演じる」ことで見える供犠儀礼
「鬼の舌震」から「ヤマタノオロチ」を連想し、さらに「因幡の白兎」までいくと、もとの話からはどんどん離れてしまう…ような気もします。しかし、実はそうでもありません。
神話に向かうときは、読むだけでなく「する」ことも大切です。物語を立体化してみるのです。神楽や能のような神聖舞踏劇として演じてみます。
すると、この「因幡の白兎(稻羽の素菟)」の物語も、同じく処女供犠儀礼の物語化であることが見えてきます。
皮を剥がれたと思っていた白兎ですが、『古事記』には「悉(ことごと)に傷つけ」られ、「裸(あかはだ)」だったと書かれます。たしかに子どもの頃に歌った『大黒様』の歌詞も以下のように「あかはだか」になっています。
大きな袋を かたにかけ
大黒さまが 来かかると
ここに いなばの 白うさぎ
皮をむかれて あかはだか
しかも、『古事記』によれば、兎がワニに剥がれたのは皮ではなく「衣服(きもの)」です。兎は衣を剥がされ、しかも傷つけられていました。それが大国主の教えた、水門(みなと)の水による沐浴と薬草、蒲を使う秘法によって再生し、しかも未来を的確に予知するという「菟神」へと変容します。
供犠の儀礼において生贄の乙女たちが清らかな衣を着ることや、沐浴をすることなどは、ホメーロスの『オデュッセイア』などにも描かれます。

この物語は、この後に続く大国主の全身の火傷と、キサ(刮+虫)貝ヒメと蛤貝ヒメによって授けられる貝殻と貝汁による母乳の秘法による再生、そして真の英雄神への変容の物語と呼応することによっても明らかなように、「死と復活」、そして「超越者への変容の儀礼」であり、またイエスの十字架の死にも似る供犠の儀礼なのです。
▼異類に捧げられる乙女と殺害欲求の神話化
処女を生け贄として異類に捧げる物語は、神話の典型的なモチーフです。
人が人を殺害して、生け贄として異類に捧げるという暴力的な行為は、農耕社会から生まれたようです。狩猟社会の儀礼において人の生け贄はあまり用いられません。人牲はむしろ農耕社会の儀礼としての方がより用いられるのです。
人が人を組織的に殺害することも、農耕社会の誕生とともに起こり、灌漑農業の発明以降、それがより加速したことが近年の発掘調査などから指摘されています。それはむろん、土地を守るための戦いということが第一の目的でしょう。しかし、それだけではないのではないでしょうか。
どうも私たちの中には、狩りをする霊長類としての殺害への欲求のようなものがあるのではないかと思います。
猛獣を殺害する(ほぼ)唯一の霊長類であり、同族を組織的に殺害する唯一の動物でもある我々人類の中には、殺戮者としての血が、深い「思ひ」として奥深くに根強く残ったのでしょう。
その欲求は、農耕という殺害を必要としない社会の形成とともに抑圧されました。
しかし、人類の深奥に残る殺戮への「思ひ」は、農耕社会になっても海月(くらげ)のように漂っています。その海月のような「思ひ」、混沌たる情動を、私たちは異類に転嫁しました。
土地によってそれはオロチとなり、あるいはワニとなります。
ところでワニとは何でしょうか。
いまはサメだという説が強いようです。
が、ちなみに『古事記』でワニになる豊玉姫は、『日本書紀』では「龍に化す」とあります。ワニの「ワ」とは「浦回(うらわ)」「川曲(かわわ)」のように曲がりくねったものを表します。
ならばワニも曲がりくねった生物、すなわち龍蛇だったのはないでしょうか。
そして、それは神迎えの先導をする龍蛇様であり、それに続く神々も、我々の抑圧している殺害、暴力への思ひの発現なのではないでしょうか。
▼国譲りと龍蛇の行列
出雲は、アマテラス一族の神々が、国譲りという名のもとに無理やりに奪った土地です。
その土地を、龍蛇を先導に新たな支配者となった神々が練り歩きます。そして、沿道の人々は家の中にこもって息を潜めて通過を待ちます。それが『聖書』の過越しに似ているのも宜なるかな、などとヤマタノオロチの旧跡を巡りながら考えました。
なお、スサノオがなぜ川上に降り、さらに川上に向かわざるを得なかったのか。そのことについては紙幅が尽きましたので、またいつか考察いたします。
長い間、ありがとうございました~。
※今回のイラスト、タッチがみなあまりに違っていてすみません(笑)。










