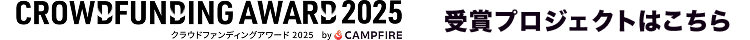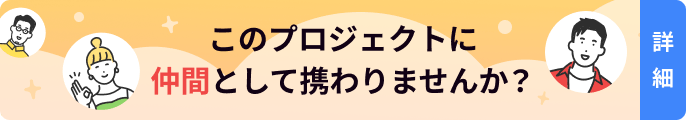私たちは、困ったとき、神仏に手を合わせます。どうか無事でありますように。どうか願いが叶いますように。それは、今も昔も変わらない人の姿かもしれません。しかし、放牛が残した道歌のひとつに、こんな言葉があります。神ほとけおがまぬさきに親拝め神や佛もうれしかるらん(神仏に拝む前に、親を敬うべきである)一見すると、親孝行を説いた言葉のようにも読めます。実際、この道歌は、極楽へ至る道において、親を敬い大切にすることが重視されてきた仏教の教えを背景に持つ言葉でもあります。ただ、放牛がこの言葉を石に刻んだことを思うと、それは教えをそのまま伝えるためだけではなかったのではないかと感じています。放牛が見ていたのは、もっと手前にあるもの。それは、生きている人への態度。身近な人、目の前の関係への向き合い方。今ここに生きている人と、どう向き合っているのか。その姿勢こそが問われているように思えるのです。放牛が生きた時代、言葉や祈りは、必ずしも人を救ってはくれませんでした。飢えや病があり、明日が約束されない日常の中で、「正しいこと」を言ったからといって、生き延びられるわけではなかった時代。だからこそ放牛は、人としての生き方を見つめる視点を石に刻んだのではないでしょうか。私たちが「放牛石仏」を守ろうとしているのは、信仰的なことを広めるためではありません。300年前、一人の僧が生き方として刻んだ問いを、この時代に手渡したい。その思いで、この活動を続けています。私たちは何を大切にして生きているのか。放牛の言葉は、今を生きる私たちにも、静かに問いかけているように感じます。