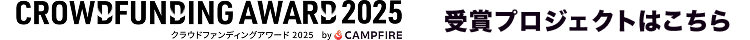今回の鳥公園の創作体制変更に始まる問題提起に対して、様々な方から応援や応答のメッセージをいただきました。ご紹介していきます!
* * *
「アーティスト・コレクティヴ、を応援する。」
内野 儀
五年に一度、ドイツのカッセルで開かれるドクメンタという現代美術の祭典について、画期的なニュースが2019年の初頭、メディアを駆けめぐりました。次回、2022年に開かれるドクンタ15の芸術監督に、インドネシアのアーティスト・コレクティヴ、ルアンルパを選ばれたのです。
ドクメンタ史上初のアーティスト・コレクティブ(ママ、引用者註)によるアーティスティック・ディレクターとなるルアンルパは、2000年にジャカルタを拠点に活動するアーティスト主導により設立。社会学、政治、テクノロジー、メディアなど、異なる分野を横断しながら、アートの創造性を駆使して、都市問題や文化的課題に、展覧会や芸術祭の企画運営、出版やラジオを使った活動など幅広い活動で応答している。(ART iT, https://www.art-it.asia/top/admin_ed_news/197963)
現代美術展の芸術監督ですから、コンセプトを作り、作家・作品を選定するわけなので、仕事的には、いわゆるキュレイターです。大きな芸術祭とはいえ、専門的なキュレイターでもなく、アーティスト・コレクティヴを芸術監督に指名するというのは、とても勇気のいることだったのではないでしょうか。ドクメンタでは、もちろんこれまでは、例外なく個人が芸術監督を務めてきたからです。
この「事件」については、現代美術の文脈ではいろいろなことが言えるでしょうし、現に言われています。しかしわたしは、この個人からコレクティヴへという国際展のキュレーションにおける流れに、現代美術の業界を超える、大きな可能性を感じたのです。というのは、フレドリック・ジェイムソンのいう「善き無名性」に、一時的なかたちを与えて、人びとの文化記憶に登記されるために必要な共同性=コレクティヴのひとつのあり方をルアンルパが示し、そこに焦点が当たったように思えたからです。
キーワードは、引用にある「アーティスト主導」です。アーティストが主導して、「社会学、政治、テクノロジー、メディアなど、異なる分野を横断」しつつ、「アートの創造性を駆使して、都市問題や文化的課題」(いただいた原稿では、「アートの創造性」に傍点付記。傍点は引用者)に向き合うというのです。それはまた、複数で創造することが前提となっている舞台芸術、広義の演劇を専門とする、わたし個人にとってもまた重要な示唆を与えてくれる活動と創作の原理でもありました。
事実として、演劇はひとりではできません(いわゆるジャンルとしてのパフォーマンス・アートは、コンセプト的には、「ひとりでできる」とはいえ)。それ以上に、演劇における集団性・共同性は、単なる現実的要請の帰結ではなく、演劇というメディウムの起源にさえおかれています。演劇と共同体という古くて新しい問題は、少なくとも西洋では、古代ギリシアからいろいろと論じられてきました。市民社会/個人主義がメインストリームとなる近代以降は、演劇は職業化し、職能も分かれていきました。日本ではしかし、1960年代後半のアングラ演劇から、職業化しない「素人」が「アーティスト主導」で任意に集団を組み、演劇革命とも呼ばれる変革をもたらしました。ところが、職業化しない任意の集団が機能するためには、既存の社会の組織と共同体のあり方、つまり、異性愛家族主義とそれを支える家父長制といった、集団生成のための原理が意識的あるいは無意識的に採用されました。そのほうが、効率的だったからです。
その後、日本社会に戦後民主主義がより強固にインストールされてくるにつれ、家父長制は社会を組織するエートスとしての力を少なくとも表面的には失っていきました。ところが、アングラから小劇場へと呼称は変わっても、これら「素人集団」としての演劇集団=劇団では、家父長制的イデオロギーが相変わらず強靱な統合のためのロジックとして使われてきたように思います(「強い表現を作るためには、暴力的かもしれない権力関係を認めよ」といったように)。
もちろん、21世紀に入って20年近くたつのに、そんなイデオロギーが構成原理として有効でないことは、自明なのではないでしょうか。と思っていたら、どうもそうではないという事例がまだまだ出てきてはいます。なぜなら、家父長制イデオロギーに変わる集団を組織するないしは共同性を維持するための原理が見つけられないからです。いわゆる劇団制が維持できなくなってプロデュース制になったとも言われますが、家族集団的に見える劇団は、まだまだ新しく生まれてきます。なぜなら、プロデュース制は資本の論理に屈服した結果でしかないからです。
では、いま、劇団、あるいは劇団的共同性・集団性はどうすれば可能になるのか。今回、西尾佳織さんが主宰していた鳥公園が、体制を大きく変えることになったと聞きました。HPには、こう書いてあります。
今回の『終わりにする、一人と一人が丘』の公演を以て、鳥公園で私が劇作と演出を兼ねる体制を終わりにします。「いったん」になるのか「ずっと」になるのかは分かりません。少なくともここから3年、劇作家・主宰の西尾と、和田ながら(したため) 、蜂巣もも(グループ・野原)、三浦雨林(隣屋)の複数演出家体制でやってみます。それに伴い、鳥公園は「演劇作品を上演する団体」というよりは「広く演劇的営みのプロセスが生成される〈場〉」になります。(https://www.bird-park.com/15-1)
「演劇作品を上演する団体」=劇団から、「広く演劇的営みのプロセスが生成される〈場〉」への移動/転換は、とても魅力的に響きます。特にわたしのように、これまで長きにわたって、アングラ/小劇場演劇の紆余曲折にそれなりに付き合ってきて、わたしが〈Jという場所〉と呼ぶ圏域では、アングラ/小劇場だけにまだかろうじて残っている、反動的で時代錯誤な構成原理でなければ、いかなる演劇的共同性や集団性も生まれないのか、とあきらめかけていた人間にとっては、「おお、そう来たか!」という思いが強くあるのです。
鳥公園は、劇団ではなくコレクティヴを目指そうとしています(とわたしは解釈しています)。この三人演出家体制の演劇的コレクティヴ、アーティスト・コレクティヴが、ルアンルパのように、「アーティスト主導」で「社会学、政治、テクノロジー、メディアなど、異なる分野を横断しながら、アートの創造性を駆使して、都市問題や文化的課題に、展覧会や芸術祭の企画運営、出版やラジオを使った活動など幅広い活動で応答」してほしいと、わたしは、心から願っているのです。しかし、まずは、鳥公園のHPで宣言されているように、「複数性の演劇」(同上)が、しなやかなかつ鮮烈な共同性のなかから、立ちあがってくることをわたしは期待しています。
(うちの・ただし 演劇批評・パフォーマンス研究)