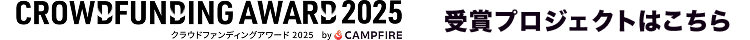一六二〇年(天和六年)九月五日。支倉常長は長崎に着いた。乗っていたのはサン・フ
ァン・バティスタ号にあらずマニラからの徳川幕府の御朱印船であった。サン・ファン・
バティスタ号はイスパニア兵をアカプルコからマニラに移送する役目を担っていた。当時
イスパニアとポルトガルはフイリッピン支配の覇権を巡り戦いが続いていた。それで大砲
十六門を備えられる五〇〇トンのガレリン船の供出を余儀なくされたと思われる。
ガレリン船とは大航海時代に活躍した三本のマストを立てた西洋式帆船。
支倉は幕府の取り調べによる長崎滞留の間に政宗に早飛脚を出している。八日で仙台に
届いた。文には、通商が叶わなかった謝罪と無念が連綿と綴られ、従者八名がイスパニア
から帰国しない旨を申し出た故に、それを認めたと添えられていた。
戻らなかった者たちの名は記されていない。
この文が政宗に届くと家老は「支倉常長一行が近々に帰ってくる」と布令を出した。
城下の関心事はイスパニアとの交易が実現できなかった苦渋より、戻って来ない者の特
定と詮索であった。戻って来ない者は誰と誰なのか。その理由は何か。八名の未帰還者の
存在だけが事実。他には何ひとつ確証がない。憶測からの噂が彼方此方で囁かれ広がる。
憶測からの仮説。仮説が仮説を呼び、尤もらしい噂話しに熱中するのは今と変わらない。
蔵之介は八名を不忠義者と断じた。
九月二〇日。支倉常長が仙台に帰還。
蔵之介は嘉蔵との七年ぶりの再会の悦びを胸に月の浦に向かった。
江戸からの船に支倉常長一行が乗っていた。下船者に嘉蔵の姿は無かった。与助も見つ
けられない。無礼を顧みず蔵之介は支倉に嘉蔵の安否を尋ねた。
「生きておる。イスパニアのコリア・デル・リオに残った。与助も一緒だ」
茫然自喪の蔵之介は支倉の側近から嘉蔵の文を渡された。
—我は故里吾出瑠里緒村に留まり候 与助も残ると申し候 詮索するに及ばす もとより
死を覚悟しての船出 我は異国の地で死に申す 然して世間から色々と取だたされし候
なれど 我は忠義を尽くし致し候 これだけは申し候。
「大海に もまれころがり 早五年 支倉の無念 如何ばかりか 而して我は 望郷を打
ち振り払い 此処に残らん 我を求めし 故里吾出瑠里緒 これぞ誠の 男伊達」—
蔵之介の受難はこの時から始まった。
「嘉蔵は忠義者と思っていたが間違いだった」
「残される家族よりもイスパニアが大事だったんだ。これまた不思議な話し」
「人は分からないもの」
「大方、女でもこさえたんだろう。そうでもないと説明がつかない」
「俺なら女を捨てて帰ってくる」
「いやいや女次第じゃて」
「よほどの女なら俺はイスパニアに残る」
「女かも知れぬが帰りも一年二ケ月の船旅。無事には済まない。海に臆したのかも」
「偉そうにしていても嘉蔵は案外、臆病者だったのでは」
「臆したのならば敵前逃亡」
「嘉蔵は弱虫か」
「戻って来ない臆病者の禄が百五〇石とは間尺に合わない」
人の口は止まらない。塞げない。こうしたヒソヒソ話しは嫌でも蔵之介の耳に入ってく
る。家族の者もすべからず知る。こたえたのは「臆病者」「敵前逃亡」だった。それでも
蔵之介を支えたのは嘉蔵の「忠義は尽くした」であった。尽くしていなければ支倉常長は
不帰還を認めない。繰り返し湧き上がるのが「親父殿に何があったのだろう」。
人の噂も四五日と云うが、城下での陰口悪口は執拗だった。三ケ月経っても収まらない。
家老は風紀の乱れを懸念した。放置すれば藩政に影を落とす。
家老は蔵之介に蟄居謹慎を命じ、政宗には瀧上家の取り潰しを上申した。
「帰還せざる者、これ不忠義者なり」
支倉は「拙者が認めた沙汰」と穏便を政宗に願い出た。
お家の取り潰しは免れたものの見せしめ的な措置が下った。家老の狙いは城下に蔓延す
る悪しき風評の封印。封印しなければ遣欧使節団の失敗の責が自分にも及ぶやも知れぬ。
蔵之介は道場の師範を解任され四十四俵の蔵米取りに。そして無役になった。彼はそれ
らを受け入れ、耐える他なかった。陰口・悪口・噂・故なき風評が止むなら、それで良し。
蟄居謹慎が解かれると往来での立ち話しは消えたが「無役のただ飯食らい」は続いた。
無役になった蔵之介は二名の家来に暇を出した。家老に頼み込んで二名を抱えてもらっ
た。与助の家族だけは守らなければならぬ。これが減俸禄時の蔵之介の決意だった。
与助は親父殿に忠義を尽くして故里吾出瑠里緒に残ったのだ。
蔵之介は長男与作に跡を継がせ扶持の二〇俵を維持した。
蔵之介は不屈だった。無役を逆手に取り、大いに活動した。
戦さが終わってから久しい。時代が落ち着くと人の往来が盛んになる。彼方此方で産業
が興る。物資の流れも益々増える。江戸の町は人が増える一方。必ず米が足りなくなる。
蔵之介は仙台から江戸への回米を考えた。それまで仙台と江戸を繋いでいたのは不定期
船だった。ここに着眼した。不定期便と定期便とでは商いの方法が違ってくる。定期船に
は人々の期待と要望が強まる。そうなれば船賃も高く取れる。
蔵之介は与作に江戸往復船に見習いとして乗り込ませた。与作も必死だった。
蔵之介は「これからは海の時代。海を制した者が生き残る」と家老に江戸往復の定期船
開設を願い出た。嘉蔵不在の七年間の蓄財すべてを資金に充て千石船を購入した。不足分
は借金で補った。千石船とは北前船の船型と同じである。千石船とは米二五〇〇俵を積み
込める。それで千石船。しかしながら当時の船の多くは百石程度。百石を越える大型船を
千石船と呼んでいた。蔵之介が購入した船の積載量は千石の半分。五百石の米を積めた。
満載で千二百五十俵。蔵之介は船の安定化を考え千百俵を上限に据えた。積載量の余裕は
百五〇俵。重さにして九トン。その余裕分で人を運ぶ計画。定員は五〇名。
家老に定期船開設を願い出た蔵之介の狙いは荷の保証だった。当時は荷への損害保険が
無かった。我国に損害保険が導入されたのは明治に入ってからである。時化などで荷に損
害が生じると、その保証は船主に帰した。万がいち船が沈んだ時には全額を船主が負担し
なければならぬ。蔵之介には不可能。不可能と分かれば信用されず、誰も荷を預けない。
今で云う江戸への定期船開設上申書は政宗の眼に留まった。自らの責任能力を超えてい
ると悟った家老は政宗に上申した。政宗は即断。
「江戸への回米は藩においても必須。今は江戸の米商人に言い値で買い叩かれている。藩
自らが米を江戸に、それも定期的に運び、競りにかけたなら高く売れる。帰りには江戸に
集まる各地の物産を積む。これらは奥州諸藩に飛ぶように売れる。定期船とは実に秀でて
いる。米の保管や運搬の段取りも付け易い。荷の保証は是。これで人の行き来も増える」
これが「江戸の米の三分の一は奥州米」の礎。
蔵之介は船に海洋丸と名付けた。
与作は働き者の他に優秀であった。三ケ月の見習い期間に江戸までの航路海図を作成し
操船技術を習得した。海図には陸の姿と黒潮の流れが描かれていた。
「沖に出過ぎると黒瀬川に呑まれ、それを恐れて陸地に近づき過ぎると岩礁に乗り上げる。
黒瀬川は海が黒い。注意を怠らなければ呑まれない。沖に出ると船足が早くなる。出来る
限り沖に出て黒瀬川を避けるならば江戸までは難しくない。早ければ三日。遅くとも四日
で着く。問題は八月下旬から十月下旬にかけての大嵐。この間は休みましょう。城内には
布令を出し早飛脚を江戸の商人に届けましょう。そうすれば信用は損なわれない」
蔵之介は与作の進言を受け、片道四日、二週間一往復を決め、与作に船頭を命じ、自ら
は船主を名乗った。江戸での競りと買い付けの責任者の選任を与作に任せた。与作は一人
の若者を江戸から連れ帰った。伍平と名乗った。伍平の父も帰還しなかった八名の一人だ
った。伍平は江戸の米商人の処で手代まで務め上げていた。与作は伍平を引き抜いたので
ある。引き抜き料は一〇両。それを与作は借金して賄った。
感激した蔵之介。
定期船は蔵之介の思惑通り仙台と江戸の人々に支持された。特に江戸の米商人には好評
だった。今までの値の三割増しで取引された。伍平は競りの仕切りが上手かった。持ち帰
る江戸に集まった各地の物産の選定にも長けていた。選定を終えると与作は品々を書き写
し、伍平が定めた買い値と売り値を記して早飛脚を家老に走らせた。飛脚の袖に心付けを
忍ばせると三日で着いた。海洋丸が湊に着くと既に人が群がっていた。我先にと物産を手
に吟味する。この時も伍平の捌きは人眼を引いた。半日で売り切ってしまった。
伍平は選定の他に客の望みを受け付けた。いわゆる予約である。予約された品々は売れ
残らない。瓦版・木綿の反物・江戸地図が町人に好まれ、伊達藩に限らず諸藩の御用人は
書籍・西陣織・江戸漆器・伊万里焼を求め、女たちは紅・簪・手鏡を所望した。
ヒトとモノの定期的な活発な動きはカネを生む。
蔵之介は米の代金の九割と物産販売粗利の三割を藩に納めた。米代金の一割と物産販売
粗利七割が海洋丸の営業利益であった。旅客の運賃を不定期船より二割安くした。従来は
不定期船故に運賃を高めに設定せ去るを得なかった。それを見越しての割安料金。
蔵之介は家老に旅客運賃の折半を申し出た。内密。家老は固辞しなかった。
蔵之介が認めた『嘉蔵始末記』によれば、ひと航海での海洋丸の純利益は莫大であった。
時には物産の粗利が米の一割を超えた。三往復で蔵之介の借金は消え、九往復で投下した
船の購入費用全額を回収できた。就航後五ケ月で蔵之介は元を取ったのである。
政宗も家老も満悦至極。与作は苗字帯刀を許された。蔵之介は「瀧上を名乗ってはどう
か」と与作に言った。与作は感極まり号泣。家系図に血縁なき者が突如、蔵之介の横に並
ぶのは与作の号泣による。海に乗り出した蔵之介と与作の夢は同床であった。外洋に出て
何時か必ず故里吾出瑠里緒の地を踏み、嘉蔵と与助に本当の訳を尋ねる。しかし二人の夢
は一六三九年の鎖国令によって消えた。消えても嘉蔵と与助の不帰還の謎は残った。
滝上家では祖父から孫に文書の読み聞かせが代々続いていた。海彦は海之進から。海太
郎は海翔。海之進は海市から。海之進は文書から『嘉蔵始末記』を選び、海彦に一部始終
を読み聞かせた。それにより海彦は蔵之介の不屈を知った。同時に「嘉蔵は偉大であるが
尊敬できない」が海彦に根づいた。海之進は読み聞かせの度に「分からぬことを詮索する
のは無駄じゃ」と言った。それでも海彦には嘉蔵不帰還の謎は消えなかった。