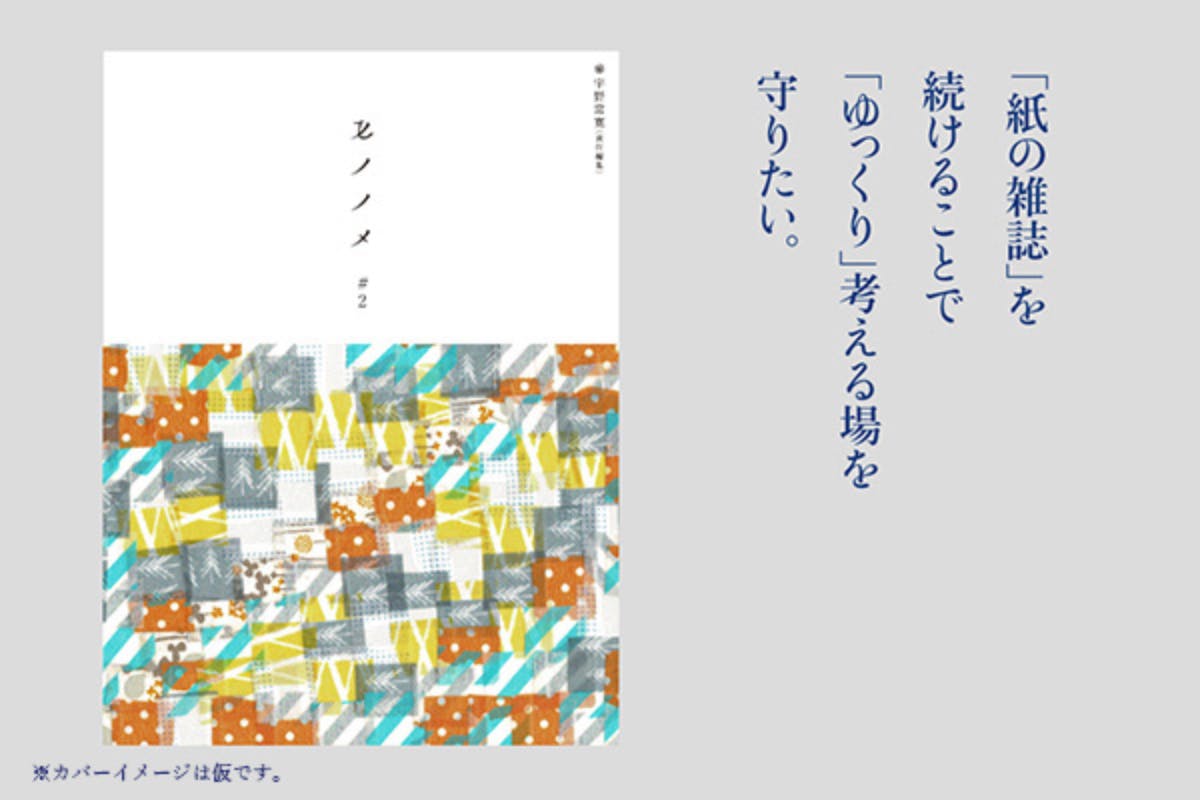副編集長の中川です。『モノノメ #2』の制作も、だいぶ佳境に差しかかってきました。
取材をした記事や著者からの寄稿などのテキストはほぼほぼ出そろってきているのですが、それを物理的な誌面でどう見せていくかという、ウェブにはない紙の雑誌ならではのデザイン制作上の課題と、目下格闘中です。
宇野と中川以外の制作スタッフは基本的にウェブ世代なので、紙媒体の編集経験はこれが初めてというメンバーも多く、アートディレクターの館森則之さん以下のデザイナーチームとどう連携すれば見た目も気持ちよくメッセージの伝わる誌面が作れるのか、ここのところは試行錯誤を続けています。
ここは編集長・宇野のこだわりが最も強いところでもあり、どんなにスケジュール的に切羽詰まっていてもクリエイティブが納得のいくところに辿り着けなければ、何度でもやり直しになります。現場との調整を預かる立場としては胃の痛いところですが、1日でも早く支援してくださった皆様のもとに理想の誌面をお届けできるよう、全力を尽くしていきたいと思います。
さて、今日ご紹介する記事も、そんなクリエイティブにまつわるスリリングな衝突を、唯一無二の表現に高めていった営みの記録です。
今回の特集テーマは「身体」ですが、その構成記事のひとつとして、「原初舞踏」を実践する舞踏家の最上和子さんと、プラネタリウムなどで上演するドーム映像を手掛ける映像作家の飯田将茂さんが2021年11月7日に実施したライブパフォーマンス・プロジェクト『もうひとつの眼 / もうひとつの身体』をめぐっての両者の対談を収録しました。
最上和子さんは、アニメーション監督の押井守さんの実姉としても知られ、『身体のリアル』という対談本もあります。宇野の主著『母性のディストピア』や『PLANETS vol.10』での『パトレイバー2』インタビューをお読みの方ならご存じのとおり、押井守監督といえば宇野が少年期に最も強烈な影響を受けた映像作家のひとり(ついでに言えば、筆者もまた高校漫研への入部当時、先輩たちにひたすら『紅い眼鏡』や『天使のたまご』、『御先祖様万々歳!』といった初期の押井作品を洗脳気味に刷り込まれた思い出があります…)。

▲『PLANETS vol.10』所収 押井守インタビューより
その押井監督が、表現の深度において、自分の映像表現がどう足掻いても到達できない領域に辿り着いている人物として最大限のリスペクトを捧げているのが、この和子姉ちゃんなのです。
つまり、言葉にするのはとても難しいのですが、最上さんの原初舞踏は、一般的な舞踊やダンスのようにある振り付けや型にしたがって四肢を激しく振るったり見映えのする所作を決めたりするというようなものではなく、その瞬間瞬間の体感にしたがって身悶えするような、記号的な意味づけを拒む予測不可能な微妙な動きの連鎖として展開されるのが特徴です。
それは、そもそも誰かの視覚に供する「表現」ではなく、身体運動の視覚情報はあくまでもひとつの手がかりに過ぎず、最上さんが自身の身体の内部で起きていることとの対話を、鑑賞者自身が自身の身体をレファレンスとして直接的に自分事として共鳴するという原理で行われているものになっている(…と、自分は解釈しています)。
これは、映像の、とりわけ物語を表象する20世紀的な劇映画の表現とはまったく異なる原理の営みであるわけです。そういう境地の存在に、押井監督も畏怖したのだと思います。
そんな背景もあって、数年前から最上さんと宇野との親交が始まっていて、PLANETSでも対談番組に出演いただいたり、『モノノメ 創刊号』でも「身体というフロンティア」というエッセイを寄稿していただいたりしたことが、今号で特集テーマに「身体」を選ぶ大きな伏線のひとつにもなっています。
ただ、残念ながら宇野以下のPLANETSメンバーが最上さんの舞踏を直接ライブで体験する機会はこれまでなくて、僕たちが過去に最上さんの独特の舞踏表限に接していたのは、もっぱら飯田将茂監督のドーム映像作品『HIRUKO』(2019年)と『double』(2020年)を通じてでした。

この2作は、映像作家としての飯田さんが、スクリーンのフレームで切り取られた「映像」の限界を突破するための試みとして、身体の内奥から発せられる最上さんの舞踏の模様を記録し、全視野を覆うドーム映像の体感性で再生したたときに、どんな化学反応が起きるのかを試そうとした実験的な作品です。
言うなれば、押井守監督が脱帽し半ば諦めてしまったところのある身体の内奥からの営みに映像の力で接近するという営みを、飯田監督が新しいツールと蛮勇をふるって改めて継承しようとした挑戦だったと言えるでしょう。
今回取材した『もうひとつの眼 / もうひとつの身体』は、そうした前2作の延長線上に、最上さんの舞踏を、飯田監督の「もうひとつの眼」たるカメラがオンライン配信のために収録していく様子を、厳粛な「儀式」としてライブで観客に体験させようという試みだったわけです。最上さんは最上さんで、自分の身体の内奥で起きていることをより外部の他者に伝わりやすくするために、人形作家の井桁裕子さんが制作した球体関節人形を「もうひとつの身体」として使役。舞踏家と映像作家が、それぞれの扱う「もうひとつの眼」と「もうひとつの身体」を介することで、お互いに歩み寄りつつも対決する、鬼気迫る緊迫感あるセッションが行われました。


この「儀礼」が行われたのが、東京・西池袋にある自由学園明日館の講堂。フランク・ロイド・ライトの弟子筋にあたる遠藤新の設計で重要文化財にも指定されている施設のロケーションの素晴らしさも相まって、宇野ともども初めてリアルタイムで体感した最上さんの舞踏は、言葉を失う圧巻の体験でした。
そしてその挙動を高さ4mものクレーンカメラで追う飯田監督の撮影動作自体もまた、ある種のパフォーミングアートになっていて、映像と舞踏が、すなわち観客自身の「眼」と「身体」が重層的に絡み合うという図式。そこには確かに、「儀礼」と呼ぶに足る何かが現出していたと、その場を共有した一参与者としては思わずにいられませんでした。

はたしてそのただ一度だけの試みから、両者が何を持ち帰ったのか。
言語化以前の境地に挑もうとしたその体験を、批評家・宇野常寛はどんな言葉で打ち返したのか。
「身体」と「眼」と「言葉」の奇妙な三角関係を、ぜひ誌面で確かめてみてください。
『モノノメ #2』のクラウドファンディングはこちらにて実施中です。