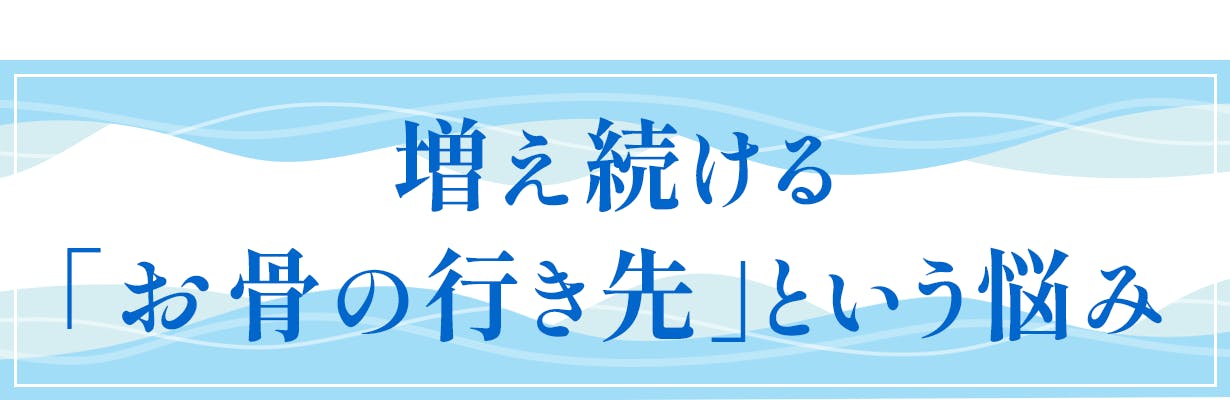
はじめまして。
高野山真言宗の僧侶として活動している(株)明兼坊の柿本明兼と申します。
これまで葬儀業界で20年以上、数多くの方々の最期に寄り添ってきましたが、
近年、切実な声を耳にすることが増えています。
それは「お骨の行き先」についての悩みです。

日々このような相談を受けるたびに、胸が締め付けられる思いがします。
実際に相談者から、寺院での永代供養には50万円から100万円もの費用がかかると耳にします。

納骨堂にしても毎年の管理費や供養料がかかります。
年金生活者の方々にとって、これは途方もない負担となっています。

そんな中で注目されているのが、海洋散骨という選択肢。
しかし、これにも新たな課題があります。
多くの場合、それは単にお骨を海に散くだけ。
供養もなく、ただ「処分」するだけのようなサービスが大半です。
「これで本当に良いのだろうか」という不安の声を、私は数多く聞いてきました。
さらにその費用も5万円前後と決して安価とは言えない金額です。
供養を依頼すれば、別に僧侶へのお布施が必要となります。
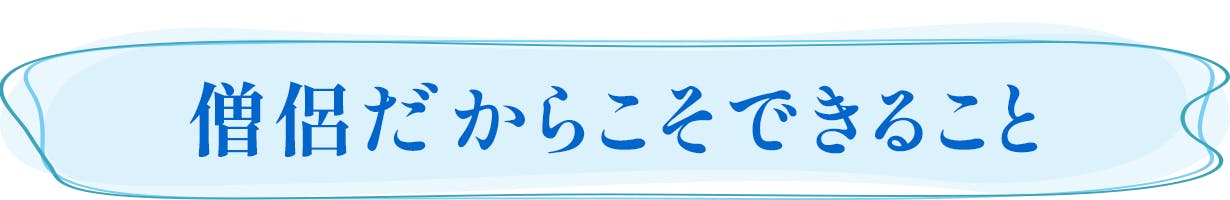

このような現状を目の当たりにし、私は決意しました。
葬儀業界での経験と、高野山真言宗の僧侶としての立場を活かし、
誰もが安心して選択できる新しい供養の形を提供したい。
それが「僧侶による供養付き海洋散骨」という新しいサービスです。

実は大阪湾には、供養の地としての深い、そして美しい歴史があります。
平安時代から、四天王寺では春秋の彼岸に「大念仏会」が開かれていました。
真西に沈む夕日に向かって念仏を唱えれば、極楽浄土への結縁が叶うと信じられていたのです。
その光景は壮観だったと言います。
身分を超えて、一般の民衆から京都の公卿まで、数多くの人々が集まり、同じ方角を見つめながら祈りを捧げた。
中には、夕日を追いかけるように入水する者までいたという記録も残っています。
この歴史は、まさに日本人の魂の救済への深い想いを物語っているのではないでしょうか。

沖に出れば、そこには息を呑むような景色が広がります。
大阪、神戸、和歌山の岬まで見渡せる美しい海。 
岸辺の喧騒を離れれば、そこには澄み切った青い海があります。
この地こそ、まさに極楽浄土への入り口として最もふさわしい場所。
そう確信させる景色が、目の前に広がるのです。
私たちのサービス名「大阪散骨」には、この千年の歴史と、 代々受け継がれてきた祈りの思いが込められています。

私は、 ひとつひとつの工程に深い祈りと真心を込めた供養を提供します。
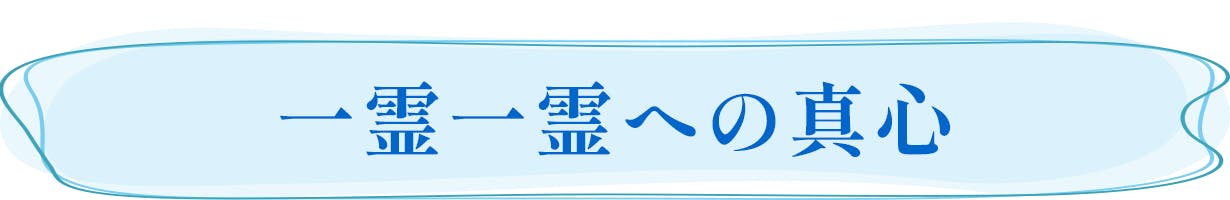
僧侶である私自身が、工程の全てを担います。
無駄を一切省くことで、海洋散骨代行を破格の「2万円(パウダー化込み)」で実現できました。
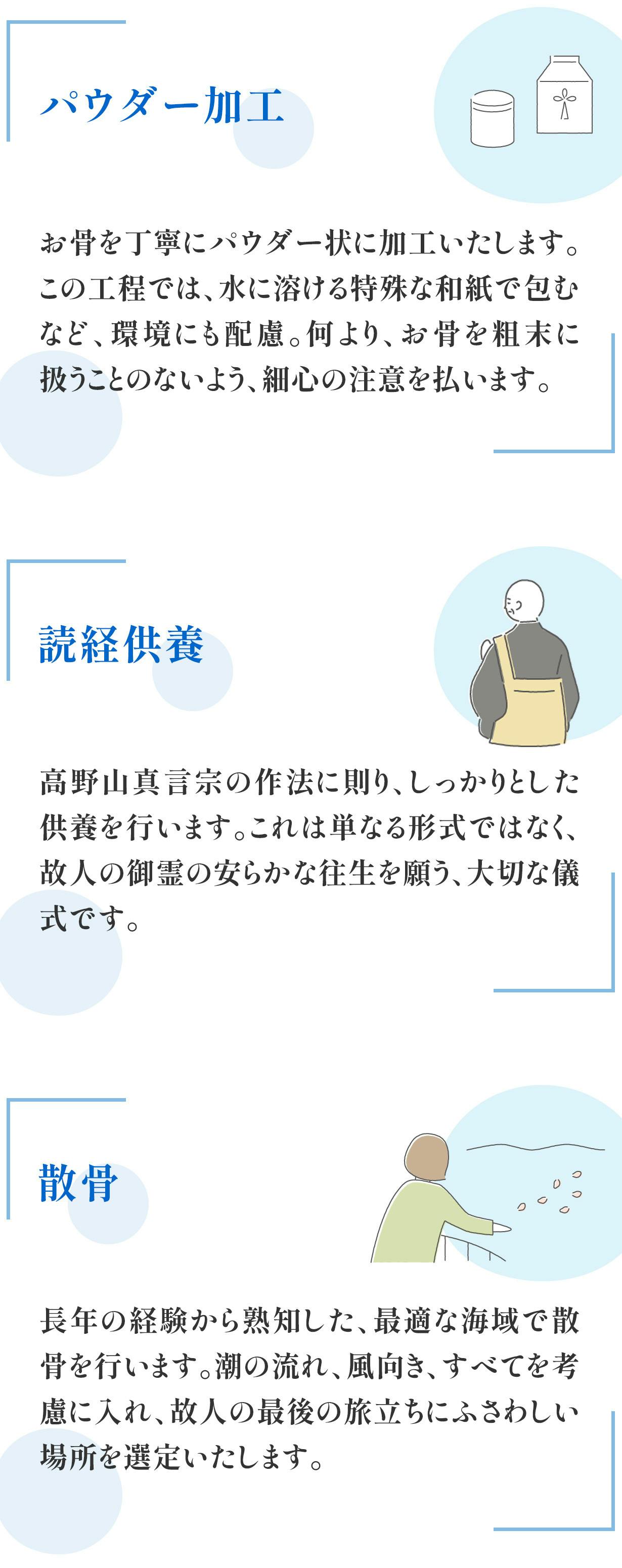

さらにご希望の方には、プラス3万円で三十三回忌までの永代供養を加えることもできます。
寺院での永代供養の10分の1以下の費用で、確実な供養をお約束します。
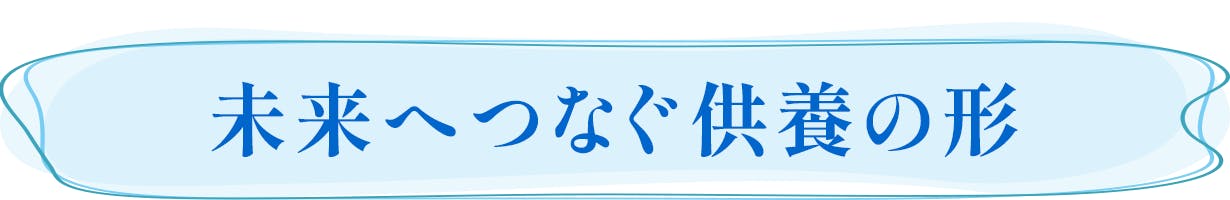
「でも、供養してくれる僧侶がいなくなったら?」
これは、多くの方から寄せられる心配の声です。
永代供養を約束しながら、実際には疎かになってしまうケース。
寺院の後継者問題で供養が途切れてしまうケース。
私は葬儀業界で働く中で、こうした現実も見てきました。 イメージ写真
イメージ写真
だからこそ、この不安に対して、責任を持ってお答えしたいと思います。
私は現在63歳です。
これから仰せつかる場合の三十三回忌の供養は96歳となりますが、一人一人の祥月命日に、お名前や戒名を丁寧に読み上げ、心を込めた供養を行います。
俗名でも戒名でも、ご希望の形で供養させていただきます。
そしてその先も、私が長年培ってきた高野山真言宗の布教会の仲間たちが、同じ信念と慈しみの心を持って確実に引き継いでまいります。
これは私からの、揺るぎない約束です。

大阪散骨は、より多くの方々に安心をお届けするためさらなる発展を目指しています。
大阪湾を見渡せる場所に、供養塔の建立を計画しています。
古来より伝わる五輪塔の様式を用い、地水火風空の五大を表現。
散骨された方々への永年の供養を象徴する、心のよりどころとなる場所を作りたいと考えています。
ご遺族の方々がいつでも訪れ、故人を偲ぶことができる。
そんな大切な祈りの場所として、丁寧に護持していく所存です。
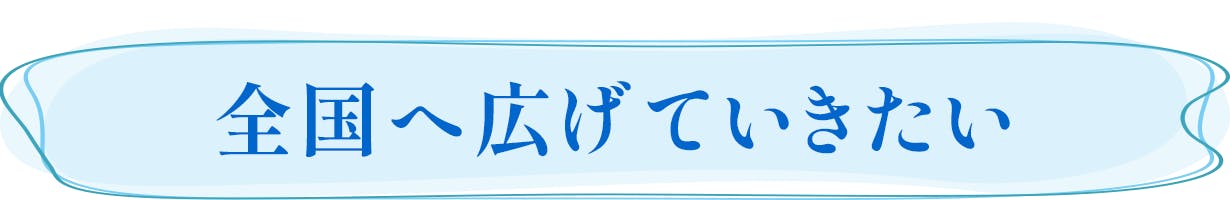
将来的には東北から九州まで、より多くの地域で供養付き散骨を実現したいと考えています。
すでに各地の信頼できる船舶業者とのネットワークづくりを進めています。
散骨に適した海域の選定、安全な実施体制の確立、そして何より、私たちと同じ想いを持って供養を行える仲間との連携。
一つひとつ着実に準備を重ね、より多くの方々に安心できる選択肢を提供していきたいと考えています。

高齢化が進む日本社会で、お骨の行き先の問題は、今後ますます深刻になっていくことでしょう。
私はその現実を日々目の当たりにしています。
「高額な永代供養は望めない」
「子どもたちには、これ以上迷惑をかけたくない」
「お墓を守れる人がいない」
こうした声の背後には、いつも切実な思いが隠れています。
本来であれば、誰もが大切な方を丁重に送りたい。
特に心を痛めるのは、経済的な理由で本来なら望まない選択をせざるを得ない方々の存在です。
また遠く離れた場所で暮らす子どもたちの負担を、 たった一人で心配し続けている高齢者の方々。
そんな方々に、私はお届けしたいと考えています。
新しい選択肢を。安心できる供養のかたちを。
経済的な負担を大きく軽減する方法を。
私にできることは、 僧侶としての使命と、長年の経験を活かして 一霊一霊に真心を込めた供養を提供すること。
そして大阪湾の歴史ある海域で、 穏やかな最期の旅立ちをお手伝いすること。
このプロジェクトを通じて、大切な方々の供養に本当の安らぎを。
残されるご家族に、確かな安心を。
それらを心を込めてお届けしていきたい。
「先祖の供養は、こうあるべき」という既成概念にとらわれすぎず、でも大切なものは決して疎かにせず。
現代に生きる人々に寄り添った新しい供養のかたちを、 皆様と共に創り上げていきたいのです。
この想いに、どうかお力添えをいただけませんでしょうか。
皆様のあたたかなご支援が多くの方々の心の支えとなり、 新しい供養の文化を築く礎となることを、 心より願っております。
株式会社明兼坊
柿本明兼

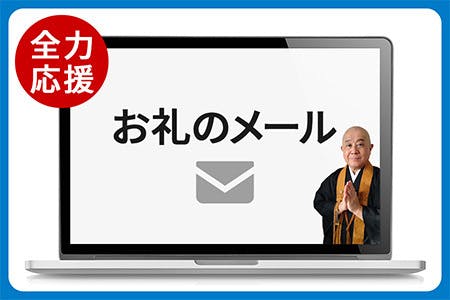


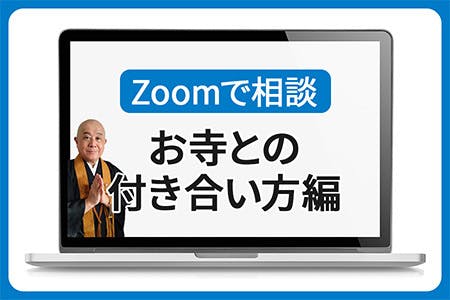
挿入予定





2025年
・2月1日:プロジェクト公開
・3月31日:プロジェクト終了
・4月末〜:リターン配送
最新の活動報告
もっと見るご支援、ご協力、誠にありがとうございました。
2025/04/02 14:01クラウドファンディング期間が終了いたしました。ご支援くださいました皆様には厚く御礼申し上げます。返礼のお品に関しましては4月末から5月初めにかけて送付させていただきます。目標金額には遠く及ばなかったものの、たくさんの方にこのページをご覧いただけたことに感謝いたします。今後も地道に努力を続け、皆様から喜ばれるサービス提供に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。感謝。合掌。柿本明兼 もっと見る祈願文(きがんもん)を一緒にお唱えしましょう!
2025/03/18 16:08朝勤行の最後にお唱えするお経に「祈願文(きがんもん)」があります。実際に最後は回向文をお唱えするので、最後から一つ前のお経です。様々なお経を読経し、様々な御真言をお唱えし、御大師さまの御法号を唱えした後ですから本当に最後の最後です。たった40文字のお経ですが、これが深い!大切なお経です。至心発願 天長地久 即身成仏 密厳国土 風雨順時 五穀豊饒 万邦協和 諸人快楽 及至法界 平等利益(ししんほつがん てんじょうちきゅう そくしんじょうぶつ みつごんこくど ふううじゅんじ ごこくぶにょう ばんぽきょうわ しょにんけらく ないしほうかい びょうどうりやく)意味:(ご本尊様)真心をもって祈願いたします。天地宇宙が永遠に生き、すべての人がこの身このまま仏と成り、この世が仏の世界と成り、天地の運行が順調に進み、農作物が豊かに実り、世界が平和で、人びとが幸せであって、仏さまの御恵み(みめぐみ)が物心両面にわたって平等でありますことを(高野山真言宗 檀信徒必携より)締めくくりに相応しい素晴らしい心に響くお経です。やはり「祈願」は世のため人のためにしてこそ価値があります。また大切な方のために祈願する姿ほど美しいものはありません。皆さんもぜひ神社仏閣や仏壇に祈りを捧げる時にお唱えしてみてください。きっとその徳心がご先祖様に伝わり、安らかな心でお見守りくださることでしょう。※「及至法界」(ないしほうかい)高野山真言宗では(ないしほうかい)と読みますが、真言宗の他派では(ぎゅういほうかい)と読まれることもあるようです。 もっと見る
お不動さんの御真言をお唱えしてみませんか?
2025/03/11 10:09【のうまくさんまんだ ばざら だん せんだ(ん) まぁかろしゃだ そわたや うんたらた かんまん】お不動さんと親しげに呼ばれる「不動明王」さま。初七日から三十三回忌までに、それぞれ亡き方を救い、成仏に導いてくださる十三の仏様。十三仏真言と言って人々にご縁の深い仏様を選んで信仰されてきました。なかでもお不動さんはそのトップバッター初七日に救の手を差し伸べられます。憤怒のお顔、青黒なご身体に右手に剣、左手に縄を持ち、後背に深紅の火焔を背負っておられます。これは世間の災難を断ち、悪事を退治し、衆生(人々)の煩悩や罪科(つみとが)を清めてくださっています。この呪文のような言葉は「慈救の呪(じくのしゅ)」と言われ、お不動さまの御真言の中でも特に広くお唱えされています。意味は【仏さまのいのちに帰依いたします。煩悩と悪魔を退治するため、怒りの姿で世間を救う明王よ、人々の苦悩を救いたまえ。】お唱えは3回、7回、21回のいずれかの回数でお唱えしましょう、 もっと見る
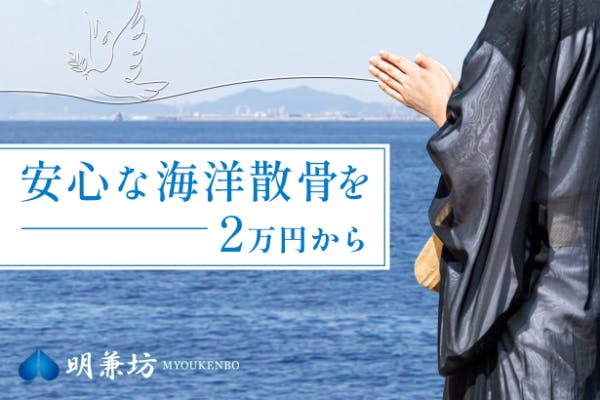














コメント
もっと見る