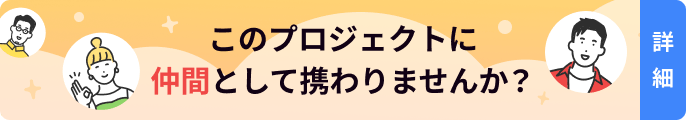11月28日(金)のMLA公演「バッハ×ヴィヴァルディ」は、皆さまのご支援のお蔭をもちまして、盛況のうちに無事終了いたしました。開場前後から多くの方が来場され、会場前には長い列ができました(お待たせして申し訳ありませんでした)。客席もすぐに埋まり、ほぼ満席の状態となりました。 終演後には、出演者へ声をかけてくださる方が多く、公演を楽しんでいただけた様子がうかがえました。 返礼品としてご案内していた、リハーサル見学にご参加いただいた方には、当日の準備や、気合を込めた最終練習の雰囲気を楽しんでいただけたようでした。 皆様よりいただいたご支援は、会場費・広報物・当日の運営などに活用され、公演の実施に大きく寄与しました。活動報告に寄せられた反応も、準備期間の励みとなりました。 リターン品は現在準備を進めており、順次発送してまいります。ご支援くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。これからも皆様に素敵な時間をお届けできるよう、一層邁進してまいります。どうぞ変わらぬご支援とご声援を、よろしくお願い申し上げます!