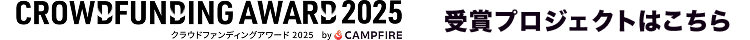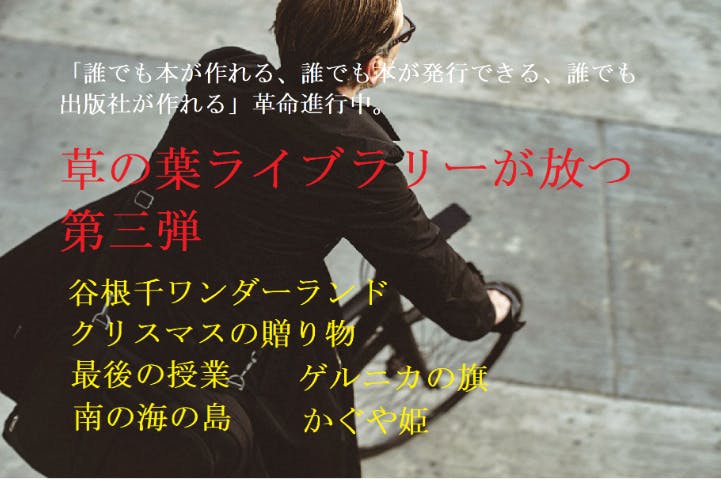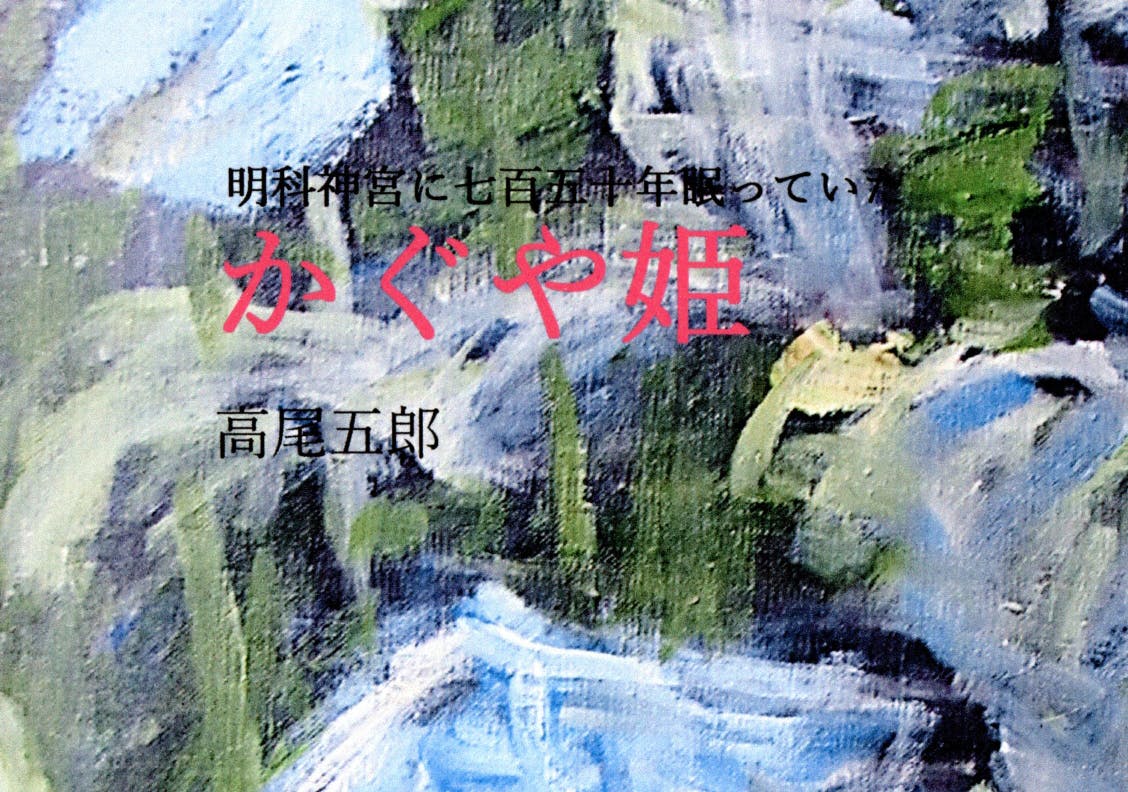日本の川下り 高尾五郎
その川下りが父と母の離婚ツーリングだなんて、そのときは知るよしもなかった。私の一家はちょっとかわっていた。というのもときどき学校を休んで一家そろって川下りにでかけるのだ。ゴールデンウィークとか夏休みとかは問題がないのだが、川は呼んでいるとか、六月の川は素敵だとか、秋の紅葉は素晴らしいとか言って、長いときには一週間も学校を休んで川下りをするのだった。
そんなとき母は、いったいどんな手を使って学校を休ませるかというと、鹿児島にいるおばさんが危篤だとか、花巻にいる父の弟が重体だとか、旭川にいるいとこが交通事故にあって生死をさまよっているとか。もういったい何人の親戚の人を危篤におとしいれたかしれやしない。
でも母の名誉のためにちょっと説明しておくと、母も最初からそんな嘘をついたわけではないのだ。最初のうちは、先生たちにきちんとありのままを説明したらしい。一週間学校を休んでカヌーで川を下ることが、どんなに私と翔太に必要かを。多少勉強がおくれても、そんなものはすぐに取り戻せると思うし、それよりも四季おりおりに姿をかえていく自然のなかに連れ出すことが、どんなに大切かを。ところが学校の先生たちは、こういう理由をがんとして受けつけないのだ。そこで母といつも議論になって、お互い不愉快になってしまう。そういうことが何度か重なったものだから、そんなに面倒くさいことなら、一層のこと、だれかを危篤にしてしまったほうがずうっといいということになったのだ。
もう一つ、母のために弁護すると、その危篤におちいった親戚の人は、私たち一家あげてのお見舞でぐんぐんと元気になったという筋書きを書いているのだ。だから私も翔太もとてもいいことをしたという気分になって、胸をはって学校にもどってくるのだった。
どうしてこんなにまでして私たち一家がカヌーに熱中するようになったかというと、なんといってもその一番の原因は父にあった。大学時代カヌークラブに入っていた父の青春はカヌー一色だったらしい。おれの人生のなかで、あんなにきらきらと光っていた時代はなかった、あれはおれの祝祭日だったと父はよく言っていた。
母を口説いたのもやっぱりカヌーだった。ひそかにあこがれていた母を、川下りに連れだしてカヌーにのせ、母が沈するとすかさず救いだすというたくらみが見事にあたって、プロポーズに成功したらしいのだ。そんな父の影響で母もまたみるみるうちにカヌーの魅力にとりつかれて、父と母のデイトはいつもカヌーでのツーリングだった。結婚して私と翔太が生れると二人の川下りも遠のいたけど、私が幼稚園に入ったときからまるでそのときを待っていたかのように、父は私と翔太を川に連れだしたのだ。
そんなわけで私の一家は日本のあちこちの川にでかけた。日本一の清流といわれる四万十川とか、紀伊半島を流れる吉野川とか、とうとうと流れる釧路川にも遠征したことがある。そんななかで私たちがずうっといきたいと思っていたのが北アルプスから流れくだってくる高瀬川だった。高瀬川は犀川へと名をかえ、さらに信濃川へと流れ込んでいく日本最長の川の源流だった。
その川を下ることになったのが、私が六年生のときのことだった。ちょうど夏休みのときだったので、まただれか親戚の人を危篤にさせて、それを救いにいくという筋書きを書かなくてもよかった。
そのツーリングは久しぶりだった。あんなにしょっちゅう私たちをカヌーにひきずりだしたのに、だんだん父も会社人間になっていたし、母も友達とつくった小さな会社が成功して、朝から夜までばたばたといそがしそうにかけずりまわっていた。だから私と翔太が川下りにいこうと誘っても、
「ああ、いこう。こんな生活はすりきれてしまうからな」
と父は言い、
「そうね、命の洗濯にいかなければね」
と母もこたえるのだが、いざそのときになるとつぶれてしまうのだった。
そのツーリングが近づいてくると、私も翔太も眠れないぐらいわくわくしてきた。ようやく翔太も私もカヌーの面白さがわかりかけていたのだ。それは私たちだけでなく、母もどこかうきうきしているみたいだったし、父も会社から早く帰ってきていろいろとその支度をするのだった。久しぶりの遠征でみんなが燃えてきて、それまではなればなれだった一家が、また団結するようになったことをそのときとても強く感じるのだった。
買物は私と翔太の役目だった。アスパラガスやシーチキンの缶詰、マヨネーズ、マスタード、ジャム、ビスケット、フランスパン、缶ジュース、缶ビール、インスタントラーメン等の食糧。それに秋葉原のスポーツ店にいって新しいパドル、ライフジャケット、ランタンの芯、ガスのポンベを買った。四WDのルーフに二台のカヤックをのせ、荷室にはファルトボートやテントや食糧や着替えを山ほど積み込んで松本に出発したのは昼下がりだった。
最初は父の運転だった。高速道路にのった車は、心地よい響きをたてて突っ走る。高井戸を抜けると車の数もへって、道路も広々としているからなのか、父はさかんに眠い眠いともらす。そこで八王子のインターチェンジで運転は母にかわった。父の運転は慎重でとてもスマートだ。それに反して母は大胆というか乱暴というか、ガクンと止まって私たちをつんのめさせたり、ガッとスピードをあげてのけぞらせたり。運転するときにその人の隠れた性格があらわれてくるというけど、ほんとうの父と母の姿はそんなものかなと思ってしまうのだった。
松本についたのは五時頃だった。長野県の最大の都市というけど、町のたたずまいはこじんまりとしていて、商店街のなかにあるそのスポーツ店は、よくこれで経営していけるなと思うほど小さくてきたない店だった。その店の前に四WDを止めると、私たちの到着をずっと待っていたのか、顔じゅう髭だらけの人がいっぱいの笑顔をつくってとびだしてきた。その人が大岡さんだった。
その夜は、松本のホテルにとまった。夕食のとき大岡さんもやってきて、広い地図を何枚も畳の上にひろげて、自分の庭のように知っている高瀬川のことを説明するのだった。
ここの瀬は七十センチ級の波が立っているとか、ここでテントを張るといいとか、このあたりの川の流れ複雑だとか、ここのテトラポットに引っかかるとちょっとやばいとか。そしてときどき変なジョークをいれて、一人でカカカカカと笑うのだった。そのジョークはだれにも受けない下手なジョークだったが、私は大岡さんのその笑い方が面白くてハハハハハと笑ってしまうのだった。
大岡さんは父の後輩だった。大岡さんもまた学生時代は明けても暮れてもカヌーだったらしいが、父とちがっているのは大学を卒業してからも、ずっとその生活をひきずっていることだった。いまでも小さなスポーツ店を経営するかたわら、日本はおろか世界各地の川に挑戦している。
「大陸のばかでかい川は、眠くて、眠くて、ほんとうに眠くなるんだよ。眠りこんで、どぼんとひっくりかえって、危うくピラニアの餌になりかけたりしたがね。おおざっぱなんだな、万事が。その点、日本の川は繊細だ。女の肌のように、やわらかくて、すべすべしていて、きめこまやかで。わかるかな、翔太君、わからんだろうな」
とエッチなことを言って一人でカカカカと笑うのだった。そんな大岡さんも父や母にむかって何度もこう言った。
「うらやましいな。一家で川下りなんて。こんな女性なら嫁さんにしてもいいと思うよ。こういう家庭をつくることが、おれの理想でもあるな。うん」