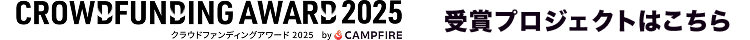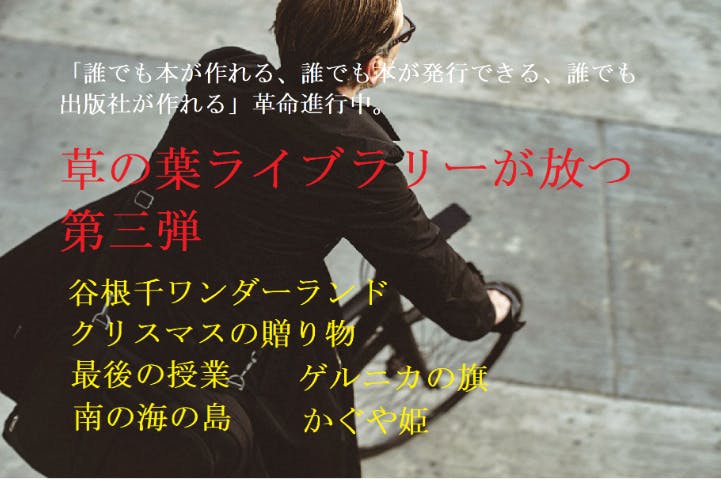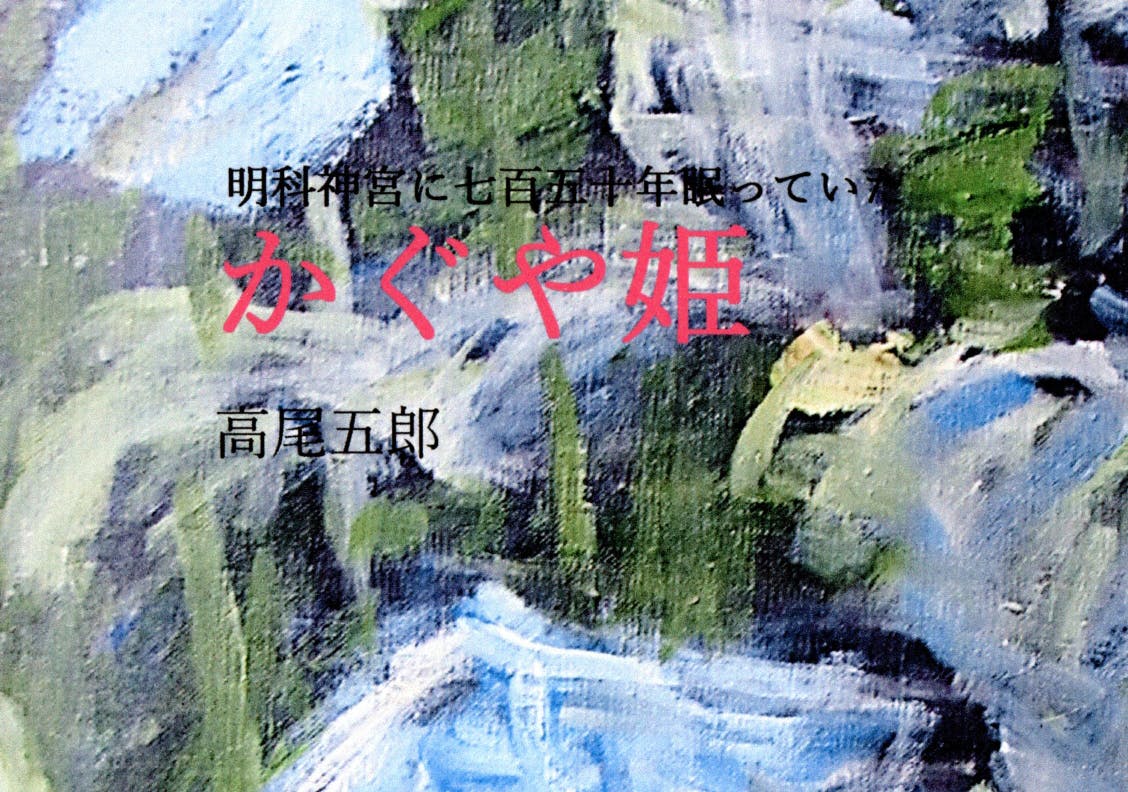決闘 1 高尾五郎
その日の朝、教室に入ると、コンタがこれが黙ってられるかといわんばかりに、
「昨日さ、南小のやつらが城南公園で遊んでやがったからさ、やつらにけりいれてやったんだ」
ぼくは「うそ、けりかよ、まじに」と応じたのは、今野太一のその話を百パーセント信じられないからだった。だからすかさず訊いてみた。
「コンタが、ひとりでやったわけ」
「野口っぺと、サテツとでさ」
それならば百パーセント信じられる。野口佑太も佐藤哲也も相手が弱ければ図にのってそれぐらいのことはやりかねない。
「南小は何人いたわけ?」
「やっぱ三人だけど、おれたちのことガンづけやがってよ。むかつく野郎たちでさ。ここは、南小の遊び場じゃないんだぞって言ったんだ。そうしたらやつらは、じゃあ、ここは西小の遊びかよと言ったからさ。そうだぜ、ここはてめらがくるところじゃあねえんだぞって言ってさ」
「それで、けりをいれたわけか」
「おれなんか、どばどばけりいれてよ。そうしたら、そいつどばっとひっくりかえりやがってさ」
「ほんとうかよ」
「野口っぺも、サテツもけりこんでさ、野口っぺなんて、顔をばしばしびんたしてよ、そしたらそいつ、わあわあガキみてえに泣きやがってさ。おれたちはそいつらに言ったんだ。ここは南小のくるところじゃねえからな、二度とここで遊ぶなよって言ったからさ、もう南小のやつらはあの公園にはこないぜ。あそこはさ、もともとおれたちのシマなんだからさ。ぜったいに南小はいれないでおこうぜ」
とコンタは小鼻をふくらませて意気揚々と話した。
そんな話があってから、しばらくたってからだった。その日、その公園の前を通ると、コンタと野口っぺとサテツが遊んでいるのだ。ちょっとぐらい塾に遅れてもいいやと思い、ぼくもその仲間に入った。ちょうど四人になったから、ジャングルジムサッカーをはじめた。二組にわかれてジャングルジムにボールをけりこむという遊びだった。ぼくとサテツは快調に点をたたきこんで、七対二という圧倒的なスコアーにしたが、そこからコンタたちの追い込みがはげしく、ばたばた点をいれられてたちまち七対六と迫られた。塾にいかなければと思い、またババアがうるさくわめきたてると思ったが、緊迫したそのゲームから一人抜けだすわけにはいかなかった。
そのときだった。公園のコーナーにケヤキの大木がどんとそびえ立っていたが、その太い幹の両側から、まるで黒い風がさあっと吹き込んできたかのように、十二、三台の自転車がどどどどっとまわりこんで侵入してきたのだ。その黒い軍団はあっという間にぼくたちを取り囲んだ。
ぼくは一瞬なにが起こったのかわからなかった。しかしコンタはあっと声をあげて逃げ出そうとしたが、黒い軍団は猫一匹さえ逃がさないぞとばかりに、有刺鉄線のような恐怖の輪を縮めてくるのだ。野口っぺやサテツの顔もひきつり、コンタなどはもう真っ青だった。その子供たちは同じ小学生なのだろうが、レスラーみたいなでぶちんや、ひょろりと背の高い子がいたりして、なんだか中学生のように思えるほどだった。ぼくたちは恐怖で棒立ちになっていた。
黒い軍団のボスらしき子が、ぼくらに火のような視線を放ったまま、
「お前をなぐったやつはこいつらだな」
とかたわらに立っている四年生ぐらいの子に訊いた。
「うん」
と、その子はコンタたちをぐいとにらみつけて、うなづいた。
「どいつだ?」
「こいつと、こいつと、こいつ」
とその子は三人を次々に指さす。三人の顔はさらに恐怖で青ざめ、教室で南小のやつらにけりこんだと意気揚々としゃべっていたその姿は今はなく、あわれなばかりにおびえていた。
しかしそういうぼくだって恐怖で顔がひきつっているのだ。そしてこれはやばいことになった、やっぱりちゃんと塾にいけばよかったと思い、これからリンチというものがはじまる、いつもはババアと呼んでいるくせに、このときばかりはお母さんとなり、お母さん、助けて、なんて甘ったれたことをつぶやこうとしているのだ。
「てめえらが、こいつにけりをいれたんだなあ!」
「いああああの」
とコンタはギロチン寸前の猫のような意味のわからない声をあげた。
「そうだろう。けりをいれただろう!」
とそのやられた四年生が叫んだ。
「やっちまえ! やられただけ、けりをいれてやれ!」
とボスのような男の子が言うと、その子はコンタにけりをいれた。しかしその子は四年生ぐらいだから、まるで力がないのだ。そこでそのボスは、レスラーのようなでぶちんを指名した。そのでぶちんがどっとけりこむと、コンタはあおむけにひっくりかえって、なんだか蛙がお腹をみせてばたばたするようにもがいた。一番悲惨だったのは野口だった。ばしりばしりと顔面をなぐられ、それでもゆるさないとばかりにあちこちにけりをいれたりしている。木村などはもうなぐられる前から、はんべそをかいて頭をかかえてうずくまってしまった。
「こいつは、どうなんだ」
とボスが言った。そのときぼくはあわてて手をひらひらと振って、
「ぼ、ぼ、ぼくはしてないよ」
とちょっとどもりながら言った。
「そうなのか?」
とボスは四年生に問うと、その子はうなずいてくれた。ぼくは助かったと思ったが、そのボスは、まだぼくを許したわけじゃないとでも言うように、
「てめえの名前は、なんて言うんだ」
「戸田です。戸田一郎です」
とぼくはふるえる声でこたえた。
「おれは笹岡だ、てめえに言っておくけど、この公園は南小のシマだからな、これからは西小には使わさない。いいな、そう言っておけよ、西小の全員に。ここで遊んでいたらぶっとばすって、ちゃんと言っておけよ。これはお前の役だからな、ぜったいに守れよ」
その日、ぼくの心はつぶれるばかりだった。生れてはじめてリンチというものを目の当りにしたショックということもあったが、それ以上に心がずきずきと痛んだのは、ぼく一人だけがなぐられなかったということだった。ぼく一人が助かってしまった。ぼくは助かりたいために、ひらひらと手を振って、ヘらへらとお愛想笑いをして、ぼくはしてませんなどと言った。そんな屈辱的な態度をとった自分にすごく腹がたち、ぼくはこんな卑怯な人間だったのかという思いでいっぱいだった。こんな深い心の傷を受けるなら、いっそあのときなぐられればよかったと思った。
そんな痛みを抱いているのに、さらにぼくには重い役が課せられた。ぼくは本質的にまじめ人間だったから、笹岡の言ったことをどのように果たすべきなのかをしきりに考えるのだ。朝の集いのときとか、校内放送とかを使えば、たちまち全校に伝わる。しかしそういう手を使えるわけがなかった。先生にその話を伝える以外にないのかなとちらりと思う。先生ならすべてうまく解決してくれるかもしれない。
しかしその手もまた使えるわけがない。そんなことをちらりとも考えてはいけないことだった。しかしどうすればいいのだ。いったいどんな方法があるというのだ。そのことがぼくの頭を占領していて、その日は食事ものどに通らないほどだった。