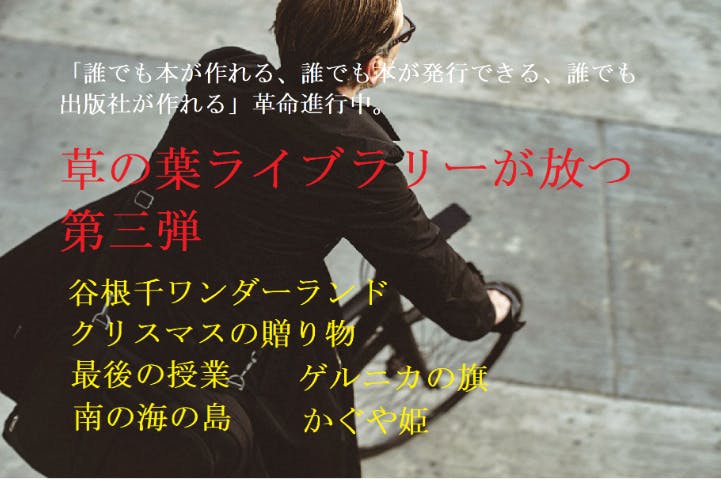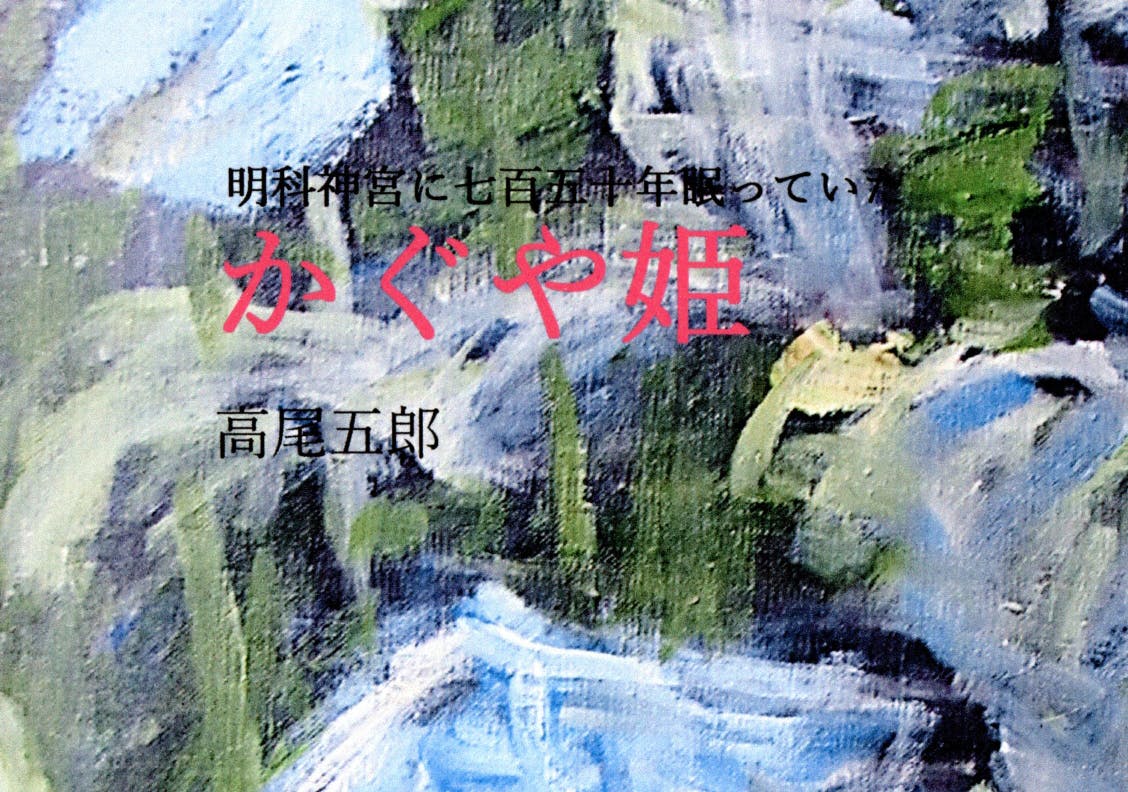ゲルニカの旗 4 高尾五郎
私がざっくりとカッターで切り取られた教科書をもって、宮田先生の前に立ったのは、宮田先生の苦しみといったものが、私の胸に共鳴するからだった。私の苦しみと、宮田先生の苦しみは通じ合うのだ。だから荒廃を深めていくクラスを、一緒に立て直したいというメッセージをこめていたのだ。しかし私の報告をうけた宮田先生がとった行動は最悪だった。
先生はその教科書をもって教室に戻ると、
「これを見ろ。倉田の教科書がざっくりと切り取られている。だれなんだ、こんなことをやったのは。カッターナイフを持ちこんだやつがやったんだ。そうに決まってる。いまから持ち物検査をする。机の上に持ち物を全部のせろ。いまから一人一人調べていくからな」
その検査で一時間がつぶれた。しかしカッターナイフなどどこからもでてこなかった。その日の授業が終わったとき、直美が私を呼びにきた。
「ちょっと、体育館にこいって」
「だれがこいって言うわけ」
「いいから、こいよ。うちら、あんたに話しがあるんだから」
私はくるものがきたと思った。宮田先生のあのやり方は、当然こういう結末になると思った。このクラスには悪童六人組と名のる男子のグループが生まれていた。それに対抗するかのように、女子にも花の六人組というグループがつくられていたが、直美はそのグループの一人だった。私は彼女たちと戦おうと思った。彼女たちとここで決着をつけようと思った。
直美は私を体育館のうらに連れていった。そこに花の六人組が私を待っていた。そのグループの中心にいる真理が私に言った。
「あんたの顔をみると、うちら、むかつくんだよ。いまでもクラス委員づらしてよ。宮田なんかにチクりやがって。宮田にチクれば犯人がわかると思ってたのかよ」
と真理は目を剥いて、ぞっとするような声で言った。クラスでみせたことのない顔と声だった。小学校五年生でも人を恐喝させる顔がつくれるのかと思った。きっと彼女たちもこの対決に必死だったと思う。私はクラスに立っているもう一つの柱だった。決して彼女たちに屈伏しない柱だった。だからすごく私の存在が邪魔だったのだ。その邪魔なものを倒すときがきたのだ。私は負けるものかと真理をにらみかえした。
「宮田なんかにチクんねえで、うちらのところにきたら、ちゃんと教えてやったのによ。あんた、だれがやったか知りてえんだろう」
「もうそれはいいよ。私にはわかってんだから」
「なにがわかってんだよ。てめえ、本当にわかってんのかよ」
「いいよ。あんたなんかに教えてもらいたくないから」
「教えてやるって言ってるんだろうが。だれがやったか知りてえんだろう。洋子、教えてやんなよ」
洋子もその仲間だった。洋子は五年生になるとぐんぐんと変わり、すぐにめそめそと泣き出す子供ではなくなっていた。花の六人組のメンバーになったからだろうか。彼女もまた真理のように目にすごみをきかせ、ぞっとするような声で、
「あたしがやったんだよ。わかるかよ。あたしがやったの」
それは思いもよらぬ言葉だった。洋子が私を抹殺しようとするいじめのネットワークに加わっているのは、花の六人組の一員になっているからだと思っていた。仲間はずれにされたくないから仕方なくそのネットワークに加わっているのだと。
「あんたってさ、あたしをいつもかばってきたけどさ、ものすごく迷惑だったんだよ。クラス委員づらしてさ、人を見下してさ、あたしなんかと人間のできがちがうんだなんて面してさ。あたしをかばってさ、いじめをやめないとか言ってさ、あたしを助けたつもりなんだろうけど、あたしはすごく迷惑してたんだよ。あんたのおかげで、よけいにいじめられたし、よけいに自分がみじめなっていったしさ」
仲間の声が、鋭く洋子に飛んだ。
「やれよ、洋子。佐織が憎いんだろう」
「やれ、やれ、洋子。やっちまえよ」
「ひっぱたけよ、そいつを」
洋子の平手が、いきなりに私の頬にとんできた。無防備だった私は、その平手をまともにくらい一瞬くらっとなり、意識を失うばかりだった。彼女はさらに足でけりつけてきた。洋子の激しい攻撃で足がもつれと尻もちをつくと、花の六人組が一斉に転がった私に蹴りこんできた。
そのとき私の受けたショックはとても大きかった。彼女たちの暴力も大きなショックだったが、一番大きな衝撃は、教科書を切り裂いたのは洋子であり、彼女はずうっと私を憎んでいたという告白だった。私はいつも洋子をかばってきた。いつも洋子の友達であろうとしてきた。しかしそれは彼女にとって、敵意と憎しみを深めていくことだったのか。彼女だけではない。クラスのすべの子供たちにとって、私という存在はそういう子供だったのか。クラスの一人一人に、敵意と憎しみを育てていく存在だった。だからみんなが、私を無視するのか。だから私を消し去ろうとするのか。そのころの私は、自分の存在にぐらぐらと揺れていたのだ。私は生きている意味などない存在ではないのかと。
私に対する攻撃はさらに続いた。その日、美術の授業を終えて、美術室から戻ってくると、私のランドセルがなくなっていた。私はみんなに訊いた。
「私のランドセル、だれか知らない。ねえ、私のランドセル知らない」
しかしだれもがさあっと私から逃げ出す。私への無視は続いていたのだ。それでも私は一人一人にとりすがるように必死になってたずね歩いた。
「ねえ、私のランドセル知らない。私のランドセル知らない」
そのとき窓側の席で、ひそひそとささやきあっている声が聞こえた。それはわざと、私に聞こえるように、ささやいているのだ。
「プールに、変な物が、浮いてるらしいよ」
「ヘえ、プールに」
プールに飛んでいくと、赤いランドセルがプールのなかほどに浮かんでいた。それは三年前に亡くなった祖母に買ってもらったランドセルだった。いまではおばあちゃんの形見にもなっていた。そのランドセルをだれかがプールに投げ込んだのだ。
私は悔しさと怒りと悲しみのないまじった涙をぱろぽろ流して、呆然と立ち尽くしていると、プールの向こう側に、小野君が現れた。小野君は黙ってそのカバンを見ていたが、やがてセーターを脱ぎ、上半身裸になった。もう十一月だった。水は冷たい。まさかと思ったが、彼はざぶんとプールに飛びこむと、ランドセルのところに泳いでいって、そのランドセルを引きながら私のところまで泳いできた。私の目はうるうると涙でくもり、ありがとうと言った。そして、濡れたズボンのことを言うと、小野君は明るく笑って、
「いいから、いいから」
と言って走り去っていった。
それまで私は、小野君とほとんど言葉を交わしたことはなかった。クラスの私への無視は依然として続いていたのだ。しかし私と小野君は言葉をかわさなくても、なにか深い心の交流というものがあったのだ。私たちは互いに目で語り合っているようなところがあった。というのは小野君もまたいじめの標的にされ、それは私なんか比較にならないばかりにいじめられていたのだ。
そんな小野君とときおり目があう。そのとき私は小野君の視線に、いじめなんかに負けるなよ、おれもがんばるからといったそんなメッセージをいつも感じていたのだ。私が不登校にもならず学校にいけたのは、そんな彼の励ましがあったからでもあった。私よりも激しいいじめにあっている小野君ががんばっているのだ。私もまた負けてはならないのだと。
とうとう私のクラスが崩壊する日がやってきた。
「先生、トイレにいってきていいですか」
と野中君が言った。これがその頃、悪童六人組が考案した授業を抜けだす策だった。授業に退屈すると六人組の一人が、トイレにいっていいですかと切り出す。もう漏れてしまうと訴える子に、先生は仕方なく許可を出す。すると、おれもぼくもと言って、六人組はぞろぞろと教室を抜け出していく。そして一度抜けだすと、授業が終わるまで戻ってこなかった。だからそのとき宮田先生は、もうその手にはのらないと、
「授業が終わるまでがまんしろ」
「がまんできねえよ。がまんできねえから、たのんでるんでしょう」
「がまんできなくても、がまんしろ」
「がまんできねえよなあ」
緊迫していく状況に宮田先生の顔面はもう蒼白だ。まるで対決の危機に踏み込むように、先生は、
「がまんできなければ、そこでしろ」
と言った。すると遠藤君が、
「えっ、ここでやってもいいんですか」
と驚いたように叫んだ。それはなんだか勝利の雄叫びのようだった。
「やっていいぞ、やれるならばやってみろ」
「いいんだって、ここでやっていいんだって。本当にやっていいんですか」
「やりたければやってみろ」
「おい、みんなやろうぜ。やってもいいんだってよ」
と野中君がみんなを煽った。すると悪童六人組が次々に立ち上がって、教室の背後にいくと、壁をむかってずらりと並んだ。
「やろうぜ、いっせいに小便をしょうぜ」
と野中君がふざけて叫んだ。そのとき宮田先生の怒りが爆発したのだった。
「ふざけんじゃねえぞ、なめるなよ、てめえら、おれをなめるなよ!」
と叫びながら、椅子をつかんで六人組のところに走っていくと、その椅子を投げつけたのだ。椅子は壁にあたり派手な音をたてて床にころがった。するとその椅子を、今度は田中君が持ち上げて、
「だれもやってねえよ。こんなところで、小便なんかするわけねえだろう。やってねえのに、椅子なんか投げつけやがってよ!」
と叫んで、その椅子を先生に投げつけたのだ。田中君の身長はすでに百六十センチぐらいあり、中学生なみの体力をもっていた。その椅子が宮田先生を直撃したのだ。先生は悲鳴をあげて、その場にうずくまった。血がぱあっと飛び散っていた。クラスが完全に崩壊した一瞬だった。
宮田先生はその翌日学校を休んだ。その休日はずうっと続き、やがて私たちのクラスにはよその学校から新しい先生がやってきた。クラスの崩壊は、宮田先生の精神の崩壊でもあったのだ。宮田先生の打撃は深く、入退院を繰り返していたが、ついに学校に戻ることなく退職したということを、数年後に私たちは知った。
私の宮田先生の描き方は、暗い面だけを強調して、一面的だという気もする。もし別の子供が宮田先生の思い出を描いたら、まったく別の像があらわれていくのかもしれない。しかし宮田先生は、あのときやはり敗北したのだ。宮田先生がつくり上げてきた、あるいはつくり上げようとしてきた教育が。
十三年たったいま、その時代を振り返るとき、宮田先生を打ち倒す最初の矢を打ちこんだのは、私だったという思いがかけぬけていく。子供なりに宮田先生の核心をつかんでいた私は、四年生の社会科の時間に、いっぱい嫌いなものがあると一つ一つ例を挙げて、先生を批判した。あのとき私の放った矢は、先生に深く突き刺さってしまったのだ。だからこそあんなに執拗に、あんなに憎悪をこめて私を攻撃してきたのだ。私を攻撃することで、先生は自らを立て直そうとした。もう一度自信にあふれた先生になろうとした。しかしそのことが、先生の崩壊の速度をはやめていったのではないのだろうか。
私のなかでそんな風にあの頃が回想されて、なにか古い傷が疼くようにいまでも私を苦しめるのだ。宮田先生の心と体に非難の矢を打ち込み、先生の崩壊の端緒をつくりだしたのは私だったのだと。