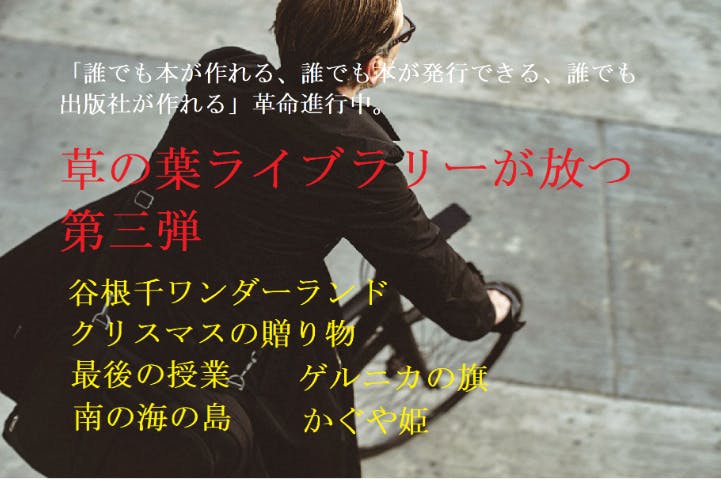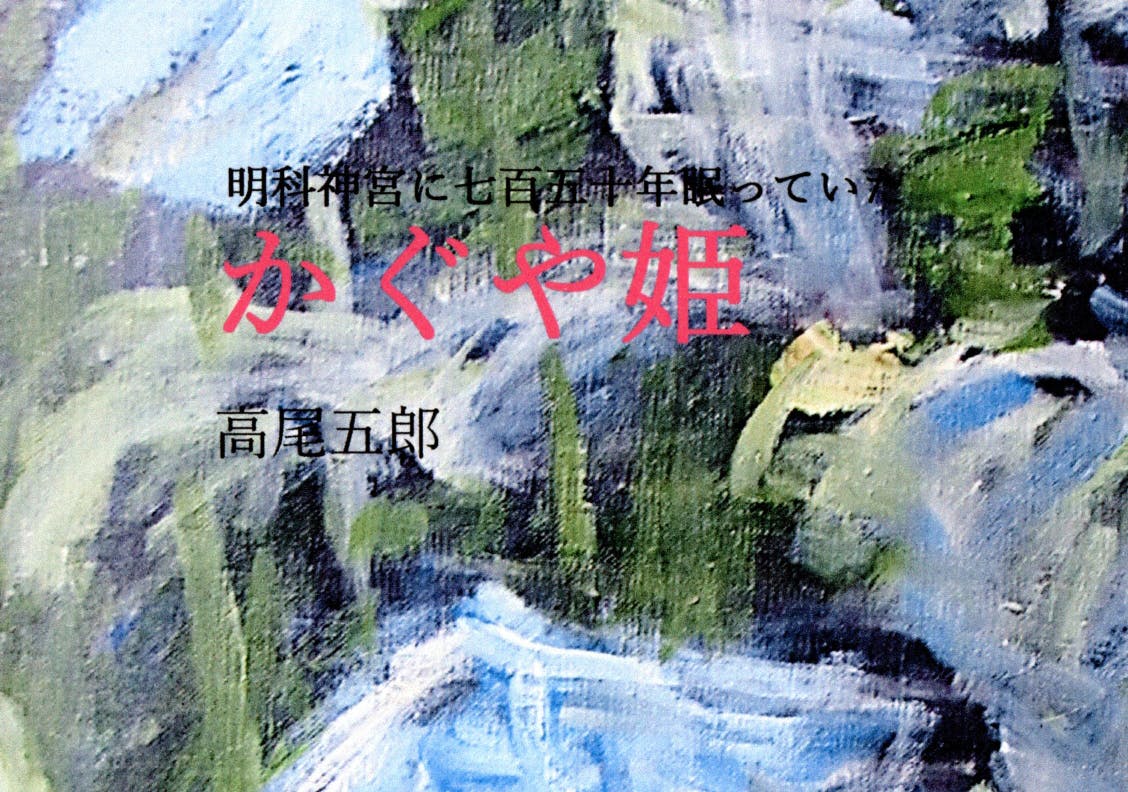夏目漱石は日本語と英語を格闘させて彼の文学を創造していった
しかし一歩外に出ると、ロンドン子たちの話す英語がまったくわからない。イギリス人はジョークが好きである。彼らの会話は必ずジョークにむかって突き進んでいく。そしてパンチライン、そのジョークの落ちが放たれると誰もがどっと笑う。しかし漱石にはそのジョークについていけない、パンチラインがまったくわからない。会話の輪がどっと笑うとき、漱石もまたその場にあわせて仕方なく笑う。彼はそんな自分を嫌悪したはずだ。おれの英語は、世間話の低俗なオヤジギャグ程度のジョークもわからないのか、おれの英語とは所詮御殿場の兎程度のものだったのか、と。
彼もまた今日の語学留学生たちのように、二年も留学すればそこそこの英会話ができるようになるだろうといった思いで英国に渡ったのかもしれない。イギリス人たちの会話の中に入って彼らの放つジョークをともに笑い、自分もまた諧謔あふれたパンチラインの二つや三つぐらい放つことができるようになるだろうと。しかし事態はそんな生易しいものではなかった。二年どころか三年四年、いや十年その地に踏みとどまっても御殿場の兎はどこまでいっても御殿場の兎なのだ。御殿場の兎は御殿場の兎に徹する以外にないと悟ったからこそ、漱石はさっさと引きこもってしまった。
こうしてみてくると、漱石はイギリス留学中に、いくつかの日本人最初の元祖的行動を引き起こした人物ということになる。引きこもりの元祖であり、語学留学挫折の元祖であり、日本人の英語とは御殿場の兎程度のものだということを悟った元祖だったという具合に。なにやら悪魔の書は、英語と格闘した明治の人間たちの戦いの表裏──成功と挫折、勝利と敗北を描くためにこの章の最後に漱石を登場させたかのようだ。
引きこもって格闘していた文学論にも挫折して、なにもかも不本意なみじめな英国留学であったが、日本に戻ってくると破格な地位を与えられる。第一高等学校の教授に栄転したばかりか、かの小泉八雲の後任として東京帝国大学講師の椅子を与えられるのである。さすがにその椅子を提示されたとき漱石は驚きあわてて、自分にはとうてい小泉先生のあとをついで講義する力量はないと辞退するものの聞き入れられず、こんなことならもっと英国でまじめに勉強してくればよかったと鏡子に漏らしている。鏡子はその頃の漱石のことをこう語っている。
「さて四月の新学期から学校に出ましたが、大学が六時間、一校が二十時間、講義のノオトを作ったりして、ずいぶん勉強していたようです。けれども学校は、ねっから面白くないらしく、自分では外国で計画していた著述でもしたい様子でしたが、これまでの行きがかりもあり、ほかに生活費を得る道もないので、目をつぶって学校に出ていたようです。しかしいやだいやだと口ではいっても、根が義務観念の強い人ですから、滅多に休んだり遅刻したりするようなことはありませんでした。かてて加えて外国から持ってきたあたまの病気が少しもなおらないので、なおすべてのことが面白くない様子でした」
その頃から漱石は、自分の内部に横たわる油田を掘りはじめていたのである。そのとき漱石自身も気づいていなかったが、それは驚くべき大油田だった。いやでいやでしかたがない教授生活の合間にこつこつと掘り続けていると、ついに大油田を掘り当てたのか、そこから猛烈なる勢いで言葉が噴き上げてくるのだ。「吾輩は猫である」の誕生である。「猫」が引き金となって爆発的といっていいばかりに新生の日本語が、新生の文体が、新生の小説が誕生していく。漱石が「猫」を世に出したのは明治三十八年、三十九歳のときであった。そして明治の終末期を走るように駆け抜けて大正五年、五十歳のとき没している。わずか十年という月日で、あれだけの膨大な作品を生み出したのは、なにかそれまで彼の内部で蓄積されていた言葉のマグマが一挙に吹き上げてきたといった有様だった。
それは日本語の爆発だった。しかしそれは同時に彼が蓄えてきた英語の爆発でもあった。まるで英文を翻訳したかのような文体で書かれたような初期の作品だけでなく、朝日新聞の嘱託となってその紙上に次々に放った小説の森、「虞美人草」「三四郎」「それから」「門」「彼岸過迄」「こころ」「道草」そして最後の大作「明暗」にいたるまで、彼の文体の背後に英語がある。彼は小説の書き方をあの「高慢と偏見」の作家ジェイン・オースティンに学んだのである。平凡な人々、平凡な人生、平凡な日常の会話のなかにこそ人生の深い真実があることを。小説だけではない。彼が書いたすべての日本語の背後に英語の骨格が、英語のリズムが、英語の触覚が、英語の空気が流れているのだ。
それはどういうことかというと、英語は漱石の言葉の地層のなかに濃厚に流れ込み染み込んでいたのである。その英語が彼の言葉の地層のなかで熟成され、発酵していった。爆発的に吹き上げていった彼の作品の文体は、濃厚に英語がブレンドされた日本語だったのである。だからこそそれまでの日本の文学の歴史にまったくなかった、かくも瑞々しい、かくも新生の息吹をたたえた新しい文学の森を誕生させることができたのだ。
漱石の英語はイギリスでは御殿場の兎であった。イギリス人の放つパンチラインがまったく理解できないどころか、彼らの会話の中にさえ入ることのできない英語であった。しかし英語は漱石の言葉の地層のなかに流れ込み、漱石の文体をつくりだしたもう一つの母国語だったのである。あるいはこうともいえる。すなわち、漱石は彼の言葉の地層で、日本語と英語を自由に交流させ格闘させ溶け合わせていくことのできた精神のバイリンガルだったと。