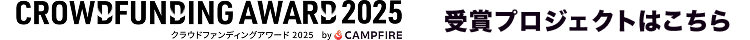小中学校時代、私の通っていた学校には特別支援学級があり、知的障害のある同級生は学校にいる間、ほとんど支援学級で過ごしていた。全校集会などの時は他の同級生と一緒に並んでいたが、集会が終わると、同級生とおしゃべりすることもなく、すぐにまた支援学級に戻っていく。
その様子を見て、当時の私は「自分は勉強ができるから、あの子たちとは違うんだ」と、支援学級にいる同級生を見下していた。今考えれば、彼らとほとんど話したこともなく、どんなことをするのが好きなのかさえ知らないのに、失礼極まりないことだ。
でも同時に、彼らを見ていると、「自分も勉強ができなくなったら、普通学級から追い出されるのだろうか」という言いようのない不安があった。学校の先生からそうはっきり言われたことはなかったが、同じ学校に支援学級があって、知的障害のある同級生は他の同級生と違う教室で学んでいるという事実が、「障害があるのに普通学級で学んでいるあなたはあくまで例外なのだ」と言っているようで、特にテストの前日などは、「このテストができなかったら、私も支援学級に行かなくてはならないのだろうか」と不安で眠れなかった。
学校行事の時は、支援学級の生徒も他の同級生と一緒に参加していたが、いつもほとんど同じ教室にいない生徒を「仲間」だと思えるわけがない。支援学級の生徒とどう話したらいいのかさえ、クラスメートは分からず、お客様扱いするしかなかった。
私も知的障害のある同級生とほとんど関わりがなかったと思っていたのだが、小学校の卒業アルバムに、修学旅行でその同級生と一緒に映っている写真を見つけ、「同じクラスで、修学旅行の班も一瞬だったのか」とびっくりした。同時に、その同級生と話した記憶がほとんどない自分にショックを受けた。(続く)