この度のご支援、まことにありがとうございました
シェア文庫「本と舍(あらか)」へ、そして温泉津へ向けたみなさまの温かいご支援、本当にありがとうございました。
令和6年11月1日から始めたクラウドファンディングは、おかげさまで目標を達成することができました。重ねて御礼申し上げます。
これからのこと
これから「本と舍(あらか)」は以下のスケジュールで進行してまいります。
令和6年11月中旬 着工
令和7年1月中旬 クラウドファンディング終了
令和7年2月〜 内装、棚づくり開始
令和7年4月〜 所蔵はじめ
令和7年5月〜 収まり次第「本と舍」開店
遅くとも6月には開店を目指し、経過をこのクラウドファンディングにてお知らせしてまいります。
ご支援くださったみなさまにおかれましては、この場を借りてお伝えしていく進捗報告をご覧いただけますと幸いでございます。
さあ、ここからが本番です。
引き続き、本と舍(あらか)を、そして温泉津をよろしくお頼み申し上げます。
第二目標達成のお礼。最終目標への挑戦。
公開から本日までで、ネクストゴールとしていた300万円を達成させていただき、たくさんの方々からご賛同・ご支援を賜りました。200人もの皆様が、島根は温泉津町に関心と思いを寄せてくださっていること。それが何よりも嬉しいです。
本当にありがごうございます。
1月12日 夜間にネクストゴールとして掲げていた300万円に達成することができました。皆様からのご支援と、あたたかい応援メッセージの言葉に日々励まされながら今日を迎えることができました。
ここまでご支援をいただいた皆様に、改めて御礼を申し上げます。
今回、西田がクラウドファンディングに挑戦させていただいたのは、自分が惚れ込んで移住した「温泉津」が、100年経っても湧きに湧いているその個性を残しながら在り続けてほしい。そのための挑戦を皆様に知っていただきたいということ。
そして西田と共にこの新しい場所づくりに賛同し、仲間となっていただきたいと考えてのことでした。
ネクストに次ぐネクストゴール
クラウドファンディングは1月18日まで続きます。あと5日。たった5日、されど5日。
西田は残りの期間、ネクストに次ぐネクストゴールとして 3,500,000円を掲げていきたいと思います。
これまで挑戦してきた中で、直接ご支援をいただいた方を合わせると236名もの皆様にご支援をいただきました。
今回、ネクストゴールで皆様からいただいたご支援は、内装・什器制作費にかかる費用として、大切に活用させていただく予定です。どうぞ引き続き温かいご支援・応援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
(令和7年1月13日更新)
目標達成の御礼
本と舍のクラファンへのご支援、並びに本と喫茶のゲンショウシャを応援いただきありがとうございます。
11月1日より開始いたしました、西田 初となるクラウドファンディング『世界遺産と温泉の町 “ゆのつ” にみんなが集える「シェア文庫」を作りたい!』が、皆様からの多大なるご支援により、目標金額に掲げる200万円を達成することが叶いました。
この度いただいたみなさまとのご縁。予想を超える速さでの達成に、驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。
改めてこの場を借りてお礼を申し上げます。
皆様からのあたたかいお気持ちを胸に、シェア文庫「本と舍」が温泉津の一員としてあれるよう、精一杯取り組んでまいります。
ネクストゴールへのチャレンジについて
実は本と舍のオープンへ向けては改修費用と内装・什器制作費を加えると費用の面でまだ課題が残ります。
そこで今回、目標を達成させていただいたこの機会を生かし、ネクストゴール300万円を掲げ、挑戦させていただきたいと考えました。
西田が挑戦を行うことで、一人でも多くの方にシェア文庫が温泉津の新たな地域と人が繋ぐ結束点となることを願っています。どうぞ引き続きあたたかいご支援・応援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
(令和6年12月19日更新)
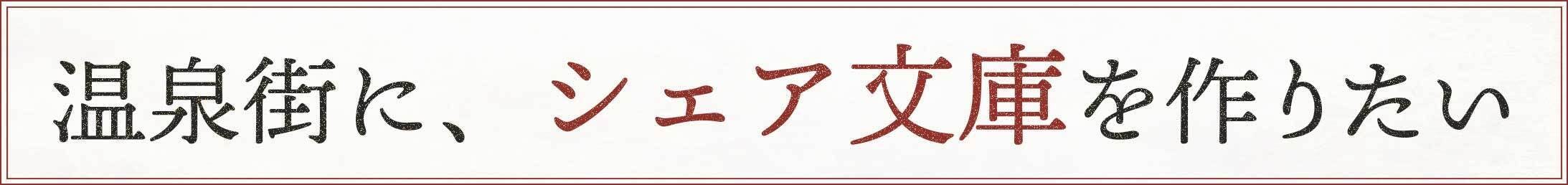
はじめまして、こんにちは。島根県の温泉街・温泉津(ゆのつ)にて、『本と喫茶のゲンショウシャ』を営む西田優花と申します。数あるプロジェクトの中から、当プロジェクトに興味を持っていただきありがとうございます。
この度、シェア文庫「本と舍(あらか)」のオープンに向けて、人生初のクラウドファンディングに挑戦します。
本と舍をどんな場所にしていきたいかをざっくりいうと、
・本を貸し出すだけでなく、さまざまな関係性が生まれる
・温泉津の未来を描く子どもたちとその親、家族が集まれる
・温泉津に暮らす人々と、温泉津を訪れる人とを結びつなげる
いわば、サードプレイスといったところです。
なぜこのような場所を作ろうと思ったか、この場所でどんなことをしていきたいか。
「湧くで温泉津」の合言葉通り、熱い思いを書き連ねました。
最後までお目通しいただき、そして、応援していただけますと大変嬉しく思います。
 引用元:㈱WATOWA私が住む温泉津は、島根県の真ん中あたりに位置する港町です。
引用元:㈱WATOWA私が住む温泉津は、島根県の真ん中あたりに位置する港町です。
かつては石見銀の積み出し港として賑わいをみせており、この地に湧く湯は、鉱夫や運び手を癒やしていたそうです。
 郷愁あふれる魅力に富んだ町(撮影 Ritsu Takada)
郷愁あふれる魅力に富んだ町(撮影 Ritsu Takada)
港から山側に伸びる温泉街は、古くから湯治場としても知られており、温泉町として全国で唯一、重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。温泉津温泉街には大衆浴場が2つありますが、私の行きつけは「元湯」。体を清め、あたためることが目的ではありますが、私にとっては、地域のみなさんとのコミュニケーションを楽しむ社交場にもなっています。
一方で、温泉津には地方ならではの課題もあります。
それは、人口減少と高齢化です。
 (撮影 Ritsu Takada)
(撮影 Ritsu Takada)
総務省「過疎地域等における今後の集落対策のあり方に関する中間とりまとめ」によると、温泉津がある大田市の9割の地区で10%以上の人口減少が見られ、その半数は20%以上の人口減少となる見込みであるとされています。人口減少と高齢化が進むと、労働人口の減少はもちろん、地域住民がこれまで通りの生活を維持することが困難になることが予測されます。
大小さまざまな課題がありますが、私が一番危惧しているのはそうした人口減少から生じる「地域コミュニティの消滅」です。
シェア文庫の名称、「本と舍(あらか)」。
舎という言葉には、在り処、御殿、宮殿という意味があります。
この場所が、①地域自治、地域住民との関係性を育む場、②文化を育む場、③コミュニティが生まれる場になってほしいという願いをこめて「本と舍(あらか)」と名付けました。
温泉津には本屋がありません。地域住民が本と触れ合えるのは、市立図書館のみです。
現状として、“本を気軽に手に取れる場”は限られています。
本と触れ合う選択肢が少ないことは、読む自由、学ぶ自由、本を通じて得られる体験の機会損失につながると考えます。
私が営む『本と喫茶のゲンショウシャ』でも本を扱っており、テーマに沿った本を選書家がセレクトしてくれています。
 本と喫茶のゲンショウシャの店内に並ぶ選書たち(撮影 Hiroki Kondo)
本と喫茶のゲンショウシャの店内に並ぶ選書たち(撮影 Hiroki Kondo)
温泉街で世界遺産でもあるという土地柄、当店には旅行者が多く訪れます。なかには、選書した本を読むために通ってくださったり、選書家がどんな人なのか興味を持って尋ねてくださる方もいます。本を借りて返しに来る地元の方は、「うちにある面白い本を持ってきたよ」と蔵書を当店に預けてくださることもあります。
本がある空間には、いろんな縁やつながりが生まれるー。
お店を始めてまだ1年半ほどですが、“何かが生まれてつながる瞬間”をたくさん目の当たりにしてきました。本と新しい出会いをしたお客様の発見に満ちた表情を目にするたびに、「もっと幅広く多くの人たちが“新しい発見と出会える場”を提供していきたい」という思いが募っていったのです。
「本と舍」は、本を貸し出すだけでなく、さまざまな関係性が生まれる場所にしていきます。
公益性がある場にするために、以下の3つの機能を持たせていきます。
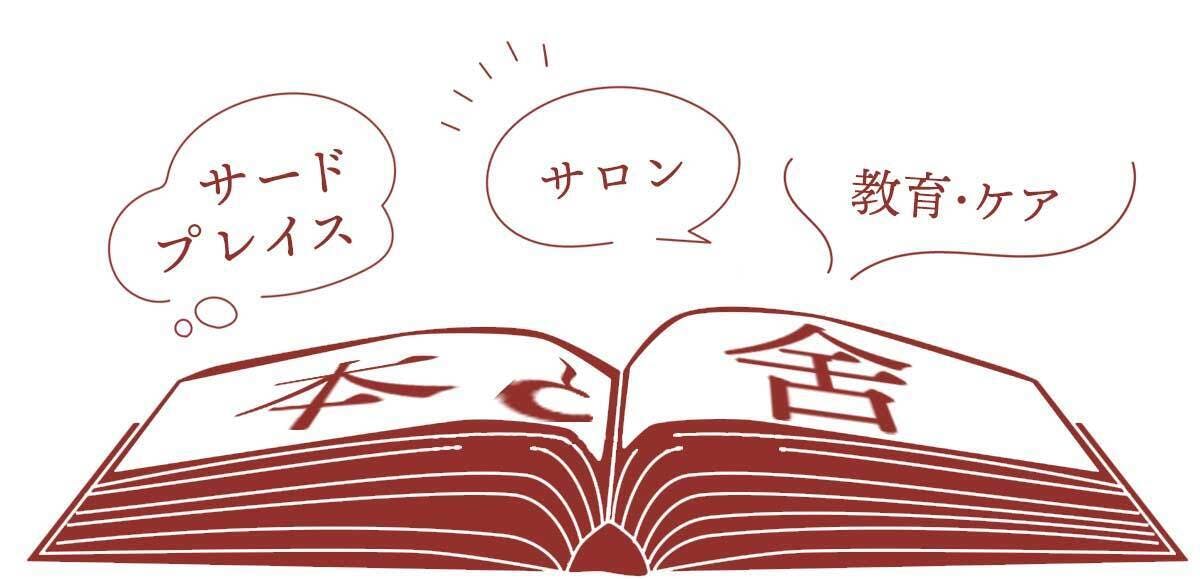
1.サードプレイス機能〜気軽に立ち寄り、集える場所に〜
地元の方にとっては自宅や学校・勤務先との行き帰り、旅行者にとっては宿や観光地を目指す合間の“何でもない時間”。次の予定までちょっと時間を潰したい、今日は何だか寄り道したいーそんなときに、ふらっと立ち寄れる気軽さがありながら、行けば何か新しい発見がある場所を目指します。その場に居合わせる人も、あなたを待っている本も、全く同じ日はありません。「暮らし」と「観光」が交差する地だからこそ生まれる、偶発的な出会いを提供します。読書に没頭するのも、誰かと話すのも、ぼんやりするのも、自由です。思い思いの時間をお過ごしください。
2.サロン機能〜人と人との交流拠点に〜
「本と触れ合える場をなくさない」と言いつつも、あくまでも本はきっかけで、一番の目的はコミュニケーションが生まれる場を作ることです。私は、こんな光景が日常になってほしいと願っているからなのです。
本を読みたいと思う方が本と舍を訪れたとします。
そこに近所の方がいれば話しかけたり、あるいは、観光客から話しかけられたりするかもしれません。
例えば、こんな風に。
「その本、面白いですよね」
「温泉津は初めてですか?」
「私もそこに泊まっているんです」
「最近できたお店のカレー、食べに行った?」
「旅するキッチン、今月はイタリアンらしいよ」
あそこに行けば誰かに会える。観光ガイドにはない温泉津のディープな楽しみ方を教えてもらえる。
そんな認識が広がれば、自然と人が集まり、さまざまな出会いが生まれていきます。
言葉を、心を交わすひとときを過ごすことで、暖かく気持ちに満たされていくのではないかと考えます。
3.教育・ケア機能〜子どもと親と。家族が訪れられるスポットに〜
温泉津のお隣、大森町では保育園留学が始まり、都心部から移住してくるご家族が増えつつあります。そして、この「本と舍」の建設予定地のすぐ側に、小児科医が子ども食堂と、そして将来的には発達障害を持つ子どもたちの診療所を作ろうとされています。
町として未来を育もうとする気運が高まり、それを成し遂げようとする人々がいる。
身近で素晴らしい試みを行おうとしている人の姿に刺激を受け、私も何か役に立ちたいと心から思いました。
そこで、温泉津温泉街で、温泉津の未来を描く子どもたちとその親、家族が集まれるもう一つの場所を作ろうと考えたのです。
本と舍がオープンした暁には、「本と舍に寄ってから子ども食堂に行こう」「診療所の待ち時間に本と舍で本を読もう」というように、それぞれの場所を行き来する流れが生まれるでしょう。
「シェア文庫」では、棚主が自分専用の本棚を作り、そこに選んだ本を置くことができます。
棚主になれる条件は、温泉津在住であること。ただそれだけです。
本の専門知識は必要ありません。老若男女問わず、棚主をやってみたい気持ちがあれば誰でも挑戦することができます。
シェア文庫には、自分が選んだ本を置けるだけではなく、それについて来訪者が感想を書き残せる仕組みを作ります。
ゲストハウスなどでみる、ゲストノートのようなもの、といえばわかりやすいでしょうか。
棚主たちのセンスが光る、シェア文庫。ここに訪れたAさんは、ある棚に心が惹かれます。
「この棚にある本、私が好きなものばかりだなぁ。棚主のお名前は…臼井ふみ。臼井さんという方が選書しているのか」
Aさんは臼井さんにどうしても想いを伝えたくて、メッセージを書き残します。
明くる日、面白い本を見つけたので棚に置こうとやってきた臼井さんは、メモが置かれていることに気付きます。
そこには、Aさんからの熱いメッセージが。臼井さんは自分が選んだ本がAさんに届いたことに胸が熱くなり、
「またオススメしたい本を見つけたら棚に置こう」とこちらが贈り物をもらったかのような気持ちになるのでしたー。
地域住民が棚主になることで「◯◯さんが選んだ本、読んだよ!」「この前シェア文庫で読んだ本を手元に置いておきたくて、本を買ったよ」といったコミュニケーションが生まれるでしょう。もし棚主さんが温泉津温泉街で商いをされている方であれば、そのお店に足を運ぶきっかけになるかもしれません。住民にとっても、“棚主の自分”といった新しい発見と楽しみが生まれます。
 ゲンショウシャで選書をしてくれた、子供の本を専門に司書をされていたまきさん(撮影 Ritsu Takada)
ゲンショウシャで選書をしてくれた、子供の本を専門に司書をされていたまきさん(撮影 Ritsu Takada)
旅先での本との出会いは格別です。日常から離れて手に取る本はいつもは選ばないような本だったり、帰ってから旅先で読んだ本を目にすると余韻に浸れたりします。温泉津は湯治場でもあるので、中長期滞在者が多く訪れます。リモートワークできる方も長期滞在することがあります。シェア文庫があることで、中長期滞在者に温泉津での滞在をより楽しみ、新たな出会いと発見をできる機会を提供できるのではないかと考えています。
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。
シェア文庫「本と舍」を作りたいという温泉よりも熱い思い、それに至るまでに経緯についてお伝えさせていただきました。
少しでも興味を持っていただけたら、大変うれしく思います。
「ところで西田って何者なんだ?」とお思いの方、自己紹介が大変遅くなりました。
私、温泉津在住の西田優花(にしだゆうか)と申します。
 イケてる家具に囲まれご満悦のわたし(撮影 Ritsu Takada)
イケてる家具に囲まれご満悦のわたし(撮影 Ritsu Takada)
西田優花(にしだゆうか)
1984年京都府生まれ。2015年 株式会社オールアバウト入社。官公庁及び自治体におけるインバウンド・アウトバウンド事業に従事。企画立案、クリエイティブディレクター、ウェブ・アプリ開発ディレクションを担当。
日本の地域支援事業(伝統産品などを始めとするものづくり関連)に携わる中で、石見地方に魅せられる。2019年に渡独し、島根の石州和紙を活用した日本の自然美を伝える作家活動をする傍ら、帰国後2021年に「日本の地域の魅力や、ものづくりの価値が最大化され、循環する仕組みづくりに寄与する」をミッションに、合同会社 現象舎を設立。2023年には島根県・温泉津町へ移住。現在、『本と喫茶のゲンショウシャ』を夫と営む傍ら、島根県西部地方の伝統芸能「石見神楽」の習得・継承を行う団体 石見神楽温泉津舞子連中に所属し、稽古に励んでいます。
温泉津に移住をした2022年に、100人を超える町民のみなさまとともに「温泉津100人会議」を実施し、温泉津のタグライン(スローガン)とステートメントを策定。現在も地域ブランディングの実践を行っています。
 2日に渡って開催し、合計111名の町民にお集まりいただき会議をすることができました(撮影 Ritsu Takada)
2日に渡って開催し、合計111名の町民にお集まりいただき会議をすることができました(撮影 Ritsu Takada)
リターンについては、主に応援プラン、体験プランの2種類をご用意しています。
「温泉津に行ってみたいけどなかなか難しい」という方は、応援プランをご検討ください。喜びます。
「温泉津を実際に訪ねてみたい」という方は、体験プランをおすすめします。熱烈に歓迎します。
温泉津の魅力はもちろん、ここ数年で温泉津がどのように変化していったのかなどをお伝えするプランもございます。
温泉津愛と未来への想い、是非とも語らせてください。
 なんでもない夏の夜に突如現れる天の川(撮影 Ritsu Takada)
なんでもない夏の夜に突如現れる天の川(撮影 Ritsu Takada)
スケジュール
令和6年11月中旬 着工
令和7年1月中旬 クラウドファンディング終了
令和7年2月 内装づくり
令和7年4月 本の所蔵
令和7年5月 「本と舍」開店
資金の使い道
空き家修繕費:約220万円
内装・什器制作費:約20〜50万円
手数料(17%+税):約38万円(目標金額200万円に対する金額)
長く人の住んでいない空き家資源をアップサイクルするかたちで施設を作るため、クラファン以外にも補助金や自己資金も組み合わせて実施予定です。(上記 空き家修繕費は想定している補助金分を抜いた修繕費です)
最後に
リターンにある宿泊クーポン、温泉津に滞在する日数が長めのものが多いなあと思われたでしょうか?
そうなんです、温泉津の魅力を知ってほしいがため、ちょっと長めの期間設定にしています。
1泊2日ではわからない、何にも追われないゆっくりとした時間があるからこそ気づける温泉津の魅力を感じてほしいのです。
とびきり熱く濃い源泉掛け流しの湯に浸かり、岩礁の連なる海や猿が行き交う山に遊び、山陰の海の幸や山菜など自然の恵みを食し、石見神楽のダイナミックな舞と囃子に酔いしれ、石州瓦の家屋や寺社仏閣が軒を連ねる町並みを歩き、次代の担い手たちが灯す明かりで憩い、土地の文化を育んできた優しくも熱い人々と触れ合う。
温泉津を五感で味わい尽くせば、日々の営みの中でこわばった体や張り詰めた心はほどけ、自分の中からふつふつと何かが湧いてくるのを感じるはず。
ひとつひとつの細胞がみなぎるような活力が。
視界がすっと開けるようなアイデアが。
変化を恐れず一歩を踏み出すための勇気が。
温泉津の町は、いつでもあなたをお迎えします。
<募集方式について>
本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。
最新の活動報告
もっと見る
令和7年6月1日、本と舍は無事ひらきました。
2025/06/02 14:20令和7年6月1日、「本と舍」は皆さまのおかげで、無事にオープンの日を迎えることができました。心より感謝申し上げます。今日はその時の様子を少しだけお届け。この日、本と喫茶のゲンショウシャでカレーを召し上がっていただいた御縁から、NHK松江局の堤キャスターによる取材を受けました。インタビューにご協力くださったみなさま、ありがとうございます!こちらについては明後日6月4日(水)に放送される予定です。https://www.nhk.jp/p/ts/YMVGG5WWZX/episode/te/N7K7VVXXMP/今週は毎日現場に赴き打ち合わせなどで外出している時間以外は、ご案内や施設のご説明をさせていただきます。温泉津温泉の飲食店でのテイクアウトドリンクなどを持ち込んでいただいてもOKです。本と舍のある温泉津町で、静かなひとときをお過ごしいただけることを、心より楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。 もっと見る
本と舍は6月1日にオープンします。
2025/05/30 06:506月1日、「本と舍(ほんとあらか)」は、ぬるりと本格オープンいたします。派手な催しはありませんが、静かに、しかし確かな熱をもって、本と人がめぐりあう場所として、扉をひらきます。「シェア文庫」とは、無料の貸本屋であり、私設の図書室のようなもの。気になる一冊と出会い、縁側でひと休み。気に入ったら、お宿や自宅へ連れて帰ることもできます。台帳に記名するアナログスタイルセルフサービスのドリンクもご用意しています(1杯100円)。ただ、ちょうどよいサイズのカップが足りていません。もしお寄せいただける方がいらっしゃいましたら、そっとお持ちいただけると嬉しいです。オープンしてからも、本棚を整えたり、本を入れ替えたり、少しずつ手入れをしながら、変わっていくことでしょう。本を読まなくても、井戸端会議のように、ただおしゃべりをしに来ていただいても構いません。本は、温泉津の宿まで、地元の方はご自宅まで、お持ち帰りいただけます。返却は、入口の返却箱までお願いいたします。どうぞ、ふらりとお立ち寄りください。本と舍(ほんとあらか)本と人にめぐりあう家。気になる一冊と出会い、縁側でひと休み。気に入ったら、お宿や自宅へ連れて帰ることもできます。場所島根県大田市温泉津町温泉津口95・愛宕神社の足元・温泉街から徒歩約20秒〜6分時間午前9時〜午後7時(まれに休むこともあります)できること・縁側で読書、深呼吸のひととき・本の貸出・持ち帰り・本への想いや出会いをノートに記すこともこれからの情報発信はインスタグラムにて行います!フォローがまだのかたはぜひ!https://www.instagram.com/hontoaraka/あとそろそろ、ポッドキャストが始動しますぞ‥ もっと見る
本と舍のタグラインができました。
2025/05/18 12:50こんにちわ!GWも終わり落ち着きを取り戻してきた頃。今日も元気な西田です。5月24日(土)に海神楽を控え、日々稽古に励んでおります。ここでちょっと海神楽の告知を‥海神楽とは、日本海を背景に石見神楽鑑賞をすることのできるイベントです。石見神楽は、島根県西部で古くから伝わる伝統芸能で、五穀豊穣や無病息災などを祈願する儀式として舞われてきました。海神楽では、福光海岸の特設ステージで、日本海に沈む夕日を背景に石見神楽を鑑賞できます。今年の海神楽演目、そして開催情報です。神祇太鼓/頼政/岩戸/龍神/大江山/恵比須大黒/大蛇※演目は変更となる場合がありますこのように、刻一刻と変わりゆく日本海の夕景とともに石見神楽を楽しむことができる、奇跡の光景です。写真:山下ミカ、五十川満■開催概要|海神楽2025日時|2025年5月24日(土)開場 16:00 / 開演 17:00(終演予定 22:00)会場|福光海岸 特設ステージ(島根県大田市温泉津町)※雨天時は《温泉津まちづくりセンター》にて開催出演|石見神楽温泉津舞子連中協力|ゆのつ組※ごうぎん文化振興財団助成事業■チケット情報(4/20〜5/21販売)・前売(一般)3,000円・前売(大田市民)2,000円 ※窓口販売のみ・当日(会場販売)4,000円▶ ワンドリンク付き▶ 高校生以下 無料※いかなる理由でも払い戻しはできません【販売窓口】・銀の道商工会(温泉津)・(有)小川商店 ENEOS福光・(一社)大田市観光協会【取置申込】(株)小林工房 ▶ info@kobayashi-kobo.jp(メール対応のみ)■お問い合わせ(一社)大田市観光協会(9:00〜17:00)☎ 0854-88-9950✉ info@kobayashi-kobo.jp(小林工房)■その他・飲食出店あり・離乳食・アレルギー食を除き、飲食物の持ち込みはご遠慮ください最新情報は ▶ https://www.facebook.com/umikagura2019/さて本題の、本と舍のタグラインとステートメントさあここで今回の活動記録の主題であるタグラインとステートメントを公開いたします!今回、本と舍のタグラインとステートメントをまとめてくれたのは、いつもお世話になっているコピーライターの杉元 宏光さん。温泉津ブランディング事業においても、彼の力をお借りしながら言葉づくりをしていきました。そして私は今回のタグラインにおいて「家」と表現をしてくれたことがとても嬉しく感じています。本と舍の役割は公益性が高く、「無料貸本」が主たるコンテンツであってもそこが「家」と表現されることで、単なるサービス提供の場ではなく、人がふと足をとめ、気兼ねなく腰を下ろし、誰に頼まれたわけでもないけれど何かを置いていきたくなるような、親密さと余白が生まれる。「家」には、迎え入れる意志と、見送るまなざしと、時に静かに距離をとる包容力がある。そしてそれは、訪れる人によって少しずつ姿を変えながら、けれども変わらずそこに在り続けるという、時間の器のような在り方でもあるように感じられるからです。そしてステートメント。本と舍という場は、「シェア文庫」ではあるものの、人の気配や、土地の記憶、時間の重なりが沁みこんだ「場」であってほしいと願っていました。この文章は、そうした根底にある願いを、過剰に説明することなく、しかし確かに伝えてくれていると思ったのです。「たくさんの人の想いで生まれ変わった古民家」「手から手へ渡ってきた本」「縁側で絵本を広げる親子」「ふと手にした本から会話が生まれる」──それらの描写はすべて、ここでの日々に実際に起こるであろう出来事として、容易に立ち上がってきます。そして「本は、人は、すべてはめぐりめぐる。/そしてめぐりあう。」という結びの言葉は、この場所の営みを静かに肯定してくれる祈りのようにも感じられました。いかがでしょうか。これからこの場所は、ここで綴られた言葉たちを大切にその魅力を伝えて温泉津温泉街からほど近くの愛宕神社の足元に佇みます。6月1日を開店日とし、着々と準備を進めます。みなさまの応援、ほんとうにありがとうございます。これからも引き続きよろしくお願い申し上げます。 もっと見る






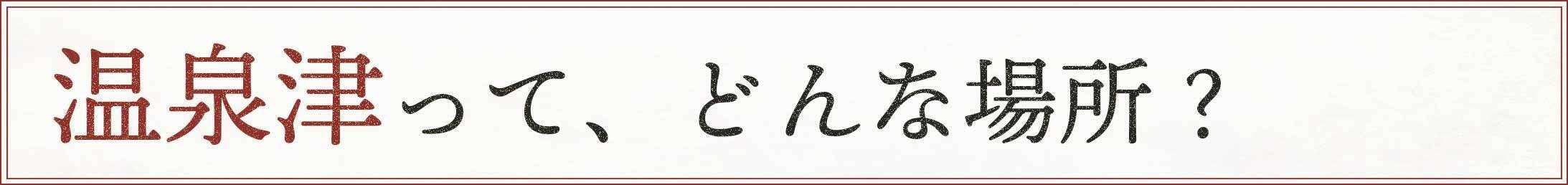


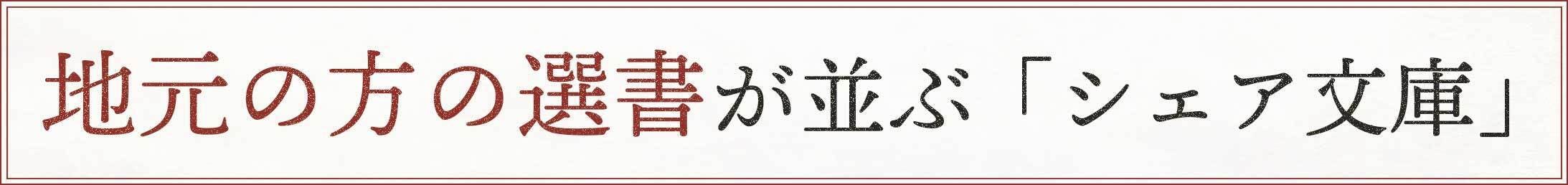
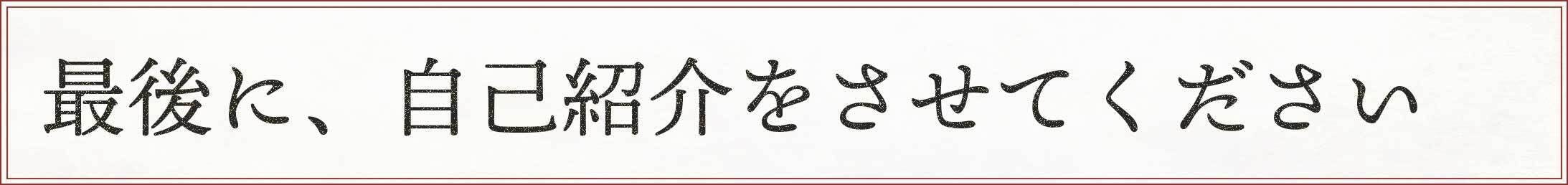
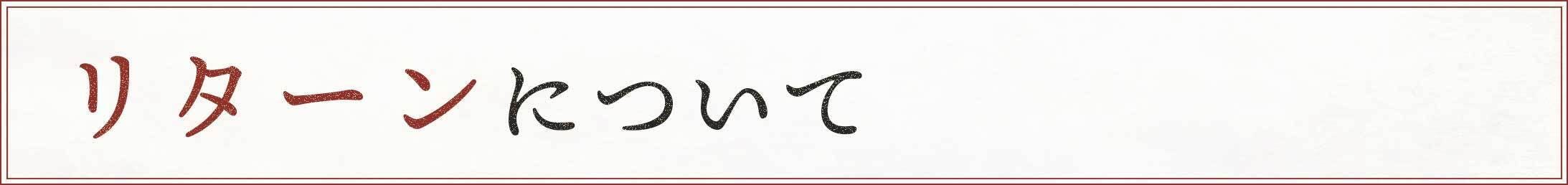







活動報告第21弾(2025年5月29日)を読みました。 5月26日(月)に特別に本と舎の中をご説明くださり誠にありがとうございました。その時の印象を一言で表すとしたら、「ほっこり」です。この場所で時を過ごせば、身も心も「ほっこり」するだろうと感じました。 そして、立地も良いですね。愛宕神社の足元というのが良いです。本と舎に寄る前であれ後であれ、愛宕神社から眺める温泉津の町並みは一際心に染みることでしょう。そして、愛宕神社に据え置かれている謎の梵鐘。その「謎性」は本と舎二階奥の間の「秘めたる趣き」に相通ずるのではないでしょうか!?
活動報告第20弾(2025年5月18日)を拝読いたしました。 「本は、人は、すべてめぐりめぐる。そしてめぐりあう。」 すばらしいメッセージですね。グッときます。 そして、「本と人にめぐりあう家」で時を過ごす人はきっと心の中のもう一人の自分にめぐりあうだろう。そう思います。
活動報告第18弾(2025年2月8日)を拝読しました。 おっしゃるように、時の経つのは早いですよね。 「歳月不待人」 それでも、それだからこそ、 「得歓当作楽」 の心意気が必要ですよね。 " 歓を得ては、まさに楽しみを作(な)すべし " 歓びを感じた時は心ゆくまで楽しむべし、ですよね。 今、優花さんは本と舎の創作ピースをひとつひとつ嵌め込んでいて、その全体像が少しずつ顔を覗かせてきていることに、人知れず、歓びを感じていらっしゃることでしょうね。 その歓びを大いに楽しんでくださいませ。 チャオ👍