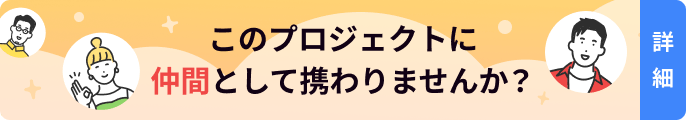いよいよコンサートが明日に迫ってまいりました。今回の活動報告も、大井駿さんの寄稿記事です。《四季》に添えられたソネットの、目的と位置づけについて掘り下げられた、今回も必読の一稿です。* * * * *ヴィヴァルディの《四季》には、それぞれの協奏曲の前にイタリア語のソネット(十四行詩)が添えられています。《春》なら「Giunt’è la Primavera…(春がやって来た)」という行のあとに、あの明るいヴァイオリンの主題が続きます。言葉で情景を思い描かせ、そのすぐ後を音楽が追いかけていく構図です。このソネットが整えられたのは、《四季》を含む協奏曲集《調和と創意の試み(Il cimento dell’armonia e dell’inventione)》作品8が出版された、1720年代前半と考えられます。出版はアムステルダムのル・セーヌ、献呈先はボヘミアのモルツィン伯爵。すでに《調和の霊感》などで名を馳せ、ヴァイオリン協奏曲の大家としてヨーロッパ市場をにらんでいた、充実期のヴィヴァルディでした。同じ頃、彼はヴェネツィアのピエタ慈善院で教えながら、作曲・演奏から興行や契約交渉まで自ら動き回る実務家でもありました。そんな多忙な作曲家が、《四季》のためにソネットという「言葉の枠組み」を用意したのはなぜでしょうか。なぜソネットを書いた(書かせた)のかソネットの作者がヴィヴァルディ本人かどうか、決定的な証拠はありません。ただ、作品8初版の段階ですでに詩と音楽がセットで印刷されていること、一行ごとに対応する描写(小鳥、雷、酔っぱらい、冬の震えなど)が丁寧に仕掛けられていることから、少なくとも彼が綿密に関与していることは確かだと見られます。当時のヴィヴァルディは、協奏曲だけでなくオペラの作曲と興行にも深く関わっていました。舞台では台本(リブレット)と音楽が一体のパッケージとして売られますから、その発想を器楽作品に移し、「言葉の台本付きの協奏曲」という形を考えついたのでしょう。実際、《春》のソネットには小鳥のさえずり、牧人の眠り、春の嵐と雷鳴が順に描かれ、《秋》では収穫祭の宴、眠りに落ちる静けさ、狩りの情景までが、詩と音の二重構造で対応しています。「ここでは鳥が鳴きます」「ここで雷です」と言葉で示し、それを協奏曲で描き分けることで、「うちの楽譜はここまで情景描写できます」と国際市場にアピールしている、とも読めます。四つのソネット、それぞれの「顔」《四季》のソネットは、いずれも自然描写の詩でありながら、言葉づかいや視点にそれぞれはっきりした個性があります。《春》は「目覚め」と「にぎやかさ」の季節です。春の訪れを祝う小鳥やそよ風、通り抜ける春の嵐、草原でうたた寝する羊飼い、バグパイプに合わせて踊るニンフと牧人たちが、田園の一日を明るく彩ります。《夏》は一転して、最初から空気が重く緊張に満ちています。焼けつく太陽にぐったりする人と家畜、鳴き交わす鳥、蚊や蠅、遠くの雷鳴への不安が積み重なり、最後に雹と雷が畑を打ちのめすクライマックスへ向かいます。《秋》になると視線はぐっと人間寄りになります。農夫たちは踊りと歌で収穫を祝い、ブドウ酒を飲んでやがて眠り込みます。世界が静寂に包まれたあと、狩人たちが角笛と銃と犬を連れて出発し、獲物が倒れる瞬間までが描かれます。《冬》は身体感覚の強さが際立ちます。凍てつく雪の中で震え、足を踏み鳴らし、歯をガチガチ鳴らし、やっと暖炉のそばでひと息つく人びと。氷の上を慎重に歩き、滑って転び、また立ち上がる姿の背後で、北風が木々や扉をきしませます。こうして見ていくと、《四季》のソネットは単なる「風景描写のラベル」ではなく、四つの独立した小劇であり、その一行一行に応じてヴィヴァルディが音楽の場面を配置していることが分かります。ソネットの顔つきの違いを感じながら音を聴くと、《四季》の協奏曲もいっそう立体的に浮かび上がってくるはずです。* * * * *これまで折に触れて解説をいただいてきた、《四季》に添えられたソネット。その位置づけや狙いについて、示唆に富んだ視点の解説でしたね。「言葉の枠組み」と「音楽」の二重構造を追求する姿勢は、まさに私たちがプロジェクトで目指す「本質を探求し、新たな価値を創造する」というテーマに通じるものです。このメッセージを力に、コンサートの成功に向けて、一層尽力してまいります。引き続きのご支援と情報シェアをどうぞよろしくお願いいたします!