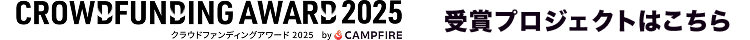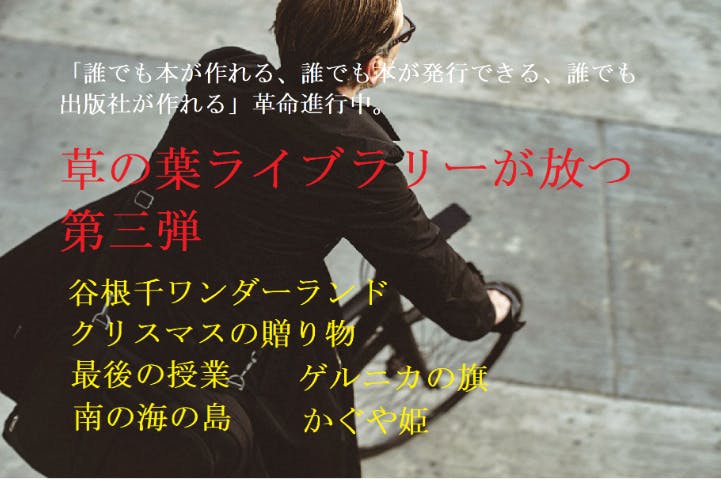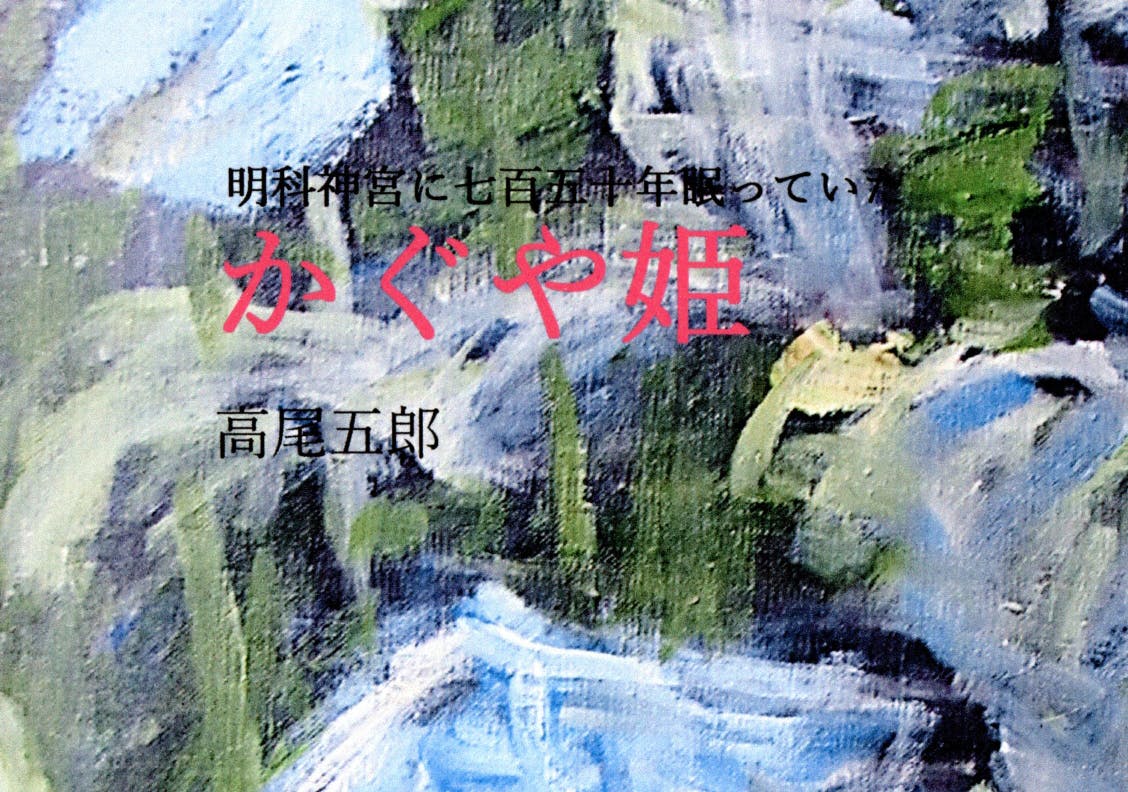ゲルニカの旗 1 高尾五郎
1
私はまた時計をみた。パリ行のエール・フランスに搭乗するまであと一時間あまりある。読むのでもなく、ただ開いているだけの文庫本を、膝の上に置いて、広いロビーを行き来する人の波を見回した。秀雄はやっぱりこないだろう。しかしやってくるかもしれない。北アルプスで、あわや遭難寸前の私を救い出しにきたときのように、彼はこの人の渦のなかからその姿を見せるはずなのだと、私はなおもすがるような思いでそう思った。
この旅はもともと秀雄とともに旅立つためのものだったのだ。長い裁判が終わった。なんと十二年にもおよぶ裁判が。それは私の解放の日だった。私は文字通り自らを解放するために、マドリードの芸術センターにあるゲルニカの絵の前に立ち、過去のしがらみをすべて脱ぎ捨てて、秀雄とともに新しくなるための旅になるはずだった。しかし一転して、この旅はその彼との別離の旅になるのかもしれなかった。彼は私がはじめて愛した人だった。私の心と体のなかに最初にはいってきた人なのだ。その彼をいま私は失おうとしている。私のなかに苦しくせつなく彼の姿が浮かび、彼が私の手に残していった、彼の書き込みが一杯にある、ヘンリー・D・ソローの「森の生活」に目を落した。
唐突にという言葉があるけど、まさに秀雄は唐突に私のなかに侵入してきた。その日、坂本教授のゼミを終え、研究室のある建物から外にでて、緑あふれる構内を並んで歩いていたその男が、いきなり私に告白したのだ。
「倉田佐織という人に会いたかったんだ。一瞬にして恋に落ちたんだからな。そういう恋ってあると思わないか」
そのときの私もなんだかすごく変だった。大学の構内を抜け出し、町に出ると、裏通りをどんどん歩いていく。その彼のあとについていったのだ。
そのゼミがはじまる前に、坂本教授はもちろんその闖入者を私たちに紹介した。岡田秀雄君は四年生だが、卒論を書くために聴講したいというので特別に許可したと。講義は教授をぐるりと取り囲んで、さかんな討議のなかで行われるが、対面にすわったこの闖入者は、なにか燃えるような視線を私に向けているのだ。私はなんだかその時間は、くらくらとしていたという伏線があったのだが。
「君に会いたくて潜り込んだけど、大学院の授業って、意外と幼椎なんだな」
その喫茶店は、松本城の一角からのびている裏通りに立っていた。テーブルが三つしかない小さな店だったが、コーヒーが松本一旨いと秀雄はいった。そのコーヒーがやってくると、彼はそれを一口すすり、自己紹介でもするように自分のことを話した。
彼の実家は会津の山奥で旅館を営んでいて、一家の期待は秀雄にその家業を継いでもらうことだった。しかし彼はそんな小さな世界に閉じ込められるのはたまらないと、高校を卒業するとアメリカに渡った。半年かけてアメリカ大陸を横断すると、目的地のニューヨークに住み着き、そこでほぼ三年、道を切り開こうと苦闘したが、世界の首都で自己を確立していくのは容易なことではなかった。そのとき彼のなかに現れてきたのは、あんなに嫌っていた山また山に囲まれた郷里だった。彼にとって新世界とはむしろあの山のなかにあるのではないのか。これからの時代の最先端の仕事は、あの鬱蒼と木立が繁る山のなかで生まれるのではないのか。
「ニューヨークで、いやというほど自分に力がないということを知った。世界を切り開くための根本の力がね。それでこの大学に入った。ずいぶん遅れた大学生だけど、しかし学問するということの素晴らしさがよくわかったよ。もし人並みに大学生になっていたら、こんなに一生懸命勉強しなかっただろうな」
それから彼はザックから「信大論集」の最新号を取り出すと、私の小論が載っているぺージを開いた。
「君のレイチェル・カーソン論にとても感心したんだ。文章が美しい。それに内容が実にシャープだ。ぼくはこの文章にたちまち惚れこんだってわけだよ。文章に恋したってわけかな。そういうことってあるもんだね」
一年に四号発行されるその学術誌の最後のページが、大学院の学生たちにあけられていた。そのページに私の四十枚ほどの小さな論が載ったのだ。それは新たに取り組んだ作品ではなく、大学時代に書いた卒論を下敷きにしたものだった。だから私の歴史を知っている人には、たぶんその小論は私の停滞と後退と、そして大学院での私の生活の敗北を告げる作品だとたちまち見破ったことだろう。とすると彼は、私の蹉跌の文章に恋をしたということになる。
「大学の先生たちの書いた本って、よくわかんないんだよな。何度読んでもさっぱりわからない。読めば読むほどわからなくなっていく。おれってよっぽど頭が悪いんだなって思っていたけど、信大に入って彼らの本が理解できない理由がわかったよ」
「どんな理由?」
「大学の先生って、はるか高みにあって、彼らの書く文章は絶対的なものだと思っていたわけだよ。とろが実際は、彼らは正しい日本語を書ける人種ではなかったんだな。彼らの書く日本語そのものに欠陥があった。だから何度読んでもわからないのは当然なんだ」
「ああ、それは言えてるわ」
「そんななか、君の文章は本当に自分の言葉だけで書かれている。しっかりと描く対象がわかっている。それに文献からの引用がない。教授たちの文章っていつでも引用だ。アメリカやヨーロッパの学者たちの論文の。彼らの知的創造がこんがらがってくると、すぐに引用してくる。彼らの知的冒険が行き詰ると、また引用だ。要するに彼らは独創的な論文を書けない人種だったんだよ」
「それは本当に正しい意見だと思う」
実に正確に、教授たちの論文の正体を見抜いているなと思った。私は大学院生だったが、なんだか彼の方が二年も三年も先輩のようにみえた。
「おれの卒論、そんな論文にしたくないよな。引用に次ぐ引用、引用をたくみに繋ぎあわせたクソみたいな論文なんてさ」
「何を卒論にとりあげたの?」
「ヘンリー・ディビット・ソローとレイチェル・カーソン」
「ああ、それでカーソンに興味があったわけね」
「二人の戦いはよく似ている。ソローは文明のなかに紛れ込んだ現代人に、自然に帰れと叫んだのであり、カーソンは沈黙の春と戦った人だ。二人の生きた航跡は似ている。おれはそういう二人の戦いをクロスさせながら、文明と自然というテーマの論文に取り組んでいる」
「とても雄大なテーマね」
「そうなんだ。ものすごく大きなテーマだ。しかし山は高いほどいい。高い山ほど人間を強く大きくしていく。おれが登るべき北アルプスなんだな」
「うん、それこそ信大魂だわ」
「君の論文を読んだとき、倉田佐織という人に会いたいと思ったわけだよ。なんかさ、おれの書くべき言葉が、そこに書かれているわけだよ。おれが書かなければならない言葉が、もうそこに書かれているわけだよ。こいつ、おれの前を走っているな、こいつの顔をみたいってね」
「実際に会ってみたら、がっかりしたというか、なあんだって思ったんじゃない」
「教室に入ってさ、すぐに君が倉田佐織だってわかったよ。なんかさ、そのときこれって運命的な出会いじゃないのかって思ったんだよ。君とおれは運命の赤い糸でつながっているんじゃないかってさ」
それが秀雄と私の最初の出会いだった。私の書いた小さなカーソン論が私たちを引き合わせたということだった。私の書く言葉にそんな力があるなんて驚きだった。しかし私には、もともと文章を書くことに、ちょっとした自信があったのだ。言葉を紡ぎだし、その言葉に磨きをかけて、上質のタピストリのように仕上げていくことに。それはある体験があるからだった。