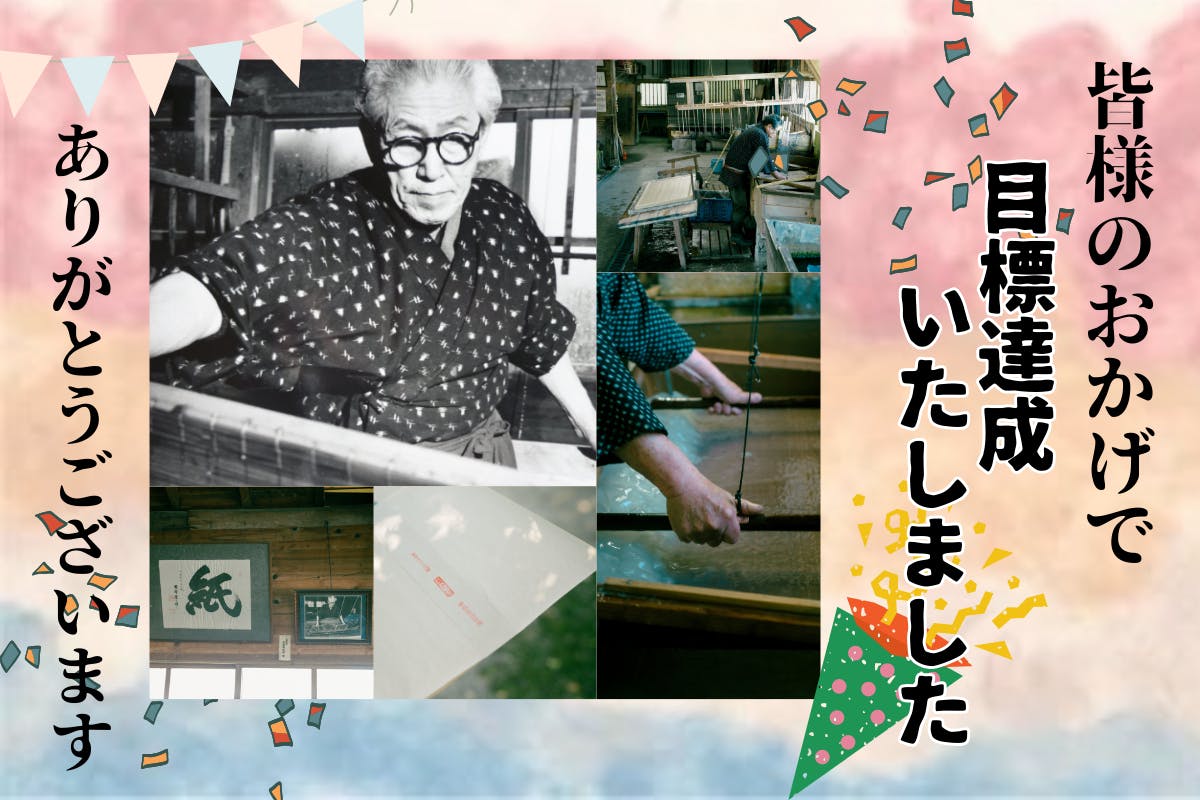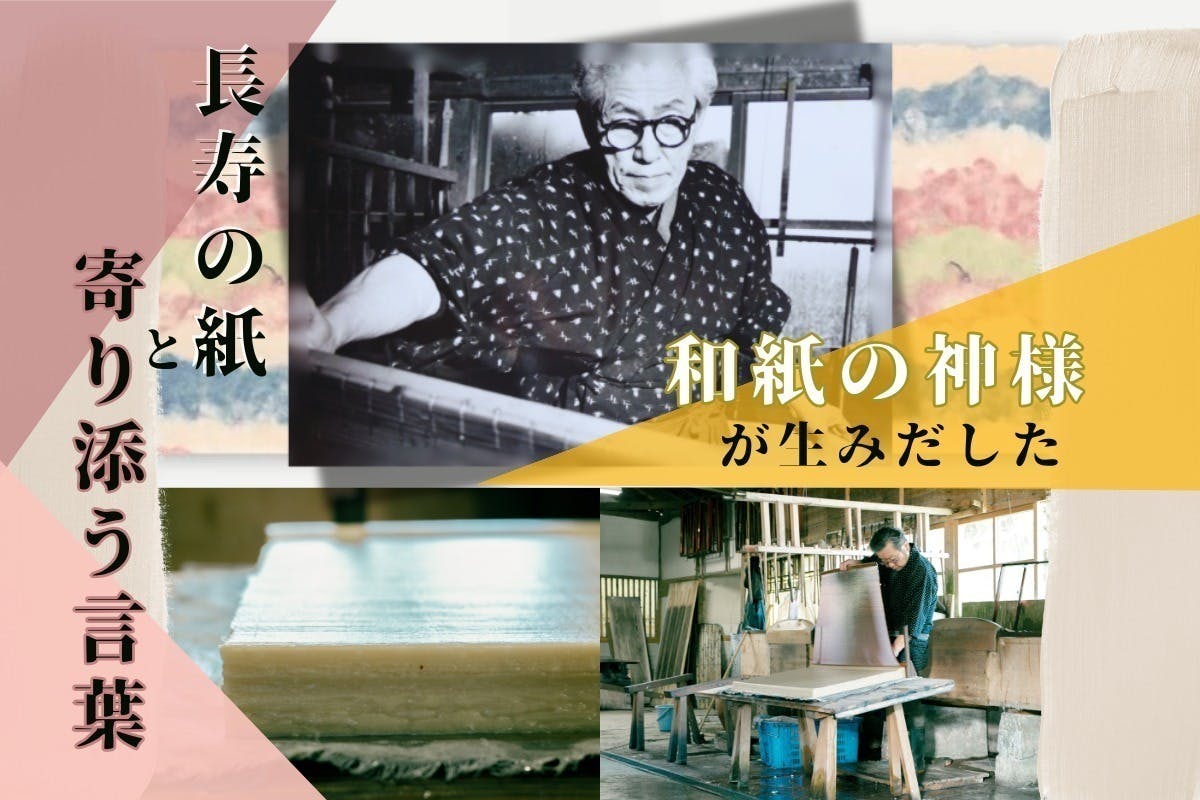おはようございます!今日は出雲民藝紙を使われている職人さんを訪れました。島根県唯一のだるま職人堀江さんです。松江市で工房を構えられ、干支だるまはもちろんのこと、アマビエだるま、出雲の神話に出てくる神様のだるまなどなど、デザインもかわいいおしゃれなだるまを制作されています。サイズも小さくて作業されているお部屋にずらっと並べられた様子も愛らしい!出雲民藝紙をちぎり絵のように貼り合わせた模様に金のリボンが描かれると完成です。安部榮四郎記念館でも購入していただけますよ!和紙×手仕事のリターンも揃えていますので、ぜひご覧くださいね!