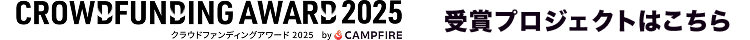島を好きになって暮らしている人たちとの出会い再び、もめです。わたしは岡山で立ち上げた宿、「あわくら温泉 元湯」と、豊島を往来して、準備をしています。ゴールデンウィーク期間は、青空カフェ実施のために、豊島に滞在していました。 豊島にいると、この島が好きになって「移住したい/移住したんだ」という方に度々出会います。特に女性が多い印象を受けます。「ここで暮らしたい」「じゃあ何を生業にしようかな」という順番。豊島は、大型店舗など便利なものは一切なく、穏やかな島。 「理由はわからないけれど、出会ってしまって好きになってしまった」 その姿は、生まれ育った神戸の街を出て、岡山の田舎町で暮らし始めた9年ほど前の自分と重なるところがあります。 街育ちの私が、田舎に暮らし始めた9年前。 私にとって田舎暮らしはじまりの土地は、岡山県のある田舎町。70年代の古着で身を固めた神戸のシティーガールが、ほぼ無人の駅に、ベージュのローファーで踏み入れた時の驚き。とっても静かで、のどかで、何もない。水路は蓋がされていなくて、水の流るる先が見えること、夜空には星が瞬いていることを知りました。豊島に居ると、何もないその町での暮らしの全てが愛おしかった、そんな瑞々しい記憶がよみがえります。 タイトなスカートから、もんぺに履き替え、田畑を耕し、古い民家の自宅に友人知人をたくさん招き、その町のファンを増やすことが喜びでした。田舎暮らしへの予備知識は何もなかったけれど、身体がその土地土地に慣らされ、あらゆることを経験しました。 初めて暮らした田舎町で田んぼをする私 三年暮らしたあと、また奥深い棚田だらけの集落に行って、山仕事をしたり、古民家の改修の手伝いをしたり、鹿を捌いて食べたり、自宅で子を産んだりしました。さらに三年あとには、森林に囲まれた地域に行き、薪でお風呂を沸かしたり、温泉宿を営んだりしました。さらに三年たった今、離島でも宿をはじめることとなりました。 2箇所目の暮らしの場で鹿を解体する私 薪を焚べる私 岡山で宿を始めた頃の私 いつでも帰れる場所があれば、生きていける 色々な土地でいろいろな出会いを繰り返し、どんな場所でもそれなりに適応できるタフさを手に入れてきたけれど、折に触れて思い出し、心の支えとなっているのは、はじめて暮らした町でお世話になったHさん。Hさんは、わたしのことを本当の娘のように大切にしてくださりました。神戸から出てきて、寂しくて心細かった時、寂しい時にはいつもHさんの家に駆け込んできました。同世代の友達もいなかったので、40くらい離れたHさんの友達グループに混ぜてもらって自転車でお茶しに行ったり、晩御飯を食べたりしました。Hさんの畑で採れた野菜は、私にとって、農法とかを超えて、何より美味しくて元気になる特別な存在です。今でもこの野菜を食べること以上に、心身が満たされていくことはありません。Hさんのいる町を離れた後も、節目節目で会いに行き、「もめちゃんが決めたこと。応援するわよ。」と声をかけてもらって安心して前に進んでいます。 田舎で暮らすことは、美しいことだけではありません。よそ者に限らず、若者に限らず、色々あります。色々とある中で、日々の暮らしを淡々と営み、出ていく人を見守り、来る人を迎え入れる。そこに帰れば、その人がいて、どんな自分も受け入れてもらえると思えば、安心して生きていける。わたし個人では到底及びそうにもないけれど、mammaという場が、そうなるといいな。誰かにとってmammaが、私にとってのHさんみたいな存在に。 そんな想いが改めて心に浮かんだゴールデンウィークでした。