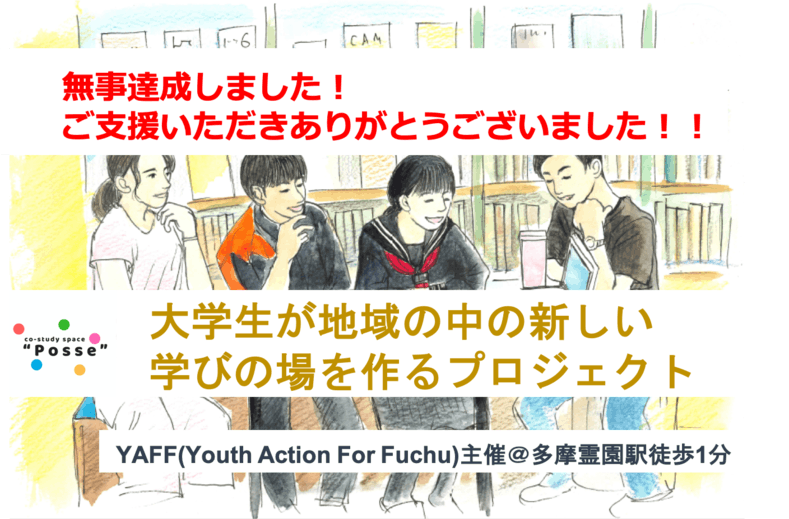YAFFのみんなとの出会いは、2018年夏に府中市で始まったキミマチプロジェクト。 中高生から大人まで、多様な人たちが自分たちの住むまちのことを、自分事として捉えて、まちづくりに参画することを目的としたこのワークショップはYAFFメンバーの強い想いを行動力で実現をしました。 その時に感じたことは、多様な人たちが自由にまちのことに意見を交わす、対話をする機会の重要性。 キミマチプロジェクトは、そんな大切な機会の創出にチャレンジをしましたが、今回YAFFがチャレンジするのは、対話や居場所をリアルに創出する「場づくり」なんだと思います。 居場所が必要なのは大人も子どもも関係ないですが、地域の中に誰にとっても居場所だと感じられる空間ができたら良いなと心から思っています。 きっとこのPOSSEから、様々なチャレンジが産まれ、色々な交流が増えて、地域がさらにアクティブなるんだろうなと、今からとても楽しみです。 そんな素敵な場づくりに、是非ともスタートアップから携わり、地域を面白くしていきましょう。 一般社団法人リテラシー・ラボ代表理事 千葉偉才也川崎市出身。放送大学卒、早稲田大学政治学研究科修了。国会議員政策担当秘書を経て、教育団体リテラシー・ラボを設立。「教育と社会をつなぐ」をコンセプトに、教育政策を軸とした公共政策の立案と実践を行っている。福島県における小中学校の学校教育や東京都での社会教育などを中心に活動。専門はメディア・リテラシー教育。早稲田大学次世代ジャーナリズム・メディア研究所招聘研究員。
サード・プレイス創りへの挑戦を応援します 音楽家 黒田京子 サード・プレイス“第三の場”というものが、今の子どもたちには必要だ、と関谷さんから聞きました。なぜ?私はまずそう思いました。そして、次に、第三の場を、第三者が創らなければならない、教育現場、家庭環境を含めた、子どもたちが置かれている現実を知りたいと思い、関谷さんに直接尋ねました。今の中高生の現状認識から出発しないと話しは始まらないだろうと思ったからです。正直に告白すれば、自分の中でまだうまくイメージできていない部分もあります。実際に子どもたちの声を聴きたいとも思いました。 私はかつて横浜市港南区及び横浜市文化振興財団が主催したプロジェクト『子ども“ゆめ”ミュージカル 「ドリーム」~未来へのおくりもの~』に携わったことがあります。これは一般公募による子どもたち45名による創作ミュージカルで、当時私がかかわっていた劇団が脚本、演出、演技指導を行い、私は作曲・編曲及び音楽の指導、全体の音楽監督を務め、本番でも演奏しました。およそ半年間、毎週末に稽古を行い、最終的にはひまわりの郷ホール(横浜・上大岡/2004年3月)で公演を行いました。 いやあ、ぶっちゃけ、稽古、指導はとてもたいへんでした。子どもたちは小学校高学年から高校生まで、その年齢層は幅広く、その個性や適性も様々でした。役や楽器や歌の割り振りも不公平にならないように気を配りました。 でも、この仕事を引き受けてよかったと思ったのは、そして、私がもっとも感動し、かつ、学んだことは、いつしか、下の子は上級生を慕い、いろいろな質問を投げかけたり教えを乞うたり、上の子は下の子の面倒をみる、ということが、子どもたちの中から自然に生まれていたことでした。子どもたち自らが積極的に他者とかかわっていく姿でした。これは、それぞれの小学校、中学校、高校と家の往復だけでは、けっして得ることができない関係であり、そこには涙あり、笑顔あり、喧嘩もあり、悔しさあり、励ましがあり、とても豊かな時間が生まれていました。 関谷さんがめざすサード・プレイスが、地域の人々の協力も得ながら、中学生、高校生、そして大学生の間に、こうした血の通った関係性を保った学びの場となることを、私は願っています。子どもたちの現状を知っている関谷さんが、このプロジェクトを立ち上げたのは、よほどの思いがあってのことだと思います。これから、実際の運営、経済的な問題など、多くの課題や問題は起きると思いますが、ひとつひとつ乗り越えて、子どもたちのための良きサード・プレイスになることを、私は応援する者の一人です。 黒田京子 東京都府中市生まれ。'80年代後半、自ら主宰した「オルト」では、池田篤(as)、村田陽一(tb)、大友良英(g,etc)等、ジャズだけでなく、演劇やエレクトロニクスの音楽家たちと脱ジャンル的な場作りを行う。'90年以降、坂田明(as)などのバンドメンバーや、演劇や朗読、無声映画の音楽などを長期に渡って務める。'04年から6年間余り、太田惠資(vn)と翠川敬基(vc)のピアノ・トリオで活動。'10年から喜多直毅(vn)と言葉と音楽の実験劇場「軋む音」を不定期に展開、デュオ活動を続けている。近年は即興演奏を主体とした演奏活動を行うほか、'06年にはオルト・ミュージックを立ち上げ、コンサートの企画も手掛ける。2019年春からは生まれ育った府中でのコンサートの企画制作を始める。次回予定は2020年1月18日(土)『耳のごちそう vol.4』鬼怒無月&鈴木大介によるアコースティック・ギターのデュオ。公式web http://www.ortopera.com/・・・・・
11月10日、支援額が50万円を越えました! ご支援いただいた皆様、応援してくださっている皆様、 改めて感謝をいたします! このクラウドファンディングを始めてからというもの、 様々な方からお声を頂き、お話をさせていただいています。 お話しを聞く中で、「中高生の居場所がない」というのは 多くの方が感じていた課題なんだ。ということを、身に染みて実感しました。 これからも頑張って、放課後や休日に中高生が気軽に寄ることが出来て、 安心して学び、かつ色々な人と出会って可能性を広めていく場を作っていきます! ただ、まだまだ課題もたくさん。 ・気軽に来れる場所にするためにはどうしたら? ・料金はどう設定すればよい? ・中高生が居心地が良いと思えるのは、どんな空間? ・お金、集まるかな・・・(´;ω;`) 等など。 ということで、一緒にPosseの在り方を考える会を開きます! 16日(土)13時~ 中高生の居場所に関心のある方や、ご支援いただいた皆様、是非お越しいただき、一緒に作っていければと思います! https://www.facebook.com/events/2694302593923770/

11月4日(月)午後、 小中高大学生、社会人それぞれが集まり、Posseの壁を塗りました! Lab.と名付けたPosseで一番広いこの部屋は、日常的には中高生が思い思いに勉強をしたりすることができる空間です。また、大きなイベントもこちらでやる予定。 落ち着いて過ごすことができるように、シンプルな白色の壁となっています。 今までくすんでいた壁を白く塗るだけで、こんなにも雰囲気が変わってくる。 みんなで壁を塗りながら、この場からこれから生まれていく学びの種や、中高生や大人たちが楽しく過ごしている様子を思い浮かべ、期待に胸を膨らませました。 まだまだリノベーションはこれから。 近々、壁の2度塗りを行う予定です^^ 今後のリノベーションもお声がけをしていきますので、ぜひ一緒に作っていってもらえたらうれしいです!
大学は、実は社会が見えにくい場所です。これは、わたし自身が学生時代に最初に学んだことのひとつです。 このプロジェクトは、中高生の居場所作りに貢献するだけではなくて、さまざまな形で参加する大学生にとっても、自身を普段は自明だと思っている立場や考え方から解放し、新たな学びに取り組むきっかけになるのではないかと思います。 私のゼミでは、インフォーマルな学びを重視しています。フォーマルな学び、つまり「学校」という制度化された枠のなかでは、教える側と教えられる側という立場がはっきり決められがちです。そして、教員も学生も「評価」を意識せざるを得ない状況のなかで行なわれる知識のやりとりには限界があるし、端的に面白くないと思うからです。 このプロジェクトの中心的な役割を担っている関谷昴さんは、東京外国語大学の卒業生ですが、大学の近くに「たまりば」というとても面白い空間を作っていて、私たちも時々お世話になっています。そこはシェアハウスですが、さまざまな立場の人が集って雑談に興じられる場所です。 私たちのゼミでは、自然や社会や地域について、食から考えることをひとつの基本テーマにしています。キャンパスの中で料理ができないという事情から「たまりば」にお邪魔させていただくことが多いのですが、毎回想定外の面白い出会いや気づきをもらっています。たわいのない雑談の中からアイデアや関係が生まれていく、そういう場が府中にもうひとつ増えそうだと知って私もワクワクしています。 大石高典(おおいし・たかのり) 東京外国語大学講師。専門は生態人類学、アフリカ地域研究。 魚釣りへの熱中が高じて、人と自然の関係や環境問題に関心を持つように。環境問題を考えるのに食は欠かせないと考え、学部では農学を、大学院では霊長類学や動物生態学の研究者に囲まれて生態人類学を、ポスドクでは心理学・宗教学、アフリカ地域研究、そして考古学の視点で地球環境問題を考えるトレーニングを経る。研究のメインフィールドはカメルーンの一村落に据え、そこでの定点観測から世界を見ることを行ってきました。外大では、「アフリカを通して日本を見る」アプローチにも積極的に取り組んでいる。主な著書に『犬からみた人類史』(共編著、勉誠出版)、『アフリカで学ぶ文化人類学』(共編著、昭和堂)ほか多数。