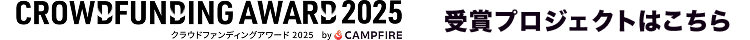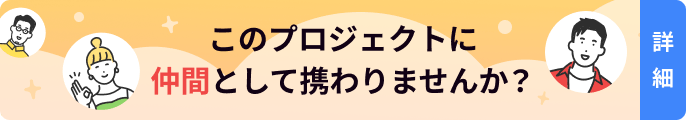『殺劫 チベットの文化大革命』は中国国内では「禁書」扱いになっていますが、国際的には多くの研究者らに注目され、論評されています。米国の代表的な中国政治研究者として知られる、コロンビア大学のアンドリュー・J・ネイサン教授は外交評論誌「Foreign Affairs」(2021年9-10月号)に寄稿した書評「チベットに関する三冊の本」の中で『殺劫』についてこのように紹介しています。「オーセルの著書が取り上げているのは、1966年の文化大革命の到来にまつわる物語である。彼女の父親は、指導的な立場にあった僧侶や貴族が公の場で屈辱を受けたり、拷問されたりする情景や、史跡が破壊されたり、勝利集会、デモ行進が行われたりする状況を、自分のカメラで記録し、毛沢東の肖像画を掲げる笑顔のチベット人の若者たちを撮影した。父親の死後何年もたってから、彼女はこれらの写真を国外で出版することを決意した。彼女は一枚一枚の写真が意味する内容を緻密な作業で読み解いた。誰がそれらの中に登場しているのか。彼らに何が起こったのか。さらには、彼女が写真を見せたときに生存者たちがよみがえらせた記憶とは――。彼女が力の限り発掘した事実を読者は知ることになるのである」
本書の著者、ツェリン・オーセル(茨仁唯色)さんと初めて会ったのは、私がまだ読売新聞の特派員として北京に駐在していた二〇〇六年八月末のことだった。残暑の厳しい午後、場所は北京市街西方の住宅地にある静かな茶館の二階であった。オーセルさんは夫の王力雄さんと仲良く連れだって現れ、当方が初対面の外国人、しかも新聞記者であるにもかかわらず、終始、顔に穏やかな笑みを浮かべながら、旧知の間柄であるかのように気さくに応対してくれた。夫妻の経歴、執筆活動から国内政治やチベット情勢に至るまで、話題はあっちへ飛んだりこっちへ飛んだりし、気がついたら、あっという間に二時間半が過ぎていた。王さんは中国の崩壊と再生を描いたベストセラー小説『黄禍』などで国際的に知られる作家で、チベット、新疆ウイグルの現地事情に通じた中国少数民族問題の専門家でもある。漢民族の知識人には珍しく、チベット問題を公平かつ客観的、しかも同じ人間としての情のこもった眼差しで取材しており、そんな王さんにオーセルさんは全幅の信頼を寄せているようだった。二人のなれそめは本書冒頭の「序」および「写真について」に書かれてある通りだが、まさしく「チベット」が取り持った奇しき因縁ということになるであろう。当局の監視の目が厳しい政治都市・北京での特派員生活は何かと息苦しい。そうした中で、一服の清涼剤を口に含んだ気分になり、中国の将来にほのかな希望を感じるのは、自分の目で世情を観察し、自分の言葉で物事を率直に語ることができる人たちに出会ったときである。オーセルさんは、そして王さんも、まさしくそのような自立思考型の人間であった。したがって、当人たちは「幸いなことに」と言うかもしれないが、二人とも共産党当局から好かれ、歓迎され、評価される知識人ではない。中国国内での自著の出版は許されず、日常生活ではしばしば「その筋」の監視の目にさらされている。茶館で別れる際も、夫妻は「先に行くね。一緒に出ると目立つから」との言葉を残し、店からひっそり立ち去っていった。 オーセル父娘の合作である『殺劫』の存在を知ったのはその懇談の場だった。夫妻に一緒に会おうと誘ってくれた中国書店代表取締役、川端幸夫さんが、半年ほど前に台湾で出版されたばかりのその本を一冊持参しており、見せてくれたのである。にわかにはイメージが焦点を結ばないチベット文革というテーマと、本自体の数奇な来歴に興味をそそられた。そのときは、『殺劫』にじっくり目を通す時間はなく、ざっとページをめくっただけだったが、次から次へと現れる衝撃的なモノクロ写真が発するメッセージの重要性にはすぐさまピンとくるものがあった。職業柄、長いこと文革には強い関心を持ち、数多くの資料に接してきたつもりでいたが、チベット文革についてまとまった形のものを目にしたのは初めてだった。しかも、有無を言わせぬ、多量の「証拠写真」付きである。本の重みが、実際の重量以上に、ずしりと両手に伝わってきた。 北京で入手できる本ではない。さっそく翌日、台北駐在の同僚に連絡し、東京の留守宅あてに一冊買って送ってくれるよう頼んだ。北京へ発送してもらっても、内容が内容だけに、税関で没収されてしまう恐れがあり、無事に届くかどうか心もとなかったからである。後日、休暇で一時帰国した折に、『殺劫』を読み通し、これは単なる写真集でも歴史の記録でもなく、沸騰した湯壷のようなチベット問題の、たぎる底流を映し出す鏡だと思った。それと同時に、チベットの過去と現在を理解する上で、日本の人々に紹介する価値がある、いや、ぜひとも翻訳して紹介しなければならない本だと確信した。その後、関西在住の中国人作家、劉燕子さんが『殺劫』の持つ価値に注目して翻訳に取り組もうとしていることを知り、日本語版発行に意欲を抱いていた川端さんをまじえて三人で相談した結果、劉さんと私の共同作業で翻訳に当たることになった。川端さんは福岡にあって長年、中国関係書の編集出版に情熱を傾けており、世界にあまり類例のない『中国文化大革命事典』の発行をはじめ、すでに多くの実績がある。また、良書発掘のため、しばしば中国を訪れ、人脈作りに精力を注いでいる。本書がこうした形で日本に紹介されることになったのも、川端さんのそうした地道な努力のたまものと言える。その意味では、この翻訳書は三人の共同作業で誕生した。(初版「訳者あとがき」から)
『殺劫 チベットの文化大革命』プロジェクトには、これまでに以下の専門家の先生方から「X」(旧ツイッター)への投稿を通じてご支援をいただいております。改めて御礼申し上げます。阿古智子先生(東京大学大学院総合文化研究科教授)https://x.com/tomoko_ako/status/1810200622282711522石濱裕美子先生(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)https://x.com/okamesaiko/status/1809567667004796966楊海英先生(静岡大学人文社会科学部教授)https://x.com/Hongnumongol99/status/1810246886324105341
プロジェクト公開からちょうど3週間がたちました。皆様のご支援のおかげで、本日昼までに、支援金総額が90万2000円(41%)に達しました。ありがとうございます。プロジェクト公開当初に比べると、支援件数の増加ペースは低下してきているのですが、9月21日の募集締め切りまでにはまだ2か月弱の時間がありますので、引き続きご支援をいただけるよう情報発信やPRに精一杯努めたいと思っております。本日は東京都新宿区のチベットハウスを訪問してプロジェクトのフライヤー配布へのご協力をお願いし、アリヤ代表からご快諾をいただきました。感謝申し上げます。皆様のご友人やお知り合いで本プロジェクトに関心を持っていただけそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ声をかけていただけるようお願い申し上げます。本の編集作業は現在、初校ゲラの校正、修正に取り組んでいるところです。お盆休み前には仕上げたいと思っています。
本書の共訳者である現代中国文学者、劉燕子さんが漢人の立場からチベットへの思いを綴った一文を紹介します。 ◇ 日中および漢蔵の狭間でマージナルな私にとって 劉 燕子 私は子どもの頃「チベット人を農奴制から解放してくれた毛主席に感謝」という、中国では広く知られている歌を聞きながら育った。また、チベットの娘が解放軍兵士の軍服を洗濯してあげる情景を歌った「洗濯の歌」では、「翻身農奴」に扮して、色鮮やかな紙で作ったパンデン(前掛け)の衣装を身につけ、「誰が私たちを生まれ変わらせてくれたのか?/誰が私たちを解放してくれたのか?/同じ身内の解放軍だ/救いの星の共産党だ」と歌いながら踊った経験もある。歌詞はさらに、チベット人を農奴制から解放し、自動車道や橋を建設し、裸麦の収穫や新しい家の建築を手伝ってくれた解放軍に感謝し、「私たちの生活は一変した/私たちは限りなく幸福だ/同じ身内の解放軍に感謝する」と歌い終わる。 この「洗濯の歌」は、文革が発動される二年前の一九六四年に発表され、広く歌われた。作曲者も作詞者もチベット人ではなく、漢人だが、そのようなことなど知らずに、私たち漢族の子どもは、教えられるままにグループで踊りながら合唱した。一九六九年三月から、ラサ近辺のニェモ県やチャムド地区のペンバー県など各地で惨烈な抗議事件が続発したことなど、もちろん全く知らなかった。 その後、一九九一年に日本に留学し、中国の地下文学や亡命文学の調査研究を進めるうちに教えられた内容とは違うチベットの状況を知るようになったが、その時はまだ抽象的な概念に止まっていた。 だが、二〇〇五年夏、ストックホルムで、天安門事件亡命者の茉莉・傅正明夫妻と会った。北欧の抜けるような青空から降りそそぐ透明な夏の日ざしを浴びながら傅正明は消息不明のチベット人の手書き原稿の詩を紹介し、朗読した* 1。雪山よもし君が人間のように立ち上がらなければたとえ世界の最高峰でもただその醜さをはっきりとさらすだけだ最高峰として寝ているよりもむしろ最底辺でスクッと立つべきだ兵士よもしどうしてもぼくを撃たなければならないのならぼくの頭を撃ってくれぼくの心臓は撃たないでくれぼくの心には愛する人がいるから この朗読を聞き、私は衝撃のあまり涙がこみ上げ、抑えようとしてもできなかった。さらにその時、一九五九年には一〇万人という規模の亡命者が出たという離散(ディアスポラ)も知り、強烈なショックを受けた。 亡命したチベット人は身体と精神の二重の苦痛を体験し、その上、母語が使えず、中国語、英語、ヒンドゥー語、サンスクリット語など様々な異邦の言語の中で亡命生活を送る者も多い。インターネットの普及で亡命チベット人が中国本土の親族や友人と通信できるようになったが、中国で広く使われているチャットのQQは、その発音から「哭哭(泣く泣く)」とも表記された。その内容が悲嘆に満ちているためであった。 こうして、チベット人の苦境を知れば知るほど、私は義憤を覚え、漢人の一人として良心の呵責に苛まれ、道義的な責任を感じた。さらに、楊海英の「内モンゴルが中国領にならなかったら、ジェノサイドもなかった、とモンゴル人は認識している」という指摘が* 2、痛烈に突き刺さった。そして、私はこのことを私自身の「生」に関わる課題と受けとめ、なお一文学者として改めて何をなすべきかと考えた。私は自分自身を振り返り、向きあった。その時、自分は日中と漢蔵の狭間でマージナルな存在であることを省察し、ここにオーセルと「生き方」をともにする立脚点があるのではないかと考えた。オーセルたちに自由がなければ、私にも自由はない。オーセルたちが泣くならば、私もともに泣こう。これは謂わば共感共苦(compassion)によるものである。 「炎にあえば御影石も溶ける」という* 3。我が身を炎と燃えがらせる抗議は、盤石に見える独裁体制も溶かすだろう。その思念や行動を記録し、伝えるところに文学の使命があり、また文学の真価が問われる。* 1この詩は、亡命チベット人の詩のアンソロジー『西蔵流亡詩選』(傅正明、Sang Jey Kep編訳、傾向出版社、蒙蔵委員会、台北、二〇〇六年)に収録された。*2 楊海英「ジェノサイドへの序曲―内モンゴルと中国文化大革命―」『文化人類学』第七三巻三号、二〇〇八年一二月、四四〇頁。*3 アンナ・アフマートヴァ『アフマートヴァ詩集―白い群れ・主の羊―』(木下晴世訳)群像社、二〇〇三年、一七三頁。