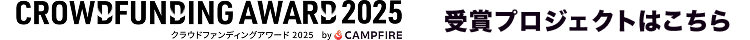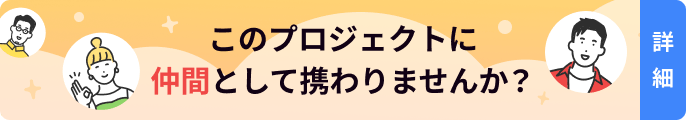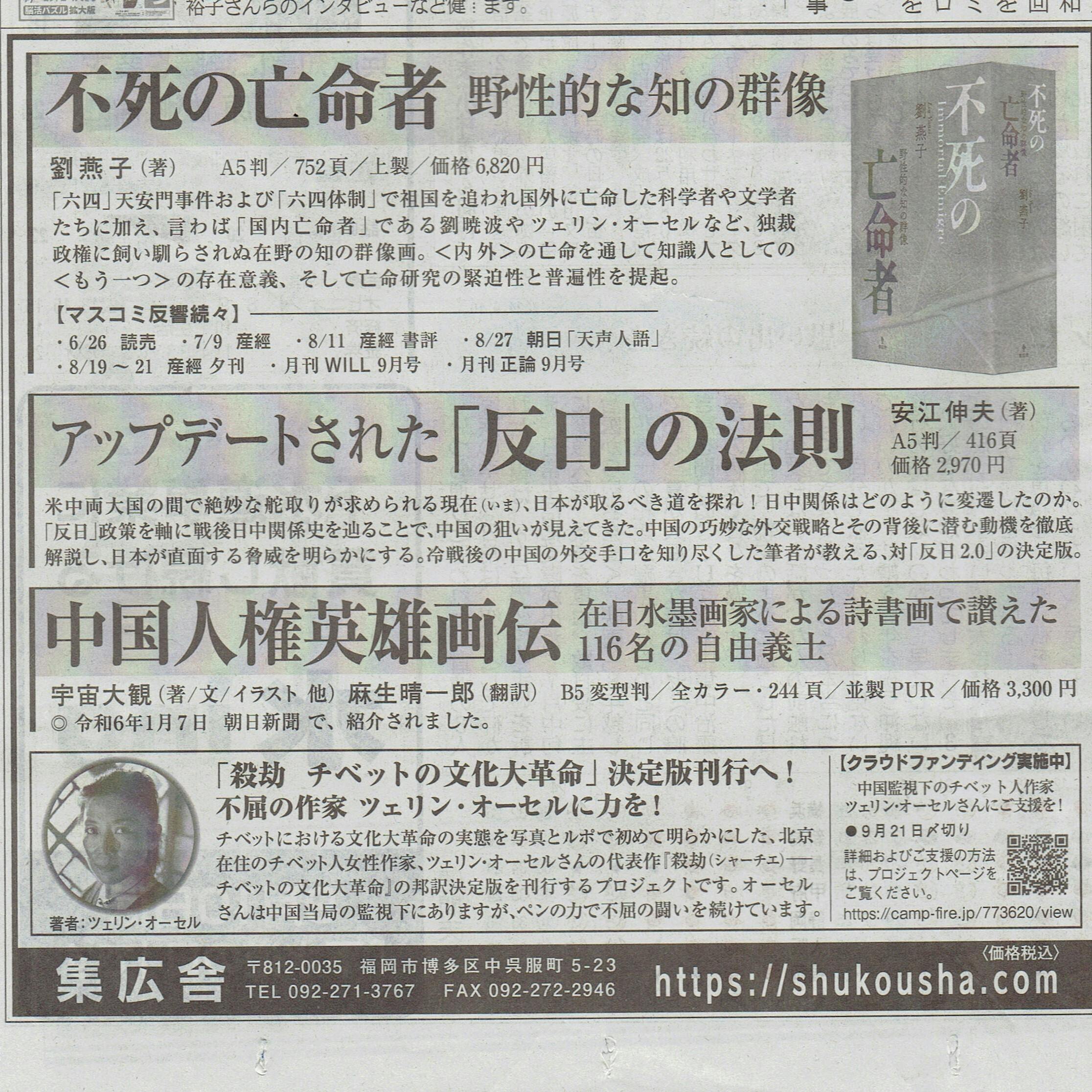周知のように、香港では2020年6月、住民の反対運動を力で封殺する形で国家安全維持法が施行され、返還後、香港に適用されてきた「一国二制度」は事実上、骨抜きにされてしまいました。こうした強硬政策はもとより北京の共産党政権の意向に基づくものですが、中国がいったん約束した「一国二制度」を反古にしたのは香港が初めてではありません。先例は今から60年以上も昔のチベット統治の転換にあったと言うべきです。 1950年にチベットへ侵攻した中国は翌51年5月、チベット当局との間で「チベット平和解放に関する17条協議」を締結しました。この「17条協議」において中国は「チベット人民は中華人民共和国の祖国の大家庭の中に戻る」としてチベットが中国の一部であることを規定したうえで、「チベットの現行の政治制度について中央はこれを変更しない」、「宗教信仰自由の政策を実行し、チベット人民の宗教信仰と風俗習慣を尊重する」などの「現状維持」を約束しました。 当時、共産党政権にとっては、社会主義路線にのっとってチベットの政治・社会体制の改革を急ぐことよりも、まずチベットの安定と民衆の人心掌握に全力を挙げることが優先課題でした。このため、党中央は1956年9月に「チベットでの改革実施の条件はまだ熟していない」として、「民主改革(旧制度の解体や農地分配)の実施は、第1次5ヵ年計画期(1953-57年)ということはありえないし、第2次5ヵ年計画期(1958-62年)のことでもない。第3次5ヵ年計画期まで先延ばしすることになるかもしれない」との通達を出しました。「民主改革」延期の理由について通達は「チベット民族の上層分子に対する一種の譲歩と言うべきだ。我々は、こうした譲歩は必要であり、正しいと考える。なぜなら、チベット民族は今なお漢民族と中央に対して、つまり我々に対してあまり信を置いていないからだ」と説明しています。建国直後の当時の中国には「一国二制度」という言葉も概念も存在していませんでしたが、「17条協議」に基づくチベット政策は今日いうところの事実上の「一国二制度」だったわけです。 しかし、1959年3月のチベット動乱およびダライ・ラマ14世のインド亡命後、中国は何はばかることなく、チベットの支配層を搾取階級として弾圧し、貧農に土地を分配するなどの「民主改革」を断行しました。これにより「政教一致の封建的農奴制度」を解体し、「100万農奴の解放」を達成したと、中国は主張しています。毛沢東は同年5月、「ネルー(ダライ・ラマを受け入れたインド首相)とチベットの反乱分子に感謝しなければならない。彼らの武装反乱はいまチベットで改革を行う理由を我々に提供してくれた」とあけすけに語っています。共産党の本音は、「17条協議」など一時的な便法に過ぎない、チベット側が「反乱」を起こしてくれたおかげで目障りな旧体制をすっきり清算できた、といったところでしょう。 翻って香港を見ると、中国は2003年以降の一連の大規模な民主化運動を、「一国二制度」改変の転機ととらえていたことがわかります。香港で「中国化」を一気に進める機が熟したというのが中国の判断だったに違いありません。中国共産党という政治集団の思考回路や行動原理は時代が変わっても、本質的な部分ではさほど変化していません。チベットと香港におけるそれぞれの変化は歴史的な文脈の中で関連付けて考える必要があると思います。