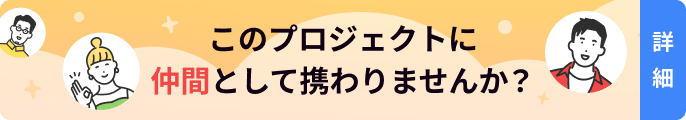本書の予価が確定しました。B5判(週刊誌大)の上製ハードカバーで、7,500円(税込8,250円)です。単行本としてはかなり高額な書籍となりますが、本書は写真が多いことや印刷部数が限定1,000部と少ないことに加えて、昨今の印刷費、用紙代など諸経費の値上がりにより、このような価格設定に至りました。リターンでご説明してあるように、1万円以上のご支援を頂いた皆様方にはメーンの返礼品として本書を謹呈させていただきます。ご期待に十分応えられるような内容、装幀の本に仕上げるつもりですので、本年12月の刊行までしばらくお待ちいただければと思います。

文化大革命期に破壊されたラサのシデ・タツァン(学堂)の廃墟。オーセルさんは「まるでラサの巨大なケロイドのようである」と、そのすさまじい惨状を形容しています。シデ・タツァンの廃墟は2018年にすべて撤去され、元の場所にかつてのシデ・タツァンに似せた建物が再建されましたが、それで仏教破壊の歴史が帳消しになったわけではありません。 フランスのチベット研究者、ロラン・デエは自著『チベット史』の中で、文革期の狂瀾怒濤の様相をこう記述しています。 「文化大革命の間、チベット自治区は今までにない過酷な宗教弾圧を受けた。1966年夏紅衛兵が『世界の屋根』を行進し、熱狂的献身で『四旧』(旧い考え、旧い文化、旧いしきたり、旧い風習)を追放し、撤廃した。8月6日、彼らはジョカン寺を略奪し始め、小便所と屠殺場に変えた。9世紀の仏教弾圧者ラン・ダルマ皇帝の『中国人末裔』の出現である。千年以上の歴史を持つ文化の組織的破壊の始まりであった。10年後紅衛兵が残したのは、国中に6000程あった寺院、礼拝所の内わずか10余りであった。つるはしとダイナマイトにより、チベットは広大な遺蹟の荒野と化した。仏像は壊されるか、中国(成都、北京)に持っていかれ、中国自身がその消滅に気付き動揺する1973年まで、何百トンと積み上げられるか、溶かされた」(ロラン・デエ[今枝由郎訳]『チベット史』春秋社、2005年、340頁) ちょっと想像していただきたいと思いますが、外来の政治運動によって奈良や京都の宗教文化遺産がこのような形で組織的に軒並み破壊されたとしたら、日本人は果たしてどこまで精神的に耐えることができるでしょうか。文革期にチベットで起きたことは単なる物理的な破壊にとどまらず、まさしくチベット人の精神文化を根底から破壊し、凌辱する行為であったのです。

「国家安全」を名目に、その筋が国内各所で様々な手段を講じて人々の言動を監視している社会では、ときに(いや、「しばしば」と言うべきかもしれませんが)「ミステリー・ドラマ」のような出来事が起きます。オーセルさんが『殺劫 チベットの文化大革命』を台湾で刊行し、その後もチベット・ラサで継続取材を行っていたときのことです。彼女はこんな不思議な事件に遭遇しました。日本では想像もできないことでしょうが、これもかの国の知られざる現実です。以下、彼女の回想です。 ◇ ……およそ2ヵ月間、私は炎天下を東奔西走し、撮影したフィルムは19本に上った。しばらくラサを離れるつもりはなかったので、旅行に来ていた漢人の友人がラサを発つ前に別れを告げにわが家を訪れた際、それらのフィルムをできるだけ早く現像するため、彼女に持っていってくれるよう頼んだ。当時、その場には私たちのほかには誰もおらず、2人の間では電話でフィルムの話をしたこともなかった。ところが、翌日、彼女は空港の安全検査を通過しようとしたところ、フィルムを入れたリュックサックに「果物ナイフ」があるとの指摘を受けた。その「果物ナイフ」は彼女が見たこともないものだったが、警察は有無を言わせずにリュックを持ち去り、荷物は彼女の見えないところで「詳細なチェック」を受けてから、搭乗機の離陸直前に返却された。驚いた彼女はあたふたと搭乗し、飛行機が着陸してからリュックの中身をあらためた。私の19本の富士リバーサル・フィルム120は、コダックの135ネガフィルム10本と富士のネガフィルム5本に変身してしまっていた。 現在、このすり替えられた15本のネガフィルムは、記念品の一つとして北京の自宅で保管している。試しにそのうちの1本を現像してみたが、何も写っていなかった。私がラサで苦労して撮った作品はこのようにして国家機関がつくり出したブラックホールの中に消えてしまった。いったい、当局は私の友人がフィルムを持ち運ぶことを、どのような方法で察知したのだろうか? 私には思いつかない。わが家に盗聴器や監視カメラがひそかに仕掛けられていたのだろうか? それとも、数キロメートルも離れたラサ公安局の信息大廈〔情報ビルディング〕の屋上に備えつけられた高倍率望遠鏡がわが家の窓を覗いていたのだろうか? 彼らがどんなハイテク技術の手法を用いたにせよ、私をそれ以上に驚かせたのは、国家の法律を代表する部門が意外にもあのような手段で私のフィルムを取り上げてしまったことだった。

本書『殺劫 チベットの文化大革命』の中で衝撃的な現場写真とともに詳述されていることですが、文化大革命期のチベットでは、チベット仏教寺院の建物や仏像、仏具、経典などは「四旧(古い思想、古い文化、古い風俗、古い習慣)」に属するものとして歴史的、文化的、宗教的な価値を全面否定され、手当たり次第に破壊されたり、焼却されたりしました。また、宗教活動そのものが封建的で迷信的なものと決めつけられ、僧侶たちは紅衛兵らからつるし上げ、引き回しなどの暴行を受け、筆舌に尽くし難いほどの屈辱をなめさせられました。チベットはまさしく「破壊と暴力」の坩堝の中に投げ込まれたわけです。 中国共産党は1976年に毛沢東が死去した後、鄧小平の主導下で徐々に脱文革、改革開放へと路線を転換し、文革については「革命ではなく、内乱であった」との結論を下します。文革期にチベットで吹き荒れた「破壊と暴力」の嵐も「誤った行為」として否定されたわけですが、共産党がチベット文革から学んだ教訓とはいったい何だったのでしょうか。 それは、一言で言えば、「破壊と暴力」ではチベット民族の宗教も文化も価値観も変えることはできない、ということです。唯物論、無神論に立つ共産党のイデオロギーからすれば、宗教は現実的存在を認めざるをえないとしても、永久に保護し、発展させるべき対象とは位置付けられていません。可能であるかどうかはともかくとして、イデオロギー的にはいつかは衰退させ、消滅させるべき対象です。こうした根幹的な考え方は現在も本質的に変化していません。「破壊と暴力」によって宗教を排除することに一度失敗した共産党が改革開放後に推進した政策は、共産党の強力な政治指導の下で、制度と法律、思想教育によって宗教活動を全面的かつ徹底的に管理するというものです。文革期のような宗教弾圧を「単純な直接的暴力」とすれば、今日のそれは制度設計に基づく「巧妙な間接的暴力」とでも呼ぶべきやり方です。 一例を挙げれば、前回の記事で取り上げたダライ・ラマの転生問題があります。共産党はダライ・ラマの転生は伝統的な手法と儀式にのっとって執り行い、中国政府が転生者を最終承認することによって完結すると主張しています。共産主義イデオロギーからすれば、転生も伝統も本来は「封建的」「迷信的」なものであるはずで、共産党がそれを踏襲するというのは大きな矛盾であるように見えます。しかし、そのことが何らかの問題や障害になるということはありません。なぜなら、共産党は「チベット仏教の伝統を重んじる」という形式を装うことによって、一貫してチベット亡命政府側の関与を排除し、次期ダライ・ラマ選定の主導権を掌握することができると考えているからです。 ダライ・ラマ、パンチェン・ラマなど高位の転生僧の生まれ変わりを選定する方式として「金瓶掣籤(きんぺいせいせん)」という制度があります。あらかじめ金瓶(黄金製の壷)の中に別々の候補者の名前、誕生日などをそれぞれ記した複数の象牙の札を入れておき、抽選で決定するというやり方で、18世紀に清朝の乾隆帝が導入しました。金瓶はラサのジョカン寺と北京のチベット仏教寺院、雍和宮に一つずつ保管されていますが、共産党はこの制度を継承すると公言しています。法的根拠を明確にするために「蔵伝仏教活仏転世管理弁法(チベット仏教活仏転生管理規則)」という法律も制定しています。次期ダライ・ラマの選定に際して、共産党が承認する子供こそが正統のダライ・ラマ転生者であると主張するための布石と見ることができます。 共産党が選定し、育成したパンチェン・ラマ11世は現在、中国仏教協会副会長、同チベット分会会長、全国政治協商会議常務委員として活動していますが、先ごろ、講話の中で「チベット仏教の中国化を積極的に推進しなければならない」「チベット仏教の活仏転生における党中央の決定権を断固として擁護しなければならない」と表明しました。共産党の期待に応えて、その政策の代弁者としての役割を果たしていることがわかります。 「チベット仏教の中国化」とは、ダライ・ラマを精神的指導者とするチベット仏教を排除し、共産党の指導に従順なチベット仏教へと構造転換することを意味します。共産党の将来構想は、すでに共産党式の帝王学を授けたパンチェン・ラマ11世が、チベット仏教界の先輩として、共産党の監督下で選定される幼少のダライ・ラマ15世を「善導」していく、というものであろうと想定されます。ここに至って、「チベット仏教の中国化」は一応の基盤整備を完了することになるでしょう。しかし、それが大多数のチベット人の主体的な意思と願望を反映したものとはならないことは言うまでもありません。

チベット情勢をめぐっては、チベット仏教の精神的指導者であるダライ・ラマ14世の転生問題が様々に論議されています。事は単に宗教上の問題にとどまらず、中国とチベット亡命政府との関係や、中国のチベット政策の行方とも密接にかかわってくるからです。複雑な問題の背景を知っていただけるよう、かつてダライ・ラマ14世にインタビューした後に執筆した原稿をここに紹介いたします。 ◇ チベット仏教の世界では、ダライ・ラマ、パンチェン・ラマといった高僧は代々生まれ変わるとされている。高僧が死亡すると、側近らが占いなどを基にチベット各地で転生霊童(てんせいれいどう=「生まれ変わりの子供」を意味する中国式の呼称)を探索し、複数の候補者を様々なテストでふるいにかけ、最終的に後継者を確定する。インド亡命中の現在のダライ・ラマは14世だが、中国との対立がこのまま長引くとすると、次の15世は中国統治下のチベット本土以外の場所で見つけられることになりそうだ。 というのも、14世は2003年11月の訪日時に私が行ったインタビューの中で、自分が中国統治下のチベットで生まれ変わることはないとの見通しを示したからである。14世がそうした考えを公にした背景には、明らかに、中国側とダライ・ラマ側との間でもめている「2人のパンチェン・ラマ」問題が横たわっている。 パンチェン・ラマ10世が1989年に死去した後、中国側とダライ・ラマ側は中国のチベット域内でそれぞれ別個に生まれ変わりの子供を探し出し、11世として擁立した。しかし、中国側の子供が帝王学を学び、公式活動を繰り広げているのに対して、ダライ・ラマ側の子供は「かつて青海省にいるとの情報があったが、行方はわからない」(14世)状況で、中国当局の厳重な監視下に置かれているとみられる。14世としては、自らの生まれ変わり問題で、パンチェン・ラマの二の舞だけは演じたくないというわけである。 1935年生まれの14世はもう69歳(2004年時点。2024年現在は89歳)になる。亡命生活に入ってすでに45年(2024年現在では65年)。すこぶる快活な性格で、いつも笑みを絶やさない。顔の色つやも良く、70近い高齢をまったく感じさせない。軽快な足取りで世界各地を行脚しているが、俗世間の常識で言えば、そろそろ全面引退しようかという年齢である。健康状態だって、いつどんな問題が生じたとしても不思議ではない。 14世がチベット本土で生まれ変わることがないとすれば、どこで転生するのか。チベット人は亡命政権のあるインドを始め、ネパール、スイス、米国など世界各国に多数居住している。14世の見通し通りとすれば、理屈上は、将来、欧州ないし米国生まれのダライ・ラマが出現する事態もあり得ない話ではない。そうなれば、チベット仏教史上初の欧米出身ダライ・ラマとなる。 一方、中国側は、当然ながら、自国領内で転生者を探し出し、共産党の政策に従順な宗教指導者に育て上げようとするに違いない。この場合は、「中国政府のダライ・ラマ」と「亡命政権のダライ・ラマ」が対立しながら、存在をアピールするという面倒な状況が生まれる可能性が大きい。14世にとっては一日でも多く長生きすることが、対中戦略上、重要な意味を持ってくる。 中国のチベット人たちは、14世に対して、今も深い敬愛の念を抱いている。また、チベット現地で取材した経験から言えば、多くのチベット人は「本当のパンチェン・ラマ11世はダライ・ラマが選んだ子供だ」と信じている。強烈な民族魂と宗教心に裏打ちされた、チベット民衆のダライ・ラマへの熱い思いが大きく揺らぐことは今後も考えにくい。中国が次期ダライ・ラマを独自に擁立したとしても、チベットの民心を掌握することは極めて困難だろう。「真の転生とは私の任務の役に立つものでなければならず、障害とはならないものである。(自分の死後)中国政府は別の子供を選ぶだろうが、それはニセ者だ」ダライ・ラマは信念を込めてそう語る。中国政府と亡命政権の接触は細々と続いている。だが、半世紀に及ぶ対立の構図に根本的な変化が生まれない限り、「14世後」のチベット問題が一段と複雑さを増すのは必至と見ていい。余談だが、最後に、楽屋裏のエピソードを一つ。ダライ・ラマへのインタビューを準備しているさなか、東京の中国大使館が、どこで情報を仕入れたのか、「読売はダライ・ラマと単独会見するのか」と、私の職場(国際部)に何度も探りの電話をかけてきた。「紙面に干渉するわけではないが、こちらの立場もある」と大使館員。部外者に答える筋合いの話ではないので、インタビューをするともしないとも言わなかったが、相手の口調からは中国政府がダライ・ラマ訪日に相当神経を尖らせている様子が察せられた。思えば、それは、国際世論がダライ・ラマに同情的であることへの中国側の苛立ちの表れでもあったに違いない。(藤野彰著『臨界点の中国 コラムで読む胡錦濤時代』[集広舎、2007年]から)