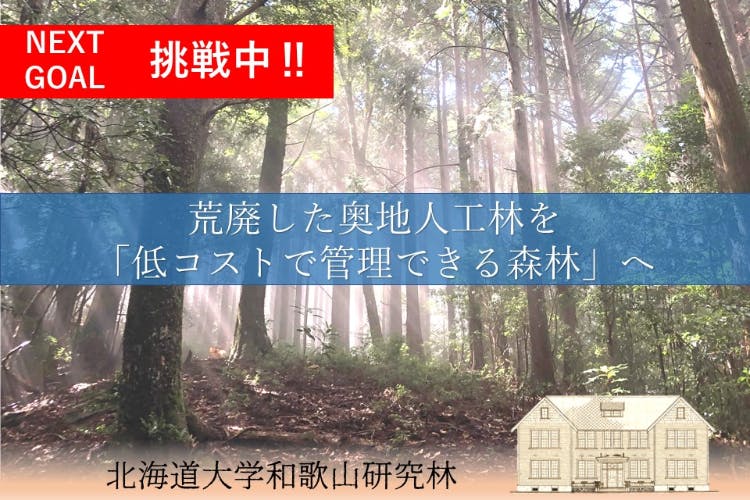今後の予定についてこんにちは。改めまして今回はご支援いただき誠にありがとうございました。今後の予定につきましてご連絡いたします。・リターンの発送 リターンの発送は、必要な手続きが全て完了した4月以降になります。暫くお待たせしてしまうことになりますが、制作過程等を活動報告ページでご紹介する予定です。そちらも併せてお楽しみいただければ幸いです。・ツアー参加者の方へ ツアー参加者の方へは12月中に再度、日程調整の方法等のご連絡をいたします。よろしくお願いします。1列目の間伐が終了しました!間伐完了部分今日は先週始まった間伐作業の1列目が完了致しました!この列は幅が10mで設定されています。10mの他には20mと5mの幅を設定しており、この下端に作業道を設置する予定です。作業道の設置にはもうしばらく時間がかかるので、伐倒した木は暫くこのまま置ておきます。この際、葉っぱを付けたまま放置することで、葉の蒸散を利用して水分を効率よく材を乾燥させることが出来ます。この技術を「葉枯らし」と言います。伐倒風景木も生き物なので水分を利用しており、伐倒した直後はしっとりと湿っています。このまま木材として利用しようとすると、時間がたった時に歪みや割れが生じてしまうので、乾燥することが必要です。現在では湿ったままの木材を丸太にして搬出し、特定の場所でまとめて乾燥させる方法が一般的ですが、かつて運搬技術が発達していなかった時代は、なるべく軽い状態で運びたいので、山の中で葉枯らしを行い軽くしてから搬出する方法が良く行われていました。搬出技術の発達に伴い、葉枯らしの技術は衰退していましたが、近年この技術は見直されています。材を軽くすることで輸送コストが低減される一方、乾燥材は生材よりもやや高い値段で取引できる可能性があるためです。また、秋田や吉野では材の色をよくするのにも利用され、「あく抜き」や「渋出し」と言われていたそうです(※1)。先人の知恵は技術が発達した今日でも通用するものがあり驚かされますね。空が開けたことで光が入ってきている伐開した部分は空が開けたことで光が入ってきました。この光に反応してどんな樹木が生えてくるか楽しみです。今後も進捗状況や今までのような森林のトピックをご紹介する予定ですのでどうぞよろしくお願いします!※1:愛媛県 1988 葉枯らし乾燥技術指針