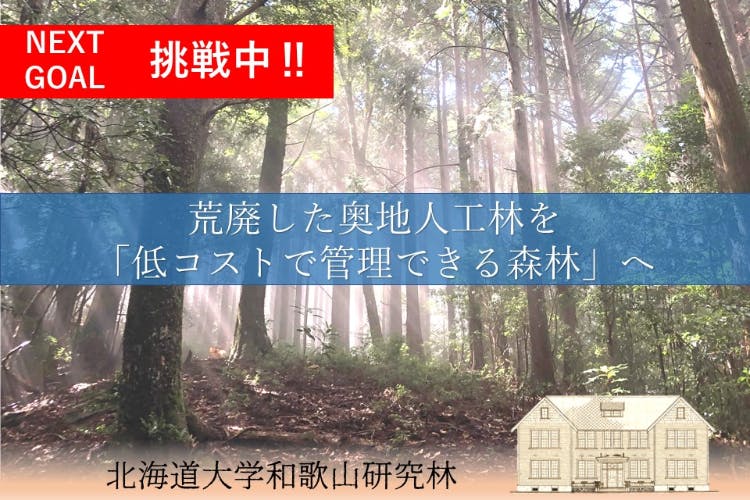こんばんは!すっかり秋も深まってきましたね。平井では稲架掛けが終わり、柚子の収穫まで束の間の休息です。今日のトピックは次の通りです。たくさん準備したのでご興味のある部分をかいつまんで読んでみて下さい!・平井産のお米!・研究進捗(土壌処理実験)・林道作設の状況・高性能林業機械の運用コスト・林内路網の諸問題・平井産はちみつ!・蜂蜜から考える生物多様性がもたらすサービス・COP15の論点 生物多様性と経済平井産のお米!前回の活動報告で紹介した田んぼの持ち主の方(研究林の職員の方)から、収穫したお米を頂きました!初めての平井産のお米です!折角頂いたお米なので、普段はアルミの鍋で炊いてますが今回は特別に土鍋で炊くことにしました。「ここのお米はちょっと水分が多いから、水は少な目の方が美味しいよ」と言われたので、普段は人差し指の第一関節をちょっと超えるぐらいまで入れている水を、第一関節少し下までにしときました。はたして結果は…なんとも美しい輝きですね。どうやら上手く炊けたようです。品種はキヌヒカリというもので、今年初めて栽培したそう。おそらく僕の人生の中で、収穫してから口に入るまでの時間が最も短い米粒たちです。お味の方は、粒がしっかりと立っていて、ほんのり甘い味がしました!栗と混ぜたら美味しい栗ご飯が炊けそうです!今度やってみようと思います。研究進捗(土壌実験)Janzen-Connell仮説に基づいた土壌処理実験の結果が見えつつあります。以前お話した通り、土壌菌類の影響を枯死率で観察しようとしたところ、思ったより実生の生存率が高く比較にならなかったので、8/27~9/27の間に増えた葉の枚数で土壌の影響を評価することにしました。この実験は以前の調査結果で出てきた、幼木の基部直径分布に対する仮説を検証するために行っています。以前の調査結果というのが下のグラフで、天然林ほど直径の小さい実生が多く、天然林から離れるほどやや太い幼木の占める割合が上昇していることが分かります(20㎜以上で天然林が上昇しているのは母樹の効果)。このパターンに対する私の仮説は以下の2つです。①実生は土壌菌類の負の影響を受け成長を阻害されている②土壌菌類の負の影響は母樹集団である天然林からの距離に依存して減少しているため、実生の成長は天然林内よりも人工林内の方が良いこの仮説に基づいて実験を行い次のような予測を立てました。①殺菌しない場合、母樹集団である天然林で土壌菌類の負の影響が出て葉の増加量は減り、天然林から離れるほど負の影響が緩和され葉の増加量が増える②殺菌すると、負の影響は緩和され距離依存性がなくなる(地点間の差が無くなる)予測結果を模式的にグラフで表わすと、下のグラフのようになります。(5m, 30mは人工林の林縁からの距離)では、結果を見ていきましょう。今回はアセビ、マンリョウ、ヤマグルマの3種を実験に用いました。それぞれで傾向が異なるため、1種ずつその違いを見ていくことにします。なお、まだ統計解析が出来ていないので、Excelの取って出しのデータになります。有意差などについては不明です。アセビまずは調査地でも出現頻度が高かったアセビです。全体の傾向として、殺菌処理の効果が最も顕著に現れました。予測通り殺菌した場合の方が成長成績が良くなっています。ただし、距離依存性については5m地点で殺菌した場合もそのままの場合も、成長成績が悪くなっています。また、殺菌しない場合に予測していた、右肩上がりの傾向は見えませんでした。この結果だけで無理やり検証をするならば、「土壌菌類はアセビの成長に負の影響をもたらしているものの、山で見られた基部直径の距離依存性に寄与している可能性は低い」ということになります。まだ1か月だけの結果なので、もう少し様子を見ることにします。マンリョウ続いてマンリョウです。マンリョウは他の2種と比較して、種子サイズが大きく硬いのが特徴です。また調査地での出現頻度は低い種でした。全体的な結果としては、やはり殺菌した方が葉の枚数は増えていました(ただし、その差は僅かなため統計解析を行う必要があります)。さらに、アセビと異なり人工林5m地点での成長成績が最も高くなっていました。ヤマグルマ最後にヤマグルマです。ヤマグルマは調査地で1個体も出てこなかった種なので、特異的な土壌菌類の影響は受けないのではないか?と予想していました。実際に観察してみると、殺菌済みで成長成績が良く、マンリョウ同様5m地点で成長成績が上がっていることが分かりました。中途考察全体として、殺菌した方が成長成績が良くなる傾向が見られたので、土壌菌類が実生の成長を阻害しているのは確からしいと考えられます。土壌菌類と植物の関係性は菌根菌などの共生関係が有名ですが、今回の結果から考えると、そういった共生関係はあくまで負の影響を抑えているに過ぎないと言えるかもしれません。つまり土壌菌類のプラスとマイナスの影響を正味で考えるとマイナスになっている、と言うことになります。また、最も影響が顕著に見られたアセビは、調査地での出現頻度が高い種でした。そのため、ある地点に多く出現する種に特異的な土壌菌類の影響が見えている可能性があります。この点については他の種でも実験を行い調査をする必要があります。いずれにせよ、しっかりとした解析を行う必要があるので、また何か分かり次第ご報告いたします。林道作設の状況一方の山では、林道の作設が進められています。雨続きのため少しずつではありますが、千井さんと室さんのご協力で、森の中へ道が伸びています。和歌山研究林で道を付けるのも久しぶりのことなので、あれこれ試行錯誤しながらの作業になります。 基本的な工程は次の通りです。①千井さんが作設予定地の立木を伐倒②4mごとに切り分けていく③室さんが分けられた丸太をユンボでミニ土場へ④ユンボで路面を形成この作業を地道に繰り返していきます。室さんが使っているユンボの先端に付けられているアダプターは、丸太を滑らずに掴む道具です。しかし、このコントロールがなかなか難しいらしく、材を引き出すのになかなか時間がかかります。ここまでの一連の作業を一台でやってしまうハーベスタ等の高性能林業機械の凄さを実感しました。この感想を千井さんにお話ししたところ、便利であることに違いはないが減価償却などを考える必要があり、和歌山研究林のように稀にしか素材生産を行わない事業体には不向きであるというお話をしてくれました。なるほど、その性能の高さに目が行きがちですが、実際に利用するとなると、そのコストも利益以上に考慮する必要がありますね。高性能林業機械の運用コストでは実際に高性能林業を扱うにはどのようなコストがかかるのでしょうか?尾分ら(2020)によると、林業機械にかかる運用経費は固定費と変動費に分けられるそうです。固定費とは売り上げに関わらず持っているだけで発生するコスト。一方の変動費とは、売上に比例して変動するコストのことです。井上(2001※)によると、固定費で高い割合を占めているのが千井さんの話していた減価償却費です。平成20年の税制改定以降、林業用設備は法定耐用年数が一律5年となっており、この間に林業機械を使えば使うほど、時間当たりの固定費は抑えられることになります。(ちなみに5年目以降の林業機械は単純に考えると、利益だけを生み出すようになりますが、尾分(2020)が行ったインタビューでは、5年目以降に修繕費が増加する傾向にあるといいます。)しかし実際は、フルに活用しきれているとは言い切れないのが現状です。少々古い文献ですが平成22年版の森林・林業白書によるとオーストリアでは林業機械が年間1500~2000時間、中には3000時間稼働しているのに対し、日本では多くても1000時間とされています。そのため千井さんが指摘するように、事業量を確保することが必要になります。また事業量を確保したとしても、小規模な事業地が散在しているような場合は、移動のコストがかかるため、林地の集約的な施業計画も必要とされています。加えて「作業工程における生産性の違い」を考慮した作業システムの構築も必要です。林野庁が平成30年に公表した生産性向上ガイドブックでも、素材生産における生産性のボトルネックとしてフォワーダによる集材過程があがっていました。いくらハーベスタがせっせと伐倒と玉切りを繰り返したとしても、フォワーダは長い距離を運ぶのに時間がかかるため捌ききれないのです。そのため運材距離に応じて、ハーベスタの性能をフルに発揮するのに必要なフォワーダーの台数を確保したり、そもそもハーベスタを使うのが本当に適しているのか考えたりする必要があるというわけです。もう一つ聞いた話では、高性能林業機械は操作が難しいので、操縦可能な人が休んでしまうと稼働時間が確保できなくなることもあるようです。事業量を確保したとしても、機械を動かせる人材が欠けてしまっては元も子もありません。従って事業体側も技能を持つ人材を常に複数人確保する必要があります。今後、高性能林業機械の普及を進めていくためには、林地の集約化やシステムの効率化だけでなく、人材の育成も重要かもしれません。固定費の話が長くなりましたが、変動費の方はどうでしょうか。同じく井上(2001※)によると、変動費は保守・修理費が多くを占めているといいます。減価償却費に対する利益を上げるために稼働時間を長くすると、その分故障やトラブルが発生する確率が高くなります。したがって稼働時間を長くしながらも、いかに保守・修繕費を抑えていくかが利益を高める鍵になります。各地の事業体の修繕費や機械更新について調査した尾分ら(2020)の研究では、様々な工夫が紹介されていました。まずは故障を発生させない工夫です。ある事業体では16時を退勤時間に設定することで、無理な稼働を減らし故障を防ぐ取り組みをしています。別の企業では、不慣れなオペレーターは習熟度が高まってから、林業機械を使うシフトに入るという工夫をしています。また、機械の更新のタイミングを5年よりも早く行うことで、機械整備にかかる費用が利益を上回るのを防ぐ取り組みをする事業体もあるといいます。 そして一番重要なのが日々の点検です。故障の兆候を発見し未然に防ぐことで、機械寿命を延ばすことができます。しかし、その重要性がいまいち伝わりにくく教育体制の拡充が必要と指摘されていました。こうした努力をしても、故障するときは故障するのが機械です。事業体はそういう場合でも何とかして修繕費を抑える工夫をしているようです。修繕を自社で行うことでコストを抑えている事業体や、保険に加入することで万が一の出費を抑える事業体などがあるそうです。前者の対策は林業機械が高機能化すればするほど難しくなるという欠点がありますが、簡単な故障だけでも直す技術を持っていれば経費の削減につながります。後者は、加入するだけで良いので労力はすくないですが、機械にかかる経費が増えるため、よりシビアに運用計画を立てる必要が出てきます。以上のように、その性能の高さに目が行きがちな林業機械ですが、計画的な運用を行わなければコストパフォーマンスの悪化や赤字につながるということが分かりました。単純には行かない森林経営の難しさが伺えます。林内路網の諸問題機械のコスパと共に考えなければならないのが、路網の配置です。前述した通り、施業システムの生産性を考えるうえで、その立地や林業機械に適した路網はとても重要になります。そこで次に、林内路網についてご説明します。林野庁によると、林内路網は規模によって大きく次の3つのタイプに分けられます。①林道不特定多数の人が利用することを想定した路網。森林管理においては幹線的な役割を担う。②林業専用道メインユーザーは森林管理者。規格は普通自動車や10tトラックの走行を想定した必要最低限の構造。幹線としての林道の補完的な役割を担う。③林業作業道ユーザーは森林管理者。特に集材時などより高密度な路網が必要になるときに設置される。規格は林業機械が通れる最低限の構造で、経済性を意識しつつも丈夫であることが求められる。これらを配置することで林内全体へのアクセスを容易にし、綿密な施業を可能にすることが目指されています。ちなみに今回、皆さまのご協力によって作設するのは、この分類では林業作業道に分類されます。現在の日本の林内路網密度は22.4m/ha(H30)で、ドイツ(118m/ha, 1986.1989)やオーストリア(89m/ha, 1992. 1996)と比較するとかなり低いと言えます。日本の林道作設が進んでこなかった理由としては、①火山噴出物が主要な地質で工事が難しかった②急峻な地形で工事が難しかった③台風等の気象害により維持管理コストが必要だった④所有者の異なる小規模な林分が多く、まとまった距離の路網を設置することが難しかった⑤材価の低迷で森林管理設備に対する投資が進まなかったなどなどたくさんあります。しかし、一般的な伐期に達している林分が半数を超したことや、温暖化ガス削減のため森林の二酸化炭素吸収機能に注目が集まり、その機能が高い若齢段階の人工林を増やそうとする動きが生じていることなどにより、安定的に大量に施業を行えるような路網整備が急務となっています。そのため、令和元年度から5年度までの森林整備保全事業計画では、今後5年間で7.2万㎞という高い路網整備目標が設定されています。ただ、路網もただ設置すれば良いわけではありません。傾斜や地質に合わせて、ロープウェイのように架線集材を行うのか、高性能林業機械の導入を見越してアームの届く距離を考慮した路網配置を行うのか、考慮する必要があります。下手に設置してしまうと、前述のようにフォワーダーの移動時間が長くなって生産性が落ちるということもあります。さらに、林野庁で今年3月に開かれた「第1回今後の路網整備のあり方検討会」では、林内だけではなく加工流通拠点との位置関係や、需給に合わせた路網整備計画の重要性、トラック運転手に配慮した設計、レクリエーショへの活用、災害に強い設計などを意識することの重要性も検討されています。森林に期待される機能が多様化する中、その管理のための道の在り方も変化していると言えるでしょう。そのため、今後は距離や路網密度などの量的な目標だけでなく、質的な目標設定も行うべきだろうとの意見も書かれていました。災害の影響を受けると修繕費や管理コストがかさむことも確かに量的な目標設定を行うと、数字を追いすぎて実態が把握できていないことがあります。例えば千井さんが教えてくれたのは林業作業道の例です。林業作業道は素材生産時に林業企業が設置する場合が多く、集材時さえ使えれば良いという設計になりがちです。そのため継続利用を考えていない傾斜や、排水設備の不備により、「距離が伸びた」と言っても、大雨が降るともう使えない林道になっている、というケースがあるそうです。そんな話を聞いて僕が思いついたのが、素材生産の利益と林道作設のコストを切り離すため、林道作設専門会社を立ち上げ、質の高い林道整備につなげるというアイデアです。和歌山には「木を伐らない林業」を行う、植林専門の「中川」という林業会社があります。この会社のように、「道を付けるだけの林業」があっても良いのでは?などと考えをめぐらしてみました。明日10月1日からは、改正木材利用促進法が施行され、その対象が公共建築物から民間の一般建築まで拡張されます。林道整備によって、国産材の安定供給システムが向上し、木材利用が加速すると良いですね。平井産のはちみつ!難しい話になったところで、一回平井に戻りましょう。先日ご近所さんから蜂蜜を頂きました。蜂蜜をもらうのはこれが2回目で、1回目は梅雨明けの7月に頂きました(もらってばかりです笑)。その7月の蜂蜜が残っていたので、味を比べてみることにしました。はたして味に違いはあるのでしょうか…?スプーンですくって食べてみた結果、明らかに味が違います。上手く表現できないのが不甲斐ないですが、7月の方は脳内に花畑が広がるような感じです。一方の、秋の蜂蜜は森が広がる感じでした。この味の違いは恐らく蜜源となる花の違いでしょう。市販の蜂蜜を食べていたころは、こんな変化に全く気付きませんでしたが、昆虫たちが季節によって訪れる花を変えているのが分かり面白く思いました。蜂蜜から考える生物多様性の価値この蜂と花の関係性、もとい昆虫(送粉者)と植物の関係性について、Bascompte(2003)が面白い研究結果を発表しています。Bascompteは植物や昆虫にいるスペシャリストやジェネラリストに注目しました。昆虫の場合、スペシャリストとは、ある単一の種の植物だけを利用する種のことを言い、ジェネラリストとは蜂のように色んな植物を利用する種のことを言います。逆に花粉の媒介における植物のスペシャリストとは、ある単一の昆虫種にのみ送粉を依存している種、ジェネラリストは色々な昆虫種に送粉を任せている種のことを言います。Bascompteはこれらの昆虫と植物の関係性を調べ、ジェネラリストとスペシャリストが相補的になるネスト構造になっていることを発見しました。詳しく説明するため下の図をご覧ください。この図で、〇は植物と昆虫が花粉の媒介において関係があることを示しています。昆虫種Jについて見てみると、植物種aとしか関係を結んでいません。この場合、昆虫Jは植物種aのスペシャリストと言えます。一方で、その植物種aについて見てみると、すべての昆虫種と関係を結んでいます。逆に、植物種ⅰを見てみると、昆虫種Aとしか関係を結んでいませんが、昆虫種Aは全ての植物種と関係を結んでいます。このように、「一方がスペシャリストなら他方はジェネラリストになっている」というのがネスト構造です。では何故このような構造になっているのでしょうか?そこで植物も昆虫もスペシャリストの場合を考えます。もしある年の気候が極端に寒く、昆虫が絶滅してしまうと、植物はそれ以降花粉を運んでくれるパートナーがいなくなってしまい、子孫を残すことが出来ず、絶滅してしまいます。逆に、植物が絶滅すると密を利用していた昆虫は、他の物を食べることが出来ず死んでしまいます。そのため、互いにスペシャリストである関係性は自然界では長期的には残りにくいとされています。一方で、植物か昆虫どちらかがジェネラリストである場合、共倒れする可能性は低く、その関係性が保たれやすくなります。その結果、ネスト構造のように相補的な関係性が蓄積したと考えられています。つまり、多様性によって安定的な関係を築いていると言えますね。こうした多様性がもたらす利益は、見えないところで人間社会に大きく貢献しています。それは環境問題と言う面だけではありません。例えば、世界の主要な農作物の75%は昆虫の受粉に依存しており、もしそれが出来なくなれば、非常にコストと時間のかかる人工授粉に切り替える必要が生じます。その場合、農業関連分野の経済的損失だけでなく、食糧危機まで問題が発展しかねません。 そこで、生物多様性の損失が人間社会に悪影響を及ぼさぬよう議論が進められています。花にやってきたカナブン。手足に花粉が付いているのが分かる。COP15の論点 生物多様性と経済10月11日から中国の昆明で開かれる生物多様性条約の締約国会議 COP15では、まさに生物多様性と人間社会の関係性について各国が集まり議論を行います。今回の会議で注目されているのは、G7が大筋合意した「各国が陸地と海洋の3割の面積を保護・保全する 」という目標に対する途上国の反応です。2010年の名古屋会議で設定された愛知目標では不十分なため、より進んだ目標設定をしたいのがG7。一方の途上国は、保護区に指定されることで、農地化や開発が制限されるため合意に踏み切れないと見られています。そのため、先進国は途上国に対し集約的な農林水産業方法の導入補助などの形で支援を行う必要があります。また、途上国は先進国が途上国内の生物資源を元に開発した医薬品や品種改良産品の利益を、途上国に分配するように主張しています。これは生物多様性条約において、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」が規定されていることに基づいており、COP15の大きな論点の一つです。こうしてみてみると、生物多様性が炭素クレジットにおける森林のように、経済的な価値を獲得しつつあることが伺えます。その推察通り、世界の金融機関では生物多様性を考慮した変化が生じ始めています。ノルウェー銀行インベスト・マネジメント(NBIM)は8月18日に投資先企業に向けて発表した文書で、企業活動がサプライチェーンを含めて生物多様性に与える影響の開示を期待すると発表しました。またフランスの運用大手アクサ・インベストメント・マネージャーズも6月に、生物多様性の損失に関わる企業を投資対象から外すとしています。他にも55の金融機関が、生物多様性の保全や生態系回復に貢献すると宣言しています。また、企業活動における生物多様性保全意識を内部から高める上で必要になるのが、そのリスクの把握です。気候変動の分野では、世界の金融当局が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に則り、気候変動が企業活動に与える負の影響の情報が開示され、全体像が把握されつつあります。これと同じように、生物多様性においては6月に設立された「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」が情報開示の役割を担うとされています。2023年中には、生物多様性が企業財務に与える影響を分析・開示する仕組みを作る予定だそうです。お金が絡むと良くないイメージを持つ人もいるかもしれませんが、活動の持続可能性を考える際に経済的な価値を高めることは非常に重要です。また、価値のある活動に対し、それ相応の対価が支払われるのは全うといえるでしょう。どの意味で生物多様性保全に経済的な価値が生まれつつある現状は良い兆候と言えるのではないでしょうか?世界初!スギのゲノム編集技術今日はここまでですが、最後に面白いニュースがあったので、次回予告の意味も含めてご紹介しておきます。内容としては、世界で初めてスギのゲノム編集に成功したというものになります。これまで樹木の品種改良は英精樹選抜と掛け合わせにより10年以上のサイクルで行うのが普通でし。しかしゲノム編集を行えば、より短いサイクルで樹木の品種改良を行うことが可能になります。また、炭素固定機能を高めつつも強度を保つ性質を持たせることで、林業の収益サイクルにも革命をもたらすかもしれません。次の機会にもう少し深く考えてみたいと思います。参考文献・路網整備の推進 林野庁HP 閲覧日2021年9月29日・高性能林業機械とは 林野庁HP 閲覧日2021年9月29日・路網整備の推進 林野庁HP 閲覧日2021年9月30日・公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(改正後:脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律)林野庁HP 閲覧日2021年9月30日・第1回今後の路網整備のあり方検討会資料 令和2年3月25日 林野庁・林野庁 平成22年度版 森林・林業白書・林野庁 路網と作業システム・林野庁 2018. 生産性向上ガイドブック (平成 29 年度林業事業体の生産性向上手法検討委託事業報告書) 第2版・井上源基 2001. 伐出コストを計算しよう.(機械化のマネジメント. 全国林業改良普及協会編,全国林業改良普及協会).※一次資料を閲覧できなかったため、止む負えず尾分ら2020を二次資料として参考。・日本林道協会 2001. これからの林道整備 現場からのアプローチ 日本林業調査会・30年のCO2吸収量、目標量の3割増検討 森林や木材活用 日経4月19日・生物多様性なくして経済なし 陸海の3割保護で合意へ 日経9月27日・スギ改良でCO2吸収量増 森林総研、ゲノム編集で実現へ Next Tech2050 日経9月27日・世界初 スギのゲノム編集技術を開発 ~針葉樹の品種改良を⼤幅に短縮する新技術として期待~ 横浜市立大学HP 閲覧日2021年9月30日・尾分 達也, 佐藤 宣子 2020. 高性能林業機械の修繕および機械更新の事業体戦略 日本林業学会 102巻2号 120-126・宮下直, 井鷲裕司, 千葉聡 2012. 生物多様性と生態学 朝倉書店・Jordi Bascompte, Pedro Jordano, Carlos J. Melián, and Jens M. Olesen 2003. The nested assembly of plant–animal mutualistic networks. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 100 (16) 9383-9387